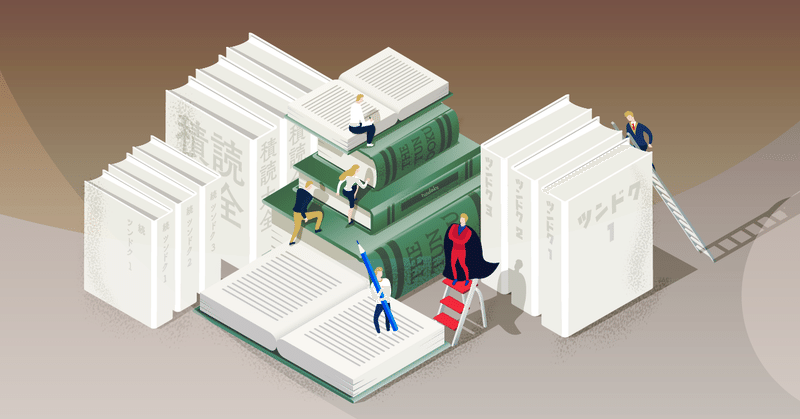
「100分で名著」ローティ『偶然性・アイロニー・連帯』所感(前編)
時々観ます「100分で名著」。ただしこれまでは、小説や古典文学がテーマの回ばかりでした。今回は、なぜかDVDデッキが自動録画していた2月分のこれをなんとなく100分一気に視聴しました。すると、とんでもない結論があって、意外に自分に近い話題であったということで、記事にしてみることにしました。私のDVDデッキ、付き合いが長いとはいえ、こんなタイトルから私との関連性を見出して録画するなんて。
ということで、ネタバレアラートです。この四回分のネタバレ(=本のネタバレを含む)があります。また、私はこの『偶然性・アイロニー・連帯』という本を読んではいません。そして、私なりに、この番組で言及された内容について理解し、感じたことを書き連ねた「所感」です。厳密に本をきっちり理解したとは言い難いのですが、あくまでも番組の感想ということで、ご了承ください。
哲学の難しい本と、その著者ローティの主張
という内容でした。ざっくり言うと。ただ、2007年に亡くなったローティさん「2016年のトランプ現象を予言した」と言われているらしいのです。なんですとぉ?
第一回 近代哲学を葬り去った男
ローティさんという哲学者が、それまでの哲学の概念をひっくり返した云々の話は、ちょっとここでは置いておくことにします(をい)。だって哲学がどうのこうのって話をしなくても、今回の感想を語れてしまうのです。私には哲学の難しい話を語れるほどの哲学に対する見識が多くないので、ちょっと勘弁してください。哲学書と哲学者の話ですけどね。
この初回で注目されたキーワードは、本の第一部のテーマでもある「偶然性」だったかと思います。または、この言葉をスタートとする、と言った感じでしょうか。
ローティさん曰く「人は、これまでの哲学が追求してきたような『定義』に当てはまるようなものではなく、『偶然性』による生き物である。」と。偶然性による生き物であるがゆえに、人間や社会はずっと同じ定義に当てはまるものではなく変化していくというのです。そしてその変化を生み出す一助となるのが「言葉」だと。おお、急に私に近い話題になりました。
曰く「偶然性によって生まれた新しい言葉や、元来の意味から変わった言葉によって、人の概念は変わる。」と。この時、司会の安部さんが言っていた例として、働くお母さんのことが挙げられました。昔、母親が育児早退(そんな言葉はなかったでしょうが)するときには「三歳児神話もあるからね〜お母さんだね」という言葉で送り出されたそうです。おそらく、安部さんはこれを好意的に、または「母親としての自分を尊重してもらっている」というような文脈で受け止めているのではと感じました。それが、最近は「ワンオペ育児じゃない?」と言われたとか。そして、このワンオペ育児という言葉を聞いた時「そうだ(自分が育児を主に一人で担っているということは)大変だと思っていいんだ。」と受け取ったとか。
この安部さんがかなりポジティブな受け取り方をしているように感じたのですが、何はともあれ、ここでは「子どもの側にいるために帰るいいお母さん」だったのが「ワンオぺ育児」という言葉の登場によって「共働きなのに子育てを押し付けられて自分の仕事を制限させられているだけでなく、帰ってからも過酷な状況が待っている可哀想な女性」という概念に変わってしまった例、ということです。この変化した方の概念に賛成できるかどうかは別として、確かに安部さんの概念を言葉が変えたということでしょう。
言葉がある、ということは、それが伝えようとしている概念があるということです。う〜ん、トランプ現象にはまだ行きつきません。
第二回 公私混同はなぜ悪い?
このサブタイトルに付けられた「悪い」という言葉が若干の混乱を生んでいる気がしますが、まあそれは置いといて、この回のテーマは「アイロニー」です。アイロニーとはなんぞやほい、ということで調べましたところ、辞書的には「皮肉」とか「反語」だということでしたが、どうやら番組での定義はちょっと違うようでした。
まず曰く、人間はその信念や自分の根幹を「ファイナル・ヴォキャブラリー」という言葉におとすことができる、それで表現しうると。例えば「俺は江戸っ子だから」という自分の信念に基づいて「粋」な言動やファッションを大事にする、みたいな。自分はこうだ、ということを説明していくと、最終的に行き着く言葉だそうです。つまり、究極の「私」とは、ですね。
次に曰く、ただし「アイロニスト」とローティが呼ぶ人たちは、この「自分はこうだ」だけを絶対の正しさや基準としては見なさず、他者のファイナル・ヴォキャブラリーについても傾聴し、理解する人た値、時にはそれによって自分の信念を発展させることさえある人たちだと。伊集院さんの例え。「親としては」みたいな話をした時に「自分には子どもがいないから、君のいうことは分からない」ではなく、「ああそうか、子供のいる人というのはこういう考えをすることもあるんだな」と思って歩み寄る。逆に「君には子どもがいないから、自分の気持ちは分からないでしょ」と切り捨てることはしない。とすることで、相互に歩み寄れるし、会話を続けられる。ということです。しかし、このアイロニストたちの考えだけでも「公」の社会は回っていかない。多様な意見を全部吸い上げても全て実現はできないし、自己主張ばかりしても社会としては時に混乱を招く、ということが問題となってきます。
ここで、人間が集団生活の中である意味バランスを取るために使ってきた方法として「公私」を分ける、ということだそうです。たとえば市場(バザール)で店を出す人が、この公共の場でお客にいうお愛想や振る舞いと、仕事が終わった後いつものクラブ(飲み屋?)で言う愚痴や本音は違っていい。また、バザール(公)とクラブ(私)の区別は、こう単純なものではなく、もう少し境界線が甘い時もあるらしいのです。また、最近では、ケースによって私にどこまで公が介入するかが違ってくることも。例えば「ドメスティックバイオレンス」や「虐待」という言葉が出てきたことで、家庭などの「私」に「公」が介入する、それは誰かが苦痛を受けていたり、力による強要を受けていたりする場合(社会の残酷さ)による、ということで、それをできる人たちを「リベラル(社会の残酷さを減らそうとする人)・アイロニスト(公私を分けながら両立する人)」としました。
これを、私は「言語的ペルソナ」ということなのかな、と思いました。いわゆるTPOに於いて、人は違った顔を見せます。時には「性格が違う」と言われるほど。この「ペルソナ」という言葉の説明だけ、大学の一般教養科目で取った「臨床心理学」の授業で覚えている言葉です(笑)。つまり、TPOに合わせたものの言いようとか、言うことと言わないことの区別をつけるとか、時に自己矛盾があっても、それは一人の人間が内包するペルソナとして成り立つよ。本音と建前ってアリじゃない?というようなことに、この回は聞こえました。
自分を言い表すファイナル・ヴォキャブラリーを表現しあって、相互理解や自己の許容範囲を広げたり、TPOによってそのペルソナが表現する言葉で社会がうまく回ったりすることがあるよ、という回だと思いました。
あまりにも長くなりましたので、前後編に分けることにしました。
四回分、100分まとめての総括や感想は、後編にて。
前編、お付き合いいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

