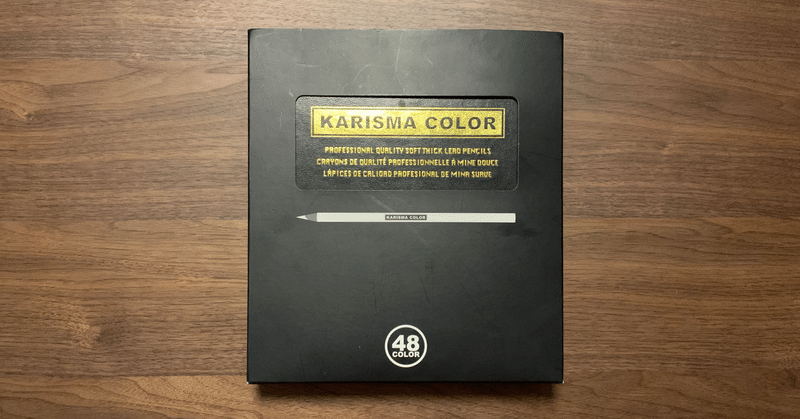
日々の100
夏休みに入ったので、合間を見つけては活字を貪っている。夏休みってすてき。
昨日はちょっとゆるく読みたくなったので、写真も含まれたこの本。
日々の100 松浦弥太郎
松浦弥太郎さんは柔らかくてとても繊細な感度をお持ちなので割と気になっている存在だ。その反面、ちらちらと「男たるもの料理すべきではない」などの男イズムを出してくるのは好かん。好かん、という程度には本は数冊読んでいるし、彼の名前が出ている記事は結構読んでしまう。おしゃれだし正しいし憧れているけど、やっぱちょっとサシ飲みするには合わへんかもしれへんわ、って感じだ。(できるか!!)
「すべては結局、私が誰とつきあっているかを知りさえすればいい。自分は一体どんな人間だろうか?」
「その人がつきあっている親しい知人が誰なのかを知れば、ひとつやふたつは、その人の本性は垣間見れるだろう。少なくとも人としての種類はわかる」
(アンドレ・ブルトン「ナジャ」)
この本の冒頭ではこの一文が紹介され、これを元に、松浦さんが日常生活でつきあっているもの100を選び、そのものとのつきあい方や出会い、思いや記憶を書かれている。その100点は、素朴な日用品から希少な本、シャツ、紙切れなど紹介するものは多岐に渡る。
私はそういう、人の生々しい生活が垣間見えるものが大好きだ。
小・中学生の頃、友達のペンケースを漁り合うのがちょっと流行ったが、私はそれが大好きすぎて、高校になっても隙あらばやっていた。ペンケースのデザイン、入っているペンの種類(国産、輸入もの、全部無印良品・・・)、バーコードは剥がすのか、リップクリームを入れる人、修正液だけ数年使っている人・・・もう流石にできないけれど、みんな癖があって愛おしかった。どれもスタイルがあって、洗練して見えた。女性誌で、バッグの中身公開の特集があるけれど、それも好きだ。OL雑誌はどれも似たり寄ったりで「嘘つけ!」って感じなんだけど。
そうやって物の使い方や愛し方から人を見るのが好きだから、「ほほう、松浦氏を見てやろうじゃないか」(変に生ぬるいところがあれば、難癖つけてやろうじゃないか)という穿った目で、まんまとポチッとお買い上げした本だった。
感想:良かった。
めちゃ濃い何か、ドラマチックなものを期待してはいけないけど、良かった。生ぬるくなかった。かといって激アツでもなく、どれも暖かく重みがある。
そしてペンケースやバッグやらを漁ってきた私なりに、この人はとても不思議だなと思った。この人は、「人」が大好きだ。出会うこと、偶然を楽しむこと、語り合うことが大好きだ。
そして、彼の愛するものは、暮らし系ライター、特に男性ライターでありがちな「どのように作られたか」「どれくらい古い(希少な)ものか」「如何に高い技術であるか」・・・つまり社会的な価値を語るものではなかった。
誰と出会った時に勧められたとか、誰が大事にしていたものだったとか、どこで拾ったとか・・・出てくる人は「誰やねん、知らんがな」という人ばかりだが、それがいい。めちゃいい。私にとっても大事な人がいて、その人について語ったら、みんな「誰やねん」と思うだろうから。
彼の愛するものは、結果的に希少なものや高価なものも含まれているけど、希少だから愛しているのではなく、惹かれた経緯や出会った経緯があるから愛している。
ええやん。松浦弥太郎さん、ええやん・・・。
一方で、やはり「男たるもの・・・」は時々ちらつかせてくるので、柔らかい感性と共感的な部分と、とても前時代的な男性観が同居しているあたり、私の頭の中には「やわらか弥太郎さん」「ごりごり弥太郎さん」が共存していて難しい。
私も、日々の100を選べるだろうか。
こういう本を読むと、早速自分の生活にも落とし込んで見たくなるものだ。素直なのはいいこと。ミーハァーーー!!!(ヒーハーのテンションで)
30歳の今、100はまだ難しい。
最初に思いついたのは、色鉛筆だった。
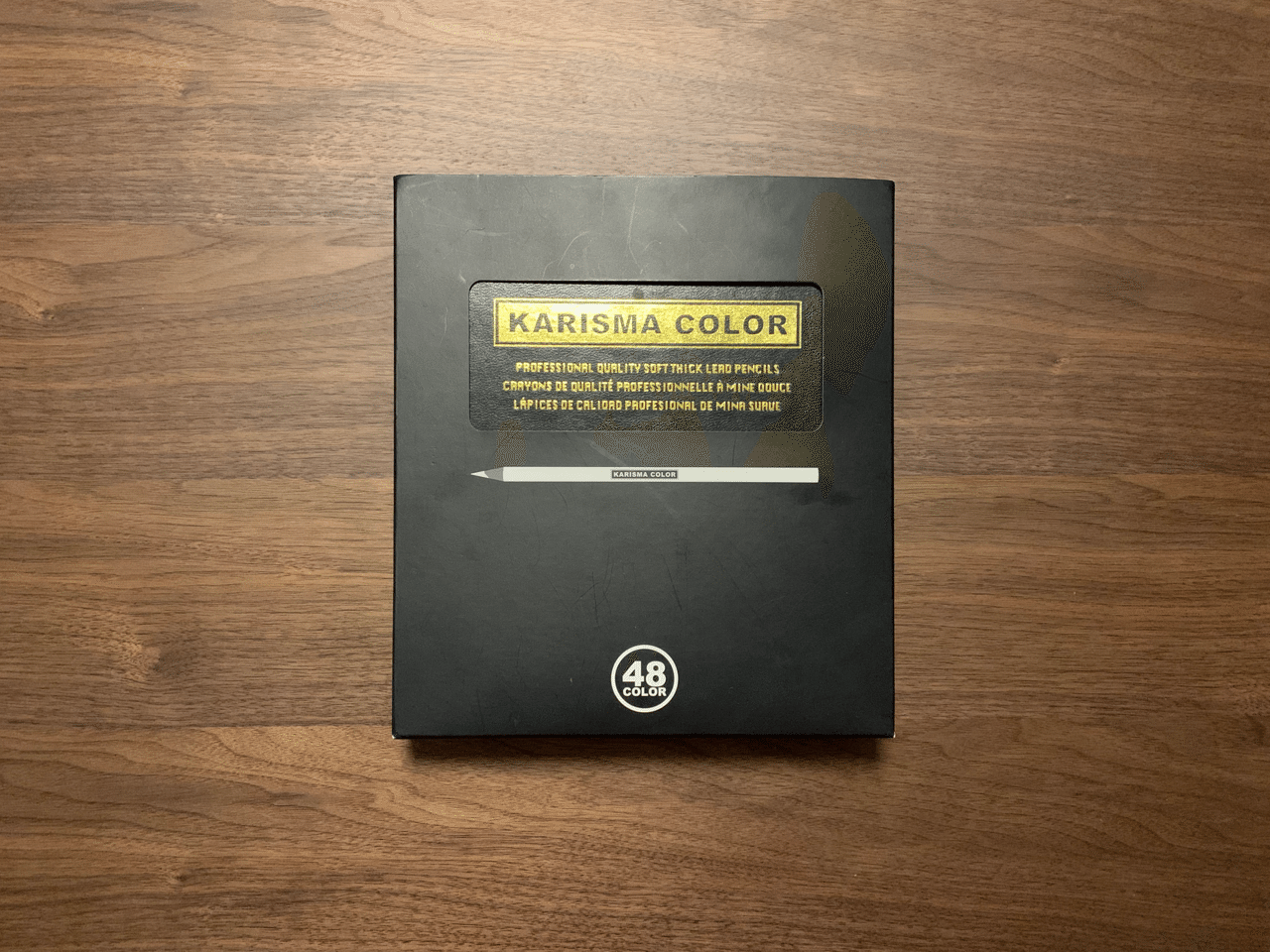
KARISMAの、48色色鉛筆。大学生の時、母が誕生日プレゼントに買ってくれたものだ。
母は、120色色鉛筆を持っている。大学生の頃に買ったものらしく、箱には年季が入っているがまだまだ現役だ。
初めてその色鉛筆を見せてもらったとき、ものすごくときめいた記憶がある。微妙な色の違いで、ざぁっと色が並んでいる。色の解像度が急に高くなるような感覚だ。
組み立てて観音開きするようになっていて、60本が2段。1段あたり50cmくらいあったような気がする。
高校生になり、強くねだって使わせてもらえるようになり、毎年年賀状はそれで書いた。お道具箱に入っている色鉛筆みたいじゃなく、その色鉛筆は年度があり、重ねれば重ねるほどネリネリと濃くなり、深い色を表現できた。もうフォトショで絵を描く友達が多くなってきている中、私は色鉛筆が好きだった。年末は指にタコを作りながら、年賀状に1枚1枚、別の絵を描き色を塗った。
やっと買ってもらったのが48色。ええっ、物足りない・・・と正直思ったんだけど、母が自分のために買った時代とは物価が違うので仕方ない。
社会人になってからも、子供が生まれるまでは、毎年年賀状を1枚ずつ違うデザインで描き、塗り続けた。
黒い箱を開けると、色鉛筆がざっと並ぶ。

だれでもときめくんじゃないかと思う・・・んだけどそうでもないのかな。
緑系〜青系を適当に順番に、ねりねりと塗っていくと、不思議な海のようなグラデーションが生まれる。黄系〜赤系をねりねりすると、太陽のような光の玉が生まれる。ピンク〜緑など、全然違う色をねりねりするのも、魔法みたいで面白い。
思えば、小・中学生の頃、デザイナーという職業を知らなかったときに出会った色鉛筆は、色で遊ぶ楽しさをたくさん与えてくれた気がする。絵の具ほど大層ではなく、手軽で、人に贈る楽しみがあり、簡単に失敗できる。
いつか120色の色鉛筆が買いたいかというとそうでもなく、厳密には母の120色色鉛筆が欲しい。あの時のどきどきはあれにしかない。ねだっても、「ボケ防止にそのうち使う」といってまだ手放す気はないようなので、気長に待とうと思う。
あなたの、大切なものは何ですか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
