
「アートとエンタテイメントの調和を」東京国際映画祭_久松猛朗さん
クリエイターを応援する業界の取り組みをピックアップし、代表者の方にその「想い」をインタビューしていきます!
(2021年1月22日 (金) 10:00 配信済)
映画界とクリエイターを繋ぐ『映画祭』
その主催者の方にインタビューを行い、主催する映画祭の特徴や今後の展望を伺います。
今回は毎年、東京で開催されるアジア最大級の国際映画祭「東京国際映画祭」本映画祭のフェスティバル・ディレクターを務める映画プロデューサーの久松 猛朗さんにお話しを伺いました。

久松 猛朗氏
マイウェイムービーズ合同会社 代表
映画プロデューサー
「東京国際映画祭」
1985年から始まった日本で唯一の国際映画製作者連盟公認の国際映画祭。国際的な審査委員によってグランプリが選出される「コンペティション」には毎年、多くの国と地域から応募作品が集まる。また開催期間中は学生、プロ、ビジネス来場者を対象としたセミナー、シンポジウムやワークショップなども多数開催している。
アートとエンタテイメントの調和
「東京国際映画祭」開催のきっかけを教えてください
初回開催は1985年です。
当時はカンヌ国際映画祭のような国際的な映画祭がアジアにはなく、そういったものを東京でやろうという思いで、当時の関係者の尽力のもと、東京国際映画祭は始まりました。
―――久松さんは、映画祭を指揮するフェスティバル・ディレクターとして就任4年目を迎えました。
第30回から第33回まで、これまでの4回の開催で一貫して掲げてきたスローガンは「アートとエンタテイメントの調和」です。
映画はアートであると同時に、製作にはとても多くの資金が必要で、産業として考えたときには投資した資金を回収していかなければなりません。
クリエイターの思いやその作家性を応援する部分と、一般の観客をより楽しませるというエンタメ部分の両立。これはとても難しいことではありますが、映画作品としても、映画祭全体としても、このバランスをとっていくことを目指してきました。
そして、このスローガンの下「映画を観る喜びの共有」、「映画人たちの交流」そして「映画の未来の開拓」という3つのビジョンを設け、映画祭を建付けています。
「映画を観る喜びの共有」とは、先ほどのアート系の作品やエンタメ系の作品など、映画の持つ多様性を広く紹介すること。
「映画人たちの交流」とは文字通り、各国の映画監督やプロデューサー同士の交流の場を設けること。「映画の未来の開拓」とは映画を作るこれからの人々を発掘、支援することと、映画観客の作品を楽しむ力を育むことです。
「映画の未来の開拓」のテーマに沿った施策としては、中学生に映画作り体験をしてもらう「TIFFティーンズ映画教室」や、若手俳優を東京で見出し、顕彰する「東京ジェムストーン賞」を実施、設立し、若手のクリエイターを支援しています。


BLOOM!信じよう、映画の力
コロナ禍で実施された第33回の開催について
―――メインビジュアルに込めた思いを教えてください。
青空の下、これから満開に向かって桜のつぼみが咲き出していくイメージのビジュアルにしました。
コロナの影響で、映画業界だけでなく、日本全体の先行きが見えづらい状況ではありますが、業界全体として、その先にある明るい未来に向けてポジティブになれるようなメッセージを届けられるよう、「BLOOM!信じよう、映画の力」というキャッチコピーを添えて、「ここからまた始めていこう」という思いを込めました。

―――これまでのプログラムとの変更点はありますか?
昨年はコロナの影響で、海外からの審査員の渡航が叶いませんでした。
その為、映画祭自体の形式を、従来のコンペンティブなものからショーケース型に変更しました。
ただ、映画祭で見いだされて次のステージに羽ばたくチャンスを渇望するクリエイターは全世界にたくさんおり、こういった方々を勇気づけたいという思いで、「TOKYOプレミア2020」という形で観客賞は設けました。
今回、この観客賞は大九明子監督の『私をくいとめて』が受賞しました。大九監督は第30回開催での『勝手にふるえてろ』以来、2度目の受賞となりましたが、こうしてまた受賞することで、注目を浴びることにもなりますし、監督自身の今後のエネルギーの源泉にもつながると思います。
また、今回は必要に迫られて、という形でしたが、作品上映後のQ&Aなどプログラムの一部にオンラインツールを導入しました。オンラインでのQ&Aは参加する人にとっては物理的な制限がなくなったことで、映画祭としてはリーチできる層が広がったり、参加する側はチャット形式でのやりとりが質問しやすい環境になったりと、オンラインのメリットも感じることができました。

フィロソフィーは続けていくことで示すもの
今後の展望について
映画祭は多面的で様々な立場の方々が関わっています。それぞれの立場から映る映画際というのはどうしても多面的な中の一部なので、映画祭を長く続けていくと、さまざまな意見が出てきます。
そういった意見も大切にしつつ、映画祭として一旦決めたことは続ける、これまで積み上げたものを守っていくという姿勢を大事にしていきたいです。
カンヌやベネチア等の国際映画祭に比べたらまだまだ歴史は半分ですが、こういった姿勢を示し続けることで、東京国際映画祭の核となるものを作っていけたらと思います。また、それがフィロソフィーという言葉にもつながってくるものだと感じています。
また、今回オンラインツールを部分的に導入しましが、改めて、フィジカルでの実施の良さを感じました。本来、映画祭はその土地の街並みや文化と密接につながっています。映画祭自体を全てオンラインで行ってしまうと、その差別化ができなくなってしまいます。映画祭をフィジカルで、そしてリアルで人々と過ごすということはとても大切です。
来年の状況はまだまだ見えない中ではありますが、来年も是非、フィジカルで開催できたらと思います。
TCPへのコメント
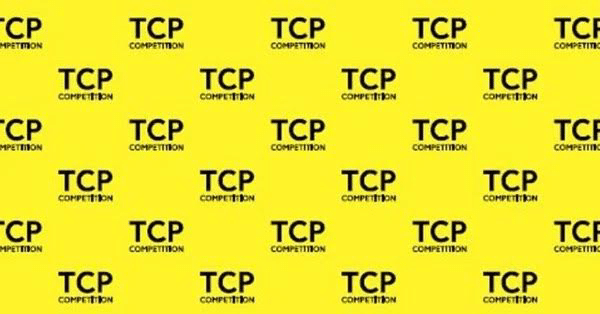
受賞作品を5,000万円以上の出資金でバックアップするということ、そしてそれをコンスタントに続けているということ自体がすごいことです。
さらに毎年、600を超える応募があり、最終審査の場にも多くの業界関係者がファイナリストのプレゼンを見に来ます。こういったプログラムは他に類をみません。
そういった意味で映像、映画業界に与えたインパクトはとても大きいものだと思います。業界にとっても重要な施策。是非、続けていってほしいです。
そして、次の挑戦としては受賞作品の商業的な面での成功につなげるという部分をどう強化していくか?というところだと思います。商業作品としてどう建付けていくか、ヒット作品に仕立て上げていくか。こういう商業面での成功体験を重ねていくことが大切だと思います。

