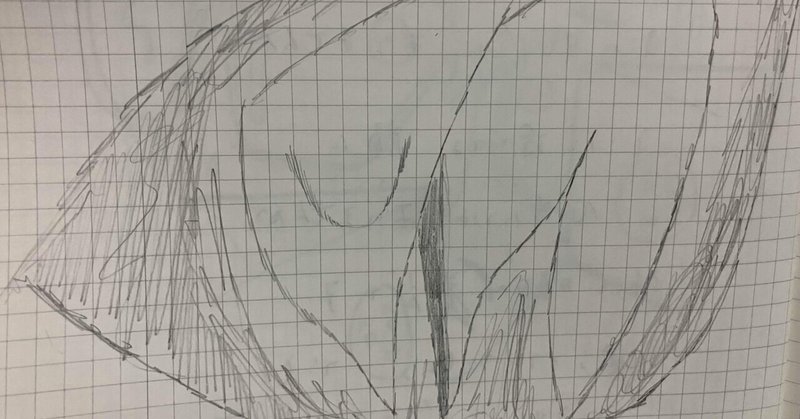
all you need is
■文章を書くのが怖いと感じる日がある。文章を書くことによって、それまで自分が知らなかった自分と出会ってしまいそうな気がする、そんな日が今日である。
人生は不思議だな、と思う時がある。久々に人に会うと「会うたびに若返っていくね」と言われる。ベンジャミン・バトンという、老人の姿で生まれて赤ん坊になり死んでいく男の映画があるが、まさにこういうことなのかもしれない。5年前の自分、10年前の自分と、今の自分で三者会談を行ったら、全員が全員に向かって「誰お前?」と言うだろう。確かに、僕は若返っているのかもしれない。
本当に「生きる」を始めれば誰でも、最初は不安に駆られるものだと思う。遅かれ早かれ誰にでも「生きる」を始める時というのは訪れる。最近の僕はといえば、「生きる」を始める頻度が増えていると思う。若返りの原因はこれかもしれない。「生きる」は色々な角度、色々な層に存在するので、自分の「生きる」だけが「生きる」だと思わないようにすることだ。そうすれば「生きる」の幅は広がる。自分の中の「生きる」の幅が広がれば、そこに「生き物」が入り込み、生態系が作られる。自分の中に生態系があると、自然と恐れが消える。生態系は命であり、命は暖かいからだ。恐れは、暖かいところに存在することはできない。と、ここまで書いて、わかった。僕は今これから、死と向き合わなければならない。だから、書くのが怖かったのだ。
死は、書くのが難しい。生きている人は誰も死んだことがない。経験したことであればそれに即して書くことができるが、死は経験したことがない。だから、想像で書くことになる。「なんでも経験が大事さ」という言説があり、一理あることもあるが、じゃあ「死を書くために、一回死んでみよう!」ということにはならない。生きている間に体験する死とはもちろん、自分の死ではない。他人の死だ。喪失体験だ。暖かかったものが失われること。自分の中から生態系が、命が失われていくこと。それが恐ろしいのだ。
例えば親の死、配偶者の死、子供の死、兄弟の死、友人の死、ペットの死。そして最後に訪れるのが自分の死である。人生とは、生と死の間にある全てのことを指す。死は全ての可能性の土台である。死があるからこそ生がある。そしてそこには命がある。もし、死がなければ、我々は一つのグチャグチャの塊として分別のつかない何かとしてしか存在できなかったのではないだろうか。そう思うと、確かに死は喪失体験ではあるが、もし死がなければ、我々はそういった一つ一つの命と出会うことすらできなかったといえる。そう考えると、死と生とは相即であり、つまり命そのものであるのだから、もし仮に他者の死が喪失体験として我々に経験されるとしても、それは命が命しているということに変わりはない。つまり、死によって命が失われていくというのは、誤解なのだ。誤解だったのだ。死とは命であり、命の中でも特に、暖かい暗闇であり、暖かい暗闇として想起されるのは胎内である。つまり、我々が生まれる前の、母の中にいた頃のことだ。「死にたい」とはつまり、胎内回帰願望、何か暖かいものに包まれたいという願いなのだ。
そのようにして死が表現される時、死はもはや恐れの対象ではなくなる。死を恐れの対象として感じてしまうのは、「今はまだ死ねない」と思っているからだ。しかしそれは、死が生とともに命の原理であるときには、「生きる」を始めることを否定することにつながる。人生を生きるコツは、こまめに死ぬことだ。死んで生まれ変わる。命はその繰り返しなのだと思う。循環の中に、冷たい領域も確かにあるのかもしれない。しかしそれは、役目を終えた命の爆発による高熱がもたらした流体が固化したもので、きっと、ちょうど次の命の骨になるようなものだ。だから何も心配しなくていい。僕が今この文章をどう終わらせるかを考えているように、どうやって死ぬか、そんなことを考えるくらいが人生はちょうどいいのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
