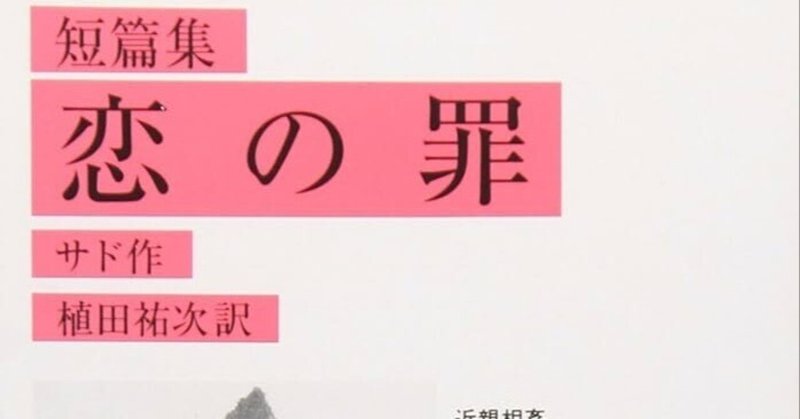
サド『恋の罪』
サド『短篇集 恋の罪』
植田祐次 訳
サドを読んだのは学生時代以来。当時は若さゆえの怖いもの見たさも正直あった。確か『悪徳の栄え』だったはず。
今回手に取った短篇集は、それに比べたら「適法」だと解説にはあるが、さすがサドだと唸らされる。清々しいほどに残酷で、ここまでくると気持ちが良い。
この作家の場合、まず先入観を持ってしまうのは避けられないだろうし、かくいう自分もそうだった。ひとまずそういった偏見を置いてもらって、18世紀フランスの小説らしい饒舌な語り口、大仰な修飾の数々を味わいたい。
この岩波文庫版(1996年刊)は、元々11篇ある『恋の罪』から4篇を精選し訳出してある。
それぞれ舞台となる時代も国も異なるものの、基本的に身分高い人たちの熱烈な恋愛がこんがらがって…という設定は共通している。そういうこともあり、実際どこか遠い時空の物語なので、およそ現実感のない御伽話として読んだ。あるいは神話に近いと言えるかもしれない。
従来、本とはこっそり隠れて読むべきもので、不謹慎で危険なものであってほしい。映画も音楽もそうだが。
世界も人間も本当に残虐だなと感じる2024年、サドの小説で少し免疫をつけておくぐらいでちょうど良いのだろう。
詳細すぎる訳註は研究者向けと思えるので、話の流れを重視したい人は行きつ戻りつするより後でまとめて参考にした方がいいと思う。
以下、各篇一言ずつ感想を記す。
「フロルヴィルとクールヴァル、または宿命」
よくこんな残酷な話を思いつくな、が素朴な第一印象。
不可抗力とはいえ、これ以上に悲惨な家族物語は有り得るだろうか?
恥という概念は生来備わっており、それが救いになっているのかもしれない。
秘められた過去の身の上話の体裁を採っており、その紆余曲折に引き込まれる。
「エルネスティナ」
若く純粋な者たちの汚れなき魂を、狡猾で貪欲な極悪人が襲う。
そのような構図もよく見られるもので、ここからの3篇はどれもそうなっている。
卑劣さは同時に重ねることで倍以上に増幅し、謀略により同士討ちさせられる。
誇りを何よりも重んじるがゆえに、より苦しい状況に追い込まれる。
物語の構造はしっかりと組み立てられており、前後にちゃんとした決着も用意される。しかも、死刑制度に反対する人にとって引用したくなるような教訓にもなっていて、妙な感動すら覚える。
「ロレンツァとアントニオ」
相思相愛の若い二人が、やはり悪の標的となり悶絶させられる。
この場合、実の父親が息子をそそのかしており、悪徳と善良さの対比がよりはっきりと表される。
貞操、純潔が重要な観念としてある。善き心は単純で騙されやすく、不道徳はそこにつけ入る。
悪に徹しきれない人物から策謀は綻んでいくが、円満な展開は得意じゃないのか、取って付けられたように淡々として簡潔。おそらくそこに主眼は置いていないのだろう。
「サンセール伯爵夫人、または娘の恋敵」
こちらは実の母親が娘を恋敵として苛む。
卑怯さに身を落とすぐらいなら、命を捨ててでも名誉を守り抜くという高邁な覚悟がある。
母に言いくるめられた娘は、本心とは正反対の振る舞いを演じるよう強要され、さらに心を痛める。
近いからこそ余計に妬ましいのか、肉親の憎悪ほど恐ろしいものはない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
