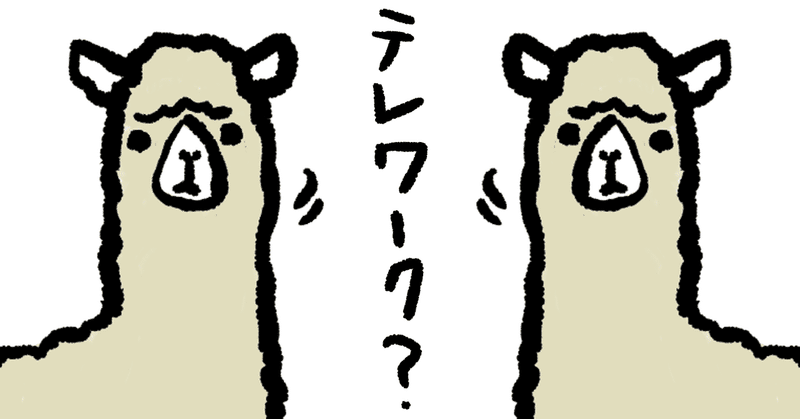
[宣言]障害者”独立”移行支援事業所!
勝手に宣言しておきます。
私は「障害者独立移行支援」を行う団体を絶対に作ります。
※この記事内での障害者は主に「精神疾患による障害者」を対象にしています。
私自身、過去に就労移行や障害者サポートにかかわる業務をおこなっていたのですが
「就労移行支援事業所ってなんか違うんですよね、雰囲気が。
電話応対、名刺交換とかExcelとか朝礼で揃って挨拶とか、そういうマナーじゃなくて、、もっとセルフケアとか自立できるノウハウが学べるような内容を学習したいんです」
という面談者からの声でした。
ほかにも「この職場がダメだったらもう働く場所が無くなるかも」「無理をしてでも残らないと」という不安な気持ちを障害者雇用で働く方からも多く聞いていました。
でもこれってなんだか本末転倒、というかおかしくないですか?
だったらもう
スキルがある人(障害のある方)には独立してもらうのが本当は一番健康的で、本人のためにもなる未来なのでは、、と考えたんです。
でも「じゃあ独立頑張ってね」と何もサポートしないのも違う。。
そこで思いついたのが
就労ではなく独立を目指す障害者をピンポイントに対象にした
『障害者独立支援事業所』を設立です。
知的障害、発達障害、統合失調症、うつ病、適応障害、さらにそれぞ軽重度も経験も違っている。こんな人たちが一緒のフロアに集められて同じビジネスマナー講座を受ける今の就労移行支援事業所ってやっぱりおかしいですよね。(全ての事業所さんでは無く、しっかりカテゴライズされている場所もあります)
※行政やリワーク(復職)施設では、もっと高度なセルフケアや障害理解から医師の定期面談のあるプログラムが組まれていますが、休職中であるなど条件が厳しく、そもそも「独立」目的ではなく、施設数が就労移行支援事業所に比べて圧倒的に少ないので通えない人も多いのです。
そんなにスキルがある障害者ならサポートなしで勝手に独立すれば、、と言われてしまいそうですが、実際はネット情報で”おかしなメンター”にひっかかり情報商材を買ってしまったり、クラウドソーシングでは不利な条件での仕事を断りきれずにズルズルと受注、なんて人も実際には多いのです。
なので受注支援、交渉支援など独立導入時のフォローを重点的に行い、『独立のソフトランディング』をサポートできる仕組みづくりを検討しています。
現段階のおおまかな草案としては
①独立のためのセルフケア、心構えのレクチャー
②目標設定と具体的技能のレクチャー
③独立後のケア
・『クライアント企業』との橋渡し(サポート体制、人的身元保証を提示)し発注の流動性を上げる
・独立者コミュニティを提供し、情報交換・共有の場とする
・独立者はフリーアドレスofficeをドロップイン利用し
相談や支援を受けることができる
と、ここまで書いてはみたのですが大きな課題もあります。
①一番は収益面です(上記内容で公的補助が無い場合、とんでもない利用料金負担:ざっくりでも10万円以上になります)
⇒就労移行支援事業所と同等の公的補助が受けられる法施行が必要になります。
②発注者にメリットが無い
まず依頼先が障害者であるということが発注者にとって何のメリットも無いということです。
そして、クラウドソーシング等を利用すればそもそも『障害者』であることをオープンにしないで受注を受けられる、という点も受注面での大きな課題です。
⇒これについては賛否があると思いますが、
私は『障害者フリーランスへの発注』の年間合計額または想定作業時間数により企業の雇用カウントに一定数補填できる、というシステムが近道だと思っています。
これであれば大企業は雇用カウントの補助的役割に、小規模の事業者では、実雇用がなくても雇用助成金を申請が可能になるはずです。
※悪意のある制度利用をどう監視するかという課題あり
そもそも私がこのような考え方に至ったのは
いまの雇用や就業の概念が
『ノーマライゼーションの偏見』にあまりにも縛られているからなんです。
”健常者と同様に働くこと” ”区別されずに同じ社会で暮らす”
なぜこれが”=雇用されてオフィスに通勤して(またはテレワークで)働く”に変換されてしまうのか? すごく疑問なんです。
障害者が自分らしく働くことに寄与しているなら
『フリーランスの障害者へ予算をかけて発注すること』
と
『自社で雇用して給料を払う』
ことがなぜ区別されるのか??
だとすると「法定雇用率」という規定すらもうおかしくて
「障害者法定自立支援率」にすべきです。
長くなりましたが
私は「人とのやり取りさえなんとかなれば、独立したい」と思っている障害者の方にその「さえ」を提供したいのです。
まず序盤は完全に手持ち弁当になりますが
既独立の障害者フリーランスの方とともに「技能プログラム」を練り、就労移行支援事業所内プログラムの1コマとして提案、実施させてもらい検証を重ねていきたいと考えています。
※「就労」という本筋からずれていない、と思ってもらえる提案が必要。
世の中はさらにニッチ化が進みます。
多様性→1個人=1ニッチという単位になっていくことだと考えています。
目的は
幅広い障害内容を受け入れられる「市販の風邪薬」ではなく
とことんニッチな「その人だけの特効薬」になる環境を提供することです。
長期目標としては、
■特化型就労移行支援事業所を5年後に開設
※独立者支援コースを併設し、開設18か月までに独立者を1人以上。
■実績をもとに行政に発注雇用カウントの提案を行う
2040年までに独立障害者への発注による「自立支援率」が導入されている
困難は(超)多いと思いますが、自分自身落ちているパンを拾い食う生活からここまで生きてこれたので、今回もなんとかやってやろうと思います。
経過は改めて報告します。それではまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
