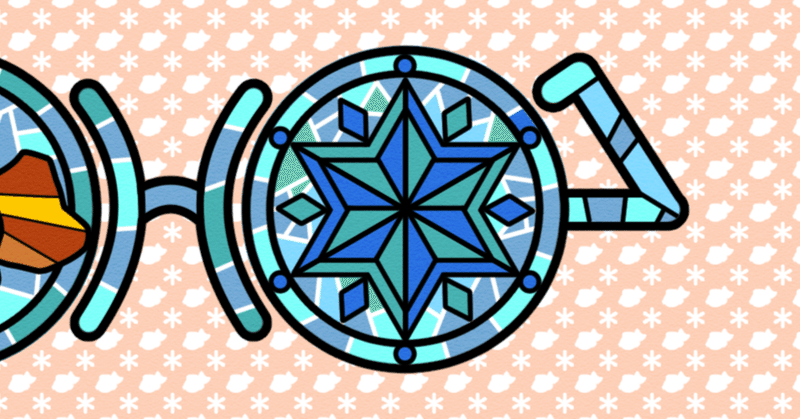
くそこん01 九相図コンプレックス
小学生の頃「二十歳になったら自殺する」って言ってたこと、きちんと記憶したまま三十路を過ぎた。
紆余曲折を経て、同級生から10年以上遅ればせで社会人になった。
私の仕事は尊厳を守ること。
一ヵ月で初任者研修を修了する怒涛の日々と、並行して週一の老健でのボランティアを経て、私は介護士になった。
ボランティアで2日関わっただけの認知症のおばあさんに「あの眼鏡の子は?」と探されたらしい。
つまりアイドルファンで言うところの〝認知〟です。認知症の方に認知された!
これには入所部の主任も「私ですらいまだに覚えられてないのに」と仰っていて、人生の登場人物として相手の心の一部を占めてしまった責任を感じた。
「来週からお願いします」と笑顔で言ってくれた主任が、初出社したらもう退職していたというアクシデントはありつつ。
ボランティアではなくパートとして、みんなと同じポロシャツを着て働けることが嬉しくてしょうがなかった。
主任不在の状態で始まったOJTは人員の不足もあり、特に入浴などは一対一で教えられる環境でないことを謝罪された。
私にとっては、まともに雇われて働くということ自体が初めてだったので、それどころではなく無我夢中でメモをとりまくった。
老健は施設長が医師なこともあり、特養や有料老人ホームと比べても医療の色が濃いらしい。
元々落ちこぼれる前は医療系を志望していたこともあり、看護師の手業を横目に働けることがとても嬉しく、誇らしかった。
初任者研修を終えたとて、わからないことだらけの中で、目をかけてくれる先輩たちもいた。
私がメモを携帯するために首から下げていたポシェットを見て「でかすぎじゃね?」と言って「死蔵していたやつだから」とちょうどいい大きさの鞄を譲ってくれた人。
「冷蔵庫に入れておくから飲んでね」とマウントレーニアのコーヒーを奢ってくれた人。一日ひとつずつ、母国の言葉を教えてもらった人たち。
休憩時間に同僚とお菓子をシェアして食べることにもあこがれがあった。通所や事務、栄養部、リハビリ部など、職種を越えて話ができて何もかも楽しかった。
口数の少ないゆっくりした栄養部の職員さんは、なんだか波長が合う気がした。
私にとって先輩たちはあこがれの人だった。
ボランティアのとき、指示されるまま利用者さんとご家族にお茶を運んだだけなのに、その後の休憩でリハビリテーション部の部門長だったPTさんに「さっきはお茶ありがとうございました」とお礼を言われたことがとても嬉しかった。
通所の介護部の主任は私と同じ秘密を持っているらしく、たった一日しか一緒にいなかったのに、私のそれを看破して、心に寄り添ってくれた。介護士ってすごいと思った。
帰り際、名札を返しに事務所によると、事務の方が「今日のボランティアはどうでした?」と声をかけてくれた。まともな職歴のない引きこもりの私に、ここの人たちはどうしてこんなにやさしく接してくれるのだろう。泣きたくなるほど嬉しかった。
人生は不思議だ。「死にたい死にたい」と思って泣き暮らしていたことが嘘みたいに、あこがれの人たちと肩を並べて働いて、嬉し過ぎて帰りの地下鉄のホームで歌い出しちゃうなんて。
人生は有限だ。どんなお姫様もいずれは死んで腐って骨になって土に還る。いわゆる九相図というやつだ。
それがわかっていても尚、時間を無駄にすることに抗いがたい魅力もあって。
けれど介護の仕事は、誰かの人生の最後の登場人物になるかもしれない。誰かの人生の最後に会話した相手が私になるかもしれない現場であって。
絵空事かもしれないけれど、無理なく細く長く続けて、多くを求めず、許さず憎まず、ちょうどいい距離感でそこにいるということが大事なのだろう。
「オムツ交換なんて100回やれば上手くなります。最初から完璧にできることなんて誰も期待してない」
初任者研修のときに講師の先生から教わったこと、今でもいくつも思い出せる。
「介護は物理であり哲学です」
「介護は情報を扱う仕事です」
この辺りは端的で、常に念頭に置きながら仕事をしていた。
「介護は準備が8割です」は、わかっていても準備不足だったことを痛感するたびにくやしい・恥ずかしい気持ちになった。
でも何より「誰だかわからないけどこの人はいい人です」と言ってもらえるケア者でいたいと思っていた。
名前も肩書も覚えてもらう必要はないけど、私のことをいい人だと思っていてもらえないと、「お薬飲みましょうか」とか「先生に診てもらいましょうか」とかって進言を受けとってもらえなくなってしまうから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
