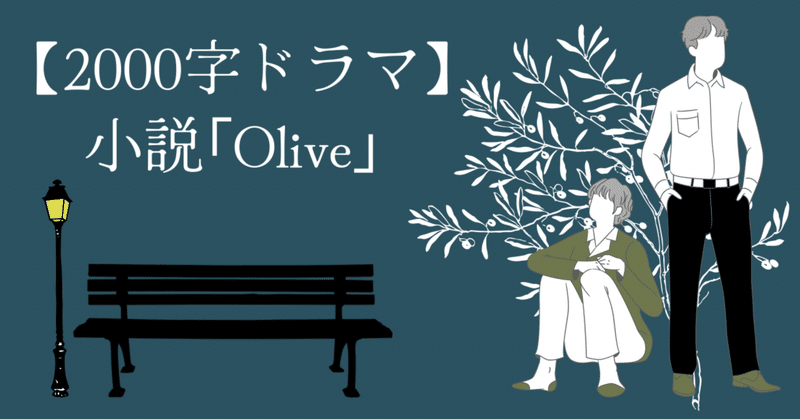
【2000字ドラマ】 小説「Olive」
凪とは、風が止まることで波が穏やかになる現象のことだ。
水曜日の午後1時。
天井の高いカフェで、英字のメニューに目をしかめる。
白い壁に赤茶の床には、緊張感と暖かさが共存している。
「先輩はオリーブのピザか、マルゲリータだったらどっちがいいですか?」
目の前の彼が、クリクリとした目をこちらに向ける。
「マルゲリータかな。オリーブってちょっと苦手なんだよね」
鮮やかなシアンブルーの椅子に背中を押されるように答えた。
だがすぐに彼の顔を控えめに覗き込み、
「でも、有川くんがオリーブの方食べたいならなら、そっちでも良いよ」
と付け加えた。
彼は右下に黒目を動かし、眉間に僅かに皺を寄せる。
5秒ほどして、ジャケットの袖に隠れた腕時計が顔を出した。
それと同時に彼の「すいません」の声が響く。
スタスタと丸顔の女子大生に見える店員がこちらへ来て、注文を聞く。
英字を難なく読み上げる彼は、いつもよりシルバー縁のメガネが輝いている。
家で飼っている犬の話や、最近読んだ本の話をしているうちに、足音と幸せな匂いが近づいてきた。
「お待たせしました」と丸顔女子大生が、少し歪んだ形のマルゲリータをテーブルに置く。
「僕が切り分けますよ」
ベージュピンクの唇と口元のホクロが動いた。
いつの間にかジャケットを脱いで、張り切っている様子が可愛らしく、お言葉に甘えた。
意外にも関節の目立つ手でピザカッターを握り、歪な丸は8等分に刻まれる。
さっきとは違い、はっきりと見えている腕時計にピントが合い、気づいた。
私たちには、そんなに優雅にしている時間はないんだった。
「10分くらいで食べて、会社戻らないとね」
切り分けられたマルゲリータは、熟したトマトソースと新鮮なバジルの色のコントラストが美しく、目を奪われる。
ピザは彼が私より1枚多く食べ、一瞬にしてなくなった。
「先輩は本当に美味しそうに食べますよね。そういうところ素敵だと思います」
思いがけない言葉と生まれたてのようなまっすぐな目に、胸がキュッと締まる音がした。
「そんなことないよ。」
なぜか、その透き通った瞳に罪悪感をおぼえた。
「じゃあ出ようか、深田先輩に次の仕事頼まれてるし早く戻らないとね」
そのとき、彼の表情が曇ったように見えたのは私の見間違いだろうか。
山積みになった仕事をなんとか終え、定時から1時間遅れて帰り支度を始める。
有川くんはまだパソコンに向かっている。
偶然、後ろのデスクの深田先輩も仕事を終えたようで、一緒に会社を出た。
「今日も疲れたな」
んーっと手を空に向けて、奥二重ぎみの目をこする姿は猫のようだ。
「疲れましたよ、まだ週の真ん中なのに」
先輩の動きを真似して、ため息混じりに星空を見上げる。
「じゃあ久しぶりに飲むか」
静寂の中、明らかに自分の心臓の鼓動が速くなるのを感じた。
風向きが変わり、互いの前髪がふわりと揺れる。
たぶん、私は心底マヌケな狸のような顔をしているだろう。
「黒田?」
その声で、やっと私の顔が戻ってきた。
今日の先輩の声は、いつもより少し掠れていて甘く聞こえる。
「はい、もちろんです」
頭上の星がひとつ増えた気がした。
先輩とのご飯は会社近くの居酒屋がお決まりだ。
ガラガラと立て付けの悪いドアを開けると、カウンター席に案内された。
「凪と2人で飲むのいつぶりだよ」
不意に下の名前で呼ばれるのは心臓に悪い。
そんなことも知らずに、先輩はふにゃんと笑っていて、切れ長の目は今にも無くなりそうだ。
「大学以来です。先輩何回誘っても忙しいから捕まらないんですよ」
柄にもなく、頬をふくらせてみる。
「ごめんごめん、まさかサークルの後輩が同じ会社にいるなんて今でもちょっと信じられないよ」
照れるように笑ったあと、舌でペロリと唇を舐める癖はあのときから変わっていない。
「これ凪には言っておきたくて。俺、もうすぐ結婚するんだよ」
大きくなった風船が割れるのはあまりにも早かった。
店を出て、先輩と別れてとぼとぼと歩く。
さっきまで掴めそうだった星はまたどこかへいってしまった。
明日の天気予報は雨だ。
いつのまにか会社の前のベンチに腰掛けていた。
明るいハニーイエローのベンチは私には眩しすぎる。
「黒田先輩……?」
振り向くと、スーツを着崩した彼がいた。
「夜はちょっと肌寒いですね」
ジャケットを私にふわりと掛け、左隣に座る。
彼は疲れているのか、いつものシャキッと感はなく、口角はゆるんでいる。
1分ほど緩やかな沈黙の時間が流れた。
「え……、なんで」
なぜだか、涙がこぼれていた。
「あー、素敵な顔が台無しですよ」
1滴、2滴、もう止まらなくなり溢れ出す。
なぜ、彼の纏う空気はこんなにも穏やかで暖かいのだろう。
そして曇りひとつない瞳は、また私を蜂のように刺す。
「私は有川くんの思ってるような素敵な人間じゃないの」
肩を震わせ、声を振り絞る。
思ったより大きな声が出たことに自分でも驚いた。
彼は、目をクリっとさせた後で右下に目線を落とす。
「ありのまま、そのままでいいんです」
「気を遣いすぎる凪さんも、オリーブが苦手な凪さんも全部が他の誰でもなく、凪さんです」
ハッとした。身体中の血という血が巡り、全てが浄化されていく。
「ありがとう」
気づいたら、口がそう動いていた。
一頻り笑い、見つめ合う。
「今度はオリーブのピザ食べようかな」
ベンチから立ち上がると、さっきまでの夜風がぴたりと止んでいた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
