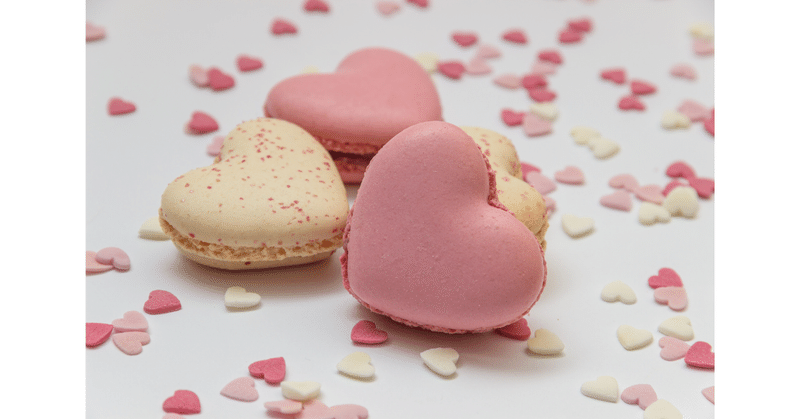
【掌編小説】夕暮れ公園での約束
「これ、チョコチップクッキー」
「お、ありがとう」
今日も一花は俺にクッキーを焼いて持って来た。はい、と渡されて俺はいつものようにそれを受け取る。そう、いつものように。これで、ちょうど一週間目だ。一花が俺に何かしらのクッキーを焼いて持って来るようになって。
最初は、突然だった。普段、メールなんてして来ない一花がくれた、一通のメール。
“樹の家の近くの公園で待ってます”
何だ急にと思って行ってみたら、夕暮れに染まった公園で一花が待っていた。そこで、はいと渡されたオレンジ色の包み。バタークッキーなの、と一花は笑って言った。そして渡すだけ渡して一花は、じゃあねと帰ってしまった。
家に帰ってから包みを開けて、バタークッキーをひとつ俺は食べてみて驚いた。それがすごくおいしかったからだ。売り物みたいだなと思った。だから俺はすぐに一花にメールを書いた。
“売ってるやつみたいにうまいよ。ありがとな”
と。
するとすぐに返事が来た。
“これから一週間、夕方に公園で待っててね”
と。
――そして、今日で一週間目だ。これまで一花はクッキーを俺に渡すと、すぐにじゃあねと言って帰ってしまっていた。だけど、今日は違った。俺に水色の包みを渡して来た後、じっと俺を見ている。何を言うでもなく。
「どうかしたか」
クッキーのお礼を言った後、俺は一花にそう言ってみた。
「あのね。お菓子って毎日食べると飽きるでしょ?」
不意に一花は言って、視線を俺の持っているクッキーの包みに下げた。「そうか?」
俺も何となく自分の手の中にある包みを見て言った。
「どんなに好きな物でも、飽きる時ってあるでしょ?」
「まあ、そうかもしれないけど」
「でもね、私ね。決めたの」
「ん、何を?」
「樹」
一花に呼ばれて俺が視線を戻すと、そこには夕暮れのオレンジ色に染まった真剣な表情の一花がいた。
「好きです」
そう言って、にこと笑った一花。
俺は、こんな大人の表情をした一花は知らなかった。
一花とは家が近所で、同じ小学校、同じ中学校に通って。時々、帰り道の途中で一花を見かけた。けれど、小さい時のように話しかけられなくて。たまに、挨拶をするくらいになって。
目の前で微笑む一花は、夕焼けに包まれていた。そのせいだろうか、まるで見たことのない一花がそこにいる。
「これから、一緒の時間を過ごしてほしいです」
一花はそう言って、すっと右手を差し出して来た。
俺は、自分の心臓の音がうるさいと思いながら、一花の手を握った。
「これから、よろしく」
すると一花が更に笑顔になった。
一花の手は小さく、温かかった。
「これ、一緒に食べるか」
「うん」
俺と一花は公園のベンチに座って、一花の作ったクッキーを食べた。
クッキーは、とても甘い味がした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
