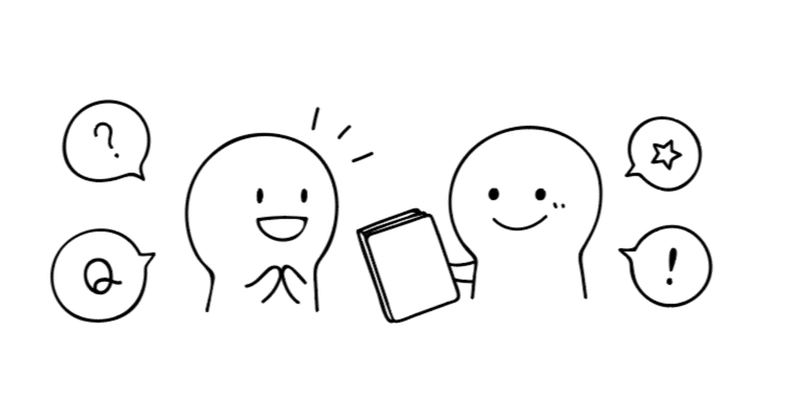
青春生き残りゲーム(2)
ウナギ少年が住む地域は田舎の割に教育感度が高く、中学校の同級生は120人ほどおり、そのうち20人以上が後にGMARCH以上の学力の私大や国公立大に入学するという状況でした。
中学校の学力テストでも、県平均を毎回20〜30点上回る地域だったのです。
だからこそ、自営業だけあって体裁を異様に気にする両親は、我が子を勉強させることに必死になっていたのです。
その多少の甲斐もあって、うなぎ少年も普段はともかく、テスト期間中は夜の12時を超える程度は勉強し、そのやり方も自分なりの工夫を盛り込んでいきました。
母の肉体言語を伴うスパルタ教育のおかげで地頭もそこそこ良く、学校の先生には良い子ちゃんぶっていたため、テストでも内申でもなかなか高い成績を取っていました。
すると、たまに勉強を教えて欲しいと言わるようになるわけです。
人に頼られると嬉しいものですね。
僕はそこで初めて頼られることの喜びを知ったのです。
それが、実は今の仕事に生きてくるわけですが、当時のウナギ少年はその仕事をするようになるだろうとは考えもしませんでした。
前回、書きましたが、中学校には小学校よりも増したヒエラルキーに繋がる要素が存在します。
その1つが、学力によるものです。
内申や順位といった数字が出ることによって、進学する高校の目星をつけていく指標となるわけですが、一歩間違えば、格付け差別の指標になりかねません。
しかしながら、学力では人生の幸福度は決まりません。
学力がいくら高くても、就職できなかったり、人間関係につまづいてしまったり、借金を背負わされたり、身内の介護で出世の道が断たれたりなどと不幸になる要素はどこにでもあります。
学力とは、あくまでもそういった不条理をなんとかして解決に導くために使う力の一部であるだけなのです。
本当に大切な力とは、相手に自分の考えを伝え折り合いをつけたり、人と人を繋いだりする力。
つまり、対人折衝能力だと僕は考え、それを信じています。しかし、なぜか学校ではそこら辺を詳しく教えてくれないようなんですよね〜。
そして、ウナギ少年は、哀しいかな、勉強できるが正義、できないが悪という考え方に染まっていったのです...。
今日はこの辺にしておきたいと思います。
読んでくださいましてありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
