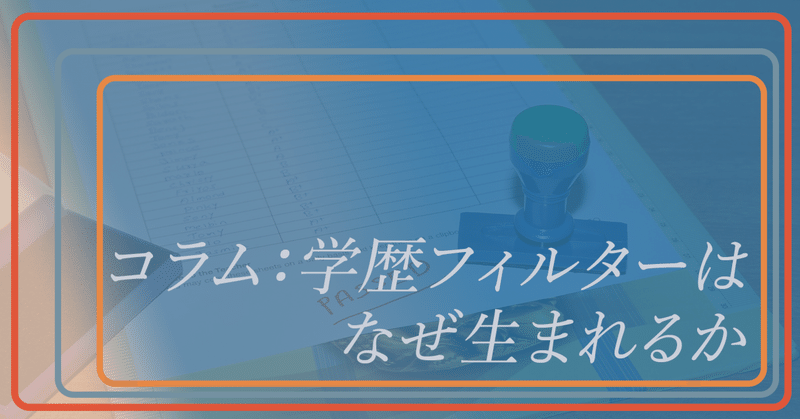
「頑張れば報われる」と信じている人へ
〇はじめに
今回もUni.Newsをご覧いただきありがとうございます。
学生生活で困ったら、「Uni.News」を見れば迷わない
そんなメディアをお届けしていこうと考えておりますので、楽しみにご覧ください。どんな人が書いているのか気になる方はこちらも参考にしてください!
■今回の記事の対象
努力と才能の関係について興味がある全ての人
■この記事を読み終わったら分かること
・「やればできる」は本当か
・学歴フィルターに対する1つの考え
1.大東亜以下⑨
2021年12月7日、就職情報を提供する「マイナビ」が一部就活生に「大東亜以下⑨」というタイトルのメールを誤送信して、物議を醸しました。
マイナビは学生を「大東亜以下」と「それ以外の大学」の2つのグループに分けたことは認めたものの、「学歴によって、一部の学生が有利になるようなことは行っておりません」とし、⑨という数字は9人のアドバイザーがつく、という意味合いだったと説明しています。
真偽はわかりませんが、偏差値帯によって学生を区別していたことは事実で、この区別がいわゆる「学歴フィルター」であるというのが物議を醸した一番の要因でしょう。
さて、「学歴で学生を区別するのはフェアではない」という意見がある一方で、「採用する主体=企業側から考えると、学歴フィルターの存在は当然である」という意見も少なくありませんでした。
つまり、高学歴の学生の方が企業が求める人材である確率が高いというのです。企業側としても採用するからには入社後に活躍してもらわないと困る。だから、できるだけ優秀な学生から採用しよう、というわけです。
その背景には、「少なくとも難関と言われるレベルの大学に入れるだけの努力をしたのだから、企業に入ってからもきっと同じように努力をしてくれるだろう」という推論が働いています。
ここには、暗黙の了解があります。即ち、「成功は努力の結果であり、失敗は怠惰の結果である」という前提です。
「あなたは名門と言われる大学に入れなかった。それは、あなたが努力をしなかったからだ」という了解であり、「あなたは名門と言われる大学に入った。それはひとえにあなたが努力をしたからだ」という了解です。
これはしかし、一見すると全く正しいように思えます。実際、そうした側面は多分にあるでしょう。難関大学に入る学生は、程度の差こそあれ間違いなく入試突破のための努力をしたはずだからです。
2.やればできるという罠
しかし、この考え方には疑問が浮かんできます。努力をすればみんな成功するのかという疑問です。そんなことはありません。
お笑いコンビ「ティモンディ」の高岸さんのギャグに、「やればできる」というものがありますよね。彼は恵まれた体格を持っていて、今でも130km/hの速球を投げることが出来る。以下は「アメトーーク!」の中で、そのギャグが披露された一幕です。(以下敬称略)
高岸:「蛍原さんでも130km/h投げることが出来ます!」
蛍原:「ちゃうて!おれは無理や。」
高岸:「投げられます!僕と同じように野球を好きになって練習すればいいんです」
岡田斗司夫さんはこの彼のギャグの面白さを次の解説しています。即ちそれは、「生まれつきの格差とか才能を否定して、努力の大事さだけを説くことの嘘臭さ」にある、と。
これ、誰が見ても可笑しいですよね。だって皆、同じように努力したって130km/hのボールを投げられるようになるわけないことはすぐわかる。どうしたって、生まれつきの体格とか運動能力とか、あるいは野球を教えてくれる優秀な指導者がいるような恵まれた環境とか、もう埋めようのない格差が存在することは明らかです。それを無視して、「努力すれば」「あなたにとっての130km/hが出る」と言ってくる理不尽さに面白さがあるわけです。
でも、これって受験勉強と何が違うんでしょう。
先天的に学習能力に差があるのかはまだ議論が必要なところですが、少なくとも環境面が結果に大きく関わるという点では同じです。
あなたたちが今日「がんばったら報われる」と思えるのは、これまであなたたちの周囲の環境が、あなたたちを励まし、背を押し、手を持ってひきあげ、やりとげたことを評価してほめてくれたからこそです。世の中には、がんばっても報われないひと、がんばろうにもがんばれないひと、がんばりすぎて心と体をこわしたひと...たちがいます。がんばる前から、「しょせんおまえなんか」「どうせわたしなんて」とがんばる意欲をくじかれるひとたちもいます。(平成31年度東京大学学部入学式 祝辞より抜粋)
つまり「努力できる」というのは当人だけの功績では決してない。「努力できる」の裏にそう思わせてくれるだけの恵まれた環境(例えば塾や予備校で我が子を学ばせる裕福さ、頑張りを褒めて認めてくれる家庭環境)があったからこそ、成功することができたのだ、というのです。
だからこそ、自身の成功を自身の努力だけのおかげだと考えないでほしいというのが上野さんの主張です。成功の裏には運の良さも間違いなく存在していたことを自覚し、謙虚に自身の運の良さを社会に還元しなければならない、と。
3.能力主義がなくならない理由
翻って、学歴フィルターの件に戻ります。先ほどの理屈で言えば学歴によって与える就職情報に差をつけるというのは全く平等ではありません。
なぜなら、あまり偏差値の高くない大学にいるのは、必ずしも彼彼女が怠惰だからとは限らないからです。単に置かれた環境が恵まれていなかっただけという可能性があり、その場合当人には何の落ち度も無いからです。
それなのに、未だに「学歴フィルター」が存在する(ように思われる)のはなぜでしょう。
企業側のリスク分散のため、というのもわかりますが、私は「貴方が成功したのは、単に運が良かったからだ」と言われることに耐えられないから、と言うのが大きいのではないかと思います。
名門と呼ばれる大学を卒業し、一定の社会的地位を築いた人にとって、「やればできる」というのは非常に気持ちよく響く文句です。「自分が成功したのは自分が頑張ったからだ」と思えますし、「だから自分の成功は自分が享受すべきもので、他の人に無暗に奪われてはいけないものだ」というロジックに繋がります。
そんな人に「貴方が成功した要因には貴方の努力もあるだろうが、運が良かったからという側面も大きい」と伝えたら、決して良い気持ちはしないでしょう。だって、「頑張った」のはおそらく本当だから。それまでの自分の努力を否定されたような気持ちになりますよね。
実際、能力主義的な社会は、環境や才能に恵まれている人にとっては恐らく楽しくて仕方がない社会です。結果を出せば認められてチヤホヤされて、その功績を独り占めすることが認められる。あなたが功績を残せたのはあなたが頑張ったからだねという捉え方をされる。
同時に環境や才能に恵まれなかった人には物凄くしんどい社会でしょう。これが江戸時代のような士農工商がはっきり分かれる身分制社会であればここまでしんどくはなかったかもしれません。仮に成功できなかったとしても、それは自分の能力の低さのせいではなく、単に生まれが悪かったから、という言い訳が用意されていましたから。能力主義社会はなまじ機会の平等を謳っている分、劣等感から逃れることはよりいっそう難しい社会だと思います。「機会は与えられているのに、自分の能力が低いせいでそれを活かすことが出来ていない」という考え方になりますから。チャンスがないという言い訳が通用しないわけです。
しかしチャンスが平等に与えられていても、結果は平等にはなりません。どうしたって生まれつきの能力や所与の環境などの違いが結果に影響を与えるからです。これは仕方のないことです。問題なのは、この能力や環境の違いをまるでないもののように扱い、反対に努力を過剰に評価している点にあるように思えます。
4.クジ引きで受験選抜
といって、ではどうしたら良いのか、能力主義に代わる仕組みとはどんな仕組みか、を考えるのは容易ではありません。マイケル・サンデルさんの著書「実力も運のうち 能力主義は正義か?」では、「一定程度の学力の足切りをしたうえでのクジ引き入試選抜制度の導入」や「金融取引への課税の強化」などが挙げられていました。
私がまず思ったのは、「受験をくじ引きにしたら皆努力しないんじゃないか?」ということです。頑張ろうが怠けようが結果が変わらないのなら、努力する必要もないのでは?と考える気がする。そして努力しない怠惰な自分が現れる気がする。それはまずいのでは...?
しかし同時に思ったのは、「なぜ頑張らなきゃいけないんだ?」ということです。無意識のうちに「頑張らなければいけない」という前提を作ってしまいましたが、これこそ能力主義に染まった思考のような気がします。
(余談ですが、『がんばれ』を英訳するのは難しいそうです。『Good luck』が近い気はしますが、後者は『人事を尽くして天命を待つ』的な、結果は自分の頑張りではなく最終的には神様の一存で決まるのだよ、というニュアンスが感じられる点で、前者より能力主義的色合いの薄い言葉のような気がします)
「頑張れば評価されるから頑張る」というのは、「評価されないのなら頑張らない」とイコールです。でも本来、例えば勉強なんかは競争とか評価とは無縁の分野のはず。「自分が学びたいことがあるから学ぶ」というのが学びの本来の姿であるはずで、「Aくんより良い点数を取って皆に認めてもらいたいから学ぶ」ではないはずなんです。
でも、努力して結果を出してそれが評価されるプロセスは正直とても気持ちが良くて楽しくて、自分にとって物凄いモチベーションです。頑張って結果を出したら自分自身が認められて褒められるというプロセスに慣れすぎて、結果を出しても「それは運が良かったから」と心の底から考えることが出来ない。
そう考えると、いっそ「くじ引きで受験選抜」くらいラディカルな反能力主義的社会にした方が良いのか...?そういう社会で育てば、競争原理以外の健全なモチベーション(学びたいものが有るから勉強して大学に行くんだ!みたいな)が生まれて、「学歴フィルター」のようなものはなくなるような気もする。でもなんだか今までの自分の努力が否定されるような気がして嫌だな...
きっとそんなことをグルグル考えて現実的な解決策として生まれたのが上野千鶴子さんの「自身の成功の裏にある幸運を自覚し、幸運を他者に還元するように促す」というアクションなんだろうなと思います。(何かいいアイデアがあればコメントで教えてください...!)
5.おわりに
正直このユニニュースというメディア自体も、「あなたたちも頑張れば私たちみたいになれる」的トーンが強いなと感じるときがあります。まあ色々な大学生活があって然るべきだけど、もし就活頑張りたいとか、資格取りたいとか、留学行きたいとか、そういう人がいるのなら、参考にしてね、くらいのテンションの方がちょうど良いのかな。
なんだかよくわからないコラムになってしまいましたが、いま私に出来るのは「恵まれている者には課税を!!」みたいな肩ひじ張ったトーンの社会変革ではなくて、自分の個人的な体験を発信して、どこかの誰かがちょっとだけ救われるみたいな、ささやかな情報発信なのではないかと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
