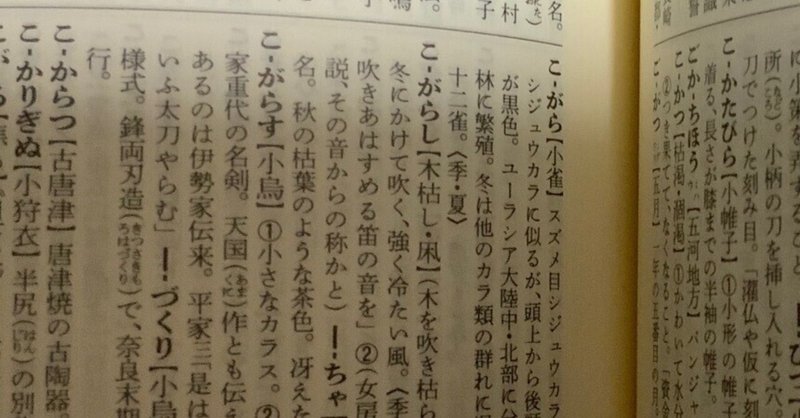
コトバアソビ集「凩と凧」
久しぶりに地元に帰った裕一は、昔遊んだ河原へ来ていた。
草が繁る斜面を段ボールで滑った思い出がある。尤も段ボールで滑っていたのは裕一だけで、同級生は草用の橇を使っていた。草滑りはこの辺りの遊びの定番だったから大抵の子どもは持っていた。千円未満から二、三千円の商品を買ってもらえない裕一は貧乏だと思われていたし、事実そうだったに違いない。ゲームや高い玩具を買ってもらった記憶が無かった。
河原には別の思い出もある。
小学5年生の冬休み前、授業で凧を作った。竹籤とビニールで作る簡単なものだ。ビニールに好きな絵を描いて、組み立てた竹籤に貼り付ける。竹籤に張りを持たせて組むのが難しく、裕一の凧はあまり飛ばなかった。低空をへろへろと曲がって飛んだ後で地面に激突した。
(あんまり良い思い出は無いけど、懐かしいもんだな)
夕日は昔と変わらず美しい。
「裕一」
土手の下から声がした。
「お?高橋?」
同級生の高橋孝義。成績優秀で運動神経も良く、クラスで目立っていた男だ。笑いながら土手を登ってくる。
「なっつかしいなぁ。お前全然帰って来ないじゃん」
「忙しくてな」
「俺今、集金の帰り」
高橋は土手の下の原付を指差す。
「さっき商店街で、お前が帰ってるって聞いてな。でも今夜戻るんだってな」
「明日朝イチで出張なんだ。飛行機の時間があるから」
「そうかぁ、都会で頑張ってんだな」
少し羨ましそうだ。高橋は実家の酒屋を継いでいる。本当は地元を出たかったのかも知れない。
「凧あげのことを思い出してたんだ」
裕一が言った。
「お前の凧が一番高く飛んだよな。お前は昔っから、何やっても上手かったもんなぁ。女子にもモテて。嫁さんも美人だって聞いたぞ」
と高橋を揶揄う。
「凧か・・・」
孝義はあまり嬉しくなさそうだ。
「あれはズルだよ」
と言った。
「全部ズルだったのさ」
と。
孝義は昔のことを話した。よく上がった凧は家で父親が手を加えたものだ。県で賞を獲った夏休みの自由研究は母親が手伝ってくれたものだった。
「俺、随分甘やかされてたんだよ。割と今もだけどな」
と苦笑いする。大した家業でもないのに跡取り跡取りと期待されて、お前は親孝行な子だと刷り込まれて、親の言うままに酒屋を継いだ。地元に残ってくれたご褒美だと車を買い与えられ、可愛い嫁さんまでが親戚の紹介だと言う。
「・・正直、昔は裕一のことを可哀想な奴って思ってたんだ。お前のお母さん厳しかっただろ。シングルだったし、お金もそんなに無いのかなって」
「あー、まぁホントだしな」
「お前のお母さん、俺たちからすると厳しいおばさんって感じでさ。あ、悪ぃ。でもな、大人になったらそれが正解だったんだってしみじみ思うんだ」
「なんで」
「俺みたいに、欲しがる前に何でも与えられてた奴はさ。いざ自分で進路を決める時になると分かんないんだよ、自分のやりたいことが。所帯を持ってから気づいた。まだ居ないけど、子どもが出来たら俺はどんな父親になるだろうと思うとな」
「でもお前は頭が良い奴だから」
「だからぁ、それがハリボテだったんだって」
孝義は少しヤケクソ気味だ。
「草滑りの段ボール。お前、ガムテで補強したり裏に蝋を塗ったり、すげぇ工夫してた。俺らなんて壊れたらすぐ新しいの買ってーだよ。それで何の疑問も無かった。結果どうよ。お前はでっかい建築会社に入ってさ。今何作ってんの。ダム?橋?地図に残るような仕事してんだろ。お前の母親の教育は正しかったんだ」
裕一は答えようがない。
日が落ちて暗くなっている。孝義はハッとした。
「悪い。行く時間だろ?」
「まだいいよ」
裕一は嘘をついた。
嫁とうまくいっていないと孝義は嘆いた。
「せっかく貰ったんだから大事にしようとは思うんだけど。向こうも親戚に押されて俺んとこ来たみたいで。本当は他に好きな奴が居たって、泣かれた」
まだ独身の裕一には慰めようもない。孝義もすぐに、忘れてくれと言った。
「ごめんな。集金って嘘でさ。嫁と喧嘩したばっかなんだ」
普段顔を合わせる地元の人間には言えないのだろう。だから裕一が居ると聞いて、探しに来たのかも知れない。
「俺の母親が何だって?」
裕一は話を逸らせた。
「厳しい凩の方が、凧は高く上がるってこと」
孝義は空を見上げた。
「お前の母親みたいに、甘やかさなくて厳しい親の方が、子どもにとってはいいんだ。俺の親なんかそよ風だよ、ぬるい奴。俺の凧は高く飛んだけど、俺自身は飛べなかった。地べたを這ってる」
「自分のことそんな言うなよ」
「ほんとごめんな、愚痴って」
「いいけどよ」
裕一は言葉を探した。
「なぁ。田舎も都会もどっちがいいってことないだろ。俺は、お前が頭良いのは本当だと思ってる。我慢せずにやりたいことやれよ」
「今さら」
「今さらって、俺らまだ30代だろ。70でスカイダイビングやってるジジイもいるぜ。カッコいいじゃん」
裕一は頭を掻く。
「嫁さんのことはアドバイス出来んわ、スマン。女心は分からん」
二人は笑い合って別れた。
裕一はタクシーを呼んで駅まで行った。予定の便は逃してしまったので切符を買い直す。スマートフォンを見ると着信履歴があったので掛け直した。
「あーおかん。いや、まだ乗ってない。知り合いに会って。え、見送りに来てた?悪い悪い。うん・・」
母親の声を聞く。
「そう。今度はちょっと長くなるわ。次いつ帰れるか分からん。だから元気でな。メールは出来るけど。子ども俺しかおらんのに、そばに居られんでごめんな。あー・・・あとさ・・・」
真顔になった。礼を言おうと思った。厳しく育ててくれてありがとうと。
だが、口から出たのは違う言葉だった。ただシンプルに。
「じゃ。行ってくる」
電話の向こうで厳しい母親が、優しい笑みを浮かべた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
