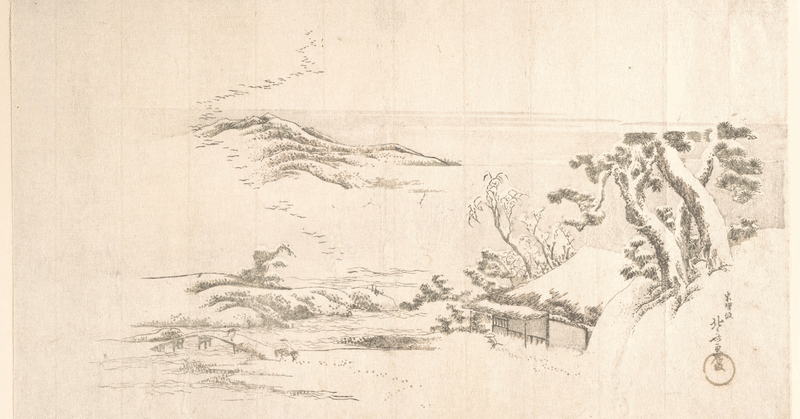
「面」(原作:川端康成『山の音』)
及川家の嫁の沙ゑは大人しい。近隣の者に「お人形さん」と言われる。胡粉を塗ったような白い顔に切長の目と小さな鼻と口を持つ。僅かに唇だけを動かせてものを言う。
人形の例えには揶揄も含まれている。肩も腰も細い。肉感のたっぷりとした御所人形ではなく、漉いた紙で拵えた紙人形の躰だ。
口さがない男衆が
「あれじゃ抱く気になれんわなぁ」
と陰口を叩く。
及川の若当主に囲い者が居るのは周知のことだ。
若当主は宗一郎と云い年齢は三十。妻の沙ゑは二十歳。妾は三十四。
宗一郎は役所勤めを終えると妾宅へ寄る。妾は元々飲み屋の女で、客として通っていた宗一郎が気に入って小さな家を持たせた。
妾はまだ飲み屋に籍があり、宗一郎が来ない日は店に顔を出す。
「よう、妙ちゃん。久しぶりだねぇ」
「ごめんネェ。だってさァ、最近ずっと旦那が通って来てたから」
「あっはっは、どっちが女房か分かりゃしないな」
沙ゑを侮る笑い声が満ちる。
及川家は明治の頃に宗一郎の曽祖父が商売を興して成功したが、父親の代で落ち目となり、負債を抱えぬうちに始末をつけた。先を見越していた父親が息子に役所勤めを勧めたのは英断と言える。
家には宗一郎夫婦と隠居した舅、姑が四人で暮らす。子はいない。妾宅から戻ると自室に引っ込んでしまう息子を見て姑は
「沙ゑさん、あなたもね。玄関でお帰りなさい、と嬉しそうに迎えれば可愛げが有るというものですよ。そんな仏頂面してないで」
と嫁を窘める。
「申し訳ありません」
舅は
「沙ゑさん、あんたもっと食べて太ったが良いな。こう言っちゃなんだが、そんな薄っぺらい体じゃ男ってもんは」
不躾に沙ゑの体をジロジロ見て笑う。
「申し訳ありません」
両親は妾を囲う息子ではなく嫁を責めた。嫁に対して遠慮がないのは、沙ゑの実家が弱い為もあった。
元々沙ゑを見つけてきたのは舅だ。
商売人の家柄に引け目を抱いていた舅は、知り合いに
「著名な学者の娘なんだが父親が死んで、病気の母親を抱えて困っている」
と聞き、それなら息子の嫁にと引き抜いた。母親は病院へ入れられ、実家は取り壊され、沙ゑは逃げ場のない体になった。子を産めば盤石な立場と成れそうなものだが、夫が子作りをせぬからどうしようも無い。宗一郎は元々精が薄く、官能的な妾に誘われてやっとその気になる位なので、妻にまで挑む余裕は無い。親に孫を急かされてたまに手をつける程度だ。相手を悦ばせようとする気がないのだから、営みは実に淡白なものだった。
「ありがたいねぇ、お前のおかげでこんな良い病院に入れて」
見舞いに行くと母親は喜ぶ。感謝を借りた呪文は沙ゑを縛り付ける。
「母さんからは何も出来ないけど、及川さんのお家にくれぐれも御礼を言っておいておくれね」
縛りつけたまま母親は鬼籍に入った。
誰も頼れぬ身となった沙ゑは、それでも特に落ち込む様子も見せず、水辺の葦のように静かな佇まいで居た。そんな嫁を舅たちは
「可愛げがない」
「大人しそうに見えて情が強い」
と言った。沙ゑをそうしたのが自分たちだとは気づいていなかった。
舅は自分を神のように崇めよと言い
姑には奴隷のように扱われ
夫には顧みられず
妾に馬鹿にされ
母に縛られ
近隣の者に侮られ
感情を引き算し
能の役者のように心に面を被ることで
自分を守り続けてきた沙ゑが
可愛げのない嫁になったとて
義実家という他人に責める権利があるのか
父親譲りの知識と教養が
沙ゑの心が剥き出しになるのを守ってくれた
大人しい振る舞いは
自分を守る術であった
沙ゑはその後も義実家に仕えた。
酒の好きな舅は早くに脳溢血で逝った。気弱になった姑は息子へ媚を売り、味方につけようと沙ゑを益々邪険に扱った。やがてボケて寝たきりになったが、沙ゑはまめまめしく世話をした。姑は沙ゑに感謝の言葉ひとつ言わぬまま死んだ。
宗一郎が親の財産を継ぐなり、妾の妙が牙を剥いた。沙ゑを追い出して自分を正妻に迎えろと言うのだ。妙には宗一郎を尻に敷いている自負があった。強く押せば要求は通るだろうと高を括っていた。だが宗一郎は別れを切り出した。
慌てたのは妙である。図々しいことを言ってすまなかったと詫びたが、宗一郎の意思は変わらず、小金を渡して妙と縁を切った。妙は時の流れを見ていなかった。及川の若当主を魅了した容色は既に衰え、関係が続いたのは惰性でしかなかったのである。
夫婦の間に、ほんのひと時の静かな暮らしが訪れた。
宗一郎は壮年を迎えて役所でもそれなりの地位を得ていた。
仕事を定時で上がって来る。帰れば大人しい妻がいる。この頃何を思ってか、宗一郎は時折沙ゑに触れてくるようになった。今までの贖罪なのか、老いが見えてきたことへの焦りか。沙ゑは黙って受け入れた。しかしそれも仮初のことで、宗一郎はすぐに飽きた。何回かの共寝で義理は果たしたと言わんばかりに、差し伸べた手はすぐに引っ込んでしまった。二人は老いていき、宗一郎は六十で死んだ。
他に人の居なくなった家で、沙ゑは花を活けている。綺麗に整った花を床間へ置く。時の経過をひとり噛み締めている。人生とは何だったのだろうと。
堪え続けて、悪意が行き過ぎるのを待ち続けて、沙ゑは笑うことを忘れていた。泣くことも怒ることも。自由とひと財産を得ても解放感は無い。籠の鳥が飛ぶことを忘れたように沙ゑの心は羽ばたかない。
沙ゑはひとりになっても毎日着物を着て、掃除して柱や床を磨き、遊びに出かけることもなく、日々の買い出しに行く他に人と交わらない。
ここに至ってやっと近隣の者は
「流石に学者の娘さんだけあって立派なものだ」
と褒めるようになった。
人形のように暮らした沙ゑは五十の歳でもまだ肌艶は良く、
「何処どこのご隠居が後添いを探しているよ」
と口をきく者も居たが、沙ゑはかぶりを振った。周囲はそれを貞操と見た。
やがて沙ゑは人生とは何だったのだろうと考えるのをやめた。
(何でもなかったのだ)と。
衣食住に困らなかった。それで十分だ。
笑うことを忘れたとて
心に被せた面が貼り付いて同化しても
誰をも愛さず愛されず
そもそも愛など生きるのに不必要で
こんな自分が子どもを産まず良かったと
それだけは安堵して
(ああ、耳を澄ませても)
何も聞こえない。誰も泣いていない。
誰も知らぬまま沙ゑは朽ち果てた。
乾いた骨は粉になって舞い散り、何も残らなかった。
近隣の者が不在に気づき、警察が家に入った。家の中はきちんと片付いていた。踏み込んだ警官のひとりが僅かに足の裏にざらりとした粉を感じたが、改めて触れてみると何もなく、今の感覚は何だったのだろうと不思議に思った。及川の遠縁にあたるものがやっと見つかり家を引き継いだ。
「造作がしっかりしてますねぇ。まだ住めそうだ」
ひとり者だという青年がそこへ移り住んだ。
「たまにね、誰か居るような気がするんですよ」
少し変わり者の青年はカラカラと笑う。
行方不明者が出た家だが気にしないようだ。
物書きだという青年は面倒見の良い女とくっついて子も産まれた。及川の家に数十年ぶりに産声が響いた。小さな足音がパタパタと弾み、母親の叱る声が後を追いかけ、変わり者の父親がカラカラと笑う、賑やかな家になった。
ある日子どもが襖を蹴破って穴を開けた。
「ありゃありゃ、しゃあねぇなァ。どれ、俺が貼り直してやるよ」
「頼めるかい?あたしは手が離せなくて」
「いいさいいさ。人に頼むと金もかかるしな」
元青年は襖の枠を外し、表面の紙を剥がす。
「こいつぁ・・」
襖の下貼にびっしりと文字が書かれていた。沙ゑの日記だ。
誰にも言えない思いが綴られていた。
「フゥン・・・綺麗な手蹟だね・・」
流麗な昔の文字を元青年は器用に読んだ。丹念に剥がし、文箱にしまった。
「及川先生、小説を書かれる際に気をつけていることはありますか?」
「そうねぇ。女の人は、不幸にならないように書いてます」
「不幸な方が話が面白くても?」
「ええ、ま。小説の中位は幸せでいいでしょう」
「(どうもこのセンセイの話にゃキレが無いんだよなぁ・・・)先生はお優しいですねえ(こりゃ新作も売れねぇな)。では取材はこの辺で。有難うございました」
もしも古本屋で及川何某という作家の小説を見たら手に取っては如何だろう。
女の人が不幸になるような話は、決して無い筈だから。
及川何某は筆者の父である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
