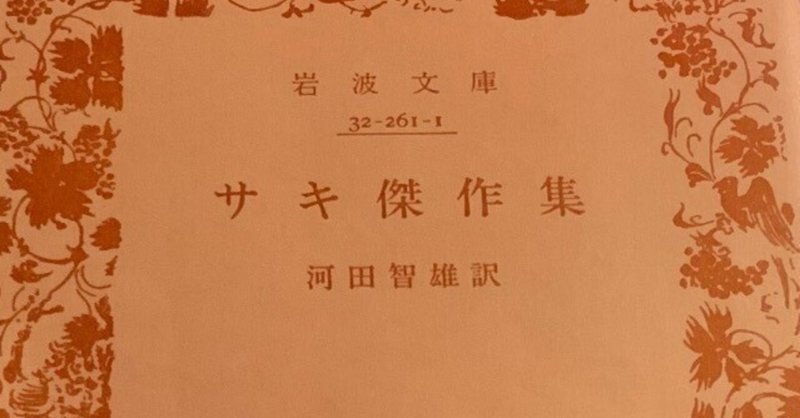
「継承」(元にした作品:サキ『スレドニ・ヴァシュター』)
「かみさま、かみさま、どうか僕のお願いを・・」
祠の中で寝ていた楠雄は子どもの声を聞いて目覚めた。
(・・まだ、お参りする子どもなんているんだな)
楠雄の実家は田舎の地主で、山を幾つも持っている。裏山の祠は何代か前の先祖が建てたと父から聞いた。祠の奥にはひとが横になれる位の隠れ場所がある。
大学を卒業した楠雄は就職が決まらず実家へ帰ってきた。今は家業の林業と不動産経営を手伝っている。しかし田舎特有の閉塞感に息苦しさを感じることもあり、そんな時は祠に隠れて一服する。
子どもは楠雄が潜んでいることには気づかないようだ。話を聞けば子どもは地元の小学生で、学校で虐められているらしい。
「どうか、どうかあいつを懲らしめてください。僕は〇年〇組の〇〇です、相手の名前は・・」
神様は素性が分からぬ相手の願いは聞かないと言われている。この祠には絵馬を売るような社務所はないから、こうして口に出すのだろう。
楠雄は昔を思い出した。自分も幼い頃祠にお参りしたことがある。この子のように泣きながら・・
子どもは祈りを終えて帰って行った。楠雄は考えた。
祠は自分の先祖が建てたものだ。子孫たる自分が祈りを聞いたのも何かの縁だろう。
楠雄は子どもの願いを叶えることにした。
数日後、地元の小学校で騒ぎが起きた。
ある児童が登校すると下駄箱に死んだネズミが入っており、『悪さをするな』と血で書かれた手紙も置かれていた。
担任がクラスを対象に聞き取り調査をした結果、裏で行われていたいじめが発覚し、その首謀者だった児童は転校して居なくなった。
ネズミは楠雄の仕業である。
(良いことをした)
と思った。
以来、祠に置かれた賽銭箱に手紙が入るようになった。内容は復讐を願うものばかり。
楠雄は賽銭箱を開け、中の手紙を持ち帰るのが日課となった。町の中で小さな事件が増えた。謝礼として賽銭箱に現金を入れる者も居て、楠雄の小遣いになった。金が欲しい訳ではないが、感謝されるのは悪い気はしない。
近頃楠雄が熱心に山の見回りに行くので、父は満足気だ。
後から話を聞かれても困らぬよう、ちゃんと見回りをしてから祠に寄る。手土産も忘れない。
「母さん。適当に山菜採ってきたけど使えるのある?」
「どれどれ。ああ、このキノコは毒。でもこっちは美味しいんだよ。天ぷらにしようかね」
そのまま台所に立って母を手伝う。
楠雄は山道を歩いて体も引き締まり、動植物に関する知識も増えていった。
「お前も顔つきが変わったな。山の顔になった」
父に言われた。
だが楠雄は自分が変わった本当の理由を分かっていた。
崇められること。
願いを叶えること。
人の業を代わりに背負うこと。
その自負が楠雄を変えたのだ。
暫くすると、楠雄の顔つきはまた変わった。
「楠雄。部屋へ来い」
ある晩、父に呼ばれた。
父は畳に地図を広げ、所有する山について具に教えた。
「公の地図には載っておらん滝がある。沈んだものは浮かんで来ない」
「この辺りには熊が出る。昔ひとが喰われた」
「母さんに野草のことを習え。同じ植物でも葉は薬になり、根は毒になる」
楠雄は黙って聞いていた。
父は知っているのだ。楠雄がひととして一線を超えたことを。
「父さん」
「うん?」
「近頃、麓で事件が増えましたね」
「そうか。誰も、何も言って来んが」
「そうですか」
「警察に知り合いが居る。何かあれば言ってくるだろう。ところで、少し前に小学校で転校した子どもがいたが。あれの親はうちの事業の邪魔になる男でな」
「そうでしたか」
「お参りしたのは遠縁の子だ」
楠雄は顔を上げ父を見た。平然としている。
「学校にも知り合いは居る」
「父さん」
「うん?」
「昔、僕も祠にお参りしたんですよ。僕を産んだ母さんのことで」
「そうか」
「見たんです。母さんが、他の男の人と。あの母さんは実家に戻ったと聞きましたが、その後どうなったのでしょう」
「さあな」
楠雄は別れた母を恋しがることはなかった。当時十歳の楠雄の目には、他の男と交わる母の姿は醜く見えた。新しい母は賢く優しい人で、楠雄はすぐに懐いた。昔の母は忘れた。
楠雄が祈ったあの時、祠には誰が居たのか。
暫くの間二人は黙った。
「楠雄。山を継げ」
楠雄は頷いた。それは全てを継ぐということだ。
自分もいずれ結婚するだろう。子どもも生まれるだろう。生まれなければ養子を取れば良い。
祈りを捧げられた時、人の願いを叶える時、楠雄は自分を動かす何かを感じた。良いことをした、悪いことをした、という感覚は既に無い。人は運命の波に乗っている。自分は僅かに舵に触れるだけだ。
楠雄は自分の部屋に戻り、布団に入った。山の音が聞こえる。
山と一体になる感覚を味わいながら、静かに目を瞑った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
