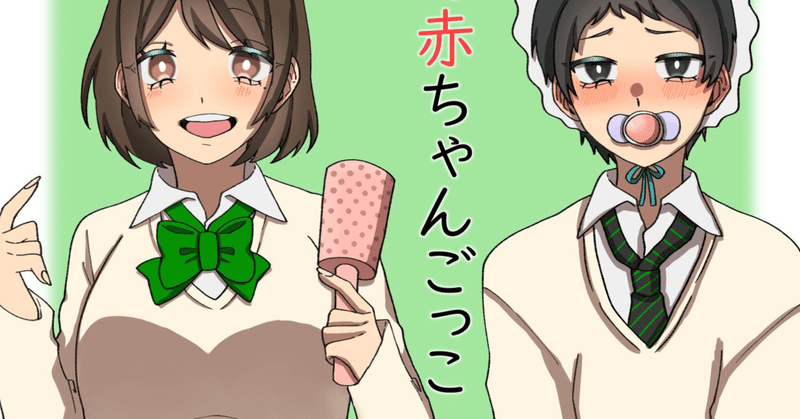
愛と正義の赤ちゃんごっこ【8ーB】
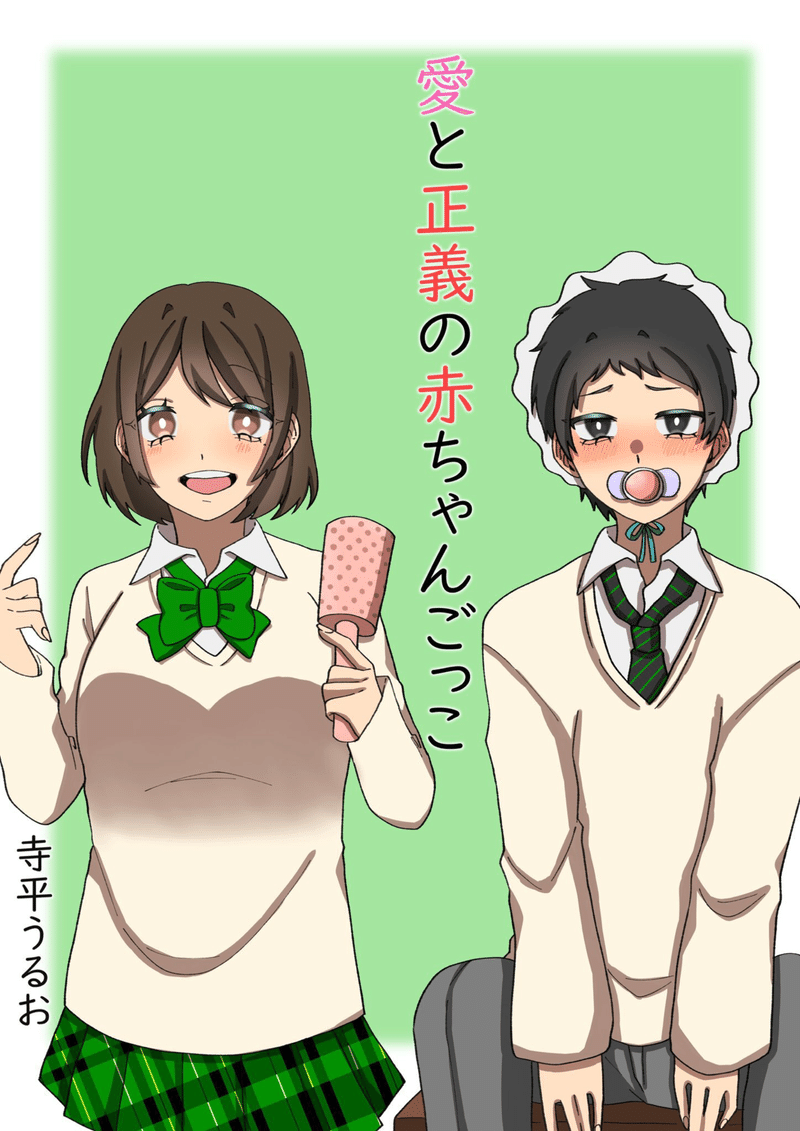
ふうっと息をつきながら、ぽっこりふくらんだお腹をさする。速水家のシチューが、あまりにもおいしくて食べすぎてしまった。空いた食器をキッチンに持っていき、一実のお母さんにお礼を言ってからリビングにもどる。
「ごちそうさま。そろそろ帰るね」
ソファーに座ってテレビを見ながら、一実(かずみ)がふり返らずに言った。
「結局晩メシ食いにきただけだったな」
なにも言い返せない。
「おジャマしましたー」
荷物をまとめて玄関に立つと、ドアが開いて一実のお父さんが顔を出した。
「こんばんは」
私があいさつをすると、おじさんは「あ、こんばんは」と言ってかたまってしまった。もう何年も会っていなかったから、忘れられていてもしょうがない。
「私、愛です。中学のときからお世話になってる」
「愛ちゃん……ああっ、愛ちゃん!」
まっ赤な顔で「ふへへ」と笑うおじさん。
「それじゃ私、失礼します」
「これから帰るの? もう遅いよ?」
おじさんはへらへらしながら、たよりない足取りで靴を脱いだ。
「いえ、そんなに遠くありませんから」
「ダメダメ、こんなかーいい子が、夜道なんて歩いたぁダメ」
ちょっとロレツのまわっていないおじさんのおことばに甘えて、今夜は泊めてもらうことにした。
おフロに入って部屋に戻ると、ベッドでゴロゴロしていた一実が私を見上げた。
「やっぱデカいな」
そう言われて姿見の前に立つと、たしかにデカい。一実に借りたロングTシャツとフリースはぶかぶかだ。
「あたしにはぶかぶかだね」
「そではあまってるのに、胸のとこだけパツンパツンじゃん」
私はベッドに腰かけて、一実の顔をのぞきこんだ。
「あたし応援するから。カズがマーくんとうまくいくように」
大げさに顔をしかめると、一実はふとんの中にもぐりこんだ。
「余計なお世話だよ」
「どうしてそんなに意地はってるの?」
上半身を起こすと、一実は私の顔を見つめ返した。
「おまえには理解できないかもしれないけどさ、世の中どうがんばったってどうにもならないことがいっぱいあるんだよ。恋愛はその典型。私はそれを知ってるから、悪あがきはしない。わかった?」
「わかんない。マーくんの気持ちは、まだわかんないでしょ?」
ちょっと考えてから、一実は小さいけど鋭い声で言った。
「おまえは赤地くんと私をくっつけて、自分が楽になろうとしてるだけだろ」
「え……」
言い返せない。正直そのとおりだった。私は床にしかれたクッションに寝ころび、そのまま眠ってしまった。
徹夜明けのクラスメートたちが、血ばしった目で教室に入ってくる。結局勉強しないままぐっすり眠った一美と私は、みんなと違って元気いっぱいだ。
「カズ、きょうこそちゃんと勉強しようね」
「おまえと違ってさ、試験に関係なくコツコツやってるよ、私は」
「そうだ、きょうはあたしんちで勉強しよ。ちょうどお母さんも出張中だし」
「桃下、おはよっ」
突然だれかが割って入ってきた。ふり返ると茶山くんが立っていた。
「おはよ。きのうは雨の中来てくれてありがとね」
「いやこっちこそ。それよりおまえ、英語いちばん上のクラスなのな」
「まあね。いちおーね」
私が茶山くんと話している間、一実は教室のいちばん後ろでマーくんとなにかしゃべっていた。
「愛、ちょっとお願いがあるんだけど」
茶山くんが教室を出ていくと、一実はこっちへもどってきて言った。
「きょうさ、赤地くんもいっしょに、どうかな?」
「えっ? うん、いいよ」
なんだ、やっぱり一実はマーくんといっしょにいたいんだ。きのうは余計なお世話だって言ってたくせに。まあいいや。親友の恋、応援してあげなきゃ。
「マーくんっ、きょうの放課後、あたんしんちでいっしょに勉強しよ?」
私が声をかけると、マーくんは自分のおでこをなでながら言った。
「ほんとにいいの?」
「もちろん」
だって、一実がどうしてもマーくんと勉強したいって言うから。私はちらっと一実を見て、にやにやしそうになるのをガマンした。
部屋の惨状を思い出したのは、家についてからだった。
「ちょっと待ってて。いま片づけてくるから」
とりあえずふたりには玄関で待っていてもらう。ちらばっている洗濯ものをクローゼットに押しこんで、あとのごちゃごちゃしたものは全部、まとめてデスクの引き出しへ投げこんだ。
「おまたせ。どうぞ」
ふたりを部屋に案内すると、私はマーくんに気づかれないように、そっと一実の肩をたたいた。
「あたし、お茶でもいれてくるね」
「オレも手伝うよ」
せっかくふたりきりにしようと思って部屋を出たのに、マーくんまでついてこようとする。
「いいから、マーくんは待ってて」
ひとりキッチンに入った私は、紅茶とお茶菓子の用意をはじめた。とっておきのダージリンにチョコパイ。ダイエット中だからチョコはガマンしていたけど、お客さんが来たときは特別だ。
電気ポットの目盛りを見て、中身がほとんど残っていないことに気づいた。お湯がわくまでの間、テーブルにひじをついてぼーっと待つ。意識が、遠くなっていく。
ポットの鳴る音で目が覚めた。ついうとうとしてしまった。
わいたお湯をガラスのポットへ移し、ティーバックを入れてもうしばらく待つ。お茶っ葉が開ききってから、3つのカップへ丁寧にお茶をそそぐ。ふわっとひろがるマスカットフレーバーを吸いこむと、バイトの思い出が頭に浮かんでくる。正直あんまり楽しくないこともけっこうあったけど、もしもあそこで働いていなかったら、石黒さんに会うことはなかったし、ギュンちゃんにも会えなかった。そう考えると、やっぱりあのファミレスでバイトをしてよかったなあと思う。
おぼんの重みになつかしさを覚えながら、ダージリンの香りをまとって、そろそろと廊下を歩いていく。一実、うまくやってるかな?
ドアの前に立つと、中からふたりの声が聞こえてきた。
「これであいつも赤地くんのありがたさに気づくはずだよ、きっと」
「ありがとう。おかげで自信がわいてきたよ。ドイツとのハーフだかなんだか知らないけど、遊び人の大学生なんかに負けちゃいられないな」
なぜか、マーくんがギュンちゃんの悪口を言っているらしい。イラっときて、乱暴にドアを開けた。
「なんでマーくんに、そんなこと言われなきゃいけないの?」
おどろいて立ち上がり、口を開けたままこっちを見るマーくん。
「帰って」
マーくんの目に涙が浮かんできた。泣いたってゆるせない。吸いこんだ空気といっしょにお腹の底から怒りを吐き出す。
「早くっ!」
マーくんは無表情で、マネキンみたいにかたまってしまった。そのまま後ろに倒れたかと思うと、壁にゴツンと頭をぶつけた。
「わっ!」
悲鳴を上げる一実の横で、だまってマーくんを見下ろす。
「なにつっ立ってんだよ!」
マーくんを抱きおこしながら、一実が私をどなりつけた。
「だって、あんなこと言われたら――」
「びゃあああああっ!」
突然マーくんが大声で泣きだした。一実はしりもちをつき、私はお茶をぶちまけてしまった。ガラスのポットが床にころがって、こぼれたお茶が私の手にかかった。
「あっつっ!」
たおれたポットをあわてて起こす。食器は割れなかったみたいだ。
「どうしよう。また、赤ちゃんになっちゃった?」
一実は私を無視して、マーくんに声をかけた。
「赤地くん? ねえ、赤地くん?」
ときどき苦しそうに息つぎをしながら、マーくんはえんえんと泣きつづける。こぼれたお茶でじゅうたんがびしょびしょになっている。とりあえずマーくんはほっといて、後片づけをしなきゃ。
「ぎゃあああああっ!」
いつまでも泣きつづけるマーくんに、おさまりかけていた怒りがこみ上げて、どなってしまった。
「いいかげんにしてよもう!」
「しょうがないだろ。おまえのせいでこうなっちゃったんだから」
一実にそう言われて、ますます頭にきた。
「なんであたしのせい? 元はといえばマーくんが、マーくんがギュンちゃんの悪口なんか言うからいけないんじゃん!」
私が大声で言い返すと、一実はうつむいて声のトーンを下げた。
「たしかに口は悪かったかもしれないけど、おまえのこと本気で心配してるんだよ、赤地くんは」
そう言うと、一実はマーくんを抱いてあやしだした。
「よしよし、いい子だね。いたかったよね。もうだいじょぶだからね」
寝息をたてはじめたマーくんをそっと床に寝かせると、一実はゆっくり立ち上がって、ローテーブルの上にあった紙のたばを無言でさし出した。
「なにこれ?」
さし出された紙を受け取って、意味もわからず読んでみる。数学と物理の問題集みたいだ。
「……これがどうしたの?」
「赤地くんがつくってくれたんだよ」
「えっ、マーくんが?」
てっきり一実がどこかの問題集をコピーして来てくれたのかと思った。
「きのうは徹夜したんだってさ。数学と物理が苦手なだれかさんのために」
マーくんは私の理数科目の成績が壊滅的なのを知っている。それでわざわざこんなものを……。解説もめちゃめちゃくわしく書いてある。これだけつくるのにどれだけかかったんだろ?
「ありがとう」
そうささやいて、マーくんの頭をそっとなでる。目を覚ましたらおいしいダージリンを飲ませてあげよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
