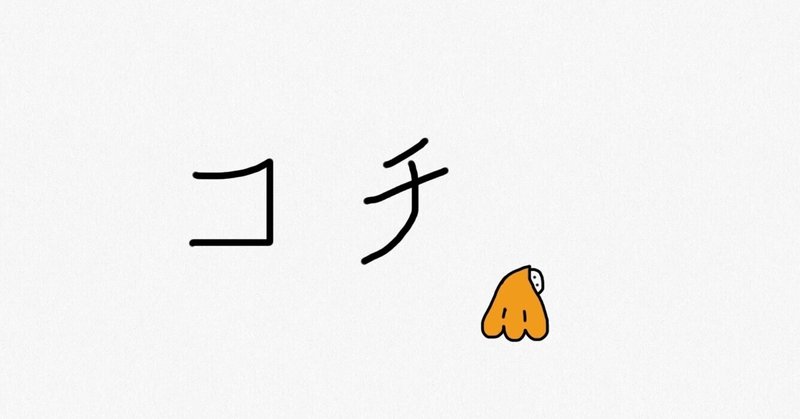
ホリデイ4
★
コチは小さな蛾。
あだ名は『木枯らし』
枯葉色した小さな羽で飛んでる姿を見て誰かがそう叫んだ。
今は春。厳しい冬が終わり、ようやく訪れた春。
そのあだ名は、春色の世界で悲鳴を産んだ。
その悲鳴から逃げ出して辿り着いた老木に1匹の蝶がやってきた。ホリデイだ。
結局、コチはホリデイと老木からも
逃げ出してしまった。
★
見知らぬ木から、木漏れ日が届く。コチは老木のジイさんを想った。せっかく見つけた寝床だったのに、突然現れた蝶のせいで帰りづらくなってしまった。コチはジイさんの優しい声が好きだった。ジイさんは僕を迷惑だと思っていたのだろうか。答えを聞かずに、コチは今ここにいる。いつもそうだった。コチの言葉をジイさんは優しく包んでくれるけど、コチはジイさんの答えを聞こうとしなかった。悲鳴混じりの世界で真実を聞く事がコチは怖くて仕方ないのだ。
見知らぬ木が揺れる。その木漏れ日は自分を嘲笑っているかのようだった。コチの休む透明なガラスはそれにキラリキラリと賛同する。コチは道路脇の街路樹の下で休んでいた。足元は透明。その場所は羽を動かしていないのに、まるで宙に浮いているようである。ここに止まった理由なんてない。疲れてポトリと落ちた場所がここだった。
✳︎
「嫌だ。気持ち悪い。変な虫がくっついている。」
若い男女二人がやってきた。
今日のデートの為に磨かれた車体は太陽の恩恵を受けピカピカと大いに輝いた。男は女に自分の車を初お披露目した。しかし、女の眼差しはフロントガラスに止まる汚い虫に向けられていた。女は、眉間のシワを寄せ、その深いシワを見て、男は、苦笑いを浮かべる。
「車が走り出したらきっとすぐ飛んでいくよ。」
男がどうにか女の機嫌を取ろうと陽気に声をあげ、カーワックスの香りが残る爪をぎゅっと握った。
✳︎
もちろん、コチは人間の話す言葉はわからない。言葉はわからなくても、車内からコチの腹を憎憎しく見つめるその二人の眼差しは言葉以上に伝わるものがある。
「そう睨むなって。どいつもこいつも僕を追い出したいようだな。でも僕は疲れているんだ。残念ながらまだここを離れる気はないんだよ。」
突然の地響き。震えるコチ。車のエンジンがかかったのだ。振動するガラスは、そこにいるコチを小刻みに激しく揺らした。揺れる体、慌てふためくコチの吐き出した言葉もまた揺れる。
「お、おい。ど、ど、どうなってる、るんだ?」
そして、男の憎しみが込められたアクセルは、急発進し速度を上げ道路を駆け抜ける。凄まじい風圧に背後から押されたコチは押し潰されるようにガラスに張り付いた。コチは身動きが取れなかったし、生意気な口も塞がれた。
なかなか飛んでいかない虫に対して、イライラしている運転手。ますます、車はスピードを上げる。コチは、振り落とされないようまだ自分の言うことを聞く体の一部にぎゅっと力を入れるだけ。ただ、そうする事に何の意味があるのかコチにもわからない。何もしなくたって体はガラスに張り付いている。ガラスに押しつぶされていない方の片目で空を見上げると、青い空にはゆっくりとちぎれ雲が流れている。「のどかだ。」ふっと意識がどこかに飛んでいきそうになった時、急に車は止まった。信号の色は赤だ。コチはこの暴走する大きな物体が突然止まった意味もわかりはしない。成す術もないほどの強靭な力の持ち主がルールという檻の中で、正しく真っ当な行動しているとは、コチは想像もしていないだろう。そんな事よりも止まっているうちに早くここから逃げないといけない。
「全く馬鹿みたいにはしゃぎやがって、いいかげ・・」
コチの捨て台詞が終わらないうちに信号は青になった。青は走れ、だ。コチはもちろん知らない。
未だに目の前を張り付く虫を今度こそ振り落とそうと、車は勢いよくアクセルを踏まれ走り出した。またコチは背後を強風に押されてガラスにびたりと張り付いた。コチの顔は風に首根っこを摘まれ、無理矢理車内に向けられた。
二人の人間の不快な顔。もう何度も見たって。いい加減、この顔に何の感情も湧かなくなる。
「そんなに嫌ならここから早く下ろしてくれ。」声は暴風に消される。次の信号は、いつだ?コチも信号のルールを知っていれば淡い期待が残されていたかもしれない。
ふと浮かんだ。「ジイさんは今、どんな風に揺れているのだろう?」風に押されガラスに張り付きながら、今どうしてコチはそんな事を考えているのだろう?いや、さっきと同じだ。気が遠くへと旅立とうとしているのだ。
だからコチは気がつかない。横から勢いよく何かが迫っている事を。
振り向くとコチの目の前に突然黒い影が勢いよく突進してきた。ワイパーだ。男の怨念の籠った魂のワイパーはコチを空高く吹き飛ばした。
運転席の男は、フロントガラスを隈なく見回した。どうやら、ガラスは汚れていないようだ。運転する男の顔色が明るい色に変わる。コチは、残念ながら、その顔を見る事は出来なかった。コチは、対向車線の空をくるくると回っていたからだ。
くるくる回る視界は、笑う太陽と冷ややかな灰色の道路を交互に映す。そして、コチの目に一瞬迫り来る車が映り、また太陽がニンマリ笑った。
「いやっ」と思った時には、車はコチの目の前にあった。風圧でさらに回る体。コチの脇を通過していった車が起こした風は、コチをさらに吹き飛ばした。そして、コチの意識も吹っ飛んだ。コチが、意識を飛ばしたのは、これが初めて。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
