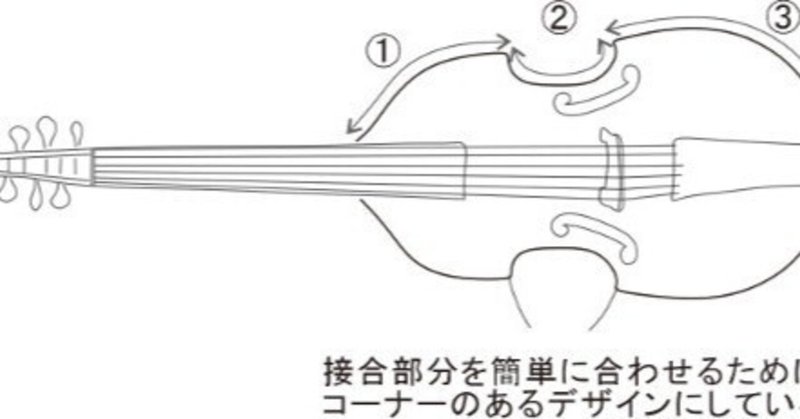
歴史 横板の薄さで「しなり」を作る
「中世フィドル」は、武弓から一枚板と経過しているので、
おそらく最初は、かなりサイズの大きな、
低音を特徴とする楽器だった思われる。
このため、「深い低音を出したい」という方向性がある。
ところが、一枚板から箱にしたことで、ボディが硬くなり
低音に向かない楽器になりつつあった。
仕方なく、弦長を短くして張力を減らしつつ、
小型化して高い音が出せる楽器になってしまったのだ。
この都合により生まれたのが、絵画や現在再現されている
小型の「中世フィドル」だろうと思う。
しかし、設計者は「深い低音を出したい」を忘れられない。
箱にした楽器を柔らかく使うにはどうすればよいか。
案として浮かぶのは、
横板の薄さで「しなり」を作れるか、である。
もともと、表板、裏板はひょうたん型で、中腹を曲げやすい。
後は、横板さえまがれば中腹がしなると考えた。
ただ、ここで1つの問題が浮上する。
現在で言えば、チェロのサイズの楽器のボディに対して、
薄く、長い横板は、用意することが非常に難しい。
この対策として、片側を3枚の横板で作るデザインが考えられた。
これを「ヴィオラ・ダ・ガンバ」のアウトラインに見ることができる。

横板を薄くして、3枚に分けたことで大型化が可能になった。
これで、深い低音を出すことができる、はずだったが
実際にはそう簡単ではなかった。
この時点では、「中世フィドル」を引き継いで
表板、裏板共に平坦な板を使用している。
#ヴァイオリン
#バイオリン
#ヴィオラ
#ビオラ
#ヴィオラ・ダ・ガンバ
#中世フィドル
#設計
#歴史
#横板
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
