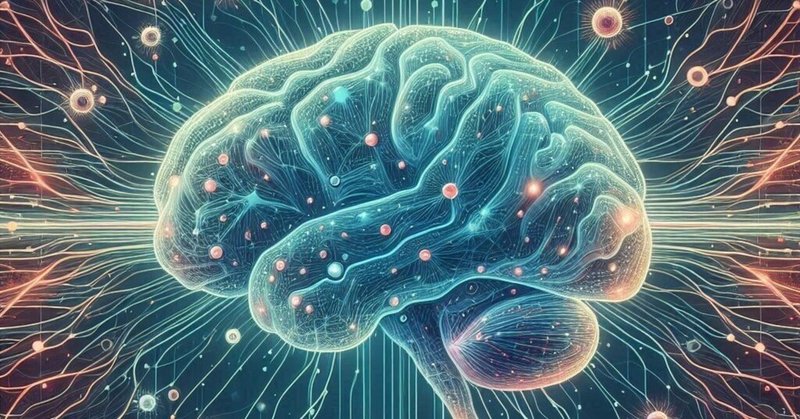
意識の生成メカニズムに対する仮説:物質と意識を統合する(1/2)
概要
意識の生成メカニズムについては、多くのモデルが提示されている。しかし現在のところ「そのモデルが正しいとしよう。では、なぜそのモデルのような状態から、意識体験が生成されなければならないのか?」という問いに明確な答えを与えているモデルは存在していないといっていい。これは、「意識のハードプロブレム」として知られるものであり、物理的な脳の状態から主観的な意識体験がどのように生まれるのかを説明することは非常に困難であるとされている。
本稿では、量子論的な素過程から意識現象に至る一連の過程を包括的に示すことで、二元論を乗り越え、世界を一元論的視座で統一する。それにより、「なぜ神経細胞の発火のような物理的プロセスから、意識体験のような主観的現象が生じるのか?」という、上記「意識のハードプロブレム」に対する一つの明確な回答を提示する。
以下に簡潔に内容をまとめる。
量子現象がミクロの基盤にあり、それがデコヒーレンスを介してマクロに現れる
この量子系→マクロ系への写像過程そのものが、情報生成とクオリア発生を伴う
クオリア生成と情報生成は等価な現象である(このアイデアが本論の核心である)
脳内の神経ネットワークは、このような情報=クオリア発生プロセスの巨大な集積システムである
無数の脳内クオリアの中から、選ばれた一部のクオリアが一つの場に統合されることで、意識体験が生じる
1. 意識体験の構成要素
1.1 仏陀の悟りとデカルトの内省
いまから約2500年前、インドのブッダガヤを流れるガンジス川の支流、ネーランジャナー川のほとりで、一人の壮年がある瞑想をしていました。名はゴータマ・シッダールタ、後の仏陀です。彼は自分の内側に現れる主観的な体験をあるがままに見つめ、その本質をとらえようとしました。
そして彼は悟りました。「私」は様々な意識の断片によって構成されているが、それを眺める中心的な「私」など存在していない。あるのはそれぞれの意識断片の繋がりだけだ。
この悟りは後に「諸法無我」と呼ばれることとなり、彼が起こした仏教という宗教の中心概念となりました。
時は流れ、17世紀のヨーロッパはフランスに、ある哲学者がおりました。
名をルネ・デカルトといい、年は41歳でした。
彼は暖炉の傍のイスに一日中腰掛けながら、自分を含めたこの世界のあらゆる物事を疑っていくという、方法的懐疑という思索を行いました。その結果、この世界のあらゆる物事が偽物だったとしても、それを疑う自分の思考だけは疑えないものとして残る、と結論し、「我考える、故に我有り」という命題を掲げました。
彼は、あらゆる意識的経験に先立って存在する「私」という実体をそこにみたのです。
仏陀とデカルト、それぞれの考えは「私」という存在に対するふたつの異なった見解を示しています。
仏陀は「中心的な自我は存在しない。あるのは諸々の意識断片だけである」と言い、デカルトは「あらゆる意識断片が偽物だったとしても、それを眺める中心的自我だけは疑えないものとして残る」と考えます。
さて、どちらの見解が正しいのでしょうか。
1.2 神経科学の示す答え
「分離脳」という状態があります。
重度のてんかん患者に対して、まれに右脳と左脳を繋ぐ脳梁を切断する、という施術が行われることがあるのですが、この右脳と左脳が分離された状態の被験者に対して、1960年代にロジャー・スペリーとその同僚達は一連の実験を行いました。
たとえば、被験者の左目に「ナット」という単語をみせ、同時に左手で机に置いてある様々なものの中から手だけをつかってナットを探し出してもらいます。すると、被験者はナットを左手で探し出すことはできるのですが、左目に何という単語が表示されたのか、口で説明できないのです。
これは、左目は右脳と接続しているため、言語を司る左脳の機能を用いることができなかったためだと考えられます。
このことは何を意味しているでしょうか?
脳梁が切断されると、左右の半球間の情報伝達が完全に遮断されます。その結果、脳の左右の半球がそれぞれ独立した意志判断を行うようになったのです。脳の分離により、意識体験が分離した、とも理解できます。
スペリーはこの業績により、ノーベル医学賞を受賞しました。
この研究は、意識がデカルト的な単一の自我によって支配されているのではなく、脳の異なる部位がそれぞれ独立した意識的な処理を行っているということを強く示唆しています。
現代の神経科学の知見では、脳が領域ごとにそれぞれ異なった意識的機能を持つことが知られています。
このことは、デカルトの考えよりも、むしろ仏陀の考えが正しいということを示唆します。
意識は単一の自我によって統合されているのではなく、様々な意識断片が複雑に相互作用することで生成されるのです。
その意識断片は、現代では「クオリア」と呼ばれています。
1.3 意識とクオリア
「クオリア」とはなんでしょうか?
それは、私たちが普段当たり前に、あまりに当たり前に感じている主観的な意識体験のことを指します。
例えば、赤い色のリンゴを見たときの「赤」という感覚、キンモクセイの香りを嗅いだときの「いい匂い」、鍵盤のC4のキーを叩いたときの「ド」という音感、これらはクオリアの一例です。
クオリアには二つの重要な特徴があります。
一つ目は、それが私秘的であり、他者には直接伝達することができない体験であること。例えば、あなたが感じる「赤」は他の人が感じる「赤」と同じかどうかを確認することはできません。
そして二つ目は、意識体験とクオリアが常に伴走していることです。どのような意識体験も、必ずクオリアを伴います。
特に二つ目の観点から、意識とは「クオリアが統合された場」ではないかと考えられています。つまり、私たちが経験する一つ一つの意識断片、クオリアが、何らかの原理に従ってひとつの意識的な体験の場に統合されていると捉えられるのです。
仏陀が悟った「諸法無我」の見解は、意識が単一の自我によって支配されるのではなく、様々な意識断片(クオリア)によって構成されるというものです。現代の神経科学の知見は、これを支持しています。すなわち、意識は脳内の多様な神経活動とそれに対応するクオリアの統合によって成り立っていると考えられます。
意識はクオリアの集まりによってできているのです。
1.4 物理世界に対する意識の因果的作用
さて、クオリアや意識は一般に、脳内の神経活動に付随して生じる現象であると考えられています。すなわち、「物理世界」→「クオリアや意識」という方向では、明らかに因果関係をもつと考えられています。
では、逆方向の因果、すなわち「クオリアや意識」→「物質世界」という方向の因果的作用はどうでしょうか?
この観点は、「現象報告のパラドックス」という問題として知られています。
現象報告のパラドックスでは、例えば私が「赤」というクオリアを経験したとき、私は「私は『赤』というクオリアを経験している」と報告可能であることを重視します。これは明らかに、意識体験の内容が口や声帯といった物理的身体の運動に介入していることの顕著な例と捉えられます。
そもそも、私たちが日常的に発している「今日は暑いね」とか「痛っ」とか「この曲はよい曲だ」などの発言は、すべて自身の主観的意識体験の内容を語っているのであり、現象報告に類するものです。
そのように考えると、「クオリアや意識」→「物質世界」という方向の因果的作用についても、明らかであると考えられます。
さらに、「プラセボ効果」も意識の因果的作用を示す重要な例です。プラセボ(偽薬)を本物の薬だと思い込むことで、実際に症状が改善するという現象は、意識的な信念や期待が脳内の神経活動を変化させ、実際の生理的な作用を生みだしていることを示します。これは意識が物質的身体に因果的影響を及ぼすことを示唆する好例でしょう。
以上のことから言えるのは、クオリアや意識体験、そして物理世界とを統合的に記述するなんらかの視座が存在する可能性が高い、ということです。そうでなければ、両者がお互いに因果的作用を及ぼし合うことの説明がつきません。
我々は「心」と「物質的な身体」を別々のものとして捉えがちですが、そのような見方を越えて、一元論的な見方で両者を統一的に眺めることが、クオリアや意識の本質を探る上では必要不可欠であることがうかがえます。
次章では、「情報」という観点から、クオリアと物理世界とを統合するひとつの視点を提案したいと思います。
2. クオリアと情報の等価性
2.1 「情報」の根源
「情報」とはなんでしょうか。
情報理論によれば、情報とはある事象が起こる確率(の逆数)の対数で定義されます。
例えばサイコロを振って、3の目が出たとしましょう。
このとき、3の目が出る確率は6分の1です。よって情報量は対数の底として2を選んだ場合、約2.6となります。
事象が起こる確率が小さいほど、情報量は大きくなります。これは直感的にも理解できます。道端を歩いていて犬に出くわしたとしてもたいした驚きはありませんが、キリンに出くわしたとしたらびっくりするでしょう。サイコロを振って3の目がでたとしても普通のことですが、3の目が10回連続で出たとしたら、その情報量は非常に大きくなるのです。
さて、情報が確率と深い関係のある概念であることがわかりました。
では、この「確率」とやらは、いったいどこからやってきたのでしょうか?
マクロの古典系においては、自然現象は決定論的に振る舞うと考えられます。サイコロを振って3の目が出る、という事象は、一見確率的な現象ですが、古典物理として考えるなら、サイコロを振る手の運動、サイコロの運動、机に跳ね返った時の運動量のやりとり、等々を計算することで、サイコロが手から離れた時点で何の目が出るかを厳密に計算することができることになります。それは最早確率事象ではありません。
一方、「確率」というものが自然界の基本的な要請として現れるような系があります。それは量子系です。
ミクロの量子状態においては、諸状態は確率的に重なり合わさっており、その状態は決定論的に記述することができません。ミクロの物理では、すべては確率に従うのが「普通」なのです。
では、ミクロの物理においては確率に従うのが普通であるにもかかわらず、マクロの物理において自然界が決定論的に振る舞うのはどうしてでしょうか?
それは、ミクロにある無数の量子状態がマクロの視点で見ると「平均化」されて、個々の純粋な確率的振る舞いが相殺されてしまうからです。このような状態を「混合状態」と呼びます。
サイコロのようなケースも、もちろん混合状態であると考えられます。サイコロを構成するミクロの素粒子がもつ純粋な確率的状態は、マクロでみると平均化されて決定論的な振る舞いとなるのです。
しかし、その確率的振る舞いの根拠がもとをたどればミクロの量子状態にあることに変わりはありません。
この世界における「確率」とは、ミクロの量子系にその由来があるのです。
そして重要なのは、「確率」と「情報」の繋がりです。「情報」は、確率的事象のうち、ある事象が「選ばれる」ことで生じる、ということが先の例で明らかでしょう。「確率」の根拠が量子的重ね合わせにあるのであれば、その重ね合わせ状態のうち、ある状態が「選択」されることが「情報」の根拠となるはずです。
そのような「選択」過程は、一般には「観測」と呼ばれています。
2.2 「観測」とはなにか
確率的に重なりあった量子状態のうち、ある状態が「選択」されることを「観測」と呼ぶのでした。
では、これをもう少し掘り下げて見ましょう。そもそも何らかの状態が「選択」される、とは、物理的にどういう過程なのでしょうか?
ここに、二つの粒子AとBからなる系を考えます。それぞれの粒子はスピン上向きと下向きの二つの状態をとると仮定し、それぞれの状態は量子的な重なり合い状態にあるとします。そして、ここが重要なのですが、粒子Aが上と下、どちらかの状態をとった場合、それに対応して粒子Bの状態が定まるとします。このような状態を「量子もつれ」と呼び、二粒子からなる単純な粒子もつれ系のことを「ベル状態」とも呼びます。
さて、粒子Aの状態は本来「上」と「下」で重なりあっており、定まりません。しかし、粒子Bが粒子Aと量子もつれ状態にあるとき、粒子Bからしたら、自分の状態が「上」か「下」かによって、粒子Aの状態が定まることになります。すなわち、粒子Aの状態が「選択」されるということです。
これが「観測」の最も単純なケースです。粒子Bは、粒子Aの状態を「観測」したのです。
一般に観測とは、被観測者(A系)と観測者(B系)の間で、なんらかの情報の受け渡しが行われる過程と定義できます。A系の状態に応じてB系の状態が定まるとき、そこに情報の伝達が起こっていると解釈できます。よって、それは観測過程と呼べるのです。
さて、ここまではAとBの2粒子からなる系を考えましたが、ここにA-Bから離れたところにいる粒子Cを仮定します。
粒子Cは粒子AともBとも量子もつれ状態になっておらず、よってそこに情報の伝達は起こりません。
このとき、粒子Aが「上」と「下」のどちらの状態であるかは、粒子Cに「とって」はわかりません。ただわからない、というだけでなく、量子論的にはその状態は「定まらない」のです。
つまり、「観測」という過程は粒子A-Bの間だけで通じる閉じた過程であり、粒子Cは蚊帳の外だということです。粒子Aの状態は粒子Bに「とって」のみ定まり、粒子Cに「とって」は定まりません。
これは何を意味しているでしょうか?
たとえばこの状況を俯瞰して眺める神のような視点があるとして、神はAの状態を知ることができるのか? それとも神にとってAは重ね合わせ状態にあるのか?
答えは、神のような視点は想定不可能である、ということです。
ここに客観は成立しません。あるのはA-B系に「とって」の状態であり、Cに「とって」の状態だけです。
このことは、粒子AとBに「とって」のみ通じる、私秘的な情報の伝達が起こっていることを示します。
では、そのような「私秘的な情報の伝達」は、どのように担保されるのでしょうか?
3.3 「観測」を成立させる必然的要請としてのクオリア
前節では、「観測」を成立させるためには「私秘的な情報の伝達」というものが必要であることを示しました。
そしてこの節が本稿の核心部分です。「私秘的な情報の伝達」がいったい何によって担保されているのか、という事を考察します。
まず、「私秘的な情報の伝達」というものが成立するためには何が必要か、ということを考えてみたいと思います。それは、
私秘的であり、因果的に離れた他の系には直接伝達できない何らかの情報の形
それが伝達される仕組み
であると言えるでしょう。
仕組みについては量子もつれというメカニズムがあるのでとりあえず置いておいて、一つ目に注目してみます。この記述はどこかで見覚えがないでしょうか?
ここで、「クオリア」の性質について1.3節の記述を振り返ってみます。以下のように書いたのでした。
クオリアには二つの重要な特徴があります。
一つ目は、それが私秘的であり、他者には直接伝達することができない体験であること。例えば、あなたが感じる「赤」は他の人が感じる「赤」と同じかどうかを確認することはできません。
そして二つ目は、意識体験とクオリアが常に伴走していることです。どのような意識体験も、必ずクオリアを伴います。
なんということでしょう。クオリアの一つ目の性質は、まさに「私秘的な情報伝達」に要請される性質そのままではないですか!!!
ここに、一つの大胆な仮説を提示したいと思います。すなわち、
仮説:「観測による私秘的な情報の伝達」は「クオリア」という形で行われる
すなわち、クオリアの生成と情報の生成は等価である、ということです。
このアイデアを元に、次章以降ではより掘り下げて、クオリアと意識との関連性について探って行きたいと思います。
続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
