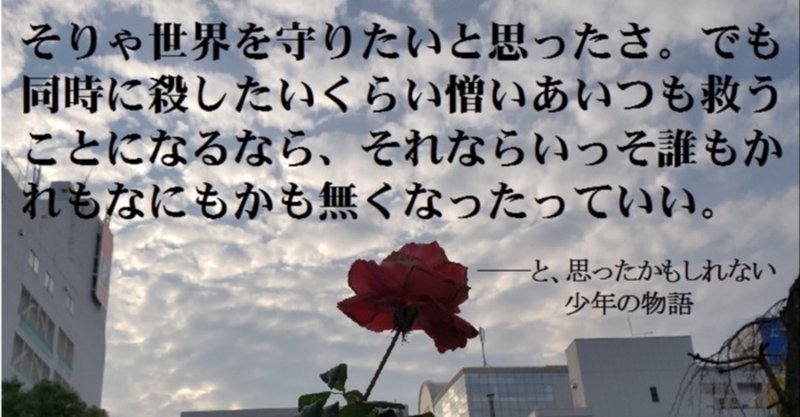
「四度目の夏」32
2046年7月27日 11:23
――1万メガバイトレベルのファイルがあれば、おそらくそれが0期だ。
マサキはそう言った。
パソコンの保管ファイルを探したってそんな大きなものは見つからない。仮に見つけたところで、復元情報をぼくが理解できるはずもなく、それが0期なのかは知りようがない。
クラウドに保管しているなら、ハッカーたちが見つけ出すはずだし、ということはレコードディスク媒体だろうか?
ぼくは立ち上がって部屋を見渡した。
壁一面の書棚。
キャビネットを二つ連ねた間仕切りの向こうの夫婦の寝室。
みっちゃんの子ども用ベッド。
キャビネットの上に並べられたいくつもの写真立て——家族の写真、夫婦の写真、よっくんが赤ん坊のころの写真、佳奈恵さんが産着を着た赤ちゃんを抱いている写真、それから三年前の、突然ぼくたち一家がここに来たときの、全員の記念写真。
キャビネットの引き出しを開けてみる。みっちゃんの子供服や、益司さんの作務衣、タオル。
ぼくは書斎壁側の書棚のガラス戸を開いた。たくさんの本を指でたどってくまなく探す。ディスクらしいものは見つからない。
ぼくは途方に暮れた。本堂から聞こえる読経が終わった。よっくんはいまも益司さんを本堂に引き止めているはずだ。でもいつ夫婦の寝室に佳奈恵さんが入ってくるかわからない。
ぼくは目を閉じて記憶をたどる。
母さん——
母さん、金色に光ってる、それなに?
——量子コンピューターのプロセッサーよ。
とても大きなコンピューターだからプロセッサーを利用するの。
そのコンピューターの処理能力はスーパーコンピューターは通常のコンピューターの一億倍なのよ。
一億倍?
ぼくは訊いた。
ふふ、一億倍なんて聞いてもピンとこないわよね。そうね、人間が走る速さと光速ほどの違いかしら。
母さんはそれからなんて言った?
――演算能力は金融機関すべての暗号を解き明かせるほどの高さなの。稼働するときにはまばゆいばかりに光るのよ。
ぼくはため息をついた。
ぼくはこの家に量子コンピューターがあるとでも思ってるんだろうか。
そんなことをマサキは一言も言っていない。第一もしそうなら消費電力は膨大なはず。白雲岳のてっぺんに太陽光電池とか? いや、衛星で簡単に突き止められることをホクトマサキがやるとは思えない——益司さんがするとは。ぼくは頭を抱えた。
「なんだよもう! 0期のファイルはどこにあるんだ!」
目を閉じると混乱するなかで意識の奥から光が見える。さっきから感じる金色の光。意識はなにをぼくに伝えようとしている?
光——
東の水平線、雲海のずっとむこうで太陽が姿を現し、一筋光がぼくらに届いたあの時、益司さんは言った。
——膨大なデータ容量を誇るUSBメモリってのは金色に光る。
ぼくは目を開けた。
寝室を出て、階段を駆け下りた。渡り廊下を走り本堂の引き戸を開けた。祭壇に向かって座っていた益司さんとよっくんが驚いた顔で振り返った。
「にいやん!」
ぼくは二人の横を通り過ぎて、足を内陣に踏み入れた。
「入ってはならん!」
益司さんの怒声が響くと同時にぼくの肩が引っ張られて外陣に床に叩きつけられたが、ぼくは益司さんを見ることもなく跳ね起きて観音像に向かって駆け出した。背後に益司さんの大きな手が掴みかかってくる。
「父さん! ちょん待って……っ! にいやん……っ行っけ……っ!」
よっくんが益司さんの脚にしがみついた。
「義之! 離せ!」
「はよ行け!!」
ぼくは足場を見つけて、白泉寺の本堂である聖観音立像の蓮の台座に足を掛けた。
「や、やめろ!! 義之! 離せ!」
「にいやん! 行けーーーっ!!!」
線香の香りが染みついているこの本堂の天井をぼくは見上げた。金の花や燈明台、それから玉や美しい飾りがたくさん吊り下げられている。金色のきらびやかな細工の装飾品が天井を埋め尽くしている。
ぼくはそれを真下から見上げる。これが極楽浄土だ。
でもこれじゃない、ぼくが探す光は。金色の光は――
さらに登っていく。目の前に悠然とほほ笑む観音の顔がある。
アナスタシアのデザインの基となった優しい顔だ。カヤの一木造でかつては金箔に覆われていたはずの丸みのある柔らかそうな黒い木肌が見える。
曲線のところどころ薄く金箔が残っているが光ってはいない。光っているのは観音像の金の宝冠だ。何人もの仏陀の彫刻が施された細工の入った宝冠の中にに手をぼくは入れた。
わざと左右対称に作られていないと思っていた宝冠の中には、正方形の黄金色のUSBメモリがあった。
「やめろ!」
益司さんが叫ぶ。ぼくは台座から飛び降りた。その衝撃で観音像は前のめりに傾いていった。そして観音像の周りの装飾品もろともけたたましい音をたてて倒れた。ぼくは間一髪、観音様の下敷きをまぬがれた。観音像の首は折れ、胴体から切り離されて宝冠とともに外陣への階段を転げ落ちた。
「なんてことを……」
「にいやん!」
ぼくは跳ね起きて歯をくいしばって本堂を飛び出した。
「待て!」
両腕を広げる益司さんをぼくはどうにかかわして本堂を飛び出した。再び益司さんの寝室に駆け込んで内側からドアをロックした。同時にドアノブがガチャガチャと鳴った。
「開けろ! ここを開けろ!」
益司さんがドアを激しく叩く。
ぼくはドアを背に荒い息をどうにか落ち着かせようと自分の胸を掴む。息を吐くとおかしな声が同時に漏れる。震える手で益司さんのコンピューターをもう一度起動させる。浮かび上がったホログラムを両手で操作してマサキにコンタクトした。
「手に入れた」
ぼくは言った。興奮して涙が出た。ぼくはそれを片手で拭いながら、反対の手で金色のUSBを掲げてマサキに見せる。
「探し物はこれじゃない? 大容量集積のUSBだ」
ホログラムに映し出されたマサキはうなづいた。
「0期の設計書のデータを変換しての解析が必要になる……こっちのラボにある量子コンピューターで解析を始める。このままハードディスクにUSBを差し込んでくれ。それだけでいい……このままハックする」
マサキは表情を変えずに言った。
「待って、ラボ? ラボってなんのこと? どこのラボだよ」
ぼくは訊き返す。ラボなんて初耳だ。こうしている間にもドアがけ破られそうな勢いで叩かれて益司さんが叫んでいる。
「やめろ! やめるんだ!!」
「早くそのメモリを差し込むんだ」
「ぼくの質問に答えるのが先だ! ラボってなんだよ!」
突然激しいみっちゃんの泣き声がドアの向こうから聞こえてきた。みっちゃんがいるってことは佳奈恵さんもこのドアの外にいるんだ。もしかするとおばあちゃんも来たかもしれない。みっちゃんが泣いている。みっちゃんが泣いているのはぼくのせいだ。マサキは質問に答えない。
「ああもう!」
ぼくはドアに駆け寄って叫んだ。
「益司さん、これってアルチメイトブロックの0期設計書なんだよね? なんでこんなものが本堂にあるの? 益司さんがホクトマサキなんだ! あなたがホクトマサキだったんだ!」
ドアを叩く音が止んだ。みっちゃんはまだ泣いている。自分の膝が震えていることに気づく—―いまにもしゃがみこんでしまいそうだ……。ぼくはドアにもたれかかった。
「今このアルチメイトブロックのせいでAIがASIに進化して人類を攻撃してるんだよ! それって、益司には想像できたことなんじゃないの……?」
益司さんは沈黙している。
「益司さんは破壊者なの? それともこの0期で救世主になりたいの? それとも地球が滅んだあとの創造主になりたいの?」
「俺は!」
益司さんは言った。
「ただの僧侶だ。家庭を持つ佳奈恵の夫であり、子供たちの父親だ」
「ぼくの父さんを殺したじゃないか!」
ぼくはありったけをこめて叫んだ。
「世界中が攻撃される地球滅亡のカウントダウンが始まったんだ! 今それを止めるには、この0期を解読してバグのDNAを消す方法を探すしかないんだ。そうなんでしょ!?」
「聞いてくれ、俺がこのアルゴリズムを作ったころ、俺は病気だった」
益司さんが言った。
「君には話したね。あの頃、俺の人生には俺しかいなかった。俺の舞台には、俺が唯一の登場人物だった。その俺の実力が世間に認められなくて、ただひたすらに苦悩していた。俺を認めようとしないボンクラ科学者たちを呪っていた。科学者だけじゃないな。この世界のすべてをだ。すべてを呪って、救いのない煩悩の渦の中にいたんだ。俺は自分を何者でもないと認めるなんざ恐怖でしかなかった。そんな俺を、俺の発明を認めたのがバーバルだった。俺のアルチメイトブロックの論文は、君の母上——杉盛博士にはね、相手にされることはなかったよ。戯言だと思われたんだろう。いやそもそも開いてもいないだろう。つまり読んでさえもいない。ところが世界のバーバル社は俺にコンタクトしてきて破格のギャランティを提示してきた。俺は世界のバーバルに認められたことで俺は有頂天になった」
「なんでホクトマサキだったの? 世界に認められたかったんでしょ? 本名じゃなかったのはなんで?」
益司さんはしばらく沈黙した。みっちゃんの激しい泣き声が続いている。
ホログラムの小さなピクセルが波のような動いて、光の粒で3Dに映し出されたマサキがぼくをじっと見つめている。
「俺がこの家——杉盛家に養子に入るまでは、俺は北斗という苗字だった。益司からマサキと名前を変えたのは、俺自身が有名になりたかったわけじゃなかったことに気づいたからだ。アルチメイトブロックというシステムが、世界に広がり、そして後世に残りさえすれば満足だ。名前なんぞどうだっていい」
だが、と益司さんは言葉を拾う。
「正直に言えば、俺はすぐにアルチメイトブロックのアルゴリズムのに重大な瑕疵があることに気づいたんだ。無論それをバーバル社に伝えた。だけどバーバル社が聞き入れることはなかった。すでにロシアのITベンチャーが開発したアナスタシアを採用して商品化していたし、アナスタシアのVer.0.1のセキュリティ対策が万全でなかったことでバーバルは莫大な損害を出した後だった。アルチメイトブロックシステムを採用することで、その損害の穴埋めは十分可能だった。そしてバーバル社は将来起こりうる単なる可能性としての悲劇よりも、現在の確実な、そして明らかな先行者利益を優先した。このプロジェクトでバーバル社はライバル社と埋めようがないほどの徹底的な差をつけるだけでなく、未来永劫の利益を確定すると見込んだ。
僕が想像するような悲劇が起きるというのは可能性の問題に過ぎなかった。仮に起きるとしても、それは台風が、火山の爆発が、巨大地震が、竜巻が、人間を殺そうと企んでいるものではないのと同義なのだと、彼らは結論付けた。俺たちは決裂し、俺はその莫大な報酬を受け取ることなく、姿を消した——逃げたんだ。すべての痕跡、足跡を消して。表向きには俺は謎めいた天才で、神秘的なストーリーができあがった。そのせいでさらにアルチメイトブロックは世界から注目を浴びたのは皮肉としか言いようがない」
「早く0期を渡せ……」
マサキの姿をしたホログラムが光りの粒子を揺らしながらじりじりと近づいてきた。ぞっとした。
益司さんが続ける。
「……そして俺は俺で、今度は世間でも世界でもなく、ホクトマサキである自分を憎悪することになった。白雲岳に迷い込んだのは、死に場所を探していたからだ。
そこで俺はきみのお爺さんであるこの寺の住職に救い出された。この山を住職と登って、俺は足を滑らせて滑落しそうになった。住職は自分の危険も顧みず僕を助けた。そうして10時間かけて頂上に登って俺はこの頂上から君が見て涙を流したあの日の出を拝んだ。俺は声を上げて泣いた。嗚咽は止まることなく、ただただ泣いた。喜びの涙でなく、絶望の涙でなく、なにかを渇望したわけでなく、あるいはそのすべてで、そしてまるで違う。
君には昨日の朝話したな、俺はあのとき苦しい産道を通って、この白雲岳の頂上でようやく産声を上げたんだ」
そして息を吐いたあとに益司さんは続けた。益司さんはもう叫んでいなかった。
「それまでの俺という存在は一体なんだったんだろう? まったく不可思議としか言いようがないのだけど、俺はここで暮らし始めて自分がホクトマサキであることを都合よく忘れてしまったんだ。俺は寺の勤めを果たし、父親としての責務を果たして、静かな臨終のときを望める立場にないことを知りながら、なぜだろうね、佳奈恵や、義之やみっちゃんの顔を見ているうちにあの頃の自分が幻のように感じるんだ。まるで長い長い悪夢をみていたみたいだ。
だけど今、はっきりとわかる。今の俺が夢で——儚き夢で、ホクトマサキが現実なのだと」
「益司さん……」
「君の質問に答えるよ。俺が作り出したアルチメイトブロックは完全無欠だ。
君も知っての通りこのソフトはノーベル科学賞を受賞した。これ以上のシステムはこの先、どんな未来にも作られることはない。まず人間には無理だ。これを超えるものができるとしたら、それはAIが作ったものだろう。だけどそれは本当に? 人間はAIに敗れるのか?
俺は知りたかった。試してみたかった。俺の発明したシステムで超AI、つまりASIは誕生し、この地球上で最も優れた、最も強い種になるのかを」
「……だからなんの手段も講じなかった、っていうの……?」
ぼくは訊いた。口の中がカラカラに渇いて、舌がもつれる。
「益司さんの作ったアルチメイトブロックのせいでASIが生まれ、そしてASIが人類に下す審判を、益司さんは見たかったっていうの? それがどんな結果を招くとしても、なにもしなかったのは、益司さんが作り上げたアルチメイトブロックの行く末をただ見たかったからだっていうの?」
益司さんは沈黙している。
「答えてよ! 益司さん!」
益司さんはなにも答えない。
「益司さん! 益司さん! 答えてよ! 益司さんのせいで地球が破壊されてるって! たくさんの人たちが死んだって!」
ぼくは叫んだ。
「そういうことだって言ってよ!」
「俺は——」
「ちがうなら否定してよ。否定してよ!!」
「なにも変わっちゃいない。俺はどうしようもなく毒に侵された科学者だ。地球上で最も強い種が人間なのか、あるいはASIなのか、今でも俺は知りたいと願ってしま——」「うわあああああん!」
みっちゃんの泣き叫ぶ声が益司さんの言葉を消した。
最後まで読んでくださってありがとうございます! 書くことが好きで、ずっと好きで、きっとこれからも好きです。 あなたはわたしの大切な「読んでくれるひと」です。 これからもどうぞよろしくお願いします。
