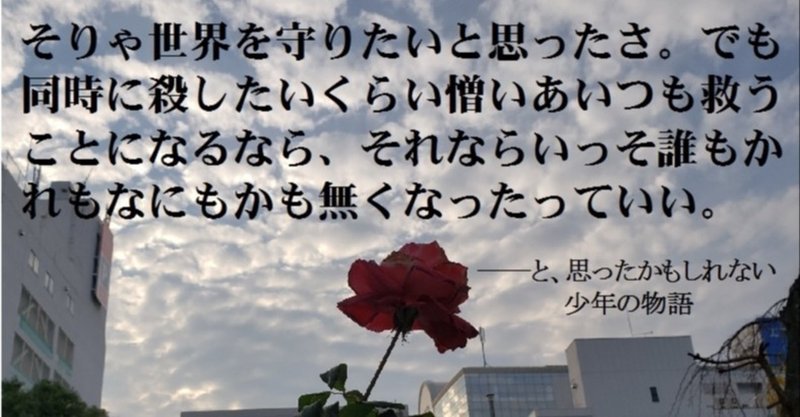
「四度目の夏」27(まえがきあり)
【まえがき:今回の『四度目の夏27』には、今般の新型コロナウイルス流行期にふさわしくない表現があるかもしれません。この物語はわたしの完全な創作であり、新型コロナウイルスの問題が深刻化するよりずっと以前に作ったものです。また実在の個人、企業ともまったく関係がありません。
どうかご承知のうえ、読んでいただければと思います。】
2046年7月27日 10:01
別荘地には人影がまるでない。どうしてここはこんなにも人の気配がないんだろう。
カラフルでデザイン性の高い家はこんなにたくさんあるのに、誰一人見当たらない。こんな暑い日はみんな家のなかに籠っているんだろうか。でも犬小屋にだって犬がいない。
こんな辺鄙なところで暮らす人なんてそれほどいないってことなんだろうか。立ち並ぶ家には人は住んでいないってこと? 別荘地なんだからこの暑い夏こそがシーズンだと思うのだけど、むしろこんな暑い季節がシーズンオフ?
一番奥の、森の手前にある三角屋根の黒いロッジ。
ぼくたちは昨日と同じ、バルコニーの下に自転車を停めた。よっくんがロッジの入り口までの階段を二段飛びで駆け上がってバルコニーのドアホンに指を掛ける瞬間にブレンダがドアを開けた。
いつもの、変わらない、柔和なあの表情だった。動かない顔だった。
母さん? これが?
まったくぜんぜん、ありえないことだと思った。
「よぅ、マサキいる? おれたちあんたたち二人に聞きたいことがあって来たんよ」
よっくんのこめかみが固く緊張しているのがわかる。いつも通りのよっくんを、よっくんは意識して演じている。それをブレンダは読み取るだろうか。
ブレンダはまだ軒下で動けないでいるぼくを見つめた。ブレンダの細いまなざしの奥の黒いレンズガラスが、もっと濃く黒くなった気がしてぼくはたじろいだ。
「どうゾ。お入りくだサイ。」
ブレンダは声を発した。懐かしい母さんの声とはかけ離れた、人工的な音声だ。
よっくんが先に入ったのを見て、ぼくはあわててかけ上がり、ドアを開けたままそこに立っているブレンダの前をすり抜けて入った。
強い合成香料の甘い香りはそのまま部屋に漂っている。
急に気分がどんよりとするのは、日の当たらない暗い部屋のせいだろうか、それとも。
マサキがいるだろうリビングルームの扉の前でよっくんが待っていた。
「自分で聞くけ……?」
先に入っていたよっくんが小声で聞いた。
ぼくはまばたきで頷いた。
扉を開くと黒いカーテンの黒い部屋は昨日やおとといと同じくキャンドルが銀色の燭台に灯っているけれど昨日より少ないかもしれない。近くまで寄らないとマサキが目を開けているのか閉じているのかも見えなかった。マサキは相変わらずソファで蓮の上の釈迦のように禅を組んでいる。
「マサキ」
ぼくは声をかけた。返事はない。ぼくはマサキの正面に立った。
「虹池でマサキとブレンダと出会ったときのこと、去年の夏のことなのに、ぼくはあまりそのときのことを覚えていないんだ。ぼくとよっくんはあの池で水浴びを楽しんでいて、よっくんがアユを釣ってぼくに見せてくれて、そこに君たちが岩場の影から音もなく現れた。太陽の逆光のせいで陽の光で君がどんな表情をしていたのか見えなかった。こんなに真っ暗な部屋で一日瞑想をして過ごしている君が、なぜあの日あんな明るい場所にいたんだろう? そして、ぼくたちはどっちから話しかけたんだろう? 君は覚えてる?」
マサキは動かない。
「ねぇ、ぼくの話を聞いてる? ぼくは君に興味を持ったよ。だから今年君に会えるのを楽しみにしていたんだ。そしてぼくはキプロスに行かずに命拾いをしたことになった」
「命……拾い?」
マサキが目を閉じたまま言葉を発した。一瞬マサキの瞼が震えた気がした。
「正直に言うよ。ぼくが君に興味を持った理由は、君がアルチメイトブロックの創造主、ホクトマサキなんじゃないかって思ったからだ。アルチメイトブロック以前と以後では世界は大きく変わった。そんな世界を変えたホクトマサキがこの白雲岳で暮らしてる。そんな想像をするだけでわくわくしたんだ。この部屋は暗くて、君はひとりぼっちでマシンと暮らしていて、ぼくのイメージした伝説のホクトマサキにピッタリなんだもの」
それからこのマシン――ブレンダ、とぼくは言った。
「君があのホクトマサキなら、現在バーバル社とホクトマサキのつながりがないなんて嘘だ。バーバル社が宣伝のために作ったファンタジーだ。君を伝説化するための。君はいまでもバーバル社とつながっている。その証拠にここにブレンダがいる。特別仕様のブレンダ」
ぼくはドアの入り口に立つブレンダを見た。
「ICタグのないオリジナルアナスタシアのブレンダ。ねぇ、ブレンダって君がつけた名前なの? なんでブレンダなの?」
マサキが何も答えないことはわかっている。ぼくはブレンダを振り返った。
「あのさ、ぼくが子供のころに母さんが読んでくれた絵本があったんだ。仕事で忙しい母さんが読んでくれたただひとつの絵本だ」
ブレンダが身じろぎもしないでただただそこに立っている。意思なんて見えない。
「その絵本はね、ブレンダっていう人形が夜中になったら動き出すんだ。ブレンダは朝になったらただの人形に戻るんだ。夜中だけが、彼女の人生なんだ。人生っていうか、人間じゃないけど。人形なんだけど」
ぼくはしゃべりながら自分の言葉を頭のなかで反芻した。
母さんは言った――機密事項。ICタグのない特別仕様のブレンダは目的を持って作られたはずだ——目的? 母さんはホワイトハッカーであり、プログラマーであり、脳科学者だった。
「ブレンダがオフラインなのは、ブレンダの頭脳がデータの移行もアップロードも必要のない既製品だからだ」
ブレンダはぼくを見ない。
でもぼくはブレンダを見つめ続ける。声が震えないようにぼくは喉に力をこめた。
「つまり人間の脳だ。ぼくの母さんの、脳だ」
「ひぃぇっ……」
沈黙の中でよっくんの唾を飲む音が聞こえた。ぼくもその音に刺激されて口の中を飲み下したい衝動にかられる。
「母さんは言ってた。AIに決定的に足りないのは人間の精神だって。どんなに『フレンドリー』ソフトウェアを作ったところで、善意や善良というものをAIが学び得ることはできない。人間とAIが安全に平和に共存する未来には、人間の脳とテクノロジーの融合が不可欠だって。そしてさらにいえば、人間の根源的な欲求を満たすもの——病気も、ケガもない、肉体から解放された次世代の人間を作り出すこと――肉体が滅んでも、生き続けること――それがもう可能なんだよね? 母さん?」
ブレンダがゆっくりと、まるでスローモーションの映像みたいに、顔だけを動かしてぼくを見た。たしかに、ぼくを見ている。
さっきまで信じられなかったのに――ぼくは確信した。
これは、母さんだ。
チタン合金でできた関節と、それを取り囲むやわらかなシリコンでできたぼくの母さん。長い髪をひとまとめにしていつも片方だけを三つ編みで編んでいた、いつも静かに思案に耽っていたぼくの母さん。
「チョコチップスコーンだけじゃわからないよ……!」
ぼくはブレンダに言った。
「それっぽっちのヒントじゃ、あなたがぼくの母さんだなんてわかるわけない!」
ブレンダはぼくを見ていた。
だれもなにも言わなかった。
「母さん、なんでここにいるの? なんでマサキと暮らしてるの? なんでそんな姿になってるの? バーバル社は母さんになにを求めてるの?」
ぼくは母さんに近寄った。キャンドルの明かりが母さんの顔を揺らす。でも表情はなにひとつ変わらなかった。ただ、やわらかく笑っているだけだ。笑っている? ちがう。笑ってすらない。なにも、なにもない。なんの表情もない。
「答えてよ母さん! 母さんの脳みそをそんなとこに入れられて、なにに使われてるの? なんでこんなことになるのさ。父さんが大変なんだよ。キプロスで死んじゃったかもしれないんだ。ぼくひとりになったんだよ。ひとりぼっちになったんだよ。母さん!」
感情がいっきにこみ上げて、ぼくは声を上げた。
「母さんでしょ! なんでなにも言わないんだ! ぼくだよ! わかってるんでしょ? なんなんだよ! なんでぼくをひとりぼっちにするの……もうほんとやめてよ。こんなことばかげてるよ!」
また時間が止まった。
ぼくだけが時間を振り動かそうと懸命にもがいても、たち打ちできないすさまじい沈黙だった。
ブレンダはその機能を失ってしまったかのように固まっている。いまこの瞬間まで母さんの顔が重なって見えたその姿も急にただの機械の塊に見えた。無機質で、無感情で、なにもかも冷たかった。ぼくの体が次第に重くなる。
「母さん……?」
いや、それともぼくがおかしくなったんだろうか? ぼくが壊れちゃってるんだろうか?
そもそもここはどこなんだろう。ぼくはなんのためにここにいて、ここにいるのは誰なんだろう?
「おばちゃん……にいやんの母さんじゃねえの? おばちゃん!」
よっくんがこの沈黙を破った。ぼくはようやく息を吸って吐くことができた。
それでもブレンダは微動だにしない。しびれを切らしたようによっくんはマサキに向いた。
「なぁお前……うお!」
そのとき、ぼくのスマートフォンがけたたましい音量で鳴った。よっくんの悲鳴と同時にぼくは尻ポケットからスマートフォンを出して開いた。
2046年7月27日 午前10:22緊急避難命令発令(東京都)
東京都中央区勝どきにて大規模の爆発がありました。これをうけて政府は緊急避難命令を発動します。ただちに非難を開始してください。西部区民センター、中央区避難シェルター、東部区民センター、……東京24区 神奈川県横浜市……の各自治体。
なお、避難する際には、道路の状況等に十分注意してください。すでに避難することが危険な場合は自宅の高い所や安全と思われる場所に移動してください。窓には近づかないでください――
「なんじゃいこれ……」
ぼくの手をのぞき込んだよっくんが声を。画面が明るくなったと思うと今度は着信が鳴った。「んだよ!」よっくんが後ろにのけぞった。佳奈恵さんからだ。すかさず応答する。
「もしもし、無事? ああよかった! 聞いたでしょ、いま東京が爆撃されたの! 電話が通じなくなったらいけないからすぐに帰ってきて! いますぐに!いいわね?」
ぼくは声にならない声をあげてただ携帯電話に向かってうなづくだけだった。横からよっくんが「わかった! すぐ帰る!」と叫んだ。
耳障りの悪いホログラムの開く音がして、黒い空間を見上げると、リビングの中心に大画面でバーバル社の衛星動画が現れた。地球だ。それがズームインで日本に、そして東京に。勝どきの海と陸の境界線に大きな真っ黒い穴が開いて、そこに海水がなだれ込む映像だった。
「まさか……これもASIの攻撃?」
画面が切り替わって世界の陸地が次々と映し出される。パキスタン、インド、アフガニスタンに噴煙を上げて巨大な真っ黒いホールができている。
「ASIがはじき出した答えは……破壊。未来に……人間は必要ないということだ」
マサキが言った。
「なにが破壊じゃ!」
よっくんが怒鳴った。
「人間が必要ないとか勝手に決めんなや!」
「彼らにあるのは『自己進化』のみ……彼らの本能はひたすらに知能を上げていくこと。そのための邪魔者を片付けなければならない……」
「じゃまもの?」
よっくんの問いにいくらかの沈黙があった。
それから人工音声が部屋に響き渡った。
「ホクトマサキ。」
最後まで読んでくださってありがとうございます! 書くことが好きで、ずっと好きで、きっとこれからも好きです。 あなたはわたしの大切な「読んでくれるひと」です。 これからもどうぞよろしくお願いします。
