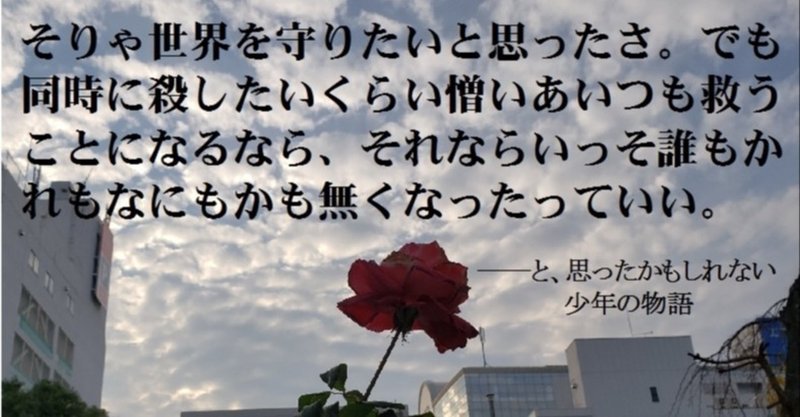
「四度目の夏」20
2046年7月26日 8時14分
心配してか、よっくんはぼくのそばから離れなかった。
だからマサキのところに行くのにも、よっくんがついてきた。
よっくんは小型のマウンテンバイクで器用に木の根を軽々と越えて行く。最初はぼくのほうが先に進んでいたけど、どうしてもよっくんに抜かれてしまう。でもそのたびによっくんはまたスピードを落としてぼくの後方に回った。よっくんが気遣ってくれるのがわかる。
ぼくは乾いた山の道の急斜面にハンドルと取られながら、昨日みたいに木の根っこにひっかからないようにどうにか進んでいった。気が付くと奥歯を噛みしめていて顎が痛くなった。昨日の筋肉痛か肘も痛く感じる。益司さんが鐘つきを代わってくれてよかったのかも――と思ったところで、今朝の鐘の音を思い出した。
脳が揺れるような響きは、ずしんとくる痛みに変わる。
まだキプロスにいるかもしれない父さんをぼくは想像してしまう。
燃える街の中を、焼けたレンガの道を必死で逃げる父さんを想像した。
食卓のテレビ聞いた情報ではキプロスの惨事は現地時間夜中の0時少し前のことだった。ただし、まだキプロスの映像は届いていなかった。ただ「キプロス島に巨大な未確認物体が衝突」のテロップと共にキャスターがその事実を読み上げているだけだった。テレビ画面の上のほうでずっとニュース速報が繰り返し同じことを告げていた。「邦人の安否は不明」と。
益司さんが外務省に電話をしても混線して通じなかった。インターネットの情報も同じだったし、白泉寺のだれもがトルコ語もギリシャ語もわからなかったけれど、翻訳ソフトを利用しても新しい情報は得られなかった。BBCニュースのウェブサイトを開いたものの、日本ニュース番組と同様だった。
別荘地の入り口のところまで行くと、よっくんがサドルに足を掛けたままぼくを待っていた。空はこんなにも青いのに空気はとても重かった。ブレーキをかけて、久しぶりのアスファルトに足を下ろした。重苦しい息を吐いたり吸ったりをくりかえす。でもぜんぜん暑くはなかった。汗が冷たくさえ感じる。蝉の声にも気づかなかった。
「こっからはアスファルトだから楽やけんさ、ちっと坂はあるけんども」
よっくんがまた自転車にまたがってペダルを踏みこむ。再びぼくのペースに合わせてくれた。よっくんは黒いランニングにベースボールキャップを被って、デニムのハーフパンツを履いていた。スニーカーのサイズはぼくより三歳も年下なのにぼくよりも1センチ大きい。腕は筋肉で引き締まってる。修験道をクリアした11歳は、去年までの小さなよっくんじゃなくなっていた。
ニュースのせいか、まだ朝が早いせいか別荘地には屋外に出ている人間がいなかった。芝を刈っているおじいさんもいなかったし、犬の散歩のおばさんもいなかった。空は高く澄んでいて、なにかのポスターから切り取ってきたみたいだ。カラフルな家が並ぶ別荘地は芝居のセットみたいだ。あの窓を覗き込んだら、中は空洞のような気がしてくる。
「見えてきたぞ!」
よっくんがサドルから腰を上げて振り返った。
マサキのコテージだ。別荘地のどん詰まりにある黒い屋根の黒い家。その向こうは深い杉林で視界を遮っている。よっくんがタイヤを擦る音をたてて自転車をバルコニーの下に停めた。
天気のいい日、今日は8月の最初の火曜日だ。空は青いし、鳶が遠い頭上を羽を広げてゆっくりと旋回している。でもぼくの気持ちは沈み切っている。昨日もぼくはここに来たのに、ずいぶんと時が経ったようにも感じる。昨日のぼくと、今日のぼくはこんなにも違う。ぼくは自転車を降りてコテージの下に、よっくんの自転車の隣に停めた。
「あ」
よっくんの声に顔を上げる。
ブレンダがバルコニーに出ていた。いつからいたんだろう。足音も聞こえなかった。ドアを開ける音にも気づかなかった。ブレンダがぼくらを見ていた。人工皮膚の色はきれいな肌色でなめらかで毛穴もない、眉はうすくていわゆる美人ともちがう、でも子供のぼくでもわかる、うつくしい、
うつくしい人だ。
いや、マシンだ。
ブレンダがぼくらを優しいまなざしで見つめていた。人工的に優しいというまなざしで。
「やぁブレンダ、マサキに頼みごとがあるんだ。入っていい?」
ブレンダはぼくの質問に答えなかった。ただぼくの背後を見つめている。
振り返ってよっくんを見た。よっくんはちょっと緊張した面持ちでブレンダを見つめている。というか、睨んでいるようにも見える。未知なものと対峙するときの顔ってこんな感じなんだろうかとぼくは思う。よっくんだけじゃなく、ブレンダも。いつもの柔和さのなかに何かがある。
「あのさ、この子はぼくのイトコなんだ。義之くんといって、ぼくの父さんの妹の子供なんだ。ちょっと大変なことがあって、ぼくを心配してついてきてくれてる。なにか問題あるかな」
ぼくはブレンダに聞いた。もしかしてマサキは会う人間を選ぶのかもしれなかった。だけどぼくは大人を連れてきたわけじゃない、連れてきたのはぼくよりも子供のよっくんだ。マサキのほうでも何も警戒することはない。それにマサキだって去年の夏、よっくんと虹池で水遊びをしたとき、よっくんと会っている。
「どウゾ。」
ブレンダがコテージの中に入った。ぼくらは後に続いて入った。昨日とは違うアロマの香り。花でもなく、木の匂いともちがう。ドアの向こうには黒いカーテンが閉まったまま、昨日と同じ姿勢で皮のソファにマサキが座っていた。まるで瞑想しているみたいに目を閉じている。最初に沈黙を破ったのはよっくんだった。
「この部屋暗いな! カーテン開けようぜ」
家の主の返事も聞かずに、よっくんは部屋を早足で横切ってカーテンを両腕を広げて引いた。黒い部屋に一気に光が差し込む。
「よ、よっくん!」
よっくんにかけ寄って腕を掴んだ。同時に唸り声が聞こえた。ぼくらはマサキを見た。マサキがソファに顔をうずめて丸くなった。その背中は震えている。ぼくはあわててカーテンを閉めた。「大丈夫だから、マサキ、もう大丈夫だから」ぼくは言った。
マサキは肩で大きく呼吸を繰り返してブレンダを呼んだ。ブレンダが水の入ったグラスを持ってきてマサキに手渡す。震える手で受け取ると、一気に飲み干した。マサキの喉が水を体の奥に押し込むたびに大きく揺れる。
「なんで……? 太陽の光がダメなんか?」
よっくんが訊いた。
紫外線が禁忌——そういう人間が少なからずいることをぼくは経験で知っていた。
体育の授業は教室からグラウンドを眺めているだけで、どんなときでも特殊なサングラスが手放せない——同じクラスの和也くん。
「よっくんだめだよ。人んちで勝手なことをしちゃ……」
ぼくは体裁を整えるように、よっくんにではなく、独り言のようにつぶやいた。
マサキがまだ水の入ったグラスをブレンダに返すと、ブレンダは反対の手でマサキの顔にかかる長い前髪を彼の左耳に掛けた。それでマサキの白い顔がキャンドルの明かりのなかに浮かび上がった。昨日よりももっと、白かった。唇はまだ水に濡れて昨日よりも赤かった。
「ごめんよ。この子は昨日言った従兄弟の義之くんっていうんだ。今日はぼくを心配してついてきてくれたんだ」
マサキはぼくを見た。なにも言わない。
「今朝キプロス島に巨大な未確認飛翔物体が墜落しただろう? 実はキプロスにいる父さんたちと連絡がつかないんだ。ギリシャの日本国大使館にもまだほとんど情報が入ってきていない。君はバーバル社のデータベースからキプロスの様子がわかるだろう? バーバル社の衛星にアクセスしてほしくて来たんだ」
「アクセス……」
マサキが言った。口を動かすと白い顎がかすかに動く。耳のしたの骨が顎と連動でして動く。アナスタシアよりも人形のようだとぼくはおかしなことを思った。
「そうだよ。できる?」
ぼくは訊いた。
「国際航空のあるラルナカ。首都のレフコシア、ビーチリゾートのアヤ・ナパ」
マサキはぼくをまっすぐ見つめたまま答える。
「すべて壊滅している。その事実のほかに知りたいことは……? 真っ黒に焦げた溶岩みたいなかつての街が見たい? 死体さえ溶けちゃってるえぐれたグラウンドが見たい?」
マサキは無表情のままそんなことを言った。長い前髪の隙間から茶色いガラスみたいな瞳だけがゆらゆらと光った。
マサキの言葉を頭のなかで反芻しながら、壊滅ってどんなふうに壊滅なんだ、とか、ギリシャ軍や国連が救助に行ってるのかとか、バーバル社なら情報持ってるんじゃないかとかぐちゃぐちゃしすぎて次の言葉が出てこなかった。
「朝食は……?」
「え?」
唐突な質問に間の抜けた声を出すぼく。先によっくんが答えた。
「食って来たよ。それがなんだ」
「父親が死んだかもしれない朝に、キプロス共和国の国民が大勢死んだ朝に、ちゃんと朝飯を……」
マサキは抑揚のない声で言った。
「はぁ?」
よっくんが頭を突き出して声を上げた。
「朝食べてなにがわりぃんだよ! ばあちゃんは息子を心配して水ものどを通んなかったがな、ばあちゃんはおれたちにどんな時でも食べんといけんってか細い声で言ったんだよ。連絡を待つのにも力がいる、って、心配するだけで、心が弱るから食べれるときに食べとかないかんって言ったんだよ。どんな気持ちで朝の飯を平らげたか、お前にわかんのか!」
「よ、よっくん」
「こいつはおれが心配してるってのも意味もわからんって顔をした。友だちの父さんがもしかしたらいなくなったかもしれんって朝に、なんじゃその態度、なんじゃその意味不明のしつもんは。父さんのことが心配だからキプロスのいまの状態を正しく知りたいってのがわからんか?」
三年前にはまだ幼かったよっくんが、見たことないくらい怒っている。
ぼくのために怒っているなんて、大人でも子供でも、よっくんが初めてだ。
小学五年生のよっくんは160センチのぼくよりも、もっとずっと小さい。150センチもないかもしれない。細くて、でも野生の猿みたいに崖をクライミングしたり、木の根っこだらけのけもの道を自転車で走ったり、虹池でマスを素手で捕まえるよっくんはたくましい。
もしもあのとき、あの教室に――よっくんがいたら。
ぼくはよっくんが息を荒げながらマサキに怒鳴っているのを見つめて思い出す。
あの教室に、よっくんみたいな子がいたなら。
小学部からのエスカレーター式で中学部に進学するのが、ぼくらの学校では当たり前だった。中学部からの特待生で入学した和也くんは弱視でコーク瓶の底みたいな眼鏡をかけていた。そして目の色が薄くて、茶色ですらなかった。ほとんどベージュのような色の瞳をしていた。だからいつもサングラスで、コーク瓶はだから、空瓶のことじゃない。黒い瓶底メガネだ。
和也くんは勉強はできても、同級生との付き合い方がわかっていなかった。それにくわえて常に黒くて分厚いメガネで見つめてくると、なんだか見下されているようでしゃくだと感じた同級生は多かった。あっという間に和也くんはクラスの男子からのいじめの的になった。
先生のいない放課後の教室で、和也くんのサングラスを取り上げてそれを取り戻そうとする和也くんは周りの男子にくらべて身長が小さい。多勢に無勢で取り戻せっこない。彼の目は、サングラスなしでは陽の光に耐えられないのに。
奴らは容赦がない。あいつらはそれが快感になってるんだ。
弱い者いじめ、って、はるか昔から学校にはびこる悪の側面だ。
そこらじゅうにAIコンシェルジュが待機して、「お困りゴトはないですカ?」と尋ねる。銀行にも役所にも、デパートにもホテルにも、そして学校にも。
和也くんは中学部校舎にいくつも待機しているAIコンシェルジュに訴えた。
和也くんは生身の人間である教師には訴えることはなかった。感情のないAIのほうがずっと平等で、理性的で、なんの偏見も持たずぼくらと接してくれる。だけど所詮マシンはマシンだ。
人間とはちがう。
ぼくの友達、優樹くんともちがう。
最後まで読んでくださってありがとうございます! 書くことが好きで、ずっと好きで、きっとこれからも好きです。 あなたはわたしの大切な「読んでくれるひと」です。 これからもどうぞよろしくお願いします。
