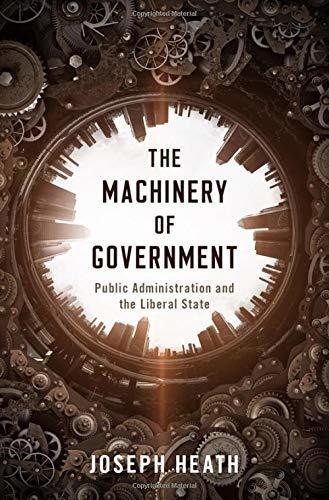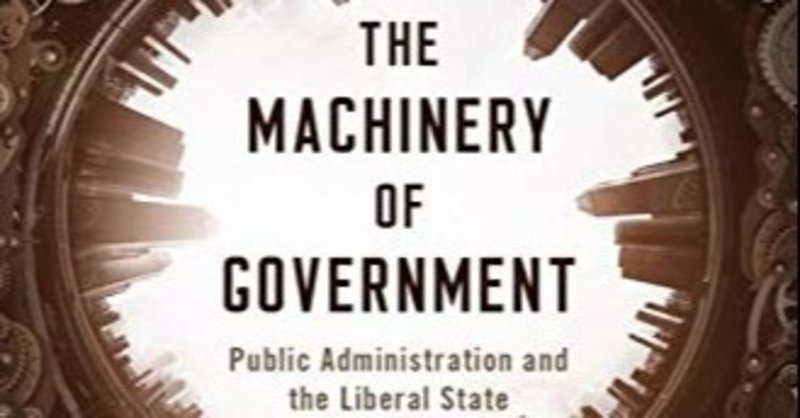
ジョセフ・ヒース“The Machinery of Government(行政機構)”要約:目次&序文
ジョセフ・ヒース“The Machinery of Government(行政機構)”要約:目次&序文
〔最初に。本エントリはジョセフ・ヒースの最新著作“The Machinery of Government(行政機構)”の読書記録を兼ねた要約である。要約者による補足は〔〕で示している。できる限り正確に著者ヒースの論旨を読み解くことを試みているが、あくまでも要約であり、要約者(=WARE_buefield)の主観によって元の書籍の要旨から逸脱している可能性がある。
固有名詞は確認できたものはウィキペディアに、書籍も確認できたものはAmazonにリンクを貼っている。〕
目次
序文
1章:行政を真面目に考える
1.1 機構に内部潜入してみる
1.2 裁量権の逸脱
1.3 行政権力
1.4 常設の〔立法・司法・軍以外の〕官公庁
1.5 政治的中立性
1.6 リベラリズム(自由主義)か民主主義か?
1.7 結論
2章:行政学倫理学における一般的枠組み
2.1 まずもっての〔争点の〕明確化
2.2 アカウンタビリティ(説明責任)の3つのモデル
2.3 階層化モデル
2.4 大衆化モデル(The popular model)
2.5 専門性モデル(The vocational model)
2.6 結論
3章:リベラリズム(自由主義):古典的リベラリズムから現代的リベラリズムへ
3.1 リベラリズム以前
3.2 古典的リベラリズムの台頭
3.3 古典的リベラリズムの勝利
3.4 古典的リベラリズムの衰退
3.5 現代的リベラリズムの台頭
3.6 結論
4章:効率性、福祉国家の台頭
4.1 平等主義モデル
4.2 共同体モデル
4.3 公共経済モデル
4.4 モデルをそれぞれ評価する
4.5 ワグナーの法則
4.6 レントシーキング的見解
4.7 結論
5章:リベラルな中立性の表明としての費用便益分析
5.1 〔先天的に〕根付いた費用便益分析
5.2 公共財の提供
5.3 規則の制定
5.4 安全性の評価
5.5 医療を配分する
5.6 環境財
5.7 三段階手続き
5.8 結論
6章:行政の裁量と法の支配
6.2 裁量
6.3 裁量の多様性
6.4 裁量的な施行
6.5 法の道徳性
6.6 行政法
6.7 結論
7章:パターナリズムと個人の自由
7.1 ミルの論拠
7.2 官僚によるパターナリズム
7.3 危害原理
7.4 双曲線割引
7.5 認知バイアス
7.6 ナッジによる枠組み
7.7 結論
8章:結論
注釈
参考文献一覧
索引
〔目次の邦題は現時点での暫定訳である。以降、本文の読解を進める過程で、適切な訳語に置き換わる可能性がある。〕
序文
・国家がどのように機能しているかについてあまり知らなくとも、政治哲学において大きな成果を上げることは可能だ。
・一例を挙げよう。私は、2001年に最初の一般向けの本“The Efficient Society(効率的な社会)”で、カナダの福祉国家モデルを擁護したが、出版直後から、連邦政府の役人に何度か呼ばれ、見解についていろいろ聞かれることになった。その呼ばれた内に、前“Clerk of the Privy Council”(枢密院書記官長)のジョセリーヌ・ブルゴン(書記官長在任:1994–1999)から連絡があった。しかし呼ばれた時点だと、彼女がその書記官長という役職名で何をやってるのか知らなかった。
・私を呼んだ前枢密院書記官長は、その時は“Canadian Centre for Management Development(カナダ運営管理センター)”〔日本では『人事院』に当たる部署と思われる〕の“the head of an agency(センター長)”だった。このセンターは、連邦政府の役人のために、マネジメント訓練の提供を業務としていた。
・私は、彼女から、“deputy minister”(連邦副大臣)が集まっての月例晩餐会のゲストスピーカーに招待された。“deputy minister”(連邦副大臣)は、カナダにおいて省庁官僚の最高職である。〔日本に置き換えると、事務次官連絡会議に招待されたと考えると分かりやすい〕。
・カナダの行政制度について説明しておこう。
・カナダでは、首相は、“Department”(省庁)を傘下に置いておらず、直下に“Privy Council Office”(枢密院事務局)を組織している。枢密院事務局の下に、様々な省庁が配置されている。
・“Privy Council Office”(枢密院事務局)内において、官僚の最高位が、“Clerk of the Privy Council”(枢密院書記官長)であり、実質的な“Deputy Minister to the Prime Minister”(副首相)となっている。
・つまり“Clerk of the Privy Council(枢密院書記官長)”は、カナダにおいて非選出公務員〔選挙で選ばれていない公職従事者〕の最高位なのだ。(女王と、女王の代理人である植民地総督を含めなければ)。
・ということで、自国の福祉国家要素を擁護する本を書いたら、その福祉国家を運営している最高位の官僚達に呼ばれたのだ。これがいかに恐ろしい体験だったか分かってもらえるはずだ。非現実的だったり、抽象的過ぎる話をしたらバカにされるんじゃないか? と。
・晩餐会まで私は非常に苦悩することになった。呼んだ人たちが具体的にどんな仕事をやっているのか全く知らなかったからだ。
・「哲学」によって、私は国家について考える場合、非常に抽象的な規範原理の観点から考えるよう訓練されていた。哲学は、「政策」の観点から国家について何を考えればよいのかまったく教えてくれないし、ましてや「運用」の観点では本当に何も教えてくれない。
・哲学(抽象)的な話を避けて、実利的な話をするつもりで、私は懇談会に向かった。
・最終的に、晩餐会での会話は、事前の懸念とは全く違うものになった。
・私が“The Efficient Society(効率的な社会)”で主張したことの1つが、「『効率性』は、福祉国家の根底にある最も重要な『価値』である」ということだった。(この主張は、本書の4章で、より詳細に再検討し、擁護している)。
・“The Efficient Society(効率的な社会)”は一般向けの本なので、この「効率性=価値」を大雑把にイコールにした上で、少し曖昧に書いていた。
・講演で、私は「厳密に言えば、効率性は原理であって、価値じゃないんですよ」と言った。すると副大臣の一人に「『原理であって、価値じゃない』ってどういう意味ですか?」と問われた。
・なので、私は“right”(正しさ)と“good”(良さ・適切さ)の区別について説明し、さらにジョン・ロールズの考察について説明した。
・このやり取りに、副大臣の全てが、興味を示したわけではなかった。しかし、「中立性」へのリベラルなコミットメントの観点では、この区別は重要なんだ、と説明し始めると、副大臣達は興味を示してくれた。
・当時、ウィル・キムリッカが“Multicultural Citizenship”〔邦訳文献タイトルは『多文化時代の市民権―マイノリティの権利と自由主義』〕を数年前に出版しており、カナダに大きな影響を与えていた。なので、私は、「中立性」の考え方が、カナダの多文化主義的政策をどのように導いたのかを説明した。移民が多数派の文化や宗教に同化しなくても、社会制度に統合される可能性を担保したことを、この中立性の考えは示していた。実際の国家運営の全ドメインに渡って、中立性と似たような規約が一般化されている様を私は説明した。
・こう説明したことで、副大臣は皆、関心をもってくれ、その日の残り時間で、皆で“liberal neutrality”(リベラルな中立性)の概念について議論することになった。
・アカデミアでは当たり前の概念について私は説明したのだが、これらは、国家官僚にとってはお馴染みでないvocabulary”(語彙・用語)だったのだ。
・懇談が終わる頃に、副大臣の一人が、「“neutrality”(中立性)という考えは、私たちが実務を行う際の一部として理解していますが、私たちはこれを言語化できていなかったのです」と心からの感謝述べてくれた。
・懇談が終わってから、「事前には実利的な話をするつもりだったのに、実際の会話内容は“抽象的で哲学的な内容”になったな」と私は思った。
・私が想定していた以上に、副大臣達は「哲学的で大きな話」や「抽象的な物語」について話したがっていた。
・私と副大臣達との違いだが、副大臣達は、私が議論で使用した“vocabulary”(語彙・用語)に非常に興味を示したことだ。
・「哲学者としての私の付加価値」は、何世紀にもかけて行われてきた政治権力についての熟考と議論にあったのだ。つまり、哲学は私に、熟考と議論によって、政治権力の制度的慣行のある側面を表現するのに適切な語彙と概念装置を、実装させてくれていたわけだ。
・私はチャールズ・テイラーやユルゲン・ハーバーマスの教え子として、哲学の中心的な役割は、我々が暗黙に実践していることを明示化する、つまり「“expressive one”(物事を表現する)こと」にあるのを、十全に承知していた。それでも、この時まで、師匠達の“methodological precept ”(方法論な教え)がどれほど重要なのが気付いていなかった。
・哲学者の仕事――規範的原理を高みから伝えたり、“kingdom of ends”(カント哲学における目的の王国)で立法者として行動することに比べれば、哲学者以外の人々が世界を理解する際に「表現すること」を手助けするのは、哲学者の仕事として刺激的ではないだろう。しかし、後者の方が、世の役に立つ可能性が高い。
・専門的な哲学者が、政治と道徳の公的議論の両方で完全に脇に追いやられて社会状況では、後者は少なからず有益だ。
・以上経験は、この本で私が採用している「少々普通でない手法」を説明するのを手助けしてくれている。
・本書で行われている研究は、「公共統治の倫理」を様々に熟考することから始まっている。
・「公共統治の倫理」とは、国家官僚が行政権を行使する際の、規範に関する問題として広く理解されている。
・私のアプローチは“reconstructive”(再構築的)なものとなっている。
・私は、公務員が「どのように仕事をしているのか」とか「職務を遂行するのにより“倫理的”であるにはどう振る舞えばよいのか」を示すのには興味がない。
・公務員らは、自身の仕事のやり方を私以上に知っているので、この件には深入りしない。
・私が関心があるのは、公務員らが保持している「非常に豊かな専門職務文化」だ。
・これは、例えば、公務員らが厳格に保持している、「すべきこと」「するべきでないこと」リストなどである。
・この公務員の「非常に豊かな専門職務文化」は、非常に洗練されているにも関わらず、暗黙に実践されてた文化となっているので、「価値観」を成文化したり、明確にする作業は行われておらず、巨大なギャップとなっている。
・ギャップが生まれている理由に、抽象的な規範概念を扱うのに、公務員自身は馴染んでいないことがある。
・これは、公務員の執筆文章は、「自身の為」ではなく「政治家に気に入られる」ことを目的にしていることに理由がある。
・結果、公務員が行使している巨大な権力を、無視することになっており、有益な知見が得られなくなっている。
・私は、トロント大で「公共政策プログラム」を教えることになった。教えるにあたって、大学の哲学科で“business ethics(企業倫理)”についても研究して教えていたので、その知見を「官僚組織(“bureaucratic organizations”)の倫理」(国家公務員の規範的意識・義務)に拡張できるだろう考えた。
・「公共政策プログラム」を教え始めてから、自分の見込みが間違えていたことを痛感することになった。「企業倫理」の文献はほとんど役に立たなかったのだ。
・次に痛感させられたのが、“the ethics of public administration(行政の
倫理)”の文献がほとんどないことだった。しかも、数少ない文献もほとんどが、特定分野の「実施(“hands-on”)処理」に関するものだったのだ。
・選挙で選ばれた議員の道徳的行動問題は、激しい議論対象になっていたが、国家官僚(“永続的”な公職従事者)が「いかに行動すべきか?」という問題は、驚くほど無視されている。
・しかも、私が「企業倫理」で研究してきた具体的なドクトリン(ドグマ・原理)もほとんど「行政倫理」の研究へと敷衍できないものとなっている。それでも、私が本書で採用した研究手法は、「企業倫理」の研究で用いたものと同じものである。
・旧来の「企業倫理」研究の問題は、企業の実際の行動と、外来の規範を分離させてしまっていることにあった。研究者(倫理哲学者)は、企業の行動を分析するのに、他所から持ってきた規範・道徳で、企業行動を分析しており、結果的に、外国人の観察・託宣のようになってしまっていたのだ。
・私が「企業倫理」を研究するにあたっては、企業や実業家が市場での関係性において実践していたり内在化している道徳的規範、つまり(“implicit morality of the market〔市場の暗黙の道徳性〕”)明示化するアプローチをとった。
・このアプローチを取るには、市場が社会の中でどのような役割を果たしているかの「俯瞰的視点(big picture)」が重要なのだ。
・私が今回「行政倫理」で取ったアプローチもほぼ同じである。“implicit morality of the state〔国家の暗黙の道徳性〕”を明示化しようとする試みである
・“implicit morality of the state〔国家の暗黙の道徳性〕”とは、統治された政治的形態の統治において、圧倒的多数を占める“public official(公務員)”(例えば、行政機関の構成員)が暗黙に実践している慣行である。
・残念ながらこれをハッキリさせるには、私のビジネス倫理の研究と同じように面倒なプロセスが必要となっており、まず社会のおける国家の役割を「俯瞰的(big picture)」に捉えねばならない。
・なので、本書の大部分が、行政それ事態に関してよりも、自由民主主義国家の歴史と、自由民主主義国家が現在の社会においていかにして重要な機能を担うようになったのかに関するものとなっている。
・公務員が職業倫理について何を考えているのかを理解しようとするのは、実業家の職業倫理を理解するよりかなり難しい。
・成功している実業家は、社交的で独断的な傾向があるので、自分が働いている世界がどう機能しているのか熱心に議論したがる。
・しかし、行政府の官僚は、実業家とは正反対の資質に基づいて選ばれている。
・ウェストミンスター型民主主義国家において、公務員は“Whitehall ethos(ホワイトホールのエートス)”に従事している。
・〔「ホワイトホールのエートス」:ホワイトホールはロンドンの官庁街名。国家公務員を統べる価値観・信念・行動様式等のこと〕
・ホワイトホールのエートスでは、「慎重さ」「秘密主義」「匿名性」が重視されている。
・ホワイトホールのエートスは制度的には利点だが、部外者からは、公務員制度がどのように機能しているのか非常に理解しづらくなっている。
・国家公務員は、積極的秘密主義でなくても、極めて目立たない存在なのだ。
・大学での公共政策学部は、退職した国家公務員をかなり再雇用しており、ここで教えることの利点の1つになっている。
・退職した国家公務員は、かなり社交的・饒舌になる傾向がある。
なので、私は、トロント大学公共政策・ガバナンス大学院の同僚達(特に元枢密院事務官のMel Cappe)との対話や交流から大きな恩恵を受けている。
・「理念」と「価値観」の語義的曖昧性を指摘してくれた、Alex Himelfarbにも感謝したい。
・前枢密院事務官との交流だけでなく、大学院で一時的に学ぶことになった国家公務員達の教師を努めたことでも、多くの恩恵を受けている。
・トロント大の中国の中山大学の交流プログラムで、中国の国有企業の管理職の教師を努めたことも、異なる政治制度(社会主義)に従事している外国人の目を通して、西洋の民主主義の政治制度がどのように機能しているのかを見るのは非常に有益であった。
・本書は、公共政策学部の学生の教材に使用したので、学生からのフィードバックにも感謝する。
・4章はいくつかの大学で発表された論文『福祉国家の3つの規範モデル』を改訂したものである。
・最後に本のタイトルについて。タイトルの“machinery of government(行政機構)”という言葉は、ジョン・スチュアート・ミルが著作『代議制統治論』で使用している造語である。ミルはこの言葉を国家官僚組織の通常業務を表す言葉として使っている。
・〔“machinery of government”は直訳すると「行政・統治の機械的組織」。過去の日本語文献では「政治機構」と訳されている事例が多いが、本ブログでは「行政機構」と訳している。〕
〔日本語訳語一覧:必ずしも用語として統一した訳語は使用していない。文脈に合わせて複数の訳語を使い分けている。
“Machinery of Government”:行政機構、
“Public Administration”:行政、行政学
“Privy Council Office”:枢密院事務局
“Clerk of the Privy Council”:枢密院事務官
“Deputy Minister to the Prime Minister”:副首相:日本における省庁事務次官
“Multicultural Citizenship”:多文化的市民権
“public administration”:公共統治
“public official”:公務員
“civil service”:官公庁、行政府、行政職員、行政府官僚、公務員、省庁官僚〕
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?