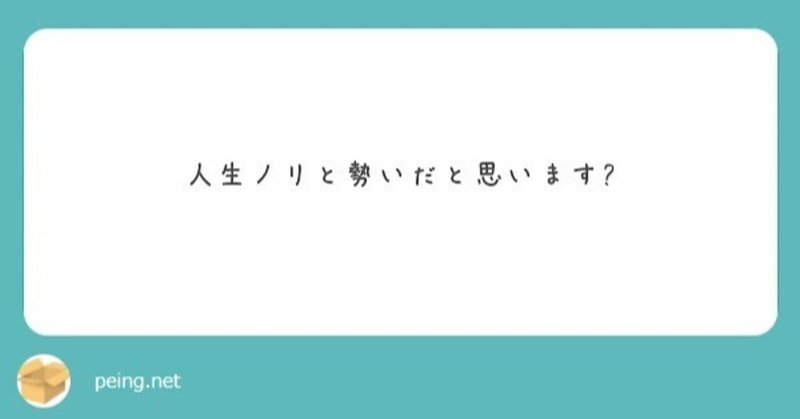
Q.人生ノリと勢いだと思います?
A.「転ばぬ先の杖」という日本のことわざがあります。
これは「前もって用心していれば、失敗することはない」という意味です。
このことわざを英訳すると「Look before you leap」。
一方、最初と最後の単語を入れ替えた「Leap before you look」という英語のことわざもあります。
このことわざを和訳すると「見る前に跳べ」。
もう少し考えてから、もう少し様子を見てから、などと言っていたらチャンスはどんどん逃げていって、目の前にあるハードルを跳ぶことが怖くなります。
そういうときこそ見る前に跳んでみる。
もちろん見る前に跳んでなんかしたら、転んだり落ちたりしてケガすることもあるでしょう。
しかし、「跳ばないで待っているより、跳んで失敗した方が断然学ぶものが多い」という意味です。
最後に成功を収めるのは、リスクを怖がらずに跳んで、たくさん失敗した人なのです。
漫才師で映画監督でもあるビートたけしさんは、この言葉を『たけしイズム』の神髄として座右の銘に選び、また同タイトルの曲を歌っています。
他に1986年に出版されたビートたけしの私小説集『あのひと』では、あとがきで以下のように書き残しています。
『見るまえに跳べ』-- あとがきにかえて
大江健三郎の初期の短編小説に『見るまえに跳べ』という作品がある。学生時代に読んだから内容についてはあらかた忘れてしまっているが、題名だけは鮮烈な印象となっていまも強く残っている。
見るまえに跳べ、好きなことばだ。
昔から何度となくそのことばを口に出していってみたことがある。そして、いうだけでなく、俺はそのことば通りに生きてきたような気がする。小説家でもなく学者でもない俺にとって、見る前に跳べ、は観念上の問題ではなく、生き方そのものだったと思う。
子供のころときから、なにか思い立ったときにすぐさま行動しなければなにもできない性格だった。少しでも時間を置いてあれこれ考えていると、必ず頭の中でブレーキがかかり、行動するのをやめてしまったものだ。
そんな自分の生理が嫌だったから、思ったことはすぐに実行する癖ができたのではないだろうか。見るまえに跳べ、ということばに感動したのもそうした自分だったからだろう。
大学を中退したときも、辞めようと思ったその日のうちにスッパリ辞めてしまった。一日あいだを置いて酒でも飲みながらいろいろと考えていたら、とても辞められなかっただろう。最近でも、例えば、コンサートをやろうと思ったらその場で日取りや会場を決めてしまうことにしている。やることを決定しておいてから、さてなにをやるのか、あれこれ思い悩むという順番だ。コンサートに耐えうる立派なものを作って、それからコンサートをやるなどと思っていたら、永遠になにもできないことになる。とにかく、まずやってしまう、そしてあとから考えるというのが昔からの俺のパターンなのだ。やってしまえば、どうにか格好はつくものだ。その意味では俺の人生はいままでのところ、“フォローの人生”だったのかもしれない。
もちろん失敗もある。大学を中退して間もない頃、金を貯めて外国に行き、通訳になろうと思ったことがある。で、すぐにタクシー運転手になった。金を稼ぐためだ。結局、金が溜まるまで時間がかかりすぎるので途中でいやになってしまったけれど、いちおう通訳になるという夢に向かってステップは刻んだのだった。これまでに俺はいろんなことをやってきたと自分でも思う。成功したとはいえないけれど、他人に、「オレはいろいろなものに手をつけた。やるだけはやった」と言い切る自信はある。持続力は無いかもしれないが、飛び出しのエネルギーだけは他人に負けないものがあるような気がする。それは一種のスポーツ感覚なのかもしれない。
俺の廻りにはなぜか運動神経のいいやつばかりが集まってくる。ラッシャー板前は柔道部のキャプテンだったし、大森はバレーボール、井手や足が早くて野球は天才的。東はインターハイ出場組だし、古田は空手とラクビー、タカは運動神経のかたまりだし、大阪はああ見えてもサッカーのCF、みんなスポーツのセンスがいい。
スポーツは理屈じゃない。理屈はやっぱりあとからつけるものだ。だから、自分の生理や感覚で人一倍強いものがあったら、その力の命じるままに動いてかまわないと思う。最低限のモラルを持ってさせいればどんどん走ればいい。
もちろん、大量テロとかのヘンな方向に「見るまえに跳べ」だったら困るけども。テロするなら、自分の内なるテロにならないといけない。
この初めての小説集は、30代の後半になって俺が見えるまえに跳んでみたひとつの結果だ。小説を書くことも俺にとっては一種のスポーツなのだと思う。楽しいスポーツを見るような感じで、この本を読んでもらえたら、ちょっとうれしい。
このあとがきを読んで、もしもあなたの中で言葉以上の震動が起こったのならば、たけしさんの言う言葉の通り「その力の命じるままに動いてかまわないと思う。最低限のモラルを持ってさせいればどんどん走ればいい。」でしょう。
そして、それは私も同じで「見る前に跳べ」な判断をしたことで自身に新たな視点・選択肢を何度も与えてくれました。
あまりに無計画だと身の破滅を招きますが、あまりに計画にがんじがらめで縛られるのもまた危険です。
だから「計画は慎重に、行動は大胆に」、つまりは「見る前に跳べ」。
人が羨むような情熱的な人生には「ノリと勢い」が編まれているのは、そういう理由かもしれません。
---------------
ちなみに、(たけしさんのあとがきでも記載されていた)大江健三郎の短編小説タイトルにもなっている「見る前に跳べ」。
この言葉は20世紀イギリスの詩人、W・H・オーデンの作品『見る前に跳べ(Leap before you look)』から来ており、大江氏は「勇気を鼓舞してくれるものとして引用した」と述べています。
『見る前に跳べ(Leap before you look)』
危険の感覚が消え失せてはならない
道はたしかに短くて急だ
ここからはどんなに緩やかに見えても、
見たければ見よ だが跳ばねばならぬ
気丈夫な奴でも眠りのなかでは
ごく簡単な約束も破ってしまう、
恐怖ではなく惰性こそ
消えやすい傾向がある
がらくたどものせわしなさが
ゴシップとかあてこすりとかビールとかが
毎年気の利いた皮肉をいくらかは生み出す、
笑いたければ笑え だが跳ばねばならぬ
十分着られそうな服でも
センスがあって安いとは限らぬ
羊のように生きるのが不満でないかぎり
何が消え去っても気にはならぬ
慈善活動については色々といえる
だが人のいないところで喜びを感じるのは
ひそかに泣くことよりずっとむつかしい、
誰も見てはいない、だが跳ばねばならぬ
一万米の深海のような深い孤独に
僕らの横たわるベッドがある
僕は君を愛しているんだが、
君は跳ばねばならない
僕らの安全の夢は消え去らねばならないのだ
また、映画評論家の町山智浩さんが『テネット』の批評を述べていたときにも引用しています。
実存主義の話です。ノーランは作品中で「a leap of faith」という言葉をよく使いますが、それは実存哲学の始祖、キルケゴールの思想を表現する言葉です。別の言葉で言えば「見る前に跳べ」です。
19世紀デンマークの哲学者、キルケゴールの著書『死に至る病』に書かれている「信仰の飛躍」と翻訳された一文。
『インセプション』の台詞でも登場する、この「a leap of faith」について、町山氏はこの言葉の解説に、以下のように述べています。
「信仰の飛躍」、これを英語では「a leap of faith」と言います。直訳では「確信のジャンプ」とわかりにくいですが、意味するところは「結果が不確実でも、出来ると信じてやること」と、オックスフォード大辞典にあります。
つまり「思いきった決断」。「Take a leap of faith」にすれば「思いきって決断する」と、動きのある表現になります。
イギリスのEU離脱もアメリカのトランプ大統領選出も、両国国民の「leap of faith」。
こう考えると、ジャーナリスティックには「大きな賭け」とも訳せるフレーズですね。
「Take a leap of faith」=「信じて飛び込め」=「見る前に跳べ」。
この言葉の背景を少し覗いただけでも、目の前のハードルに「ノリと勢い」で跳びたくなってきたのでしょうか。
えー、ここまで能書きを垂れる講師スタンスの私も、今回の講義を通じて重々に肝に銘じます。
だって、さあ、「教える」と「出来る」は必ずしもセットじゃないじゃん……ねえ?(上目遣い)
---------------
【あなたからのご質問、ノージャンルでお待ちしています】
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【螢雪書店[本日の推薦図書]】
本日も最後までお読み頂きありがとうございます。この記事は無料です。この記事をスキ以上に応援したい方は、下にあるサポートをご利用ください。サポートして頂いた売上は、今後の記事を書く為の活動資金にあてさせて頂きます。不審な誤字や表現にお気づきの場合は、コメント欄までお知らせください。
