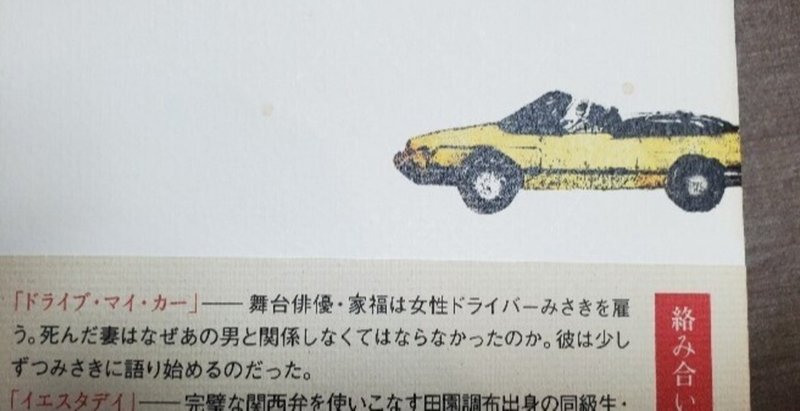
ルッキズムはNGの時代に、小説「ドライブ・マイ・カー」で、村上春樹が「ドライバー、みさき」の容姿を克明に描写した、その表現に注目して、作品批評を試みる。
映画はまだ観ていないのですが。予告編を見る限り、アカデミー賞で「脚色賞」ノミネートされているだけあって、初めの設定を利用して、ものすごく別物、ドラマチックな展開になっているようだな。
キャスティングも、「おー、そうか」、かなり大胆にイメージが変えられたり年齢が変えられたりしている。特に男性二人。映画HPの人物紹介とキャスティングを見ながら、小説の設定と比較して、まずいろいろ整理してみる。
主人公、家福についてわかっていることを、小説から。年齢関係から整理しよう。(名前も、小説では名字の「家福」しかわからないと思うのだが、映画のHPでは家福悠介、フルネームがついている。)
妻と出会ったのは29歳。結婚してたのは30歳で、結婚期間は20年間近く(ということは19年とする)。足し算をすると、妻を亡くした49歳のとき。その直後に高槻と友達になる。それを、今からおよそ10年前と言っている。つまり、今の年齢は、59歳くらい。生きていれば、今、24歳になる子供を、生まれて三日目で亡くしている。35歳の時のことだ。妻の浮気はその後からという。
職業・容姿については小説から引用すると
「家福はいちおう「性格俳優」ということになっていたし、入ってくる役もいくぶん癖のある脇役であることが多かった。顔はいささか細長すぎたし、髪は若いうちからもう薄くなり始めていた。主役には向かない」
妻が正統的美人女優で、妻の方が初めは、仕事の上ではそれにふさわしい扱い、おそらくはヒロイン役とか、そういう立場だったが、
「しかし年齢を重ねるにつれて、彼の方がむしろ個性派の俳優として、世間で評価されるようになっていった」
とある。この条件だと、本当は西村雅彦さんあたりのイメージではないのだろうか。現在61歳。若い時から髪が薄く、だんだん演技派個性派として認められ。ねえ。そうでしょう。
→ところが、映画ではイケメン西島秀俊さんがキャスティングされたわけだ。映画の主役なもんだから。たしかにイケメンだけれど演技派だしちょっと変人だし、しかし。髪は薄くないわな。
西島さんは、今、51歳だから、高槻と会っている回想シーンのほうの年齢にぴったり、という感じだな。ドライバーと一緒の「現在」だと、ちょっと若すぎる。
ドライバー渡利みさきは、24歳。このnoteで書こうと思っているのは、この人物の容姿について、「ルッキズム」と批判されないように注意しながらも、そのことはわりと大切な要素なので、村上春樹が、いろいろな人物のセリフとして、また地の文として、どう、容姿があまり優れていないことについて書いているか。なのでそれは後で論じるとして。とりあえず、24歳で、北海道の十二滝町というかなりの僻地出身らしい。みさきが八歳のときに父親は家を出てみさきと母を捨てた。家福とみさきの父は同年齢だ。みさきの母はみさきにつらくあたり、みさきが17歳の時に、酔っ払い運転で木にぶつかり、即死している。
→みさきを演じているのは三浦透子26歳。北海道出身というのも、みさきと同じだ。容姿などの役作りについては、後ほど小説の容姿描写を見ながら分析する。
妻の浮気相手、高槻について、家福と会っている10年前のこととしてこう書いてある。(名前も、家福同様、映画HPでしか下の名前は分からない。高槻耕史となっている。男性は姓のみであり、女性はフルネームが明かされ、下の名前で呼ばれるのである。)
「長身で、顔立ちの良い、いわゆる二枚目の俳優だった。四十代の初め、とくに演技がうまいわけでない。存在感に味があるというのでもない。役柄も限られている。だいたいは感じのいい爽やかな中年男性の役だ。」
「僕が最後に友だちを作ったのは十年近く前のことになる。」と家福はあきらめて目を開けて行った。「友だちらしきものと言った方が正確かもしれないな、相手は僕より六つか七つ年下で、なかなかいいやつでもあった。
現在シーンには登場しないが、もし映画に現在シーンがあるなら50歳を過ぎているはず。回想シーンで40代前半。ところがキャスティングは
→岡田将生かあ。さらに若く年齢変更。32歳だから。しかし「二枚目だけれど、底が浅い感じ」という役柄を得意としている、という役を演じるには、まあなかなか最適な感じかと。また、妻は浮気相手にいつも自分より若い俳優を選んでいた、ということを表現しようとすると、これくらい若くした方が、その感じが出ると考えたのかな。
小説の中では、家福と高槻と会っているシーンは家福49歳、「相手は6つか7つ年下で」と小説中にもあるから、高槻42~43歳。
小説中では。西島と岡田将生ほど、年齢は離れていない。
妻、家福音は、主人公より2歳年下。出会った時は27歳で、結婚が28歳。子どもを出産して直後になくしたのが33歳で、死んだとき47歳。死んだときには高槻とはもう終わっていたのだが、おそらく40代前半のどの時点かで4歳か5歳年下の高槻と「三か月か四か月の間」高槻と浮気して、何度かセックスしていたのである。
→キャスティングされたのは霧島れいかさん、41歳。回想シーンは、おそらく高槻との浮気シーンと死の直前あたりが多いだろうことを考えると、死んだときには若いが、浮気回想シーン年齢的には、まあほんのちょっと若いくらい。なかなかいい線だと思う。
さて、本題。この小説、妻が正統的美人俳優、浮気相手・高槻がこれまた、顔立ちのよい二枚目俳優。に対して、主人公・家福は若はげ気味で面長すぎの個性派俳優。その専属ドライバーになる渡利みさきは田舎出身の容姿に恵まれていない女性。家福とみさきは、年齢関係的に、「なくした娘」と「自分を捨てた父」の年齢関係だということで、「異性」としてではなく、疑似的「父と娘」のようでもあり、この父娘は、「容姿に恵まれない」という共通ベース、疑似家族的類似を持つ関係として描かれているのである。
いまどき、女性の容姿を描写するときに、あまりに露骨に否定的な表現はいかん。いかんとはいえ、この「容姿に恵まれていない」ということをベースとした主人公二人が、「美人妻と美男俳優の浮気」ということの与える痛み、ダメージについて考えるというのが、作品的にすごくだいじなことなのである。だから、みさきの容姿については、執拗に詳細に、村上春樹は描写する。地の文でも、また会話文で、誰かの発言としても。
小説の初めから、順を追っていく。
まず、修理工場の経営者、大場が、家福に専属ドライバーとして推薦するときの会話文。
「でもね、なんというか、ちょいと変なところがありまして」
「どんな?」
「ぶっきらぼうで、無口で、むやみにタバコを吸います」と大場は言った。「お会いになったらわかると思うんですが、かわいげのある娘というようなタイプじゃないんです。ほとんどにこりともしません。それからはっきり言って、ちょっとぶすいかもしれません」
「それはかまわない。あまり美人だとこっちも落ち着かないし、妙な噂が立っても困る」
言葉おじさん的には「ぶすだ」という正しく形容動詞もしくは名詞+断定の助動詞ではなく、あまり使わない「ぶすい」という誤用形容詞を使っている点に、村上春樹の配慮があるように思う。ブスというきつい言葉ではなく、無粋ということばでもあるような「ぶすい」(本では傍点がついている)という表現。ファッションが野暮だ、という無粋といったようでもあるが、文脈から、これは「美人ではない、ブスだ」ということを伝えようとしている。伝わっている。しかし「ぶすい」という言い方をしているのが、なんだか、印象に残ったわけだ。この一文があったので、このnoteも書こうと思ったし、その点に注目して読解したくなったのだ。
で、次は初対面の時。地の文だけれど、家福がそう見た、と読める。
身長は一六五㎝くらいで、太ってはいないが、肩幅は広く、体格ががっちりしていた。右の首筋に大きめのオリーブくらいのサイズの楕円形の紫色のアザがあったが、彼女はそれを外にさらすことにとくに抵抗を感じていないようだった。たっぷりとした真っ黒な髪は邪魔にならないように後ろでまとめられていた。彼女はどのような見地からも美人とは言えなかったし、大場が言ったようにひどく素っ気ない顔をしていた。頬にはにきびのあとが少し残っていた。目が大きく、瞳はくっきりとしているが、それはどことなく疑り深そうな色を浮かべていた。目が大きいぶん、その色も濃く見えた。両耳は大きく、まるで僻地に備えられた受信装置のように見えた。五月にしてはいささか厚すぎる、男物のヘリンボーンのジャケットを着て、茶色のコットンパンツをはき、コンバースの黒いスニーカーを履いていた。ジャケットの下は白い長そでのTシャツ、胸はかなり大きい方だ。
これは、意図をもって、容姿が、この小説において重要だからこそ、こんなに克明に、ある意味、容赦なく、描写をしているのである。どういう意図か。それはおいおい分析していく。とにかく、どう読んでも、意図がなければ、こんなに描写しない。
彼女の運転している様子も詳細だ。操作についての記述まで引用すると長くなるので、外見的印象と関係するところだけ、引用する。
彼女は運転していないときより、むしろ運転しているときの方が、緊張がうまくとれるらしかった。その表情の素っ気なさは薄らぎ、目つきもいくらか温和になっていた。
彼女はオープンカーが屋根というか幌を上げているとき、信号待ちの合間にタバコを吸うのだが
吸い殻には口紅はついていなかった。爪のマニキュアもない。化粧というものをほとんどしていないようだ。
彼女は、ほとんど表情を変えない。家福が音楽をかけても
彼女がそれらの音楽を好んでいるのか、苦痛に思っているのか、あるいはまったく聞こえていないのか、家福にはどれとも判断できなかった。感情の動きが表に出てこない娘なのだ。
みさきが自分の容姿のことをどう考えているかで、大事な発言がある。母の交通事故死と父の失踪を、家福に話している車中の会話だ。
「君は酒はいっさい飲まないのか?」家福は話題を変えるためにそう尋ねた。
「体質的にアルコールを受け入れないみたいです」とみさきは言った。「母親がお酒でよく問題を起こしていた人で、そのことも関係しているかもしれません」
「お母さんは今でも問題をおこしているの?」みさきは何度が首を振った。「母は亡くなりました。酔っぱらって運転して、ハンドル操作を誤り、スピンして道路から飛び出し、木にぶつかったんです。ほとんど即死でした。私が十七のときのことです」
「気の毒に」と家福は言った。
「自業自得です」とみさきはあっさりと言った。「いつかはそういうことは必ず起こっていたでしょう。早いか遅いか、それだけの違いです。」
しばらく沈黙があった。
「お父さんは?」
「どこにいるかも知りません。私が八歳のときに家を出て、それから一度も合っていません。連絡もありません。そのことで母は私を責めていました」
「どうして?」
「私は一人っ子だったんです。私がもっと可愛いきれいな女の子だったら、父は家を出ていなかったはずだ。母はいつもそう言っていました。私が生まれつき醜いから、捨てていったんだって。」
「君は醜くなんかない」と家福は静かな声で言った。「お母さんはそう思いたかっただけだよ」
このあと、家福に対してみさきが「友達がいないのか」質問し、話の流れで、妻と浮気していた男としばらくの間、友達だったという、ヘビーな話をする。
それを聞いていたみさきについての描写
みさきは大きく深呼吸した。胸がジャケットの下でゆっくり盛り上がり、そして沈んだ。
胸についての描写、ふたつめ。これは家福が性的な目でみさきをみているということではない。と思う。家福がではないが、「容姿についての複雑なコンプレックス」から、男性物のジャケットを着て、化粧もしないみさきが、まぎれもなく女性である、ということ、女性として、家福と妻と高槻のことについて理解し、考え、意見を持つことができる女性であることを、表現している、ある種、終結部への伏線である。
すこし話はずれるが、この会話の中で
「それで家福さんには理解できたんですか。どうして奥さんがその人と寝たか?」という質問をされて、あれこれと要領を得ない答えをし、追い打ちをかけるようにこう聞かれると、家福は象徴的動作をしてしまう。
「でも理解はできなくても、その人と友達ではあり続けたんですね?」
家福はもう一度野球帽を取り、今度はそれを膝の上に載せた。そして手のひらで頭頂部をごしごしと撫でた。
そう、家福は、若い時から髪が薄いのだ。西島秀俊ではなく、西村雅彦を想像して、このシーンを思い描いてほしい。髪が薄い家福は野球帽をいつもかぶっている。いちばん悩んだり難しいことを考えると、その、薄くなっている頭頂部をごしごしと手のひらでこすってしまうという癖があるのかもしれない。容姿にコンプレックスを抱いているのは、みさきだけではない。このシーン、映画でどのように描かれるかわからないが、小説では、二人ともとても深刻な告白をしあいながら、じつはちょっと可愛らしい感じのシーンでもある。
家福は高槻と月二回ほど会っては酒を飲むということを半年ほど繰り返したのちに、会うのをやめた。電話に出るのもやめたら、そのうち電話もかかってこなくなった。ということを車中の会話でした後で、ルールを破って、屋根をおろしたままでタバコをすってもいいよ、と家福がいい、みさきがタバこを吸う、というシーンになる。小説の最終盤である。
みさきは窓ガラスを下ろし、クルマのライターでマールボロに火をつけた。そして煙を大きく吸い込み、うまそうに目を細めた。しばらく肺に留めてから、窓の外にゆっくりと吐き出した。
「命取りになるぞ」と家福は言った。
「そんなこと言えば、生きていること自体が命取りです」とみさきは言った。
家福は笑った。「ひとつの考え方ではある」
「家福さんが笑ったのを初めて見ました」とみさきは言った。
そう言われれはそうかもしれないと家福は思った。演技ではなく笑ったのはずいぶん久しぶりかもしれない。
「前から言おうと思っていたんだが」と彼は言った。「よく見ると君はなかなか可愛い。ちっとも醜くなんかない」
「ありがとうございます。私も醜いとは思いません。ただあまり器量がよくないだけです。ソーニャと同じように。」
家福は少し驚いてみさきを見た。「『ヴァーニャ叔父』を読んだんだね」
「毎日台詞を細切れに、順序もでたらめに聞かされているうちに、どんな話なのか知りたくなったんです。私にも好奇心はあります」とみさきは言った。「『ああ、いやだ。たまらない。どうして私はこうも不器量にうまれついたんだろう?つくづく嫌になってしまう』悲しい芝居ですね。」
「救いのない話だ。」と家福は言った。「『ああ、やりきれない。どうにかしてくれ。私はもう四十七になる。六十で死ぬとして、これから十三年生きなくちゃならない。長過ぎる。その十三年をいったいどうやって過ごしていけばいいんだ?どんなことをして毎日を埋めていけばいいんだ。』当時の人たちはだいたい六十で死んでいた。ヴァーニャ叔父さんは今の時代にうまれなくてまだよかったかもしれない。」
和んだ空気の中で発した、家福のいささかうかつともいえる発言
「よく見ると君はなかなか可愛い。ちっとも醜くなんかない」
これに対し、みさきが
「私も醜いとは思いません。ただあまり器量がよくないだけです。ソーニャのように」
ここ『ヴァーニャ叔父』における、ソーニャという登場人物について分からないと意味不明なのでかいつまんで説明する。大学教授の娘で器量に恵まれないソーニャは、父の主治医アーストロフに恋をするが、アーストロフは大学教授の美しい後妻、ソーニャの義母であるエレーナに恋をしていて、ソーニャは失恋する。主人公ヴァーニャ叔父は、大学教授を、尊敬し、その領地経営を長年努力して来たのに、教授は領地を売り払って移住するという。長年の努力を無駄にされたと、ヴァーニャ叔父は絶望して教授をピストルで撃とうとして失敗する。器量に恵まれないソーニャの人生、努力が報われないヴァーニャ叔父さんの人生を、それでも生きて行かなけばならない。それでも人生は続く、という演劇、戯曲である。
後半の「47歳になる私が60歳まで生きなければならない」というヴァーニャ叔父のセリフの期間は、家福の、妻を亡くしてから、今現在までの人生の時期にほぼ重なる。妻を亡くした空虚の中を生きてきて、60歳を迎えようとするが、現代の日本に生きている限り、まだ長い人生が続くのである。
ここで、みさきのことを、疑似・父と娘の関係としても年齢差からも「大人と子供」だと思っていた家福に対して、みさきが「わたしも自立した、自分の考えを持つ大人である」という態度が強く表明される。別に家福を批判しているわけではない。そうではなく、気づくと、しっかりとした大人になっている。みさきは自立した一人の大人の女性である。その気づき、関係の変化が、この会話にはある。器量があまりよくないだけで醜くはない。そう自らのことを受け入れている。戯曲を読む知的好奇心もある。
そして、「なぜ妻が高槻というなんでもない、底の浅い男に心を惹かれ、抱かれなくてはならなかったのか」という家福の問いに、自立した女性としての意見をみさきが語る。
「それはある意味では、家福さん自身に向けられた侮辱のようにさえ感じられる、そういうことですか?」
家福は少し考え、正直にそう認めた。「そういうことかもしれない」
「奥さんはその人に、心なんて惹かれていなかったんじゃないですか」とみさきはとても簡潔に言った。「だから寝たんです」
家福は遠い風景を見るみたいに、みさきの横顔をただ眺めていた。彼女はワイパーを素早く動かして、フロントガラスについた水滴を取った。新しくなった一対のブレードが、不服を言い立てる双子のように硬く軋んだ音を立てた。
「女の人にはそういうところがあるんです」とみさきは付け加えた。
言葉は浮かんでこなかった。だから家福は沈黙を守った。
「そういうのって、病のようなものなんです。家福さん。考えてもどうなるものでもありません。私の父が私たちを捨てていったのも、母親が私をとことん痛めつけたのも、みんな病がやったことです。頭で考えても仕方ありません。こちらでやりくりして、吞み込んで、ただやっていくしかないんです。」
どうやっても呑み込むことのできなかった妻と高槻のことだから、家福もみさきの言葉ですべて納得したわけではなかろう。しかし、わが子が育っていればその年になっていたかもしれない、器量の良くない、つらい人生の経験をしてきたドライバーの女性に、そう言われるという体験自体が、家福にとって、この先を人生を生きていく上での救いになっているのである。初めは何を考えているのかもまるで分らなかった娘/みさきが、戯曲を読んでくれたこと、つまり自分の仕事への興味も持ってくれていたことも含めて。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
