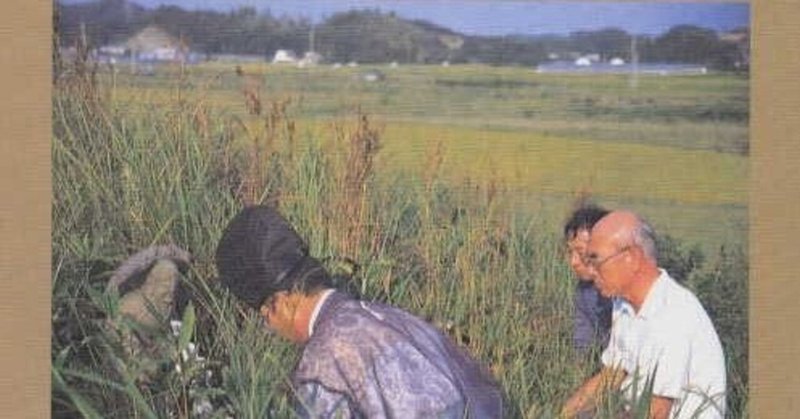
青山幹雄『宮崎の田の神像』解説草稿
本稿は、青山幹雄『宮崎の田の神像(みやざき21世紀文庫)』(1997、鉱脈社)再刊の際、解説の草稿である。
はじめに
実にユーモラスな田の神像、これが一般的な田の神像に対するイメージであろう。頭にシキを被り、手には大きなメシゲを持ち、タスキ掛けに裁着け袴をはき、手足をあげて踊り、眉目を下げ口を曲げ笑った庶民的な姿をしている「田の神舞型」が従来田の神像の代表とされ、また近年の観光パンフレットなどにみられるタノカンサアはえびの市などの農民型が主流となっている。しかし本書を読むに当たって読者にはこのような先入観を捨てていただきたい。例えば教師が生徒のそれぞれの個性を認める姿勢のようにである。そうすることが、田の神像を研究するうえで宮崎県というフィールドがいかなる重要性を持つかを理解する早道になるのである。
宮崎県は他県との関わりなしに歴史や民俗について語ることはできない。なかでも鹿児島県との関係は古代から近代に至るまで密接であり、近世における薩摩藩領の文化は現在にまで文化やことば、考え方にまでその影響を残している。民俗文化に関しては、旧薩摩藩領をまとめて「南九州」という括りで研究されることが多い。両県にまたがるテーマの場合、まずは各県ごとの研究が積み重ねられ、次に南九州という範囲で両県の研究が統合されるというのが理想的であるが、宮崎県側は研究者の数も少なく刊行物も少ない状況で、「南九州の・・・」と題する文献でもほとんど鹿児島県の事例のみで構成されることが多く、民俗研究に関しては鹿児島県が主導権を握っている。そのようななか田の神研究については本書が宮崎県側の独自性を主張した、南九州の田の神像を考えるうえで欠かせない文献とされている。様々な民俗事象の中でも田の神像についての研究が宮崎県の事例無しには語られないという状況は本書の存在に負うところが大きいのである。ただし、宮崎県と鹿児島県で分類用語が異なっており、本解説でわかりにくい点がある。青山幹雄氏は田の神を大きく「神官型」「地蔵型」「農民型」の大きく三つに分類しているが、鹿児島県の研究者には、それぞれ「神像型」「仏像型」「田の神舞型」という用語が使われている。以下、鹿児島の記述については後者の分類を採用するが、その使い分けの意味については後述する。
田の神像研究において宮崎県というフィールドの重要性は数多く上げられるが、大きくは二つの点を指摘できる。まずは神官型の源流が宮崎県であるということ、次に農民型。田の神像の発生としては地蔵型が最も古く、次いで神官型が続いたとされている。その神官型の源流が現在の宮崎県小林市であることは本書によっても十分証明され、その後鹿児島県の研究者によっても認められているところである。さらに近年、小野重朗氏によって提起されている農民型のモデルとなった田の神舞は宮崎県米良地方の神楽にみられる「室(へや)の神」という番付や高鍋神楽にみられる「盤石(ばんぜき)」という番付にあるという説(「田の神舞の成立」『鹿児島民俗』第九八号)によって、ますます田の神像の発生について研究するうえで宮崎県というフィールドが重要になってきている。今後ますます宮崎県と鹿児島県を統合する研究が進められるなか、宮崎県における田の神像研究の先駆的業績となった本書が再評価されている。
発刊当時の時代背景
青山氏は大正四年佐土原町生まれで、昭和九年に宮崎師範学校を卒業、県内の小学校に勤務。昭和四九年に退職後は郷土史などの編集に力を注がれている。現在は佐土原町内の寺社縁起について調査をされており、当時田の神像を研究する上で重要だと思っていた霧島信仰を再評価しなければならないような資料を研究中であるという。
本書の内容は主に「日向の田の神像」『宮崎県地方史研究紀要 第一輯』の論考が基本になっている。その後、「佐土原城と城下町」『宮崎県地方史研究紀要 第六輯』を『佐土原城と城下町』として、「まぼろしの佐土原人形」『宮崎県地方史研究紀要 第一四輯』を『佐土原土人形の世界』として確実に業績を積み重ねてきている。こうした郷土史研究の延長線上に田の神像研究があったという。それまでの郷土史の研究で学んだことは、古文書や石塔の文字の解読には個人によって読み方が違ったり、読み間違いがあったりして、結局は自分で再調査することが多かった。一つ間違えば考察も間違ってしまうために、自ら確認できたことの範囲で言えること、考えられることに限定したという。当時としては前に研究者はいないが、かえってゼロから歩いて確認した事例のみからいえることに専念したといい、二九九例という事例は県内の田の神像の総数からいえばほぼ半分になるであろうが、宮崎の田の神像の性格を把握するには十分といえるであろう。ちなみに田の神像調査を始めたときのことを次のように振り返っている。
昭和四十三年宮崎市より初めての地域、西諸県郡の野尻小学校に勤務中、校区内各地を見渡せる路の傍らに、豊作を請い願う石像の田の神さんが鎮座しておられるのに気付き、素朴なその姿にひかれて尋ね歩くうち、その分布が旧薩摩藩全域のみに広がっている石像と気付き、仕事の余暇活動として、宮崎県内の田の神像に限って調査収集することにしました。初めは地理不案内と、よそ者にはその所在を隠して教えないという土地の仕来たりにあい、簡単にはお逢いできない田の神さんでしたが、その後退職するまでの七年間に、三百余体の田の神像の一つ一つにお逢いし、それも我が手で触れ、話し掛け、聞き廻り、問い掛け、書き留めして、見届ける事が出来ました。(『佐土原土人形の世界』)
青山幹雄氏が田の神像の調査を初めた昭和四十三年から本書が刊行された昭和五十四年という期間には、鹿児島県においても基礎調査から全県的な分布の把握、そして田の神像成立の解明へと研究が進んでいた。研究としては鹿児島県側がはるかに進んでおり、青山氏は、数多くの田の神に関する文献を読みデスクワークは万全であったが、高岡を調査する頃から一切の文献を読まなくなったという。なぜならすべてが鹿児島の田の神像についての文献で、頭が鹿児島になっていたという。宮崎の田の神には宮崎の雰囲気と型があり、それはそれで田の神の独自性なのであるが、鹿児島を中心に考えると、いわゆる田の神舞型が基本になってしまうのである。当時の状況については次のように述べているが、後述するように現状は余り変わったとはいえない。
この田の神研究については、鹿児島県では、寺師三千夫氏の『薩摩のタノカン』をはじめ、多数の出版物があり研究にことかかない有様ですが、宮崎県側の神像については全国的な研究は進んでいないし、発表もされていないのが実情です。
本書を執筆するにあたり、青山氏には二つの難関があった。一つは前に研究者がいない。野尻町の真方良穂氏らなど一部地域の郷土の研究者はいるが、全県的に研究は遅れ、ほとんどゼロからの調査であった。その土地にまでは車で行き、ある場所に車を置いて後は土地の人々に尋ねながらただひたすら歩いたという。もう一つは田の神の所在を教えてくれない。この実感は実際に調査するまでは想像もつかなかったことではあるというが、はじめは何故教えてくれないかが分からなかったという。その理由については本書で印象的に語られているとおりである。
青山氏の文章の特徴は一般的に分かりやすく、紀行文としても叙情的であり、調査を積んだ順に構成されているので、それぞれの地域で気づいた疑問を解決していくという構成になっている。青山氏の優しげな語り口にもよるのだろうが、読者も同様に田の神を尋ね歩いているような経験ができる。青山氏が小学校の教諭であったことが大きく関わっている。本書を読み返すと、田の神を生徒を見つめるようなまなざしから出てくる表現に気づかされる。青山氏はこうした文章のスタイルについて次のように述べている。学校の先生をやっているとその土地の歴史や伝説などを知ることから始まると、地域への愛着も湧き、子供との共通話題ができるのでよい。特に民俗的な伝承は「あなたの爺さんから聞いた話ではこうこうだった」などというと、子供も関心を示したし、生徒との親近感が沸いたという。特に野尻町などの文献史料のないところでは、石塔や芸能や伝説、昔話などから入るとよいという。「永年の学校勤務中、受け持ち児童一人一人をはっきり把握するため、その家庭・地域・環境・土地の歴史等児童の周辺を調べ、それに浮かべて把握するよう努力してきましたが、それは教師の習性のようなもの」(『佐土原土人形の世界』)であったという。
田の神だけでなく、民俗全般にわたってその土地の空気というものを感じずにその土地の文化は語れない。本を読むだけではその土地の空気までは感じることはできない。田の神像もその信仰や人々の生活を知ることではじめてその田の神信仰の中の田の神像のことが分かりはじめる。像はいわばその信仰の抽象化されたものである。その土地その土地での文化が反映されて像が造られる。
題名を「宮崎の田の神」としたかったのですが、田の神像の「像」という文字を入れたのは田の神さんと生活される農村の方々の生活史に触れる暇がなく、生活史のない田の神という感がして、何となく昆虫採集で虫をピンで止め、その多さを語るのみの様で、恥ずかしくなったからでした。
(『佐土原土人形の世界』)
と述べるように、この著書ではその辺の所まで、『宮崎の田の神』というタイトルで田の神信仰についてまで触れたかったが、時間もその幅の広さもあってそこまでは及ばなかったという。その後『佐土原土人形の世界』では文化の背景まで触れることができたという。
さらに自らが歩いて調査した事例ということもあり、記述が詳細で、調査項目や論考の項目に関しては実に的を得た問題意識を持って書かれ、数多くの問題を残してはいるもののそこに整理された事例は入門書としては他にないものである。
鹿児島県の研究状況
本書では恣意的に鹿児島の研究について触れていないことは前述したとおりであるが、読者の好奇心に応えるためにここで鹿児島県における研究状況について簡単に説明を加えておきたい。
昭和九年の岡島銀次著『田之神』(鹿児島高等農林学校博物同志会発行)に始まる田の神研究は、民俗文化財として多くの地域から調査報告書(約五〇冊)が刊行され、郷土史(約三〇冊)にも取りあげられ、昭和五十九年には鹿児島県立図書館から『「田の神さあ」関係資料目録』が編集されている。野田千尋氏、山田慶晴氏、花田潔氏、平野良雄氏、向山勝貞氏らにより地方の雑誌に報告がなされている。
なかでも寺師三千夫氏と小野重朗氏の業績は鹿児島県を中心に、しかし宮崎県を視座に入れたかたちで、田の神像の分布とその発生について研究された。医者であった寺師氏は五二〇体の田の神石像を図表をもとに型の分布とその伝播経路について言及した画期的な著書『薩摩のタノカンサア』(鹿児島放送文化研究会)を昭和四十二年に刊行している。寺師氏に続き、小野重朗氏も昭和四十五年には『農耕儀礼の研究』(弘文堂)、昭和五十六年には『民俗神の系譜』(法政大学出版局)を刊行し、鹿児島県の田の神像についてはほぼ把握するに至っている。小野氏はその後『宮崎県史』(民俗1・2)の執筆を契機に宮崎県における田の神信仰について業績を残しているが、青山氏の成果を踏まえたものであることはいうまでもない。
以上のような研究成果を集大成したのが、昭和六十二年に行われた黎明館企画特別展「田の神」(村田煕・小野重朗監修)である。その図録には総数二〇一八体(宮崎県を含め)をもとに田の神像の発生と伝播を次のようにまとめている。南九州の田の神像を把握するために少々長くなるが引用する。
田の神像はまず、仏像型として造られた。それが薩摩半島中央部を中心として僧型になり、この型 は大隅半島のほうに伝えられたと考えられる。やや遅れて、薩摩半島中央部で僧型から旅僧型のものが考え出され、数多く造られた。大隅半島中部に分布している旅僧型の造立は、だいぶ遅れて一八世紀後半になってからである。出水・阿久根地方でもそれぞれ独特の旅僧型が造られたが、これも一八世紀末からのことである。仏像型にやや遅れて、宮崎県諸県地方で神像型椅像のものが、大口地方で神像型坐像のものが造られ始めた。神像型坐像はしばらくして姶良地方に伝えられた。また、日置地方を中心として立像の神像型のものが造られ始めたようである。大隅半島東部では神像型坐像にシキを被せ、メシゲとスリコギを持たせた神職型坐像が造られ、大隅半島南部では神像型立像がのものが考え出された。薩摩郡周辺で、神像型坐像のものとほぼ同時に神職型立像のものが造られ始めた。また、神社の神舞や田の神講で田の神舞を舞う神職の姿をかたどった田の神舞神職型が考え出された。この田の神舞神職型のものは変化に富み旅僧型と並んで数多くのものが造られた。さらに、旅僧型、神職型、田の神舞神職型のものから、さまざまの形をした田の神像が造られたと考えられる。
鹿児島県側のこうした田の神像の成立を考慮した上で宮崎県の田の神像の系譜を考えることが、今後の研究に必要な姿勢であろうことはいうまでもないことである。
田の神像の分類とその系譜
まずは分類について見ていく。青山幹雄氏は田の神を大きく「神官型」「地蔵型」「農民型」の大きく三つに分類している。この分類は寺師三千夫氏の分類に従っているというが、事例をまとめるための便宜上の分類であったようである。表の中で仏像型や頭布坐像など分類の他の用語が使われている点からも分かる。
「神官型」に関しては寺師三千夫氏の予想通り宮崎県がその発祥の地であることは一六〇頁と一六一頁の表から明らかであろう。その後も多くの研究者が追随し、小野重朗氏も「古い神像型田の神が特に小林市から高崎町にかけて多数に分布していることは、この地が神像型田の神の発祥の地であることを示している」(『宮崎県史 民俗1』)と指摘している。鹿児島県側にも分布する神官型に関しての論考は宮崎県側の研究が、といっても青山氏のものが中心であるが、主導権を握っているように思われる。
「地蔵型」に関しては、宮崎県内には事例が少ないためか多くを語っていない。ただ一つ一向宗との関係で宮崎県側に「地蔵型」が少ないと指摘しているのみである。その点に関しては、宮崎県側と違って薩摩地方には多くの仏像型田の神像が分布し、多くの碑文に「奉供養」という文字が見られることは事実であり、この論には青山氏も述べているように資料が少なすぎるようである。しかし一向宗禁制の取り締まりに対して違いがあったと考えれば大変に重要な指摘であるといえよう。
「農民型」とは、青山氏の分類であり、寺師三千夫氏の考えに基づいている。それに対して鹿児島県側の研究者に採用されているのは「田の神舞型」である。本来の意味あいでは「田の神舞型」が適しているのであろうが、一概に訂正すればよいという問題ではない。青山氏が農民型という言葉を採用した背景には、鹿児島県内の田の神舞型が躍動感に溢れ動的な像であるのに対して、宮崎県内の像は静かにたたずむもので決して鹿児島の田の神舞と同一のものではないという意味合いも込めてであったかに思われる。ただ、その後の宮崎県の田の神研究において無批判にこの「農民型」という概念が採用されていることは今後の大きな課題である。
このほかに「自然石」「文字碑」「石塔型」などの分類があるが、なかには「僧衣立像」「旅僧衣結跏坐像」「頭布座像」など分類に困難なものもあり、こうした未分類の項目を含めて、鹿児島県側の分類を考慮した上で南九州という範囲で鹿児島県と宮崎県の共同で構築される必要がある。
本書の二九九例の事例を一覧表と地図に整理したので、それらを参考にしながら本書の内容について地域ごとの特色や今後の課題についてまとめてみる。
宮崎の田の神像の分布
※この表は『宮崎の田の神像』にあげられた二九九例を元に作成した。( )内の数字は近世期以前の年号のある像を示している。※後日掲載
本書の冒頭で語られる小林市の陰陽石のエピソードは田の神信仰を考えるうえで実に象徴的である。多くの「農民型」田の神像の後ろ姿はまさに陽石を象ったものであり、「神官型」の発祥の地に田の神信仰の根源ともいえる陰陽石が存在することは、「なぜ東方からのが一番古いか、やはり陰陽石の影響からかなと思いました」とその関係をにおわせてはいるように、小林市に隣接してえびの市や野尻町に自然石の田の神が見られることと関連して重要な課題である。また「神官型」が小林で生まれたことはほぼ間違いないにしても、「神官型」がなぜ小林に生まれたのかについての歴史的背景については不明な点も多く、小林地方が早くから開墾されたという指摘や、えびの市・高原町・高崎町・山田町などに近世期の神官型の分布が広がっていることなどは田の神像の伝播経路についての手がかりになる。また「日州雅楽」の例などは田の神技法の流通を考えるうえで貴重な資料である。川内川と大淀川が交差するこの地域では民俗全般に渡って文化の交流が見られる。例えば下野敏見氏により種子島踊りから城攻め踊りへ伝播することが指摘されているように、川内川を上流する文化がえびの市に伝播し、さらに大淀川を下流するという視点からも田の神像文化の伝播経路について考えられる必要があろう。青山氏が「大淀川と川内川をわける分水嶺が、田の神の空気を変える分水嶺。その境は小林と飯野の境になります」というように小林・飯野の分水嶺がダイナミックに田の神像の様式が異なるということは実際に現地を歩くと感じることができるという。
鹿児島県に近い都城市やえびの市に農民型が多いのは、農民型が鹿児島型であるというゆえんである。「農民型」はバラエティーに富んだ持ち物から細かな形態分類を進めるなかでその系譜や時代が明らかになるであろう。一七五頁の表のように、シャモジとお椀を持った像が最も多く広範囲にわたっており、農民型の基本形となっている。都城市周辺の地域全体にいえることは、オットイタノカンサーの習俗が盛んであるということで、農民型の田の神像の伝播にはそうした習俗とセットになった伝播も考えられる。高岡における明治期の農民型の田の神像の普及との関連で捉える必要があろう。諸県地方でも高城町・山之口町は神官型の方が多いのは高岡町と都城市をつなぐ地域として重要な意味を持つであろう。
高岡町の特色としては、「徳川期は神官像ばかりだったのが、明治になって農民型ばかりになった事も珍しい事です。」とあり、二度の建立ブームがあったことを示している。本書でも薩摩藩以外の事例が紹介してあるが、国富町や宮崎市の多くの田の神が明治期になってからの建立と考えられるようである。国富町八代の文字碑の多さは綾町や高岡町とともにこの地域の特色ともいえよう。また「打首になった田の神」の項で指摘している明治期の廃仏毀釈の影響は、薩摩藩の真宗禁制とも合わせて田の神像文化に大きく影響していることは事実であろう。
田の神像の系譜
田の神像及び神官像の建立の要因について青山氏の考えをまとめると次のようである。享保年間の度重なる霧島山の噴火に対し、その当時の全国的な地蔵建立の流行にのり田の神像が急速に普及した。ただし薩摩藩では一向宗禁制の影響もあり仏像は忌避され、田の神舞をモデルにした農民型が鹿児島県 側で普及し、宮崎県側では神官型が普及した。神官像のモデルとなったのは、この地域の神社拝殿前の善神王像(武人像)であり、あるいは宮崎平野部から諸県地方にかけてみられる社日講の掛け軸の社日様の絵であった。
霧島山の噴火が田の神像建立の要因になったという説について村田氏は、『田の神』(鹿児島県歴史資料センター黎明館 昭和六二年)という図録において「『宮崎の田の神像』という本をみると、この型(神官型)の田の神は霧島噴火の影響で真言山伏などがその造立に関係していると推定し、その腰かけ姿は神社の拝殿前に立つ善神王とそっくりだと述べている。」と指摘し、「いまのところ、私は前述の霧島噴火を契機として造立されたという説に注目したいと思う。」とまとめている。さらに、
科学の発達していない中・近世の農民たちは噴火や風水害・旱魃・疫病などの災害や鳥獣・虫の害などにしょっちゅう苦しめられたので、ひたすら神仏にすがる一方、日待・月待・庚申待などの物忌 行事や山伏・盲僧をはじめ民間宗教者等による呪術的修法やまじないによって、除災招福を祈ったが、それでも自然の異変が起ると、宗教者の勧めによって、地蔵・観音の造立と並行する形で郷士階級を中心に田の神像が造られ、そのあとは庶民も加わり、講中・郷中・二才中・女人相中など講集団や年令集団、地域集団の名で造立が行われるようになったのは自然の成行だったといえる。
と霧島山噴火が田の神建立の契機になったとしている。ただし、鹿児島において地蔵建立も積極的に行われたことが指摘されており、一向宗禁制が神官型を普及させた理由にはならないのかもしれない。あるいは諸県地方においては別な展開があったとも考えられ、さらなる研究が進められなければならないであろう。
神官型には鹿児島県側の研究によっては坐像と立像があり、坐像は宮崎県小林市周辺で普及したもので、立像は鹿児島県日置地区で普及した。坐像という視点から考えると神官像のモデルが神社拝殿前の善神王像(武人像)であることは納得いくが、その後の研究が続いておらず、実証的な研究が必要であろう。一方、社日講の掛け軸の社日様の絵が神官像のモデルになったという説については小野重朗氏の社日講の分布図が理解を助ける。図のように社日講の分布は小林市までの広がりを持っておらず、それほど大きな影響を与えたとは考えられないようである。
田の神習俗と田の神信仰
前述したように青山氏は本来『宮崎の田の神』と題したかったというが、そこには二つの意味が考えられる。一つは田の神像をめぐる習俗について、もう一つは稲作儀礼を含めた田の神の信仰についても言及すべきだという意味であろう。ここでは本書刊行以後の研究動向について多少触れておきたい。ただし、この分野に関しては小野重朗氏によって精力的に研究されており、『農耕儀礼の研究』と『宮崎県史 民俗1』を中心に説明を加えていく。
田の神像をめぐっては様々な習俗が行われており、特にオットイタノカンについては本書でも別項をたて多くが触れてあり、なぜ盗むのかについては豊作だった田のタノカンサアにあやかると説明している。「オットイタノカン」については、都城市を中心とした地域から鹿児島県にかけて多く見られた慣行であるが、これに関しては高桑守史氏が「儀礼的盗みとムラ」(『日本民俗文化体系8 村と村人』小学館、昭和五九年)において本書を引用し、民俗行事に見られる「盗み」の意味について考察している。また、都城市や高城町では田の神を一体造ると集落の女性が一人いなくなるといい、だから新しく田の神を造らないという伝承がある(『農耕儀礼の研究』)。
廻りタノカンについては田の神祭り・田の神講・田の神踊りとともに考察される必要もあり、本書では余り触れられていない。この廻りタノカンの田の神像は屋内に祀られるもので小型の像がほとんどであり、これらは相当数にのぼるため、屋外で祀られるようになったもの以外は数に入っていない。田の横に据えられた大きな田の神に対して、田の神講の際に宿から宿に移動される小型の田の神は田の神講の座のために造られた新しい形と考えられている。
青山氏は田の神の性格について「絶対にたたらない神様」という指摘は重要である。田の神について、神無月になるとすべての神が出雲に集まるが田の神様だけは土地に残り人々を見守る神様であるという伝承がある。田の神信仰が聖的な神仏ではなく、日常的な神仏という性格にはこの地方に見られる「ウッガン(内神)信仰」にも通じるものがある。
今後の課題
田の神信仰は実に多彩で様々な要素を吸収したものである。本書だけでも、陰陽石、田の神祭り、神楽、田の神舞、田の神講、社日講、二十三夜待ち、観音様に転化する話、田の神の化粧、虫除け、山の神との交替など多くの項目があげられている。様々な年中行事、民俗芸能、神社祭礼などにみられる田の神信仰あるいは稲作儀礼などの研究とともに田の神像の研究も進められなければならない。
これまでの田の神像の研究は民俗分野から多く行われてきたが、推論の域を脱しない点が数多く残されていることはしばしば指摘されるところである。これからは歴史史料からのアプローチによって田の神が建立された時代背景についての研究が進められる必要がある。田の神像がいつ建立されたかは銘文と形態分類で分かるとして、誰によって何の目的で建立されたかについてはまだ不明な点が多い。霧島山や桜島の噴火や台風などの自然災害に際して建立されたものが多いことは本書でも触れているが、山下真一氏はこうした田の神像建立が藩による農民支配に利用されたという視点から再考している。南九州にのみ見られるウッガン信仰とともに薩摩藩の行った門割制度との関連で田の神像建立がどのように進められていったかを銘文と古文書から捉え直す段階に来ているといえよう。
今後の研究者の努力で『宮崎の田の神』という本が刊行されることが青山氏の望むところであろう。『宮崎県史 民俗1』では四二四例があげられており、おそらく六〇〇体以上になると思われる。青山氏が「土地の方が調査されるとかくれた像が姿を現わし、いったいどれだけの田の神があるのか、全体はつかめないのです。それだけにまだ新発見の可能性があるわけです。筆者の調査もその点ではまだまだ不充分ですが、今後つけくわえて欲しいと思っています。」というように、少しずつでも事例を積み重ねていくことが必要でしょう。
南九州という地域は全国的にも注目されているフィールドである。なかでも田の神信仰やウッガン信仰など特徴的な民俗があり、鹿児島県を中心に研究が進められている。しかし民俗文化の解明にはその周辺部分に大きな手がかりが残されていることが多く、その意味でも宮崎県というフィールドの重要性が注目されているのである。鹿児島県の研究に頼るのではなく、宮崎県からの研究成果を示し、鹿児島県の研究に影響を与えたという点では青山氏の功績は大きいといえよう。
青山幹雄参考文献
【田の神関連】
「野尻の田の神像より」『ひなもり第十一号』昭和四六年
「田の神像あれこれ」『ひなもり第十二号』昭和四七年
「宮崎の田の神像」『ひなもり第十四号』昭和四九年
「えびのの田の神像」『えびの第八号』昭和五〇年
「日向の田の神像」『宮崎県地方史研究紀要第一号』昭和五十年、宮崎県立図書館
【その他】
「柱のきず」『MGK第十七号』昭和二六年
「地名から見た野尻の開発」『ひなもり第十号』昭和四五年
「島津啓次郎」『朱笛文学第七号』昭和五二年
「佐土原城と城下町」『宮崎県地方史研究紀要 第六輯』宮崎県立図書館、昭和五五年
『佐土原城と城下町』佐土原町教育委員会、昭和五五年
「日講上人と古月禅師」『宮崎県地方史研究紀要 第七号輯』宮崎県立図書館、昭和五六年
「戊辰戦と佐土原藩兵」『ひさみね第一号』昭和五七年
「町史編纂の影の人達」『ひさみね第一号』昭和五七年
「戊辰戦役と佐土原藩兵」『まいづる第一号』昭和五八年
「広瀬護国神社奉納額より戊辰戦役従軍者一覧」『ひさみね第二号』昭和五九年
「万陀羅縁起考」『まいづる第二号』昭和五九年
「まぼろしの佐土原人形」『宮崎県地方史研究紀要 第一四輯』宮崎県立図書館、昭和六三年
『佐土原土人形の世界』鉱脈社、平成六年
参考文献
『鹿児島県文化財調査報告書 八』鹿児島県教育委員会 昭和三六年
『鹿児島県文化財調査報告書 九』鹿児島県教育委員会 昭和三七年
『鹿児島県文化財調査報告書 十』鹿児島県教育委員会 昭和三八年
『鹿児島県文化財調査報告書 一五』鹿児島県教育委員会 昭和四三年
『鹿児島県文化財調査報告書 一六』鹿児島県教育委員会 昭和四四年
『鹿児島県文化財調査報告書 一八』鹿児島県教育委員会 昭和四六年
『鹿児島県文化財調査報告書 一九』鹿児島県教育委員会 昭和四七年
平野良雄「吉松の田の神1」『つつはの 1』昭和四七年
平野良雄「吉松の田の神2」『つつはの 2』昭和四七年
平野良雄「吉松の田の神3」『つつはの 3』昭和四七年
平野良雄「えびの市の田の神1」『つつはの 5』昭和四九年
平野良雄「えびの市の田の神2」『つつはの 6』昭和四四九年
平野良雄「えびの市の田の神3」『つつはの 7』昭和五〇年
平野良雄「吉松の田の神サアー」『つつはの 10』昭和五二年
昭和四四年から昭和五七年まで『民俗資料調査報告書』及び『有形民俗資料報告書』が刊行されている。
赤尾譲『石像さつま田の神』三一書店 昭和四八年
小野重朗『農耕儀礼の研究』弘文堂 昭和四五年
小野重朗『南九州の民俗神』南日本出版文化協会 昭和四七年
小野重朗『民俗神の系譜』法政大学出版局 昭和五六年
小野重朗『田の神サア百体』西日本新聞社 昭和 年
岡島銀次『田之神』昭和九年
楠元義男『田之神の里 大口』昭和六一年
島津久敬『石のさつま』南日本出版文化協会 昭和四一年
鶴添泰蔵『田の神まつり』国書刊行会 昭和五二年
寺師三千夫『薩摩のタノカンサア』鹿児島放送文化協会 昭和四二年
野田千尋『田の神像』木耳社 昭和四六年
野田千尋『田の神さァ その心と形』南海陶苑 昭和五〇年
野田千尋『大隅路の田ノ神像』木耳社 昭和五四年
『「田の神さあ」関係資料目録』鹿児島県立図書館 昭和五九年
山田慶晴「川内のアベック田の神石像」『鹿児島民俗 六八』昭和五三年
花田潔「出水地方の田ノ神について」『鹿児島民俗 六九』昭和五四年
山田慶晴「樋脇町の田ノ神石像について」『鹿児島民俗 七〇・七一』昭和五五年
山田慶晴「串木野市の田の神石像」『鹿児島民俗 七三』昭和五六年
岩城久賢「松元町の田の神石像」『鹿児島民俗 七四』昭和五六年
郡山政雄「郡山町の社寺と民間信仰」『鹿児島民俗 七五』昭和五五七年
野田千尋「珍しいベロを出した田ノ神像」『鹿児島民俗 七八』昭和五八年
野田千尋「田ノ神石像の美と魅力」『鹿児島県立図書館教養講座 五』昭和六一年
山田慶晴「一石双体像の田の神像と道祖神」『北薩民俗 四』昭和五八年
寺師三千夫「薩摩・日向の民俗とその歴史に就いてー特に田の神像についてー」『ひなもり 第五号』昭和三九年
『ひなもり 二五(田の神特集号)』昭和五九年
生目地区郷土史研究会『生目地区史跡遺跡と文化財ガイド』平成三年
山下真一「薩摩藩の田の神石像文化と農民支配」『宮崎県地域史研究第五号』平成六年
『瓜生野倉岡郷土誌』
『高原町の文化財』
『須木村の文化財』
『山之口町の文化財』
『野尻町の文化財』
『三股町史』
『高原町史』
『高岡町史』
『高城町史』
『高崎町史』
『野尻町史』
『えびの市史』
『都城市史』
参考文献
瀬戸山計佐儀『太郎坊町史』
『高原町史』
小林史談会『ひなもり五号』
寺師三千夫『薩摩のタノカン』
真方良穂『西日本新聞』昭和五十三年六月九日
『平家物語』
黒木為雄『高崎町』
『高原郷土史』
『日向地誌』
『高岡名勝志』
『毎日新聞』昭和五十二年五月二十三日
『高岡郷土史』36頁
郷土誌『たかおか』第4号
赤尾譲『石像さつまの田の神』
福永勝美『血染めの都城真宗史』
【相場惣太郎氏の経歴】
一九二四年青森県生まれ。昭和一八年青森青年師範繰上卒業。終戦後宮崎で写真業。
本来は、相場惣太郎氏の写真集に青山幹雄氏が文章を寄稿するという話がすすんでいたというが、いつのまにか逆になってしまったという。
【相場惣太郎関連文献】
『高鍋大師』相場惣太郎 高鍋大師信仰会 一九九一
『通浜の生活、風土、自然を写して三〇年』かわみなみ写真クラブ・高鍋写真クラブ 一九八三
早野慎吾「宮崎県諸県域における田の神信仰」『宮崎大学教育文化学部紀要人文科学 第26号』 (2012)31-40頁
https://miyazaki-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=1226&file_id=22&file_no=1
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
