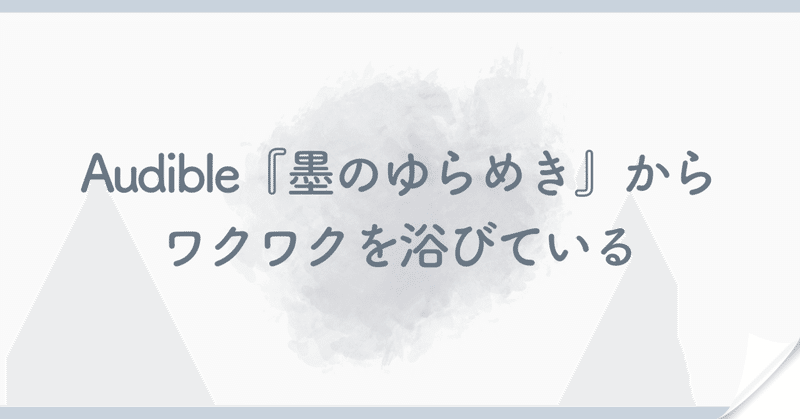
Audible『墨のゆらめき』からワクワクを浴びている
※まだ聴き終わってない
こんにちは。会社員をしているとたくさんメールを書きますが、大体どれも「お世話になっております」「ご確認いただけますと幸いです」「よろしくお願いします」を使えば成立してしまい、これらだけではやや力不足なメールを打つ時、適当な言葉を思いつくまでの時間が、日に日に長くなっていっているように感じます。
26歳でこの衰えか…と嘆きたくなる今日この頃。
少しでもボキャ貧を脱却したく、Audibleを聴き始めました。
思い返せば、小学生時代は国語の先生から「文学少女」との称号をいただいたくらい本を読んでいた(正しくは、友だちと遊ぶのが下手だった)し、高校生の時も授業中に机の下で『図書館戦争』を読み耽るくらいには、本は私の友達でした。
それが大学に入って環境が変わり、全く読書をしなくなり、卒論のために論文や書籍はいくつか読んだものの、読むスピードが落ちていることが体力的にも気持ち的にもしんどく、卒業後やはり読書から離れてしまいました。
自分の学力も語彙力も人生トップクラスで、言葉に対して繊細だった高校時代に戻りたいと何度思ったかしれませんが、時はすでに遅く、kindleで本を読んでもすぐにXやinstagramに浮気してしまい、ページは一向に進みません。
そんな半絶望状態のなか出会ったAudibleは、自分にとってかなり画期的で、すぐに数冊読み(聴き)終えることができました。
個人的にいいなと思ったのは以下の2点
・歩きながら聴ける
・わからない単語や文章があった時、「わからない」私を置いて先に進んでくれる
特に2点目。Audibleで本を聴くという行為は、読者に比べてかなり受動的な行為です。
読書をしている時は、単語や文章がわからなくてつまずくと、調べるためにスマホを開いてSNSに脱線したり、嫌気がさして本を閉じてしまうこともあります。
それに対して、Audibleは「わからない私」にお構いなしで話を続けてくれます。私はわからない文章を聞き流し、面白いと思える場面が耳に入ったらまた集中を取り戻せばいい。
そうやって、身になってるのかなってないのかよくわからない、でもお気軽で、読書をしている達成感は確実に味わえる聴書(?)体験を続けてきました。
私の聴書歴をいくつか挙げると
凪良 ゆう『汝、星のごとく』
ゆうこす『教官SNS 丸く尖る発信で仕事を創る』
西 加奈子『サラバ!』
逢坂 冬馬『同志少女よ、敵を撃て』
米澤穂信『いまさら翼といわれても』
貧乏性というか、外れを引くのが怖いので、ついよく知っている作家さんや、話題作ばかりに手を出してしまいますね。
Audibleユーザーの方からすると、面白みのないラインナップかと思います。
今回タイトルに上げた『墨のゆらめき』も、作者の三浦しをんさんのお名前に見覚えがあったので聴き始めました。
高校生の時、週に12本くらいアニメを観ているほどアニメが好きで、深夜帯の作品も録画して観ていました。
その時に観ていた『舟を編む』の原作者が三浦しをんさんです。
正直なところどんな話だったかは覚えていませんが、好きだったという当時の感触は覚えています。今サイトを引用して気づいたのですが、『墨のゆらめき』の朗読をしている櫻井孝宏さんは、『舟を編む』の主人公・馬締光也を演じていたんですね。
Audibleのナレーションは、作品や作者に由来のある方がキャスティングされている感があるので、これは納得です。
さて。
長すぎる前置きでしたが、『墨のゆらめき』の話をしたいと思います。
といっても、冒頭でお伝えした通りまだ最後まで読み終わってはおらず、1.7倍速で聞いてまだ二章(全五章)なので正直1時間分にも満たない気がします。
それでも、自らのボキャブラリーの無さを嘆いた私からすると感動もので、興奮が抑えきれず、こうして記事にしたためているわけです。
何がそんなにって、要するには文章の面白さです。
お話はわりに単純で、主人公の続 力(つづき ちから)が風変わりな書家・遠田 薫(とおだ かおる)とひょんなことからタッグを組み、「手紙の代筆業」を始めるというものです。たぶん。まだ最後まで聴いていないのでわかりませんが。
物語はこの続の一人称視点で語られるのですが、この続という男はホテルマンという職業柄か観察力が高く、趣味が読書ということでいちいちその描写が詳細なのです。
続は人が良くて、振り回されやすい性質ということもあり、内心でいろんなものにツッコミを入れています。
そして、その一文一文が面白くて、聴いていてワクワクするのです。
私の場合、Audibleだと情景描写はほぼ聞き流している状態なのですが、『墨のゆらめき』はたびたび一時停止して面白さを噛みしめたいくらい、ひとつひとつの文章が魅力的です。
(ちょっとタイトルからは想像できないんじゃないかなと思います。騙されたと思って聴いてみて!)
思い出すのは西尾維新さんの『化物語』シリーズ(私の読書履歴は児童文学~ライトノベルに偏ります)。
あれも文章が面白くて、言葉遊びが楽しくて、あっという間に一冊、果てはシリーズ全巻を読み終わってしまいました。
物語が面白いのとはまた違った喜び、エンターテインメント性がこれらの本にはあって、特に私はそういう本が好きなんだなと感じました。
そして私が喉から手が出るほど欲しかった「日常生活で頻繁には使わないけど、いざという時に使えるようにしておきたい言葉」が、これでもかと使われています。
夏、からからに干からびた喉を麦茶で潤しているような喜びと満足感。スカスカの脳にぶわーっと語彙が染みわたっていく感覚がとても心地良いのです。
そして、いったいこの一編でどれだけの言葉に出会えるのだろう、とワクワクするのです。
今までAudibleで聴いたどの本も面白かったり、学びがあったりしましたが、私の当初の目的を満たしてくれる本にやっと出会えたという感がありました。
お話自体もほっこりと面白く、ナレーションも良いので、このままだとあっという間に聞き終えてしまいそうですが、それが勿体ないと思ってしまうくらいには楽しい時間を過ごさせてもらっています。
未読(聴)の方はぜひ聴いてみてください。
Audibleファーストの作品(Audibleだからこそ「書く」ことをテーマにされたというのも秀逸)ですが、調べたら書籍や電子書籍もあるようなので、読む派の方はそちらも試してみてください。
最後まで素敵だったら( レビューは良さそう)、私も買おうかな。
それにしても、
こんなに長く記事を書いたのに、本文からの引用が一つもないというのは奇妙なものです。
というのも、悲しいかな、「一文一文が面白い」と言いながら、私はどの文章もソラで書けるほどは覚えていないわけですね。
Audibleは面白かったページにブックマークができなかったり、「あの文章に戻りたい」がやたらと面倒くさい(だってあの文章が何分何秒に読まれたかなんて覚えていない)というのが難点で、その点は紙の本に軍配が上がるかなと思います。
また、人間は「場所」で記憶するらしく、例えば「あの本の右側のページの3行目くらいにあったな」という覚え方が得意なのだそう。
だから何かを覚えたい時はipadとかよりノートの方がおススメだ…みたいなことを、先日聴いたpodcastで医師の下村健寿さんが話されていました。
(当時の配信は既に削除されているようです)
そういうわけで、私の目的である「語彙を増やす」を達成するためには、やはり活字での読書が必要そうです。
意識だけはあるので積読が本棚に溜まりつつありますが、三浦しをんさんの作品なら読めるかも!と思ったので、頑張ってチャレンジしたいと思います。
面白い作品が読めたらまたここで紹介できればと思います。
ではでは。
ここまで読んでくださった方、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
