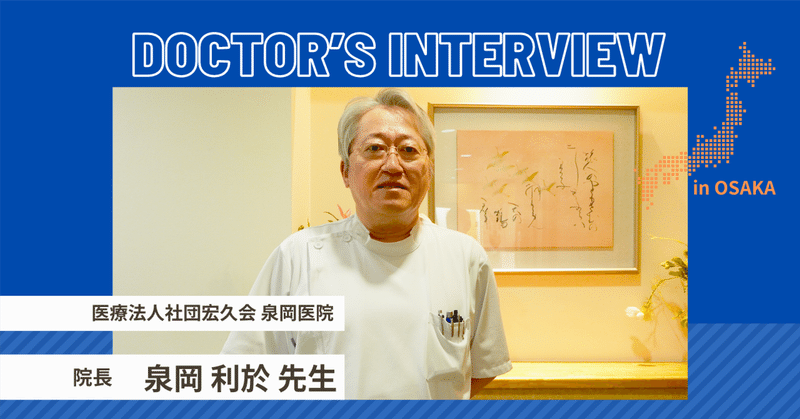
データの蓄積は少しでも早いほうが良い--PHRの活用で、かかりつけ医としてのアドバンテージを向上
今回は、大阪市都島区で昭和35年より二代にわたり京橋の地で地域医療に取り組まれている、医療法人社団宏久会泉岡医院・院長の泉岡 利於(いずおか としお)先生にお話を伺いました。
早期から電子カルテで患者さんの診療データを蓄積するとともに、現在は約300名の方がPHRを活用。データを活かした診療で患者さんの日々の健康・生活習慣管理に携わるかかりつけ医として活躍されています。
どのようなお考えのもと積極的にデジタル化を推進してきたのか、その背景と見解を教えていただきました。
疾患が重篤化する前に「防ぐこと」、そのために日々の状態確認とコミュニケーションが大切
-まずは先生のご経歴について、伺わせてください。
泉岡 利於(いずおか としお)と申します。もともとはスポーツに傾倒しておりまして、中学はサッカー、高校では陸上をやっていました。その際に心拍数を見ながら、異常が見られたら次のステップのトレーニングには進まないなど、内科的・科学的なアプローチが日々の練習に取り入れられていて、心臓や脳に興味を持ちはじめました。その後医大に進学し、さらに両者への興味が強まりましたが、最終的には自らの適性も考慮し循環器系へと進むことを決めました。
-循環器系の中でも、専門は様々に分かれると思いますが、その中でも「内科」をお選びになった理由はどこにあったのでしょうか。
大きなきっかけは、父が1960年から開業医をしていたことでしょうか。
もともとは父の跡を継ぐ気持ちはそれほど強くなかったのですが、大学時代に研修医として救急搬送されてくる心筋梗塞や狭心症の働き盛りの方々をよく見ていて、「もう少し日頃から気をつけていれば」という思いが強くなっていきました。
「血圧のコントロールができていたら」「禁煙指導ができていたら、こんなことにはならなかった」と日々思いは強まり、患者さんの日常に関わって下支えする父の仕事の重要性がわかってきたのです。
急性期医療として「命を助ける」その前に、その状態にならないようにすることはかかりつけ医の使命でもあります。
-最近は心不全治療への考え方も違ってきているのでしょうか。
心不全のステージにもAからDがあります。重症患者さんがCDだとすると、軽症な段階のBでいかに気づくかが大切になっており、最近ではその考え方が浸透しています。
その重要性に早い段階で気づけたことは、自分にとっても良かったと思っています。
-ステージBの方がご自身が気づいて申し出るということは、なかなか難しい気もします。
現在も研修医が日々学びに来ていますが、彼らに言っているのは「患者さんのキャラクターによって話し方・聞き方を変える」ということです。
丁寧に話したほうが良いのか、砕けたコミュニケーションが好まれるのか、それとも端的に「日常のこれとこれだけ気をつけて!」と言い切ったほうが良いのか。相手にもっとも理解していただける口調で話すように指導しています。
その際に患者さんの日常生活を数値で知ることができるPHRは大変便利です。
-先生には、当社のPHRプラットフォーム・Welbyマイカルテ(以下、マイカルテ)を7年前からご活用いただいておりますが、PHRの使用前後で、先生の診療に変化などはおありでしたでしょうか。
やはりきちんとPHRで記録をつけていらっしゃる方は圧倒的に血圧のコントロールなども良いです。実は以前、パソコンで記録する方法を試したことがあるのですが、約20名に試していただいて、継続できたのは日常的にパソコンを使用している2名の方だけでした。
その点マイカルテはスマートフォンアプリですから、すごくアドバンテージがあると思っています。日常の中で使用するものですから、継続しやすいですよね。
またこの地域は転勤族の方も多くいらっしゃいます。先々転勤してどこにいても適切な治療を続けられるよう、マイカルテのパンフレットをお渡ししているのですが、驚かれる方もまだまだ多くいらっしゃいます。医療にデジタルを取り入れることで「進んでいますね!」と良い印象で受け取っていただけているようです。
私たち開業医はガイドラインに則った治療を行います。その中で、より患者さんに寄り添った治療を行っている医療機関の特徴、そして差別化につながる価値として、PHRは適していると思います。
-なるほど、ありがとうございます。血圧手帳など他の管理ツールもあると思いますが、マイカルテでご評価いただいているのはどのような点になりますでしょうか。
まずは医師が確認できるデータをエクセルでダウンロードできる点でしょうか。そして、グラフも見やすいと思っています。またデジタルデバイスと連動して、歩数などが見られる場合は、それを見ながらコミュニケーションをとることもあります。
そして何よりアベレージを自動的に算出できることが役立っています。
例えば、ある患者さんでたまに血圧が150-160など高い値で出たときも、「この日はストレスで〜」など原因や理由を確認しやすく、同時にアベレージが120程度であることが確認できれば、それが問題視しなくてはいけない状態なのかどうかがひとめでわかります。
治療においてアベレージは非常に大切ですから、それがひと目でわかるマイカルテは重宝しています。

実は導入障壁は高くない
PHRを勧めるのに必要な時間は「約1分」
-ありがとうございます。とはいえ、多くの先生方とお話していると「PHRを活用したいが、患者さんに利用いただくまでの説明がネック」とのお声もいただいています。その点、先生はどのように患者さんに推奨してくださっているのでしょうか。
パンフレットを渡し、QRコードを読み込んでもらって、当院のIDを入力してくださいというだけです。それで「使えない」という患者さんは、当院では現時点までおひとりもいらっしゃいません。正直、説明には1分もかからないくらいです。
当初は私も「説明が大変かもしれない」と思っていましたが、ご高齢の方でご自身はできなかったとしても、ご家族に設定だけはしてもらい、その後は順調に使用されています。
現在は300名くらいの患者さんがマイカルテを活用されています。

デジタル化はクリニックとしての信頼を高め、「差別化」につながる
-なるほど。心強いお言葉をありがとうございます。
先生はPHRの他にもデジタル化を推進していると伺っています。その他にはどのようなことをされているのでしょうか。
患者さんの利便性を高めることで差別化につながることとしては、キャッシュレス決済なども行っています。受付業務の時間短縮にもなりますし、多少窓口支払いが多くなったときでもカードで決済していただくことで、当院側の事務管理もスムーズになります。
また少し古い話になりますが、当院では2001年から電子カルテを導入しています。以前、父の代から通ってくれている患者さんに「通院し続ける理由」についてのアンケートを取ったことがあるのですが、「私の体を一番わかってくれているから」という回答が多数を占めました。
紙のカルテの保存義務は5年間です。しかし電子化することで、それよりもずっと長い期間、患者さんの記録を保持できます。そして、そのような院内環境を作って行くには、デジタル化は早ければ早いほど良いと言えます。その期間分だけ、データが蓄積されるからです。
それが「私の体を一番わかってくれている」かかりつけ医となるための大きなアドバンテージであり、財産となるのです。
昔と今は時代が違います。データの蓄積が安心感につながり、「私の体を一番わかってくれている」ことの実証ともいえると考えてます。
-ありがとうございます。最後に当社に期待することを教えていただいてもよろしいでしょうか。
先日PHR事業者協会の執行役になられたと聞きました。このような活動により、PHRを安心して使用できる社会的な環境が作られていくことに期待しています。
そして、マイカルテの話で言いますと、未病分野への対応でしょうか。
かかりつけ医は地域医療の要として、そこで暮らす方々の健康を考えていかなくてはいけません。そうした時に、健康状態が良いときから管理し、万が一治療が必要なときにはPHRを使用して管理できると後の治療がスムーズになると思います。
かかりつけ医がデータを活用できる素地が広がることで、地域の方々の健康にさらなる貢献ができれば、それ以上のことはありません。

【医療機関情報】
医療法人社団宏久会泉岡医院
〒534-0024 都島区東野田町5-5-8
TEL06-6922-0890/FAX06-6922-1927
所要時間:京阪京橋駅は中央出口から徒歩7分/JR京橋駅は中央北口から徒歩7分
WelbyのPHRについて知りたい方、採用についてのお問い合わせはこちらよりお願いいたします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
