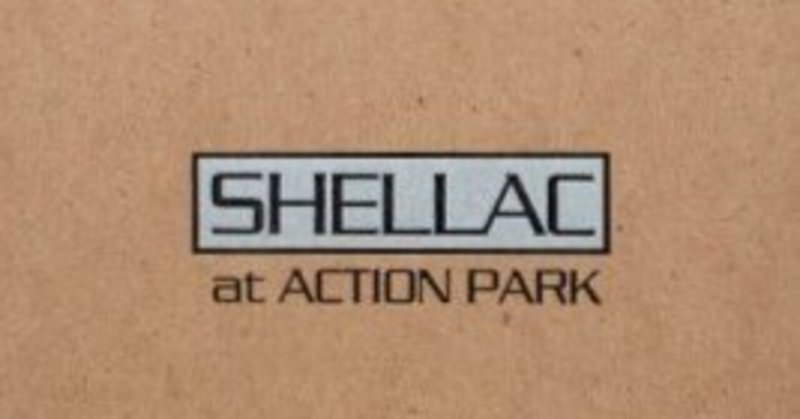
スティーヴ・アルビニに続く才能は、あまり見当たらない。
スティーヴ・アルビニ逝去。享年61は早すぎる。ミック・ジャガーやイギー・ポップがあんなに元気にピンピンしているのが、恨めしくなるほどだ。
小野島大氏は、以下のように指摘する。
とはいえ、ミニストリーの「Twitch」とビッグ・ブラックの「Atomizer」が同じ1986年に出たという事実は重要。スレイヤーの「Reign in Blood」とビースティ・ボーイズの「Licensed to Ill」も同じ年に出ていて、アメリカのロックの新しい流れはこの年に決定的になったと言って過言ではない。
— 小野島 大 (@dai_onojima) May 16, 2024
1986年において、アルビニ率いるビッグ・ブラックの『Atomizer』と、ミニストリーの『Twitch』が、同種のノイズを鳴らしていたのは、ロック史の重要なトピックだと思う。
"Kerosene"の4分46秒~と、"Where You at Now? / Crash & Burn / Twitch (Version II)"の9分33秒~の、奇跡的なシンクロを体感してほしい。
まあ、中年の俺も後追いではあるのだけど、この2枚は、自分のロック観の大切な部分を占めている。
レコーディング・エンジニアとして名高いアルビニの仕事で最も知られているのは、ニルヴァーナの『In Utero』だろう。これは俺はリアルタイムだ。ファースト・シングルの"Heart-Shaped Box"がラジオで流れたとき、「なんかドラムの音が生々しいな」と思ったことをよく覚えている。
PJハーヴェイはセカンド・アルバム『Rid of Me』でアルビニを起用したときのことを、以下のように語っていた。
"The way that some people think of producing is to sort of help you to arrange or contributing or playing instruments, he does none of that. He just sets up his microphones in a completely different way from which I've ever seen anyone set up mics before, and that was astonishing. He'd have them on the floor, on the walls, on the windows, on the ceiling, twenty feet away from where you were sitting... He's very good at getting the right atmosphere to get the best take."
「プロデュースというと、アレンジを手伝ったり、楽器を演奏したりしてくれるイメージがあるけど、彼はそういうことは一切しない。ただマイクのセッティング方法が今まで見たことのないような全く独創的な方法で、それが驚きだった。床に、壁に、窓に、天井に、さらには座っている場所から20フィートも離れたところにマイクを設置していた。彼は最高のテイクを引き出すための適切な雰囲気を作るのがとても上手だった」
なるほど、あのサウンドは、決してマジックなどではなく、マイク・セッティングの地道な作業だったというわけだ。
とはいえ、ニルヴァーナにしてもPJハーヴェイにしても、他のアルバムのサウンドもかなりいい。ニルヴァーナの場合、前作『Nevermind』はブッチ・ヴィグのプロデュースということもよく知られているが、『In Utero』よりもダイナミックで、はじけるような強さがキャッチーさとつながっている。これはこれで時代の空気を適切に反映していて、グレイトだ。
PJハーヴェイの場合、前作のデビュー・アルバム『Dry』はロブ・エリス、『Rid of Me』の次のサード作『To Bring You My Love』はフラッド&ジョン・パリッシュのプロデュースで、三枚三様に良い。
つまり、アルビニのプロデュース、エンジニアリングは、バンドの才能を水増しすることがない。ポテンシャルを最大限生かしてくれるともいえるだろう。ただ、バンドにとっては「アルビニ頼り」になってしまう恐れもある。ジーザス・リザードは、アルビニがプロデュースしたデビュー・アルバムから4thまでの尋常ならざるヤバいオーラと、満を持してメジャーに移っての5thのいまいち感は、正直、同じバンドとは思えない。
ただ、ジーザス・リザードの”ハードコア・ジャンク”というべき独特の音楽性は、アルビニがその後に自身のバンドとして立ち上げたシェラックのサウンド・コンセプトに影響を与えているのは間違いないと思われる。そこからよりソリッドに、無駄をそぎ落として、ロックの骨組みだけにしながらも、エモーションが熱く息づいている、という奇跡のようなフォーマットなのである。
奇しくも、新作の『To All Trains』は遺作となってしまった。前作の『Dude Incredible』では、80年代のUKハードコア的な陰惨さが新味だったのだが、そこからまたマイナーチェンジしている。大ナタでぶった切るような豪快さが戻り、いかにもインディーズでアンダーグラウンドな排他性は抑えられ、今様のビッグプロダクションといっていいほどの解放感。いやこれは、アルビニが変わったというより、時代がアルビニに追い付いてきたということかもしれない。それをライヴで確認したかった。
アルビニが虚ろにメロディを歌う"How I Wrote How I Wrote Elastic Man (cock & bull)"は新境地ではないだろうか。
アナログなメディア、環境にこだわりがあったアルビニだが、そのうち新作のLPレコードはCD付きになり、過去作のストリーミングも可能となった。それってけっこう意外ではあるのだが、一般のリスナーの聴取環境に配慮してくれたからだと思う。そこに彼の人柄が現れている。
ロックをハードコアに突き詰めた先で、アート性とエンタテインメント性を両立させた、類い稀なミュージシャン。職人であり、行動する思想家でもある。率直なところ、ロックに限らず音楽シーンで、彼に続く才能はあまり見当たらない。その意味でも、彼の死は、とても重く、つらいものがある。彼の残した仕事が、未来の音楽家を刺激することを、ただ祈るしかない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
