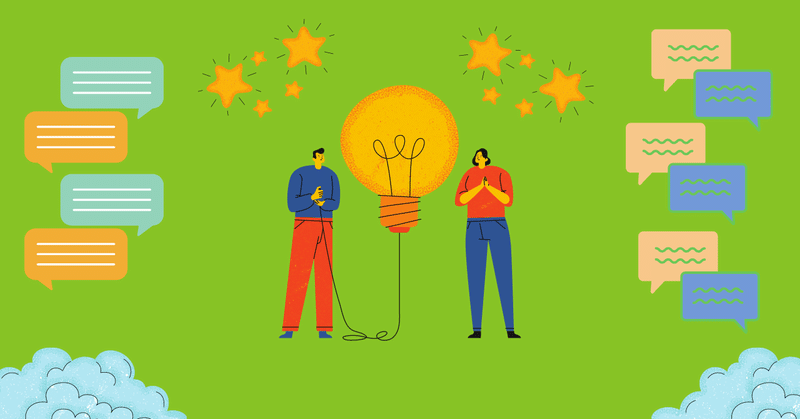
グッバイ・マイ・スイーツ/ハロー・マイ・ハッピー・リグレット〜新しい歌声が聞こえれば
約 束ー・ー・ー・ー
「えっ 異動ですか?」
「そうなんだ。昨年秋に販売開始したASC社の新規市場開拓の更なるテコ入れが必要なんだ。来月からスタートの新設専門部隊だ、期待してるよ。是非ガンバってくれ」
*
新設部署に転籍して2年間順調に成果を上げてきたが、1年前から大手コンペティターが新たな付加価値で勢いを増し、入社1年目の5ヶ月連続予算未達以来、今の部署では2度目の2ヶ月連続未達になった。
アシスタントだった元カノのプレゼンフォローで去年の12月にようやく未達記録をストップしたものの、係長として2年目、ここのところの停滞はそろそろやばいかもとは思っていた。
代理店営業とは違う新規開拓での受付突破の難しさは嫌というほど味わってきたが、市場相手が政令指定都市規模となると、毎回大手サプライヤーとの凌ぎ合いだ。
後発のうちのマンパワーでは到底敵わないが、東京と神戸にショールームを持っていることが幸いし、そこで商談をつなぎ止めながらこの2年間を走り続けてきた。
そして、たびたび係長としての期待に押しつぶされそうになりなりながら、ようやく今年の忘年会を迎えることができた。
営業経験6年以上の30前半男性8人に、セールスアシスタント課のアラサー女子6人の忘年会は、今年で2回目となっても新設部門の若さそのままだ。
2時間を一発芸やモノマネでバカ笑い、カラオケで拍手喝采し、テーブルを移動しながらのおしゃべりでみんなの浮かれ気分はさながら合コンの様相だったが、貸切の店の予約メニューも残りのポテトフライを最後にして恒例の課長の締めの言葉が始まり、あっという間にお開きの時間となった。
(・・・みんな呑気だよな、ほんと)
そんなモヤモヤした気分をダウンジャケットに包んだまま、ひとり駅に向かってトボトボと歩いていく。
「ねぇー せっかちさ〜ん!」
小柄な女子社員がそう呼びながら、目じりを下げて走ってきた。
同期入社の仲良し二人組のひとり、山下まゆの声だ。
彼女が学生時代からテニスをしていたのは、ボクがここに転籍したとき彼女の自己紹介で聞いていたし、仕事終わりの2時間弱、5、6人集まっては一緒にインドアテニスをする仲間のひとりだった。同好会とはいえ、混合ダブルスを組めばその片鱗を見せて息を合わせてくれる。
「『せっかちさん』ってなんだよ。それに体育会系がどうした〜 息切らしちゃってるし」
「もぉー!そんなことより、次行かないんですか?」
同期の佐久間美波もすぐに追いついて、彼女の誘いに一役買ってでる。
「そうですよ先輩、歌いに行きましょうよ!」
「今日はそんな気分じゃないしな」
「えーッ どーしてですかー?」
「来年の予算ヤバいだろう?こう見えてけっこうブルーなんだから」
「まあ 確かにね」
「確かにねって、二人ともバックルームでお菓子ばっか食ってないでさぁ。もう少し勉強しろ〜 それからならいいよ」
彼女の方からせっかく声をかけてくれも、ボクのちっぽけなプライドがこういうせっかくのタイミングをムダにする。
山下まゆは学生時代にミスキャンパスの最終メンバーに選ばれるくらいだ。
新人配属時からショールームで受付を任され、一度会ったお客様の顔と名前をすぐに覚えていたし、1年目で取り扱い製品全ての説明もできる様になった注目株は、ショールームにビジネスパートナーを招いて商談に勤しんでいたボクにとってはよく知る相手だったし、男性社員のあいだでも人気だった。
「イイですヨ。じゃあ、それ、約束ですよ!」

憧れの下書きー・ー・ー・ー
最初の頃はたわいもない会話のボクらだったが、ショールームに行くたびに山下の方から声をかけてきて、毎回あいさつがわりにボクにお菓子をサジェストしてきた。
今年2月のイベントに向けて準備が始まるバックルームで、ひとつ食べ終えた口元をいつもの様に指先で触れながら、イタズラっぽく聞いてくる。
「食べます?これ、新製品なんですよ。ふわっふわでけっこーおいしかったよね〜」
「そー 私もこれ好き!」
「まぁ〜た二人してお菓子食ってるのか?そんな時間が羨ましいよ。。。」
「も〜 そんなに心配しなくても大丈夫、なんとかなりますよ!ワタシたち強い味方がいるじゃないですか〜 はい座って座って!少し休憩しましょ」
聞きたがりの彼女の興味がここで会うたび、ボクに向けられてくる。それを受け取れるこころの準備すらまだ持てないボクは、うやむやな気持ちのまま過ごしていた。
それに、山下、佐久間たち6人のうち3人は中堅社員との不倫沼状態、残った彼女たちにも警戒線が張られていたし、社内はそんな愛の奪い合いで恋バナすらできない雰囲気もあった。
同期の男連中にはとりわけ人気者で人一倍寂しがり屋の恋する乙女は、ボクにはあるイミ高嶺の花だ。
「ジャーン!おみやげ〜」
引き出しから赤い紙袋が出てきた。
お気に入りのマグカップで両手を温めながらボクの反応を少し伺う。
「この前『それ美味しんだよね』ていってたから。わざわざ買いにいったんだからねー 絶対食べてくださいよ」
2ヶ月前の10月 ショールームに寄ったとき、
同期の美波とバターサンド片手にインテリア雑誌のチェックをしていた彼女にボクが何気に言ったのを覚えていた様だ。
「お〜!それそれ、間違いないやつ!あれ?北海道行ったの?」
手にしてたマグカップを置いて、まゆの顎が自慢げにツンと上を向く。
「もちろん!好きなものチャンと覚えてるんですからネー」
向かいに座る美波が思わず吹き出す。
「うそ〜、デパ地下じゃん」
「もおー 美波〜!」
「なんだよそういうこと?じゃあこれ全部頂き。いいだろ?」
そう言って、騙されたお返しにとばかりに彼女の前を邪魔する様に手を伸ばす。
「ダメですよ!みんなでシェアするんだから」
イタズラな子をさとすようにボクの手に触れてきた彼女の指輪は、好きな人に近づく証の様にも見えた。
「じゃあ、ジャンケンで決めようぜ!」
勝負はあっけなく終った。
「やった〜!全部アタシたちのもの〜」
「チェッ、まじかよ〜 そんならいらんし」
「じゃあ〜 なんか、かわいそうだから・・・半分コしてあげる!」
イタズラっぽく笑って救いの手をだしたのはまゆの方だった。
仕事仲間として半年ほど過ぎた頃、学生時代にテニススクール以外にセレクトショップのバイトもしてた、そう山下から聞いてた。
相手の気持ちを声やしぐさから感じとって、自分から近づいて話しかけたり、見つめたり、無邪気に触れたりしながら聞き上手になってくれるし、落ち込んでる時には相手の心を掴んでしっかり励ましてくれる。
そんな彼女のやさしさを自分だけのもの勘違いする男性連中も結構いるらしい。
アホな連中だなっと思っていたが、いつの間にか自分も彼女の魅力に引き寄せられていたのかもしれない。
同じ課で主任を務める成田海斗はボクの仕事仲間でもあり、よく飲みに行く後輩のひとり。そんな新婚の彼が、冷静な観察と既婚者の勘で耳打ちしてきた。
「先輩。オレの勘っすけど、山下ってもしかして先輩のこと好きかも、そんな感じしません?」
「んなことあるわけないだろう?」
「だってアイツ、先輩と話してるときの目、ちがいますよ」
週 末ー・ー・ー・ー
「ねえ、まゆ。大丈夫なの?」
「エッ 何が?」
「ここんとこよく神戸行ってるみたいだし。結構心配してるんだよ」
「ん〜 正直、行くたびに悩んでる」
年始のあいさつ回りもひと段落し、継続してた商談の刈り取りも始まるここ丸の内ショールームもまもなくフル稼働となる。
事前打ち合わせ、セッティング、サンプルの用意とまゆ達スタッフも次の見込み客までの空き時間にお菓子を食べている余裕などなく、お互いの資料とPCの睨めっこでデモ手順を作りあげていく。
ボクたちの共同作業も1ヶ月ほど続き、2月に入って間もない今も、ランチに行ってアイデアを出し合い、すぐにバックルームに戻っていくつか具体化する。夕方に3件目の商談客を見送ったあと、反省会のテーブルでようやくコーヒーを口にしてひと息つく。そんな毎日の連続にみんなの気持ちも次第に束ねられ、ひとりでは味わえないアンサンブルの魅力が響き合う。
ビジネスパートナーのニーズや変化を探り、コンペティターが気づいてない本質的な課題を解決し、創造力を掻き立てる様なデジタルコンテンツを新たに作り上げ、パートナー企業以外にも直感的にその魅力を体験できる展示やデモルームにアップデートしていく、そんな怒涛の4週間があっという間に過ぎていく。
ここ数週間のまゆは見違える様だった。
パートナーとの共感や情報リテラシーとコミュニティとのつながりを大切にする美波の意気込みや、ボクたち営業の日々の行動量に負けるとも劣らない気持ちで、最近の導入事例、新たに生まれた価値、新しい課題など現在進行形で未来も内包するユーザーの声を集めるために、東京や神戸にいるお客様のところに何度も足を運んでいた。
「二人ともやるじゃないか」
「なにがですかぁ?」
「けっこう勉強したみたいだからサ。おかげですごい訴求力になったよ」
「先輩、まゆの本気ちゃんと見てくれてました?」
美波のフォローにまゆが反応する。
「そーですよもぉ〜 こんなに頑張ってるのに」
甘えんぼのスイーツ女子だと思ってた彼女の本気を見れたのは、少し意外だったけど嬉しかった。
「ん まあね。それはそうと週末のショールームっていつも閉めるの早いんだっけ?」
「たぶん」
「七時頃とか?」
キーボードの上でまゆの指がとまり、美波も画面の向こうで優しく見守っている。
ボクがめずらしく彼女たちの仕事終わりの時間を聞いてきたからだ。
まゆ自身もなにか感じとった様に急にイジワルな顔になる。
「ん〜わかんないかも」
「チェッ相変わらずだなぁ〜 そっか、わかったよ」
「え〜ちょっと気になる」
美波も話を掘り出す気だ。
「いや、ちょっと知ってるかな?と思ってさ」
「何がですか?」
「去年お世話になった人で何度も商談プッシュしてくれた人がいてさ」
「一緒に行ったとこですか?」
こちらに椅子を向けたまゆの手がふたたび止まった。
「そう、神戸のね。あの時、営業部と総務課の女子社員の皆さんが後押ししてくれなかったらもうどうなってたことか。。。それで何かちょっとお礼したいって思ってて。スイーツとか」
「そーゆーことなんだァ」
「女子目線で店のチョイスとかアドバイスもらいたいなって思ってさ。ここから六本木まで近いし、どんなのがいいと思う?」
「オレより下の、たぶん20代後半かな?背は山下と同じくらいだったかも。。。グレーだったかな?フィーザスローっぽいやつに、机に置かれたカップからいつもダージリンティーの香りがして・・・」
そんな特徴的な記憶を確認しながら、美波の分析とアイデア、『スイーツ女子』まゆのお気に入りのセレクトを徐々に引き出していく。
胸元の鮮やかなスカーフの前で書類を抱えたまま、近づいてきたのはまゆだった。
「今度の金曜 来ますか?」
「金曜か・・ちょっと遅いかも」
「七時過ぎてもぜんぜんいいんですけど・・」
もう一つの約束ー・ー・ー・ー
2月の2週目を迎えた週末には、3月の予算と合わせ、2ヶ月分の予算達成の目星もつけることができた。
昨日まで吹いていた風も今日は少し落ち着いている。
いつものプレイリストをイヤフォンから外し、バックを持ちかえてスマホの時間を確認する。
(予定の時間には十分に間に合うな)
お気に入りのネクタイを締め直し、はやる気持ちをダウンジャケットの奥に仕舞い込んで、丸の内のショールームに向かって電車に飛び乗った。
待ち合わせ場所はいつものバックルーム。
ドアの前で、駅からここまで駆け抜けた息をフゥーと整える。
「お待たせ!」
彼女はすでに着替えて待ってくれていた。
パソコンの向こうで微笑みながら小さく両手を振っている。
「おつかれさま!早かったね」
ブルーのラメニットにブラックスカート。シンプルだけどよく似合っている。
ダウンを着たまま、壁の時計を見上げる。
「そう、夕方のアポがリスケになったんだ。ラッキーだったかも」
そんな照れ隠しのような理由を伝えながら、こうやって二人だけで向き合って話すのは久しぶりだった。
今日は美波がいない。
そんな日、ボクを呼ぶときはいつもこうだ。
「ねえ」
「ん?」
「コレ・・」
去年日本初進出で彼女たちが話題にしていた神戸発のスイーツボックスのロゴ。2色のピンクリボンで結ばれた温かいチョコレートブラウン色の小箱。
「けっこーがんばったでしょ?」
ここで一緒にいる時間、いままで見たことないの彼女の魅力も愛しさもずっと感じていた。
いっしょに過ごした時間も、
崩れそうになった思いも、
この胸の鼓動も、
そんな彼女の前ではもう信じていいのかも。
「うん、ありがとう。いいの?」
新しいスプリングコートが並び始めたショーウィンドも、恋の季節を迎える様にライトアップされ、昨日までのボクの気持ちを後押しする。
手元にあったパンフレットを慌てて片付ける彼女の横顔に、整えられた髪の奥で見覚えのないピアスが揺れていた。
更衣室から急いで手にしたコートを抱えたまま、もう一度ボクを見つめてくる。
「ん?どうした?」
「ねえ、1年前の今ごろ 一緒に行ったお客さん覚えてるでしょ?」
「もちろん!このあいだ話した三宮インダストリーだろ。長いあいだ、何度も通ったとこだし。まゆには何度も行ってもらったよなあ、あのときはありがとう」
その営業部から、彼女はずいぶんと気に入ってもらっていた様子だった。
「うん。
あのね・・・」
「ワタシ・・」
「ワタシ 会社やめることにしたの」
「そんな、やめるなんて・・・・なんで急に」
うちは中堅メーカーだけど、この業界に自信を持って製品を出してるのは、貴女によく理解してもらっている。
貴女がプレゼンの際に伝えてくれたとおり、おかげさまでお客様の消費マインドにも変化が生まれ、この製品がお客様に新たな付加価値を生み出す様になり始めてね。
うちの営業部は少数精鋭だが、貴女に是非うちに来てもらってこの製品を大きく育ててほしいんだ。どうだろう?
「社長からそう言われたの。もちろん断ったよ」
あそこにはフィットネスクラブへの販売を推進していく営業部門が新設され、うちの製品は三宮インダストリーが新規参入する製品の後押しになると確信してプレゼンした。
その可能性を一番に信じていたのは彼女自身だった。
「でも、何度もアプローチがあって。食事にも誘われたの 営業部の人に・・・」
「えっ!」
うちにおいでよ。
僕はここで貴女の本気ともっと向き合ってみたいんだ。
貴女が一瞬一心を大事にしていることは僕が一番分かってるし、僕らのチャレンジが貴女の幸せにもなる。だから『すべての可能性を信じていこう』、そう思わせてくれた。
実はボクが貴女のことを社長に説得したんだよ。
大丈夫、僕に任せて!
「そう言われて・・・」
去年の忘年会ころから、お互いもっと近づける、もっと理解し合える、そう思い始めていた。そんな無責任な自信もようやくこのごろ持てたはずだった。
(あの日もらったアドバイスも、お世話になったお客様へのお礼を理由にしたけど、ほんとは)
止まらない動揺を隠す様に声を絞り出す。
「そっか・・・・・。あのさ、帰りに 丸の内のイルミネーション 見に行かない?」
伏し目がちだった顔を上げ、彼女も小さくうなずいてくれた。
新しい歌声ー・ー・ー・ー
彼女を食事に誘ったのは神戸駅前に本社を置く三宮インダストリーのトップセールス、営業一課の係長で、今年の秋、二人が結婚することをしばらくして美波から聞かされた。
正直、冷静でいられなかった。
確かだったのは、
キミと一緒に歩いたあの夜、
イルミネーションの下でトリニティリングがキミの指で輝いていた。
それは未来の愛への忠誠だったということ。
一番好きな人に出会えたんだね。
笑顔がもっと輝いてキミはしあわせになっていく。
なのにボクはそんな事実に背を向けてしまう。
『ほんとはさみしかった、でも言えなかったの。だからがんばったし、もっとたくさん話したかった。一緒にいたかったし、ずっとそう思ってたの。だからね・・・』
そう言ってくれるはずだった。
あのとき、愛し方なんて何ひとつ知らなかったボクは、自分の揺れる思いをうやむやにしていた。すべて上手くいくって勝手に思い込んでいた。
なんてサイテーなヤツだったんだろう。
ほんとは、もっと伝えたいことあったはずなのに、どうして言えなかったんだろう。
言い訳なんか、今更成立しないよね。
でも、もしあの日、手にしたスイーツボックスがアリガトウとサヨナラで結ばれていたと気づいたとしても、切なくて優しいキミの気持ちをひとときでも分かち合えたんだ。
なんてボクはしあわせだったんだろう。
・・・だからね
さみしさをこらえた
キミの言葉を探し続けて
そろわないパズル合わせなどしない様に
メビウスの輪の様な
しあわせな後悔と
永遠に続くひとつの愛を
あの日を飛び越えて願ってみるよ
キミの知ってる懐かしいボクに
いつか新しい歌声が聞こえてくるまで
☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
あの冬を駆け抜ける様に
ハンドルを握るぼくの肩に
ダウンを抱えたまま身をゆだね
穏やかに眠るキミの横顔が
テールランプでそっと照らされたとき
こわれそうだったこころも
あの日の様に輝いて
『ハルノヒ』の歌声が
通り過ぎていく春風を見送るように
夜更かしの高速を走り抜けていった
ー・ー
☆フォトロケ地
新国際ビルヂング
丸の内パークビルディング
東京国際フォーラム
☆ 『ハルノヒ』
あいみょん
(ワーナーミュージック・ジャパン)
★☆登場人物、ストーリーは想い出フィクションです
最後まで読んでいただき有難うございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
