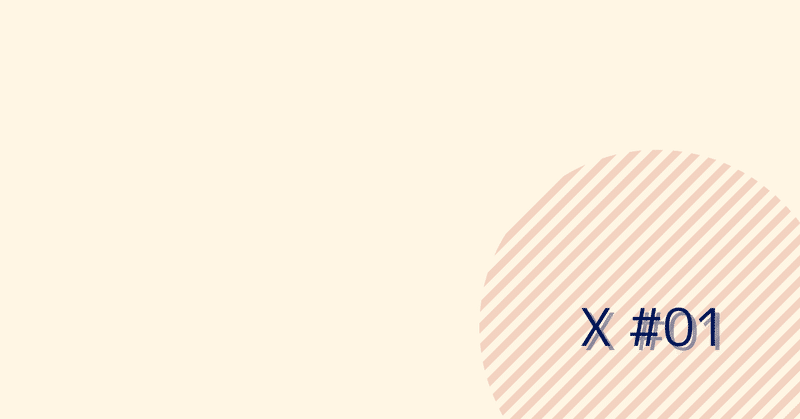
Xデザイン学校2022マスターコース#01(22/05/14)
昨年のベーシックコースに引き続き、Xデザイン学校のマスターコースを受講することになりました。
初回講座の振り返り(気づきや学び)になります。
今回はデザインに関する多くの概念を座学で学んだ後、グループに分かれて強みドーナツを書いて共有するWSを行いました。
まだ今年の課題が発表されたわけではないのですが、ベーシックコースとの違いとして、社会(課題)に関する視点を考慮することが大きいのかなと思いました。
デザインの役割
「現在の問題を解決すること」だけではなく、「未来のためのビジョンを提案すること」もデザインの役割であるということ。特に今の時代、問題解決ではなく、社会へ新しい意味を問うこと(新しい意味の創出)が強く求められてきていると思います。
未来を作るということ
過去のデータをもとに予測しても、従来の製品・サービスの延長になってしまい、そこからイノベーション(新しい意味の創出)を起こすような製品・サービスは生まれない。
過去のデータ分析や、現在の延長線上にとらわれないことと、あるべき未来がこうなれば良いのに、自らありたい姿を自由に思い描けることが大事になっている。
本質を理解する
UXデザインやサービスデザインに関するプロセスや手法はネット上にいくらでも転がっているが、その本質を理解して活用することが重要。(決してペルソナを作ること、CJMを書くことが目的になってはいけない)
自分も昨年これまで学んできた多くのことに関して、ただ理解したつもりになっていて、本質を全く理解できていなかったことを痛感しました。
今では多くの企業で例えばデザイン思考を組織に導入しよう、という動きがあると思います。この時に、流行っているから導入するのではなく、ちゃんと本質を理解した上で、導入し実践できる仕組みの構築の方がより重要なのかなと。
エフェクチュエーション
不確実性が高い環境下での意思決定プロセスや思考に関する大事なマインドが詰まっているなと感じました。
成功している起業家に共通する思考や行動パターンらしいのですが、その一つ一つは成功者特有の特殊なマインドということではなく、ある種当たり前の項目が多いなと思いました。物事の考え方や捉え方をほんの少し変えてみるだけでも良いのかもしれません。
また、「『〇〇がない』からできないのではなく、『今あるもの』の活用方法を考える」という考え方は、ビジネスの文脈に関係なく、普段からでも活用できそう。
学びを自ら楽しむ
ベーシックコースで学んでいる時に、"初めての料理で美味しいものは作れない"という話をしていただいた。
初めて作る料理で美味しい料理は作れない。途中で最後まで作ると不味いことが分かっていても、止めずに最後まで作り切る。そしてそれが不味くても食べる。
2回目に作るときはもう少し手際が良くなっていて、1回目よりは美味しい料理が作れるようになる。それを繰り返す。
この講義も料理と同じで、その都度その都度で何を学んだか?が大事で、自分たちのチームはその学びが足りなかった。
Xデザイン学校では失敗が許容されている場所なので、色々なやったことのないこともやってみたいし、せっかくなのでちゃんと楽しみながら学びたいなと思っています。
その一方で、失敗だけではなくちゃんと成功もしないとモチベーションが保てないので、2回目の料理は少しでも上手く作りたい。
これまで学んできたものを空っぽにした状態で、自分の成長に気づくことができれば良いなと思います。
最後になりましたが、
先生、運営スタッフの皆さま、受講生の皆さま、これから1年間よろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
