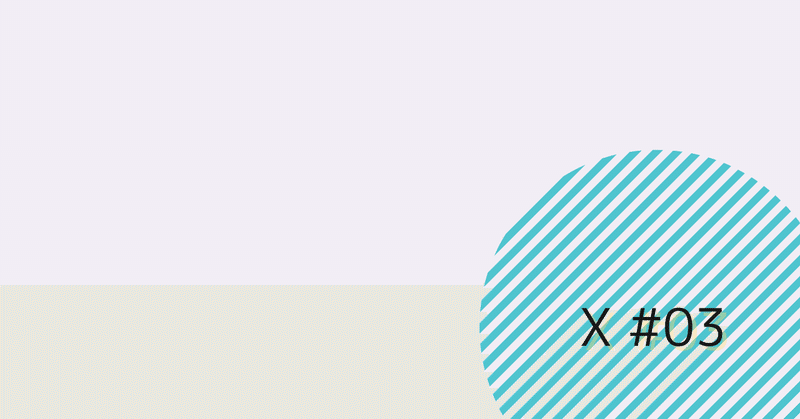
Xデザイン学校2022マスターコース#03(22/07/16)
3回目の講座の振り返り(気づきや学び)になります。
今回は「チーミングとビジョンデザイン(妄想とビジョン/意味のイノベーション)」の講義を聞いた後、自分を再認識するための個人ワークとペアによる批判的対話を行い、最後にチームのビジョンを作るグループワークを行いました。
クリエイティブなチーミング
オンラインで仕事をすることが普通になり、リアルで会ったことがない人と一緒に仕事をすることも当たり前になってきました。そういった状況下で創造的なチームを作るチーミングを行うことは、以前にも増して重要になってきていると思います。
心理的安全性
新しい提案を行っても否定されないといった安心感を持つことや、チーム内で自由に意見を言える環境を作るということは、チーム活動が有効に機能するために不可欠です。私もこれまでに、自分1人だけ別組織からプロジェクトに参画した時や、すでに活動を行っているプロジェクトに途中からジョインするケースで、どうコミュニケーションを取っていけばいいのか悩むことがありました。(相手が自分に何を期待しているのかも分からない状況)
心理的安全性を作るためには、まず自分の価値観を相手に理解してもらうことが大事。そのために伝える努力をして、その後に相手の価値観を把握する。"自分のことを分かってもらえていない・・・"と思うのではなく、
まず1対1の対話から始めてペア間での心理的安全性を体験し、それをグループに広げる、という考え方は参考になりました。
クリエイティブなマインドを持つ
過去を振り返ると、学生の頃はモノを作ることや考えることが楽しく、目に見えて動くプロダクトを作ることに熱中していた記憶があります。しかし社会人になってからは、役に立つ・効率化を行うようなモノを作る機会が増え、誰かを笑顔にさせるようなプロダクトを作ったり考える機会が無くなってきているなと。
講義中に出てきた5つのクリエイティブマインドを持つことは、UXデザインの理論やプロセス、手法を学ぶことよりも実は重要で、普段からこういったマインドをいかに形成できるかが大事だと実感した。
ビジョンデザイン
ビジョンという北極星があることで、チーム内で大きな方向性を作ることができ、ゴールに向かって進んでいく指針や、判断に困ったときの拠り所になる。これはVUCAの時代においても重要なことで、途中で登り方や道順が変わり回り道をすることになっても、その先にあるゴールは変わらない。
チームでボトムアップ的にビジョンをデザインする1つの方法として、まず個人の妄想と熱い想いから、良い社会を作るために未来のありたい姿を描く。次に、それら個人個人のビジョンを深掘り、奥底にある共通点を対話によって導いていく。(共通点を抽象化し、「要するに自分たちは何がしたいのか?」を概念化する)
この時、ビジョンを抽象化しすぎると耳障りの良い言葉が並び、個性がない綺麗に丸まったビジョンになってしまう。実際にビジョンデザインを行ってみることで、ここでも普遍性と雑味が大事だということを実感した。
講義ではボトムアップでのビジョン作りを推奨していて、そこは自分も賛同しますが、会社のトップダウンで作られた(フワッとした)ビジョンとどう折り合いをつけるのかが気になった。
グループワークと批判的対話
過去や現在の自分を俯瞰し、改めて自分を知るためのWSは、短い時間だったが自分のことを再認識することができて楽しかった。また、チームメンバーと対話をすることで、これまであまり知らなった相手のことを知ることができ、FBをもらうことで、自分も気づいていなかった価値観にも気づくことができた。
講義中に、2人ペアのスパーリングで、心理的安全性を考慮した批判的対話をすることにより仮説を深めることができる、という話があった。"批判する"ということは、自分の視点を持っていることでもあり、相手のアイデアを批判するだけでなく、アイデアをブラッシュアップすることにもつながる。
また、対話をするということは、議論や討論ではないというところも肝なのかなと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
