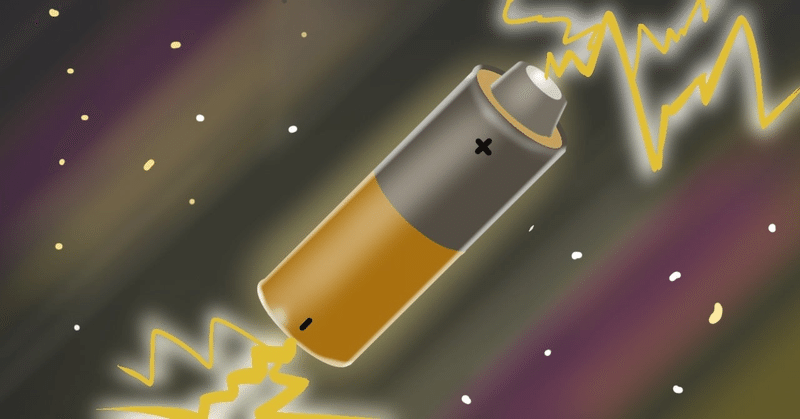
電池の技術革新が日本を支える
携帯には充電できるけど、電力は蓄電できないって聞く。
なぜだろう、と思ったため調べていました。
本日のニュースです。
Point
・EV車が高いのは量産化ができていないからである。
コストダウンの鍵は量産化にある
・車用電池には寿命を伸ばし、狭い空間に多くのエネルギーを詰め込める”大容量”であり、”軽量”であることが求められる
・日本メーカが世界を牽引するには”全固体電池”の実現が鍵
従来のリチウム電池より安全性が高まり、航続距離も2倍以上、充電時間が数分の可能性がある。
感想
脱炭素社会実現に向けて、自動車産業が大きな展開期に迎えている。従来のガソリン車から電気自動車へと移行しようとしている。そんな、EV化の最大の課題が”電池”にあった。
車載用電池には充電式の二次電池が使用される。この二次電池を大容量かつ軽量化し、寿命を延ばすことが求められている。これを解決するのは一筋縄ではいかないが、現在のガソリン車に負けないEV車を生産するためには、二次電池の技術革新が必要である。また、現在のEV車の価格帯では、広く社会に浸透することができない。量産化を実現し、シナジー効果によって、コストダウンすることが求められる。
米国ではEV化実現の為に巨額な投資が実施されている。日本はパナソニックが高い技術力を誇り、電池市場で競争力を維持している。しかし、各国も電池の技術革新によってEV市場を席巻しようと考えている。日本も諸外国に負けないスピードと技術で電池の技術革新に挑んでいる。二次電池の技術革新ができれば、日本が世界のEV化を牽引する可能性がある。日本の自動車産業に底力が試されている。
メタ情報
・電池には化学電池と物理電池がある。化学電池は化学反応をエネルギー源としている。化学電池は使い捨ての一次電池(ex懐中電灯)、充電式の二次電池(ex.スマホ・PC)と燃料電池がある。物理電池には、太陽電池(ex.ソーラー時計)がある。主なエネルギー源は物理エネルギーである。
・リチウム電池(携帯などの使用されている)は使用と充電を繰り返すと、劣化してしまことが課題。理由は、リチウム電池の中の化学反応がスムーズに起こらなくなるから。
・リチウム電池の中では、リチウムイオンが正極(+)と負極(ー)の間を移動することで放電・充電が起きる
・車載用電池には三つある
円筒型、角形、ラミネート型
・電池を構成する4つの素材
電池容量の6割の性能を決定する”正極材”、正極材との相性が重要な”負極材”、正極材と負極材の間に挟み、異常発熱や発火を防ぐ”セパレーター”、リチウムイオンの正極、負極間の移動を促す”電解液”がある。
・電池の構造は約40構造、4000種類。
用途にあった適切な電池の開発・使用が重要である
・一次電池の市場規模は約620億円であるが
二次電池の市場規模は約7120億円である。
・二次電池の課題は寿命を延ばすことにある
・電池部品メーカーの市場規模は約2兆円
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
