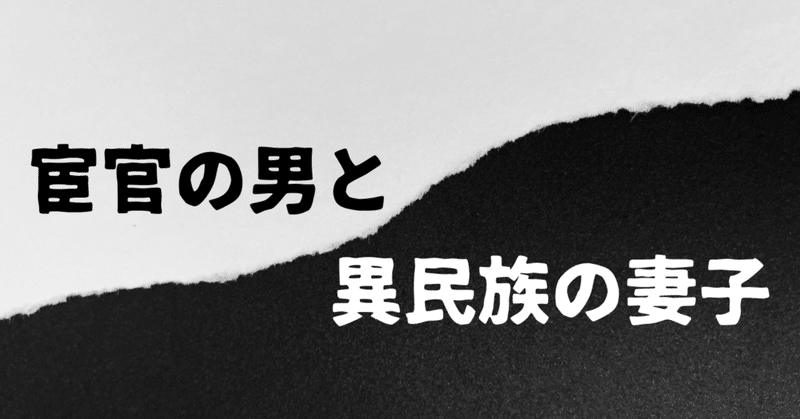
宦官の男と異民族の妻子
音声データ
こちらからダウンロードしてお聴きください。
詩編・聖書日課・特祷
2023年8月20日(日)の詩編・聖書日課
旧 約:イザヤ書56章1〜7節
詩 編:67編
使徒書:ローマの信徒への手紙11章13〜15節、29〜32節
福音書:マタイによる福音書15章21〜28節
特祷
主よ、どうか絶えることのない憐れみをもって主の教会を守ってください。人間ははかないものであり、あなたに頼らなければ倒れてしまうほかありません。み助けによって、害のあるすべてのものからわたしたちを守り、益となるものを与えて常に救いの道に導いてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン
下記のpdfファイルをダウンロードしていただくと、詩編・特祷・聖書日課の全文をお読みいただけます。なお、このファイルは「日本聖公会京都教区 ほっこり宣教プロジェクト資料編」さんが提供しているものをモデルに自作しています。
はじめに
どうも皆さん「いつくしみ!」本日もよろしくお願いいたします。
先週は8月15日に、台風の中ではありましたけれども、78回目となる「終戦の日」を迎えることができました。「終戦の日」を含めて、この8月という月は「戦争と平和」を覚える期間として、皆さんそれぞれに祈りの時を過ごしてこられたことと思います。今月僕は、皆さんの前でお話させていただくのが今日が初めてですので、今日の礼拝ではあらためて、かつての戦争に関するお話を交えつつ、聖書のメッセージを語らせていただきたいと思います。
日本のアイデンティティ
さて、かつてこの国の指導者たちは、日中戦争を契機に「国民精神総動員」という政策を導入して、人々を戦争へと駆り立てました。兵士だけでなく、非戦闘員、つまり女性や子どもも含めて国民全員の戦意を昂揚させる目的があったんですね。さらに、太平洋戦争へと突入していきますと、「一億玉砕」あるいは「進め一億火の玉だ」というような、言わば「滅私奉公」(お国のために自分を棄てる)のスローガンが謳われるようになっていきます。
大日本帝国憲法制定までの時代において、この日本に住む人々の中には、「国民/臣民」という意識がほぼありませんでした。「日本国民」という括りではなくて、皆それぞれに「◯◯の地域の人間」というような自己認識を持っていたんですね。けれども、日本政府は、そのような様々なアイデンティティを持っている日本の人々を、国家と天皇の名のもとで、一億の「臣民」として統一しようとしたわけなんですね。
今回、この話を準備している中で初めて知ったのですけれども、この「一億玉砕」と言うときの「一億」というのは、日本の人たちだけの人数じゃなくて、台湾や朝鮮といった「植民地」に住む人々も含めた数らしいんですね。当時、日本本土の人口は約7,000万人。つまり、1億の内の残りの3割は、台湾や朝鮮の人たちが占めていたという計算になるわけです。つまり日本政府は、日本の人たちだけでなく植民地に住む人々に対しても「滅私奉公」火の玉として玉砕する覚悟を求めたということになります。
台湾や朝鮮などの植民地においては、アイヌや琉球の人々にしていたのと同じように、「同化政策」が行われました。言語の撲滅、名前の変更、信仰の破壊、風俗の矯正などが為されたんですね。そのような、いかにも帝国主義的で身勝手な考え方のもと、いわゆる「内地・外地」を問わずに、様々な背景を持つはずの人々が「一億の臣民」という一つの大きな括りの中に縛られていたわけです。
78年前、日本が戦争に敗れたことによって、「一億の臣民」という枠組みは崩壊しました。しかしながら、この国では今もなお、日本国民のことを「単一民族」というように表現して「一つの枠組み」の中に入れようとする政治家たちがいます。古くは中曽根康弘、最近では麻生太郎といった国会議員たちですね。
日本という国は、様々な民族が集まってできた混合民族だというのが今や常識となっているわけですが、同じような言語、同じような文化を共有している我々にとって、その事実を実感する機会というのはなかなか無いような気がします。あるいは、そういったことを分かっている人でも、たとえば、琉球やアイヌ、また在日コリアンというようなマイノリティの人々に対して無理解な人たちが多いように思われます。
自分(たち)はそもそも何者で、この国はどういった人たちによって形作られているのか。そのようなアイデンティティに関わる問題に正面から向き合おうとしない限り、この国はいつまで経っても、あの「一億玉砕」「滅私奉公」の時代から本質的に生まれ変わることはできないんじゃないかと思うんですね。
捕囚後のユダヤ人のアイデンティティ
さて、聖書のお話に移りたいと思うんですけれども、本日の聖書のテクストは、旧約聖書の箇所として、イザヤ書56章1〜7節というところが選ばれておりました。この内の2〜5節は、聖書日課では“省略しても良い”という指示があったんですが、とても興味深い内容だったので、あえて選ばせていただきました。
このイザヤ書56章からそれ以降の内容というのは、預言者イザヤ本人ではない、後の時代の無名の預言者、通称「第三イザヤ」と呼ばれる人物によって書かれたとされています。第三イザヤという人物は、かつて、古代イスラエルを襲った「バビロン捕囚」という事件のあと、この箇所を書きました。バビロニアに強制移住させられていたユダヤ人たち。彼らは、バビロニアが滅亡したあと、故郷エルサレムに再び移り住むことを許されました。しかしながら、彼らの故郷における新たな旅立ちというのは、決して順風満帆なものではなかったんですね。と言いますのも、バビロン捕囚から解放された後のユダヤ人たちは、ある大きな壁に直面していたのです。第三イザヤと呼ばれる著者は今回の箇所の中で、その彼らユダヤ人たちが陥っていたある問題について扱ってくれています。
彼らが直面していた問題とは何か。それは、自分たちユダヤ人のアイデンティティの問題だったんですね。廃墟となったエルサレムの跡地には、元々バビロニアに連行されなかった同胞たちが残されていました。また、彼らに加えて、他の地域から移り住んできた異民族の人々もそこにいたんですね。彼らは、ユダヤ人たちがバビロニアに強制連行されていった後、その土地で新たな生活を始めており、すでに半世紀ほどの年月が経っていました。そうしますと、ユダヤ人たちは、彼らの元・故郷において「よそ者」になってしまったということなんです。国が滅ぼされ、民族としてのアイデンティティが崩されてしまい、そして元々の故郷では「よそ者」になってしまった。そんな彼らがもう一度、その土地を自分たちの「安住の地」にするためにはどうすれば良いのか。それは何よりもまず、自分たちは何者であるか、自分たちはこの地でどのように生きるか、という問いの答えを見つけ出す必要があったわけなんです。
異民族排斥を目指したユダヤ人共同体の始まり
旧約聖書の他の書物(エズラ記やネヘミヤ記など)を読んでみると、エルサレムに帰還したユダヤ人たちは当初、非常に“排他的な性格”を持っていたことが伝えられています。彼らのそのような性格を象徴するエピソードを一つご紹介したいと思うんですけれども……。
ユダヤ人たちは、新しい共同体を創り上げていく上で、一つの方針を打ち立てました。それは「純血性」です。彼らは、古来から存続してきたとされる「イスラエル民族」の血筋を受け継ぐ者のみを、共同体の構成員として(自分たちの仲間として)認めることにしたんですね。「単一民族」を主張する日本の政治家たちと共通する部分があるように感じるのは僕だけでしょうか。
しかしながら、島国である日本とは違って、ユダヤ・イスラエルは陸続きで様々な地域と繋がっていたので、ユダヤ人たちは異民族との交流を盛んに行なっていたんですね。そのような中で彼らは、バビロニアに住んでいた頃も、エルサレムに移住してきてからも、ユダヤ人ではない異民族の女性と結婚し、子どもをもうけるということを行なってきたようなのです。
そのような状況を受けて、彼らの指導者たちは、人々にとんでもない命令を下すことにしました。何と、男たちの中で異民族の女性と結婚した者は、その妻と、妻との間に生まれた子どもを共同体から追放するようにと命じたんですね。外国人は強制排除せよ!というわけです。
ネヘミヤ記という文書によりますと、ユダヤ人たちはその後、「混血の者を皆、イスラエルから切り離した」と書かれているんですが(13:3)、まぁそれが本当かどうか、その史実性も含めて疑わしいものがあります。けれども、このエピソードが表しているように、ユダヤ人コミュニティの出発というのは、「他」と「自分たち」とを区別するところから始まったわけなんですね。
ユダヤ人社会に対する第三イザヤの挑戦
先ほどもお話したように、バビロニアから帰還した当時のユダヤ人の指導者たちにとっては、「ユダヤ人」という“枠組み”を設けることが喫緊の課題でありました。この箇所の著者である第三イザヤもおそらく、それに関しては同じ意見を持っていたのだろうと思います。けれども、第三イザヤは、そのようなユダヤ人指導者たちが目指している、いわゆる「純血主義」に関しては反対の意見を持っていたようなんですね。
3節には次のように書かれています。「主のもとに集って来た異邦人は言うな/主は御自分の民とわたしを区別される、と。」これはどういうことかというと、「異邦人」つまり異民族・非ユダヤ人が、「わたしは神に認められていない。共同体の中には入れてもらえない」と言っていることに対して、第三イザヤが「決してそんなことはない」と諌めているわけです。
第三イザヤは、続く6〜7節に記されておりますように、「主のもとに集って来た異邦人が/主に仕え、主の名を愛し、その僕となり/安息日を守り、それを汚すことなく/わたし(主)の契約を固く守るなら/わたし(主)は彼らを聖なるわたし(主)の山に導き/わたし(主)の祈りの家の喜びの祝いに/連なることを[許される]」のだと考えていました。うまり、古代イスラエル(ヘブライ人)の子孫であろうとなかろうと、異民族の女性やその子どもであったとしても、自分たちと同じように生活するのであれば、みな仲間なのだ……と、そのように第三イザヤは宣言したわけです。このような主張は明らかに、当時の排他的なユダヤ人社会に対する「挑戦」であったと言えます。
去勢されたユダヤ人男性たち
さて、この箇所では、異教徒のほかに「宦官」と呼ばれる人物に関して言及されています。「宦官」というのは、去勢手術を受けた王宮で働く男性のことを言います。去勢の仕方もいろいろあったそうで、生殖機能を失わせる方法から、男性器すべてを取り除いてしまうという方法まで、様々なやり方があったようです。
どうして第三イザヤは、この箇所で「宦官」と呼ばれる人たちのことを取り上げているのか。それは、宦官のように去勢手術を受けた男性が、ユダヤ人コミュニティから排除されていたからなんですね。
旧約聖書の申命記にはこのような記述があります。「睾丸のつぶれた者、陰茎を切断されている者は主の会衆に加わることはできない。」(23章2節)……人類の歴史において、子孫を残すことは常に最も重要な使命の一つとされてきたわけですけれども、古代イスラエルにおいては、その役目を果たせない者は、共同体を維持していく上で妨げとなると考えられ、神の会衆に加わることが許されなかったそうなんですね。
バビロニアに強制連行されたユダヤ人たちの中には、バビロニアの慣習に基づいて去勢を受け、宦官や奴隷として働かされた者たちが多かったのだろうと考えられます。おそらくそれは、帰還後のユダヤ人社会において無視できない数だったのではないかと思われます。しかしながら、当時の極端な民族主義に陥っていたユダヤ人社会は、律法に違反した存在である彼らを仲間として受け入れるべきか否かを議論できる機運を作り出せずにいました。そのような状況にこの時、一石を投じたのが第三イザヤだったわけなんですね。
第三イザヤは、異民族だけでなく、宦官(去勢を受けた男性)もまた、神の会衆として認められるべきだと主張しました。去勢した男性は、子孫を残すことができなかった。一方、この箇所で先に挙げられていた「異邦人(異民族)」は、ユダヤ人との間に子どもをもうけることが許されていなかった。子孫を残せない者たち。子孫を残すことが許されていない者たち。そのような人々が当時のユダヤの地には住んでいたわけですけれども、そんな彼ら彼女らのことをユダヤ人社会は切り捨てる(排除する)方向で動いていた。しかし、そのような社会の課題として浮かび上がってくる中で、第三イザヤはまさに「預言者」として(神の言葉を伝える者として)、去勢された男性も、異民族の女性やその子どもたちも皆、彼ら彼女らが望むのであれば、他のユダヤ人たちと同じく「神の会衆」に加わることができるのだと“預言”したわけですね。そしておそらく、このように第三イザヤの言葉が聖書の中に収録されているということから推察するに、当時のユダヤ人社会は、彼ら彼女らのことを「受け入れる」という選択をしたのだろうと考えて良いのだろうと思います。
おわりに
第三イザヤの言葉は、社会から遠ざけられてきた人々にとって、まさに解放を告げる福音となったのではないでしょうか。その精神は、ユダヤ教の根底に伏流的に存在し続けた。そして、第三イザヤの時代から数百年の時を経て、あのイエス・キリストの時代に大きなムーヴメントを生み出すことになったわけですね。
その後のキリスト教はどのような歩みを続けてきたのかと言うと、皆さんご存知のように、必ずしも教会は「解放的」「包括的」であり続けたわけではありませんでした。「キリスト教」と言えど、所詮「宗教」とは人間が形作っているものですので、時に我々教会は、第三イザヤから受け継がれてきた解放の精神を蔑ろにして、救いの範囲を制限してしまうこともありました。自分たちとは価値観が異なる人々を排除するということも行なってきました。けれども、そのように「救いの扉」が開いたり閉じたりする中にあって、今この我々の時代は、どちらかと言えば「開かれている時」なのではないかと感じます。ですので、この時代に生きる我々の使命は、外の空気に押し戻されそうになる救いの扉を押し返して、より包括性と多様性に富んだ教会を築いていくことなのだということを、今日あらためて確認しておきたいと思うんですね。
それと同時に、外の世界に向けて救いの風を届けていくことも、我々キリスト教の大切な役目であると言えます。冒頭で触れたように、この国は未だに、先の戦争で反省すべきだった「国民のアイデンティティの問題」を引きずり続けています。かつて日本の人たちは、アイデンティティ、つまり「自分とは何者か」という答えを権力者たちに握らせてしまっていました。「お前は『一億』の中の一人だ」と言われて、無批判にそれを受け入れていたわけです。
戦後78年が経過した今でも、多くの人たちが“誰かによって作られた”「日本」という枠組みの中に自分を入れてしまっているように思います。だが、それは明らかに間違った生き方だと言わざるを得ません。日本という入れ物があって、その中に我々が住んでいるのではない。そうではなくて、他の誰でもない「自分」という存在が大勢ひしめき合いながら形作っているのが、この日本という国であるはずなんですね。
自分が「自分」を失ったとき、そこには「戦争」が起こる。誰かの「自分」を否定しようとするとき、そこには「差別」が起こる。だから、自分を失ってはいけないし、誰かの自分を失わせてもいけないのです。
いま、戦争の足音が遠くから聞こえてくるような、そのような不穏な空気が広がっています。また、かつての帝国時代の日本のように「滅私奉公」を強いられる時代が来るのではないかと心配しています。そのような中で、我々キリスト教は、まさに第三イザヤがそうであったように、社会の中に「一石を投じる」存在でありたいと願います。かつて「民族主義」に陥ってしまい、「滅私奉公」の精神の権化となってしまったこの国が、二度と同じ過ちを繰り返さないために、この国を形作っている我々一人ひとりが、「自分が自分であること」の尊さを、そして様々なアイデンティティを持っている人々と共に生きているその喜びを、しっかりと胸に刻まなければならないのではないでしょうか。
……それでは、礼拝を続けてまいりましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
