
タスクは管理する、人とは対話する
「リモートワークによってあなたの生産性はどう変わりましたか?」と聞かれたら、人はどうしたって、自分の生活の変化全体に対する印象を混ぜ込んで答えてしまう、という話しを書いた。
ビジネス(≒パブリック)パーソンとしての「自分」と、パーソナル・パーソン(個人的個人)とも言うべき「じぶん」が溶け合う。
これはもう、良いとか悪いとかの話しではなくて、そうなってしまうという性(さが)としての話し。
だったら、普段の仕事のなかにも、感情みたいな人間臭いものを前向きに取り込んでみたらどうだろう、という問いが起きる。好き嫌いとか、やりたいやりたくない、みたいな、ある種「子供じみた」パラメータを積極的に使ってみる。そうすることで、「投下した単位リソースあたりの得られたリターン」という組織文脈での生産性も上がるのであれば、個人も組織もみんなハッピーじゃないかと。
「苦手な人へのメール」というタスク
昔からある、バブルマップというタスクの見える化手法が手っ取り早い。
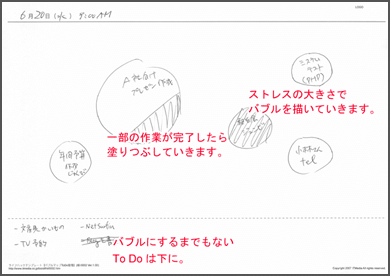
バブルの大きさはそのタスクから受けるストレスの大きさで表します。つまり、いや~な感じのするToDoは大きなバブル、すぐに片付けられそうなToDoは小さなバブルを描いていくわけです。
『#002 バブルマップ型ToDo管理シート』より
落合陽一が言うところの、タイムマネジメントからストレスマネジメントへ、というのに通じる。タスク管理というと、見える化しましょう、細分化しましょう、所要時間を見積もりましょう、優先度をつけましょうという流れが一般的。それに対して、仕事起点のパラメータ(所要時間や優先度)でお行儀よくソートするのをやめて、個人起点のパラメータ(いや〜な感じ)でもってぶちまけてみましょう、というアンチテーゼなわけだ。
これは自分のよくある一日を思い返してもしっくりくる。
タスクリストのなかに居座る「苦手な人へのメール」というタスク。いざ取り掛かってしまえばおそらく10分で終わるはず(仕事起点のパラメータ)だし、このメールを出さないと後続の作業に影響する(仕事起点のパラメータ)のは、頭ではわかっている。
そう、頭では、わかっている。でも、気が乗らない。
そうしてアリバイづくりで他のタスクに取り掛かってしまい、一日の終りにため息とともに、明日のタスクリストに先送りする。次の朝に見るタスクリストのなかにも居座る「苦手な人へのメール」というタスク。
という無限ループ。
この無限ループを良いとか悪いとか断じることもできるのだけど、そうしないで、それが人間の性(さが)なのだと捉えなおせば、「人間なんだからそういうもんだ」と肝が据わる。そして、大きなバブルで描かれた「苦手な人へのメール」が片付いたときには、豪快に塗りつぶしながら達成「感」を噛みしめる。
メール一本書くことは、仕事全体から見れば達成(成果)とは呼べないかもしれないけど、生身の人間が達成「感」を感じる(成長)のは自由だ。だって「感じ」なんだから。
バブルマップを自分ひとりのタスクについて描いてみるのもいいのだけど、これを人材育成やチームマネジメントという「他者との関わり」に積極的に使ってみるのもよい。
相手も生身の人間、という当たり前の事実に向き合ってみる。
進捗を報告するのではなくて、感情を共有する
1つ目の応用場面は、リーダーとメンバーの間での1on1。
メンバーの進捗がなんだか良くない。いったい何にそんなに時間がかかっているんだ?ということで、仕事起点のパラメータ(所要時間や優先度)でお行儀よくソートされたタスクリストを一緒に見ながら、タスクの進捗について話し合う。
よくある光景だけど、こういうときメンバーは実は、前述の「苦手な人へのメール」みたいなタスクでもって、いわゆる「ふんづまってる」状態だったりする。でも、「苦手な人へのメール」はタスクとしては些細すぎてタスクリストにあらわれてこなかったり、仮にタスクリストに乗っかったとしても、リーダー(他者)の目には「そんなのちゃちゃっと送っちゃえばいいじゃん」と映る。なぜならリーダー(他者)は、メールの送り先の人を苦手だと思ってないから。
もうひとつ別のパターンとしては、「将来に対する漠然とした不安」でもってふんづまってるときもある。
この先このプロジェクトはどうなるの?そのときは私はどうなるの?有り体に言えば、組織や個人のビジョンが見えない、ということなのだけど、進捗が悪い理由として「ビジョンが見えないから」というのは、そもそも本人が気づきにくいし、気づいたとしてもそれを他者に言うことは憚られる。
「苦手な人へのメール」パターン以上に、こちらの「将来に対する漠然とした不安」パターンが実は多いんじゃないだろうか。プロジェクトや自分のミッションにしっかり向き合うからこそ、こういう不安が出てくるのだと思うと、これは、メンバーのコミットメントの表れという前向きな状況とも言える。
でも、引っかかってるものは引っかかってるわけだから、そこをなんとかしないことには、前に進まない。別にビジョンが定まるまで仕事の手を止めるわけではなくて、まず「先が見えなくてモヤモヤしてるんです」とメンバーが吐き出すこと、そしてそれに対してリーダーが「そうか、じゃあ一緒に考えようか」と向き合う。そうやって解きほぐすことで事態は氷解していく。
その第一歩が、「この先どうなるのだろう?」というバブルなのだ。
タスクを共有するのではなくて、頑張っていることを見せあいっこする
2つ目が、チーム内で各メンバーのタスクを共有する場面。
各メンバーが複数のプロジェクトを掛け持ちしていると、隣の人がどれくらい忙しいのか、なんでそんなに忙しいのかがわかりにくい。なので、各メンバーにバブルマップを描いてもらって、それを持ち寄ってみんなで見せあいっこするという取り組みがある。
そうすると、気にしていることが本当に人それぞれだし、ああこの人こんなこともやってるんだということがよくわかる。これは仕事起点のパラメータ(所要時間や優先度)でお行儀よくソートされたタスクリストからでは絶対に見えてこない。だって仕事起点で考えれば、「気にしていることはすべてタスクリストに載っているはず」だし、タスクリストは担当者ごとではなくプロジェクトごとに分けられていることが普通だから。
だから、「あえて」個人起点で向き合う時間を取る必要がある。
これをやるときの注意点は、純粋に見せあいっこ「だけ」をする、ということ。そして話すのは「感じたこと」だけ。絶対に「タスクの細分化」や「工数の見積もり」や「役割分担の見直し」をその場で始めないこと。同じ時間のなかでそれを始めてしまったら、結局どこまでいっても仕事起点の時間になってしまう。個人起点の話しだけをして、その時間は閉じる。
そうすれば、もともと設定されている定例の進捗ミーティングなど「仕事起点」の時間のなかで、必ず「タスクの細分化」や「工数の見積もり」や「役割分担の見直し」が始まる。しかもそれは、タスク(仕事)を見ての話しあいではなく、隣の人(個人)のことを感じながらの話しあいになる。こういうのを、「思いやり」と呼ぶのではないだろうか。
ビジネス(≒パブリック)パーソンとしての「自分」と、パーソナル・パーソン(個人的個人)とも言うべき「じぶん」が溶け合う。
人間は感情の生き物とは言い古された言葉だけど、と同時に、他者とつながるためには論理が必要とも言える。
感情だけでは仕事にならないけれども、論理だけでは居心地が悪い。感情と論理をバブルでつないで、そして他者と対話する。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
