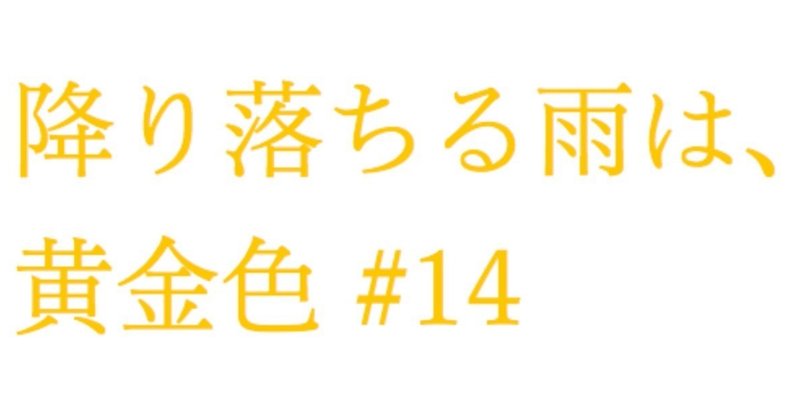
降り落ちる雨は、黄金色#14
佳代の家は新築マンションの最上階にある。父親は放送業界の人らしく、インテリアも華やかでテレビのセットの様に生活感がない。
彼女は家の中では花や苺柄のデザイナーブランドのパジャマを着ている。本人曰く、身体の締め付けがなく楽だと話していた。
「あのさ…」
「なに。好きな人でも出来た?」
佳代の瞳が煌々と輝いた。
「小説家になりたい」
「ウケる」
私のやりたい事が決まったお祝いに、コンビニでお菓子を買いに行こうと佳代が言い出した。佳代はマスクをつけ、パジャマの上に黒のレザージャケットを羽織った、その姿は海外セレブの様だった。
「偽パリスみたい」
佳代は百円ショップで買った派手なピンク色のサングラスをつけ、私を笑わせた。
「それで出るの?」
「家の中だけ。ちょっと待って」
佳代は洗面台に行き、高そうなブラシを持ってきた。
「髪やってあげる」
佳代はブラシで私の髪を梳かしだした。体温の上昇を感じる。私のドキドキが伝わったらどうしよう。恥ずかしい気持ちでいっぱいになった。
部屋の中は時計の音と空気清浄機の音しか聞こえない。気まずい。佳代の集中力が伝わってくる。近所で不発弾でも見つかってこのモヤモヤを吹き飛ばして欲しい。
「おしまい」
拷問のようなブラッシングが終わった。佳代は作品を完成させた様な満足げな顔をしている。彼女のプレイに付き合って私はひどく消耗してしまった。まるで犬のようだ。犬は偉い。彼らは飼い主に玩具の様に扱われても、何事もなかったかの様に尻尾を振りながら無邪気に近づいてくる。私には出来ない。
機嫌の良くなった佳代はハネムーンに出かけるように私の手を掴み、ふたりでコンビニへ出かけることにした。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
