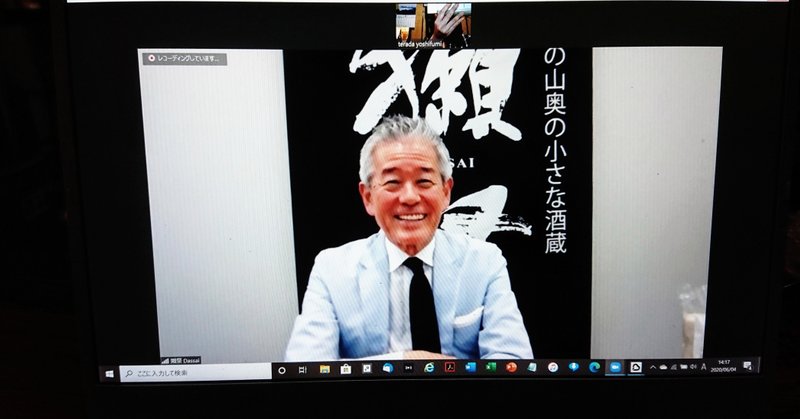
「蔵元のことばかり」つづくこれからの話“獺祭”桜井博志会長の場合。(後編)
こんにちは、山内聖子です。
前編では、まさか、売れている日本酒の蔵元から聞くとは思わなかった、予想外の言葉に面食らった話からはじまりましたが、
引きつづき“桜井博志会長の場合”後編をお届けします。
(本連載は拙書である『いつも、日本酒のことばかり。』の特別企画としてはじまり、新型コロナ感染症が世間に蔓延するなかで、蔵元さんたちがそれにどう向き合ってきたのか。蔵元さんたちの「今まで」と「これから」について書いていく記事です)
後編のはじめに
私のなかで桜井会長とは、優れた経営者である以上に、”酒蔵の仕事が大好きなかっこいいおやじさん”です。旭酒造で長年働いているある方に「桜井会長は趣味も酒蔵」と言わせるくらい、酒蔵の仕事つまり、酒づくりに熱中している蔵元なのです。
酒蔵の規模が大きくなるにつれ、ものづくりをしている人というよりも、だんだん語ることも行動も経営者然としてくる蔵元が多いなかでも、桜井会長はいつまでも、昔のうたい文句だった「山口の小さな酒蔵」でお酒をつくっていた頃のつくり手としての視点や姿勢を大事にしているように見えます。
いつだったか「獺祭とは自分が好きな味」と言い切っていた桜井会長は、経営者としてどうやって売れる酒をつくるかよりも、どうやったら自分が好きな味をおいしくつくることができるのか、というような、つくり手としての志を常に持ちつづけている蔵元だと思います。
コロナのような災難がふりかかっても、目先の利益を考えるのではなく、獺祭のおいしさを追求することを優先するあたりも、私が“かっこいい酒蔵のおやじさん”と言いたくなるゆえんでもあります。
「CRAFT獺祭」の試みも、つくり手の視点を持っている人でなければ、思いつかないアイディアなのではないでしょうか。
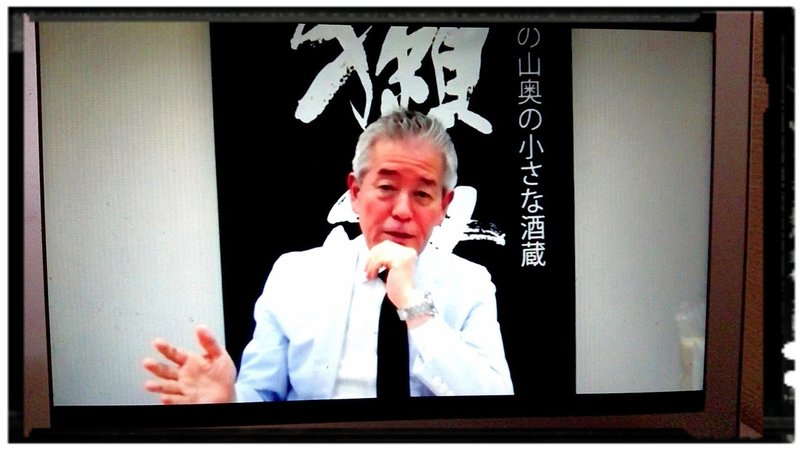
やっぱり地域の酒屋さんとともに生きていく
実は、去年からずいぶん悩んでいたのが販路についてです。日本酒ファンの方からしたら、獺祭はどこにでも売っていると思われるかもしれませんが、愛好家以外の一般のお客さんからにとっては、まだまだどこにでも手に入る酒ではありません。
一昨年くらい前から、大手だけではなく、いろんな酒蔵がスーパーやコンビニでも酒を売りはじめました。そんななかで私どもの酒蔵はどうするのか。“獺祭”は、冷蔵庫で保存してくれる高級スーパーには卸していますが、一般的なスーパーにはまだ置いていないんですね。コンビニにも売っていません。
獺祭は、数量を限定して手に入りにくい酒にするのではなく、求めるお客様に広く届けるために製造量を増やしてきたのですが、果たして、販路は今のままでいいのだろうか。とても悩みました。
しかし、やっぱりこのままでいこうと。地域の酒屋さんとともに生き残っていこうと覚悟を決めたのです。
そんなときに、コロナが降りかかり、売上の数字がガクッと落ちていって…。獺祭の販路の薄さがもろに出たと思いました。
こんなことを言ったら、酒屋さんに石を投げられるかもしれませんが(笑)こうなると、やっぱりスーパーに卸していればよかったかな、なんてことも頭をよぎるわけです。
それを見透かしたように、今まで取引していなかった大手の業務用酒販店やスーパーが、「うちで獺祭を売らないか?」と売り込みに来るんですよ。数字も落ちていましたし、正直、オロオロしますよね。
でも、やっぱり私は地域の酒屋さんを大切にしたい。日本酒だけではないですが、世の中の小売業がすべてコンビニやスーパーだけになってしまったら、日本の経済も、ものづくりの価値観もおかしくなると思います。
そして、大手の売り場に卸せば、短期間で売上を伸ばして利益を増やすことはできますが、販路が急に広がる反動で、確実にブランドを壊してしまう。獺祭を求めるお客様に広く届けたいという思いとの葛藤はありますが、うちはブランドを壊される方向に行きたくはないんです。
ですから、今後は販路をどうするか考えるよりも、お客様が買いたくなるような魅力があるもの、お客様に大事にされるようなものをつくることの方が先決なのではないかと。これが、おそらく獺祭にとっての正解です。
抱えている在庫について
もうひとつ懸念しているのが、取引先が抱えている在庫についてです。どの店もコロナの影響で売れない酒を抱えている状態で、例えば、全国の空港にある免税店に卸している在庫だけでも1億くらいあるんですよ。
というように店によっては、獺祭を仕入れたら冷蔵庫で保存して冷蔵で売る、というサイクルが完全に断ち切られてしまったので、抱えた在庫はどんどん劣化して、たぶん大半が売り物にならないでしょうね。
ではどうするのか。完全な答えは出ていませんが、小売店ごとの個別対応になると思います。古くなってどうにもならない酒は交換してほしいなど、いろんな要望がこれからきっと出てくるはずなので、それに対してはきちんと対応させていただくつもりです。
ここの対応を今、大事にしていかないとお客様が離れていってしまう。獺祭っておいしくないよね、となってしまいます。皮肉な話をすると…なんせいつもよりも製造の現場が暇なので、新しい酒をつくる余裕はあるんですよ(笑)ですから、引きつづき、どうやってお客様においしい獺祭を届けることができるのかを第一に考えています。
困った困ったと言いながらもおもしろいことをやる
というように、現状抱えている悩みは尽きないのですが、困った困ったと言いながらも、この期間を利用して獺祭らしいおもしろいことをしたいと考えました。
そのひとつに、「CRAFT獺祭」があげられます。

稼働率が落ちた製造の現場を利用して、若手の社員たちに酒をつくってもらったんです。これは今、私の中でよい手応えを感じている試みです。若手社員の技術を伸伸ばすためにはじめたことでもありますが、私自身の個人的な気持ちもきっかけの根っこにあります。
今の社会というものは、何事もどんどん大型化、寡占化しつつあります。それはやっぱりおかしいんじゃないかと。
酒蔵の規模を拡大した今の獺祭からすれば矛盾した考えかもしれませんが、小さな酒蔵からはじまっている私の会社としては、画一的なものだけではなく、若い人たちが力を発揮してつくる酒のような、バラエティに富んだ酒もこれから必要だと思ったんです。
とはいえ、ただバリエーションを増やすためのものではなく、おいしい獺祭をつくるひとつの目標に向かっている中で、必然的に生まれるバラエティな酒です。
今後は、若手が小さなチームでつくっていく酒と、定番の獺祭とふたつの方向で酒をつくっていくことを考えています。もしかしたら、2万石は今までと同じ酒をつくり、あとの1万石は若手がつくる数百石が寄り集まってできた酒、という方向でいくかもしれません。
若手がつくった酒も正直、とても出来がいいんですよ。
私が蔵に帰ってきたばかりの頃に自分でつくった酒よりも、腹立たしいくらい(笑)完成度が高い。CRAFT獺祭をはじめてから、若手社員の目つきがいい意味で変わりましたね。今まで以上に、社員同士が切磋琢磨できるのではないかと思っています。
ますます本質的な価値で勝負していかなくてはならない
私どもの酒蔵はコロナが収束するまで2、3年は、全体の売上が4割落ちる覚悟でやらなければならないと考えます。売上を支えていた飲食店に客足が戻るまでは、まだまだ時間がかかるからです。特に高級店はきびしいのではないでしょうか。
宅飲みの需要が高くなってきているとはいえ、家で飲むのは安い酒でいい、という方も多いので、日本酒の中で最も高級な純米大吟醸だけをつくっている獺祭は、ちょっときびしい立場に置かれていくと思います。
しかし、獺祭は日本酒の中でも高級酒の部類には入りますが、今まで実質的に価値がない高いものをつくってきたつもりはまったくありません。その証拠に日本酒は高級酒ほど原価が高いので、値段のにわりに安いものをつくってきた、という自負が常にあります。
言葉は悪いですが、意味のない高い酒なんて世の中にいっぱいあるわけですよ。そういう商売も成り立っているのでしょう。
でも、これからは、ただ高いだけの水増しした価値で売っている酒は、見向きもされなくなるでしょうね。ますます本質的な価値で勝負しなければならない時代になると思います。
図らずも、私の中で答えが出たんですけれども、つまり、今は目先の利益だけを追い求めていては、これから酒蔵は生き残っていけないですよ。
おいしい日本酒をつくるのはもちろんのこと、どうやっておいしい酒をお客様に届けることができるのか。おいしい酒を供給しつづけることができるシステムを、しっかり再構築していくことが今もっとも大事なのです。
(終わり。最後まで読んでいただきありがとうございました)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
