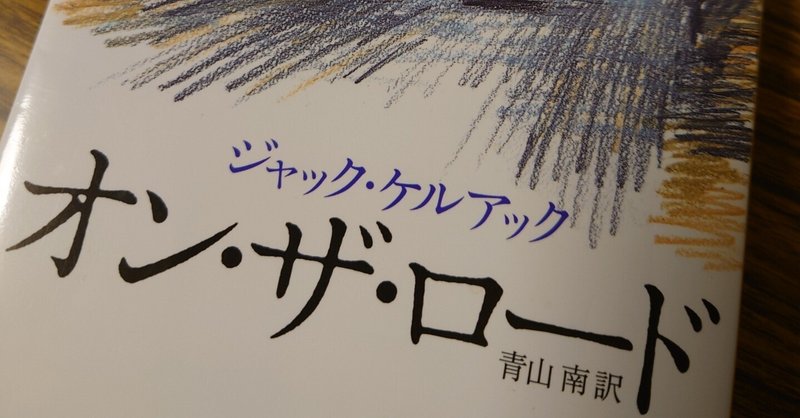
失われたXX年と『オン・ザ・ロード』
出発の日は二日酔いだった。たしかにワインを1本呑んだが、二日酔いになるほどではない。はずだった。しかし、バッチリ二日酔いのまま、新幹線に間に合うように家を出る。
最寄りの駅まで歩くのが面倒だったので、タクシーを拾う。私を見て、運転手は「帰省ですか」と尋ねてくる。
「ご両親も帰ってくるのを楽しみにしているでしょうね」
とかそんな話をした。マスクをしていたからわからなかったのかもしれないが、私はまあまあのおっさんだ。帰ってきて喜ぶようなものでもない気がする。
新幹線に乗る時は、お弁当とお酒を買い、道中でガッツリ呑むというのが長い間定番となっていた。だが、二日酔いがまだ残っていたので、まったく食う気にも呑む気にもならなかった。お茶だけ買って、新幹線に乗り込む。
帰省のピークだったが、こちらも素人ではない。ちゃんと指定席を買っている。そもそも指定席以外のチケットを買ったことがない。帰省ラッシュの地獄のような普通車に乗る気はまったくない。金があろうがなかろうが、ずっと指定席を買っていた。なので、実際のところ、普通車の状況がどういうものなのかは知らない。しかし、地獄で間違いないだろう。独自通貨で缶ビールを買うようなところなんだろう。間違っていても知るか。
車内は家族連れが多かった。だが、ここは指定席だ。利発な子どもしか乗れない。騒がしくする子どもはいなかった。普通車だとこうはいかないだろう。時間を潰すために、年末に買っておいたジャック・ケルアックの『オン・ザ・ロード』を読み始める。
高校生の頃に旧訳の本を読んだ。青春のバイブルなのだ、とか、ビートジェネレーションの幕開けなのだ、とかヴィレヴァンのポップに書いていたので手に取った。ティーンのイタい衝動をくすぐるのには充分な売り文句が並べられていた。その当時の読んだ感想はというと。
わからん、の一言だった。
本の中に難しいことは何も書かれていないが、何がそんなに素晴らしいのか理解できなかった。
本の中身は、主人公がイカれた友達と車で貧乏旅行して、馬鹿騒ぎして、たまにすけべする。そんな内容だ。
またその本を読もうと思ったのは、新訳が出たことと、少しは中身がわかるようになったんじゃないかと思ったからだ。
実際、思った以上にするすると文章が頭の中に入ってきた。自分が書く文章に少し似ているように思った。知らないうちに影響されていたのだろうか?
もうひとつ持ってきていた本がチャールズ・ブコウスキーの『勝手に生きろ!』だ。
こちらも、主人公が転々と流浪しながら、酔っ払って、すけべをし続ける話だ。違うのは、こちらはずっと酔っ払って、すけべしているという点だ。ただ、この本は途中で読むのをやめた。それは小説の中の一文のせいだ。
おれは想像していた。糞のスジが少しだけついたカルメンのパンティが、おれの爪先に引っかかっているさまを。
秀逸な文章だ。一度読んだら忘れない。おかげで思い出すことができた。
私は以前この本を読んだことがある。
それからはずっと『オン・ザ・ロード』を読んでいた。
新大阪に到着して、駅の中で何か食べようかと思ったが、ピンと来るものがなかったので、そのまま実家に向かった。途中、乗り継ぎの駅で何か食べようかと思ったが、いまいちピンと来なかったので、結局、何も食べずに地元の駅まで行ってしまった。疫病のせいで3年近く帰っていなかったせいもあって、もう大阪はピンと来ない街になったのかもしれない。
最寄りの駅でたこ焼きだけ買って、実家で食べた。
東京はたこ焼きが高い。イカれてるくらい高い。大阪はまだまともだ。そのへんは。
夜に地元のホーミー(友人)から連絡があり、呑みに行かないかと誘われた。帰ってきたばっかりだし、翌日、昼から呑む約束があったので、どうしようと思ったが、結局行くことにした。
向かったのはあべの橋である。もうすでに店に入っているらしいので、店の名前を聞いて、そこへ向かった。『勝男』という店らしい。
路上では、なんというか、ほどよく民度の低い若者たちが集まって、次の店の相談をしている。
「呑みかキャバか女か」
若者の言葉に、キャバと女は一緒ちゃうんか、と無言でツッコむ。なにわのツッコミの肩も少しは温まってきたと実感した瞬間だ。
店は意外とすぐ見つかった。外に『勝男』とでかでかと書いていたからだ。ビルの上階らしいので、民度の低そうなスーツ姿の男たちを吐き出したエレベーターに乗り込む。
パンティが落ちていた。
ギャルのパンチィー、かどうかは知らないが、紐みたいなパンティだった。これが大阪のクオリティやで! とばかりにエレベーターが店の階でぽーんと音を立てて止まった。
出ていくとゴリゴリのギャルたちが小銭で会計をしていた。店員に先に来ているホーミーがいると告げて私は店の奥に行く。もしや落ちていたパンティはレジ前のギャルのものだろうか。
「お嬢さん、パンティ落としてましたよ」
と声をかけた方がよかったのか? 声をかけていたら私はゴリゴリの変態扱いされただろう。
あるいはあれは糞のスジがついたカルメンのパンティだったのかもしれない。
ホーミーと合流する。バカみたいにデカいハイボールを頼む。それがバカみたいに安い。東京にこんな店はないな、と言ったが、普通にあると教えられた。
ホーミーはOとJとYの3人である。OとJは東京進出を考えているようだった。本気がどうかは知らない。Yは彼に説教をするだけが仕事だった上司が定年でやめたらしい。手巻きのタバコをマリファナみたいに吸っていた。
みんな、いい歳のおっさんなので、それなりに生きていた。若い頃のようにカツカツの生活ではなくなっていた。
それなりに生きる。私の世代は、それなりに生きる能力に長けている気がする。誰かに与えられるわけでもなく、何かを作るわけでもない。自分の持っているものや出来ることで、それなりに生きる。そんな生き方が染み付いているように思う。
いわゆる「失われた世代」なのだが、正直言って、失われたものが何かすら知らないので、悔しがることすらできない。ないものには興味がない。だから、それなりに、いまあるもので生きてきた。いまだといろんなことでマネタイズできるから、そういったものに乗って、稼いでいる奴もいるだろう。それはそういう道具がそこにあったから、使っただけだ。そうやって生きてるだけだ。
『オン・ザ・ロード』はアメリカの1950年代に出現したビートジェネレーションのバイブルといわれている。ケルアック本人はビートジェネレーションという言葉には否定的だった。彼はただこの小説の中で、「打ちのめされた=ビート」という表現をいくつか使っているに過ぎない。
だが、そうした言葉遣いや放浪と放蕩を繰り返す若者を描いたことで、ある種の世代の感覚を表現してしまったのだろう。それをその後のメディアなどが安易に世代化した結果、ビートジェネレーションが生まれた。しかも、その世代の代表のように扱われるのだ。ケルアックからすれば、迷惑なことだろう。
私も同じだ。「失われた世代」といわれているが、失われたと思っているのは何かがあったと思い込んでいる人たちがそう言っているだけで、私は何ひとつ失っていない。知らんがな。それに尽きる。
しかも、失われた時代は10年、20年、30年と伸びている。もはや失ったと思っている方が狂人じゃないか。30年前に妻を失った男なら、まだ妻を失ったと言い続けているだろう。その男はイカれているからだ。
しばらくその場所で呑んでラストオーダーだというので、別の店に移動する。そこもすぐに店を閉める時間になり、また追い出される。帰りの電車に間に合うか間に合わないかの時間だ。だが、もう考えるのが面倒なので私はタクシーで帰ればいいと思っていた。そんな二十歳そこそこが気にするようなことはもう気にしない。
年末の真夜中の街をぶらぶらする。四人のおっさん。私の知らないうちにできた明太子で有名なやまやの店の前を通りかかる。ランチは明太子食い放題なのだ。いい店か? そんなことはない。ご飯がおかわり有料だ。あんな塩辛いものだけおかわり自由とはどういうことだ。イカれている。少量のおかずで大量の飯を食うのが、我々の世代の習わしだ。地獄に落ちろ。
なんとか流れ着いたバーで酒を呑む。帰りの電車はもうない。我々は貧困ビジネスについて語り合う。べつにやる気はないが、やろうと思えば出来るな、という話だった。貧困までビジネスになるのだからイカれた時代だ。
午前2時まで呑んで、Oと一緒にタクシーで地元に帰る。途中、何軒かなか卯の店舗を通り過ぎる。東京だとあんまりない。なぜか私の近所はすき家で八門遁甲の陣を敷かれている。すき家には用はない。私はなか卯の親子丼が食べたい。けど、その夜ではなかった。赤と緑と白の看板が遠ざかっていく。

翌日は昼から大阪で働いていた頃のフッド(友人)との呑みだ。なぜか帰るたびに行われている。みんな身が軽い。呑もうとなったら、秒で決まる。
話すことは大体、業界の楽屋ニュースである。誰が出世したとか誰が政治争いに敗れたとかそんな話が多い。あとは下世話な話だ。
実はこの後、夜からまた地元のホーミーたちとの飲み会があったので、酒の量はセーブしていた。そのうち、酒を飲みながら元気になればと思って、レッドブル割りばかり飲んでいた。飲みながら元気になるから無限に飲める。死ぬ時は突然死ぬんだろう。翼を授けてくれるから。
ただ、死ぬことはなくほどよい感じに酔いながら、再び地元へ戻ることになる。大阪市内から再び地元へと来た道を戻る。
『オン・ザ・ロード』で描かれる旅も行きっぱなしの旅ではない。ケルアックの分身であるサル・パラダイスは、旅の終わりには叔母の家に戻っていた。だから正確に言えば、小説の中で描かれているのは旅ではなく、ケルアックもそう書いていたように、「路上(ロード)」へ帰る行為だった。「路上(ロード)」から都市に移動し、また「路上(ロード)」に帰る。そして最後には叔母の家に戻る。主人公たちが真に重視していたのは、都市への到着ではない。ボロボロの車とギリギリのガス代を持って「路上(ロード)」にいることだった。
ありきたりな表現を使えば、どこでもない場所にいたかったのだろうか。まあ、その気持ちもわからないわけではない。ずっと同じ場所にいることは苦痛だ。その場所やそこにいる人々や自分が、溜池の水のように腐っていくような感覚。徐々に老いて、死んでいく感覚。同じ場所に居続けるとそういった時間の流れに飲み込まれる。その重力から逆らってみたいと思うのは、わりと普通のことだ。ケルアックたちが何を考えていたかはわからない。彼が書くのは、旅の情景とアメリカの景色と、酒とジャズと女と、苛立ち、それから焦りだ。なぜ彼らを旅に駆り立てるのかは説明されていない。だが、小説なんてそういうものだ。
小説に何かを説明してもらおうと思う方が間違っている。たぶん、高校生の頃の私はそれがわからなかった。酒も女もよくわかってない。いまになって、ようやくこの小説の読み方がわかったのだろう。書かれていること、人物、描写、文体。ただそれを読んでいればいい。そういう奴らがいたのだた、そういう言葉の使い方があったのだ、と思いながら。解釈しようとすると、途端に「路上(ロード)」は遠くなる。
時間も距離も高校生の自分から遠く離れた自分だから、そのことがわかる気がした。
地元の飲み会に合流。寿司を売りにした居酒屋らしいのだが、入店した時からすでにシャリがなくなっていた。だから、寿司はない。哲学的な問題だろうか。
地元のホーミーたちとの飲み会。これも3年ぶりくらいだろうか。何を喋ったかはほとんど覚えていない。2軒目だったからだ。魚を食っていたような気がする。そのまま、そこで年明けを迎える。気力もやる気もない年明けだ。近所の神社に初詣に行くが、人の多さと寒さで、すぐに蕎麦屋に入る。
儀式やしきたりなどもはや関係ない。そこに、地元の「路上」に集まっていることが重要なのだ。路上だと寒いので、店の中にいるが。
わたしは肉そばを頼む。べらぼうに美味かった。酒ばかり飲んでいたからかもしれない。10年以上、通っているのに店のおばちゃんと初めて絡んだ。失われた時間を取り戻すつもりがあったわけではない。なんとなくだ。
帰り道のコンビニでホーミーたちにアイスクリームを奢る。会計はちょうど1000円だった。何かいいことがあるかもしれない。
店を出たら高校の同級生だという女性と遭遇するが、ホーミーのほとんどがピンと来ていなかった。たぶん、ヤンキーぽかったあの女の子じゃね? というぼやっとした結論を残して、コンビニを後にする。
帰り道はやたら遠回りして、国の文化財だとかいうでっかい古墳の側を通ってかえる。我が町はでっかい墓ぐらいしか誇れるものがない。
ホーミーたちとも別れて、ひとりで地元を歩く。東京より暗い。ひとりで久しぶりに地元を歩いてくるとこみ上げてくるものがある。何がこみ上げてくるのかと思ったら、さっき食った蕎麦だった。排水路に吐いた。全部吐いた。年越し蕎麦は長寿だったり、家族との縁が続くように、願かけして食べるものだが、全部吐いたらどうなるんだろうか。やっぱり無しってことになるのかな。まあ、所詮、作り話だ。気にすることはない。蕎麦もオン・ザ・ロードに帰りたかったのだ。
元旦は、我が家の人間が実家に集まって、新年会が開かれる。昼から酒を呑む。これも数年ぶりに開かれた。
しかし、このスケジュールだと、大阪に帰ってきてから、起きてる間はほとんど飲んでいることになる。さすがに酒に口をつけてもまったく美味くない。まだ体が拒否してくれている。生きろとわたしに言っているのだろう。しばらくしたら普通に飲めるようになっていたので、建前だけのことばだったのかもしれない。
新年会も終わり、ようやく帰省という名の馬鹿騒ぎも終わりが見えた。最近、帰省すると体調を崩すことが多い。理由は明らかだ。濃密すぎるんだ。限界間近の体を休めるために、震えながら眠った。冬の木造建築は寒過ぎる。
2日は東京へ戻る日だ。早めに出て、星野グループが西成に建てたホテルと公園を観に行こうと思ったのだ。でも、途中で面倒になってやめた。西成に喜んで行く義理もない。昔は安い映画館があったので観に行った。いまもあるのかもしれない。あの街にはほとんどのものがある。酒と女と貧困と品位と。などなど。なんでもあるが、全部ガラクタか偽物だ。素敵な街。最近は観光地になっている。わたしの知っている街とは違うのかも。長い間、行っていないのでわからない。興味もない。
新大阪で、自分へのお土産として「とん蝶」というおこわを買う。賞味期限が当日なので、自分へのお土産にしかならないのだ。あとはお弁当として、塩握りと鮭が入った鮭弁当を購入した。酒は買わなかった。行きも帰りも酒を買わなかったのは、わたしの中では異常事態といえる。それにしても米が多い。バランスを全然考えていなかった。
車中で鮭弁当。東京に帰って、家でとん蝶を食べた。帰宅して思ったのは、もう大阪が遠い場所になっていたことだ。「路上」であり、ただ立ち寄った場所だった。すこし留まり、馬鹿騒ぎをして立ち去る。叔母のいない家に私は帰る。叔母どころか誰もいない。
だから、わたしはいつでも路上に戻ることができる。
居心地がいいから、いまはここにいる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
