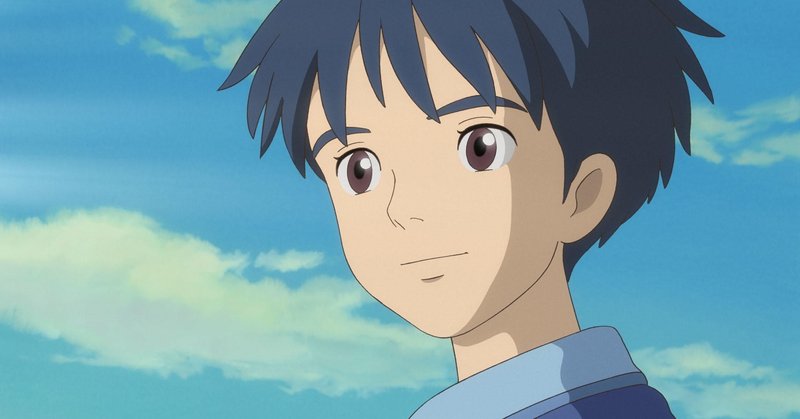
目標に具体性を与える上で大事なこと
前回以下のnoteで紹介したように、リーダーが部下の目標達成力を高めるための武器としてもっておくべきエッセンスを考えてみます。
今回は「やり抜く人の9つの習慣 コロンビア大学の成功の科学」の「第1章 目標に具体性を与える」というテーマを取り上げます。
目標は具体的にすべきなのは間違いない
「目標は具体的にすべきである」ーこれは目標を語るとき、あらゆる場面で言い尽くされている教訓です。良い目標の5つの条件として有名な「SMART」でも「具体的であること」はその筆頭に挙げられています。
例えば「やり抜く人の9つの習慣 コロンビア大学の成功の科学」の例を借りるとこんな感じです。
「もっと睡眠時間をとるようにする」ではなく、「平日の夜は夜10時までにベッドで横になる」
「母親との関係をよくする」ではなく、「母と週に2回以上、ゆっくり話す時間を取る」
例を見れば言いたいことは伝わると思いますし、「目標は具体化すべし」ということに異を唱える人は誰もいないと思います。ただこの目標の具体化はこれだけで十分なのでしょうか?
「目標」と併せて具体化すべきは「阻害要因」
先の「やりぬく人の9つの習慣」では、「メンタル・コントラスト」という心の作業を紹介しています。
1 目標を達成し、成功したときの「感情」をしっかりと味わう。
2 心の中で、そのときに起きていることを明瞭にイメージする。
・周囲の様子はどうなっているでしょうか?
・どんな声が聞こえてくるでしょうか?
3 そこに至るまでの、障害を考える。
引用:ハイディ・グラント・ハルバーソン著「やり抜く人の9つの習慣 コロンビア大学の成功の科学」
「メンタル・コントラスト」とは、目標に対する心象解像度を高めることで目標への意識を高め、行動を起こしやすくするという効果で、先の書籍でも心理学的にその効果が確認されているということでした。
この「メンタル・コントラスト」ですが、私は業務における目標達成力に関して指導する場合は特に「障害を考える」というプロセスが大切だと考えています。(心の機微に触れることも大切ではありますが、実際の仕事の場面ではやりたいかやりたくないかという話を超えた次元で「やらなければならない」ことを指導する場面が多いと思います。)
言い換えると、「目標」と同じぐらい具体的にすべきなのは「目標達成への阻害要因」だとも思うのです。
目標と阻害要因、この2つはセットで具体的化しないと片手落ちになります。ゴールが具体的なだけでも不安はぬぐえないし、リスクが具体的なだけでも前向きさを維持できません。
平日の夜10時にベッドにはいるためには、やるべきことがちゃんと終わっていないと不安ややり残した感で眠れない人は多いはずです。毎日夜10時に寝るというのは、毎日のタスク管理ができないと維持できない可能性は高いはずなのです。だから就寝時間の目標達成には、毎朝一日の作業予定を埋めることが必要になる可能性も高いわけです。
具体的な部下への指導方法
ですので、適切な目標を設定できない/なかなか目標達成プロセスが回せない部下を指導する場合は、
・達成すべき目標を具体的に説明すると?
・その状態を現実にするために最も排除すべき阻害要因は何か?
この2つの質問を適切に投げかけて、達成したい状態とそこへの阻害要因を本人にできるだけリアルにイメージさせると同時に、計画が理想論になりすぎていないかをチェックしてあげる必要があるのです。
プロジェクトマネジメント的に言えば、プロジェクト計画とリスク管理の両輪と言い換えられるでしょう。達成したい状態と阻害要因は必ずセットで具体化しましょう。
あわせて読みたい
お薦め書籍
部下の目標達成力を高めるための武器を一つでも多く手にしておきたいというリーダーに、もちろん自身のそれを更に高めたいという方にもうってつけの本です。何といっても簡潔で読みやすいのがお勧めです。
「#毎日リーダーシップ」とは?
みんながリーダーシップの本質を知り、何らかの領域でリーダーシップを発揮できるようになれたら最高だなと思い、日々学んだり考えたことをこのハッシュタグ「#毎日リーダーシップ」でつぶやいています。良ければフォローしてみてくださいね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
