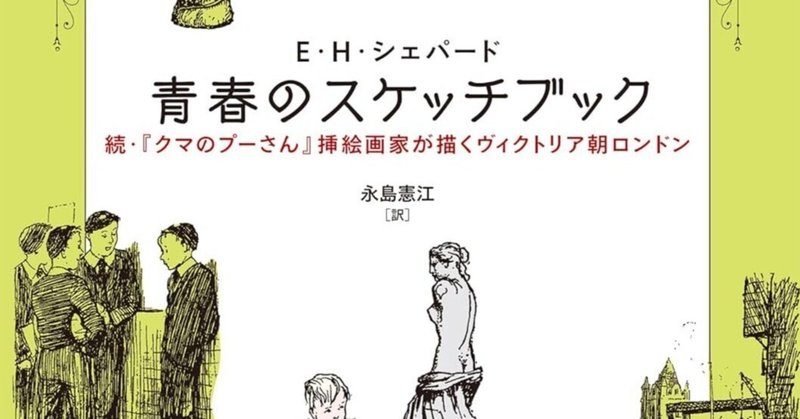
俣野麻子評 E・H・シェパード『青春のスケッチブック――続・「クマのプーさん」挿絵画家が描くヴィクトリア朝ロンドン』(永島憲江訳、国書刊行会)
評者◆俣野麻子
挿絵画家が描いた自伝の続編――自らの青春とヴィクトリア時代のイギリスを写し出す
青春のスケッチブック――続・『クマのプーさん』挿絵画家が描くヴィクトリア朝ロンドン
E・H・シェパード 著、永島憲江 訳
国書刊行会
No.3618 ・ 2023年12月09日
■「クマのプーさん」は日本でも長年愛されているキャラクターだが、本書はそんなプーさんの生みの親である挿絵画家、E・H・シェパードの自伝エッセイ第二弾だ。一作目『思い出のスケッチブック』では、七歳から八歳にかけての少年シェパードの思い出が描かれている。それに続く本作は、著者が十歳のころから始まり、二十代半ばで結婚するまでの青春の日々が綴られている。一作目から読み進めるのが順当な読み方と言えるのかもしれないが、本作からでも問題なく楽しめる。
本書の醍醐味は何と言っても、著書が描いた豊富な挿絵だ。挿絵のおかげで、文章だけでは想像しがたいヴィクトリア時代のロンドンでの生活風景が浮かび上がり、登場人物たちは目の前で動き出す。本書の訳者も「挿絵を手がかりにすることで、訳していて疑問に思ったところを何度も助けてもらいました」(二九四ページ)と訳者あとがきで記している。イラスト一二〇点の中には、画家になろうと決めていた十五歳のときに宿題として描いたスケッチなども含まれている。これだけでも、シェパードには当時から画家になる素質があったことが見てとれる。
画家として大成したのは、本人の才能や努力によるところが大きいのだろうが、本書を読むと、絵描きの道を歩むことが促されるような環境の下で育ったのだとわかる。建築家である父も絵をたしなんでいて、息子の夢を喜び、アトリエで絵の練習ができるようにしたり、美術学校に通わせたりした。一年間病の床についた後、著者が十歳のときに亡くなった母については、次のように書いている。
「母さんは、ぼくが絵を描くことを、どんなときでも応援してくれていた。母さんには絵の才能はほとんどなかったものの、絵の具の使い方を教えてくれたし、ふたりでぼくが大人になって画家になったときの計画をたてることもあった。父さんより、母さんのほうが、絵を描くことを応援してくれていた。母さんが死んだあと、ぼくはふたりの時間をたまらなく懐かしく思い、母さんが信じてくれていたぼくの絵の才能を、証明してみせようと心に誓った」(一三ページ)。
末っ子の著者が母と過ごした、短いながらも楽しかった時間が心の支えになったのだな、と読む者の胸に響く。ちなみに、母方の祖父は水彩画家のウィリアム・リーだ。
本書は、十九世紀末から二十世紀初めのイギリスの歴史の一端を記録した資料としても価値があると言える。たとえば第九章では、一八九七年にヴィクトリア女王の在位六十周年記念式典に沸くロンドンの様子が描かれている。シェパード家はパレードが見たくて、それが通過する通り沿いにある部屋を借りた。ジュビリーの当日は朝の五時に起き、「興奮しすぎて朝ごはんはあまり食べられない」(一三八ページ)ほどの熱狂ぶりだ。
一八九九年にボーア戦争が始まり、イギリス軍の形勢は悪化していき、「つらく悲しい気分が国じゅうにただよ」ったと記されている。世相を反映してか軍人にあこがれていた著者も、「この戦争に熱い思いは抱けず、ヨーマン帝国義勇騎兵連隊に志願しようなんて、これっぽっちも思わなかった」(一九九~二〇〇ページ)。
本書に通底しているのは、著者と彼をとりまく人びととの心温まる交流だ。三人兄弟は仲が良く、おばさんたちは母を亡くした彼らにやさしい。パブリック・スクールやロイヤル・アカデミー・スクールで過ごした友人たちとの日々。つつましくも幸せなパイとの結婚。
読み終えてしばらく余韻に浸っていたとき、英語版の『クマのプーさん』を持っていたことをふと思い出した。本棚を見ると、たしかにあった。東京ディズニーランドの値札シールが貼られたままのWinnie‐the‐Pooh and Some Bees。高校の卒業旅行でディズニーランドへ行ったときに買ったのだった。幾度かの引っ越しを経ても手放さずにきたけれど、実はちゃんと読んだ覚えがない。年を重ねた今、E・H・シェパードの挿絵を味わいながら読むときが来たようだ。
(翻訳者/通訳ガイド/大学英語講師)
「図書新聞」No.3618・ 2023年12月09日(土)に掲載。http://www.toshoshimbun.com/books_newspaper/index.php
「図書新聞」編集部の許可を得て、投稿します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
