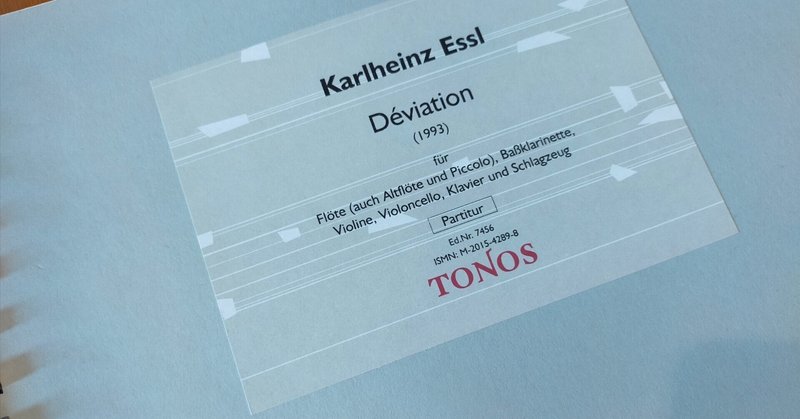
楽譜のお勉強【88】カールハインツ・エスル『デヴィアシオン』
カールハインツ・エスル(Karlheinz Esel, b.1960)は現代オーストリアを代表する作曲家の一人です。電子音楽を中心に発表しながら、器楽作品も多く書いてきました。ウィーン国立音楽大学の作曲科教授として後進の指導にも当たっています。有名な美術蒐集家である父も同姓同名であるため、カールハインツ・エスル・ジュニアやゾーン(息子)などとも呼ばれます。ヨーロッパで時々見られる、完全に同じ名前を子どもに付けるシステムは日本人の感覚からしたらよく分かりません。
エスルの名をとりわけ有名にしたのは、1992年から2010年まで続いた『レキシコン・ソナタ』(»Lexikon-Sonate«, unendliche Echtzeitkomposition für computergesteuertes Klavier)というプロジェクト・作品です。コンピューターで制御されたピアノで延々と音楽が自動生成される作品でした。楽譜とはほとんど関係がないので、この作品について「楽譜のお勉強」では取り上げませんが、彼の代表作であるこちらも作曲者自身のライブ・パフォーマンスの様子を動画を上げておきます。ピアノに接続されたコンピューターに指示を入力していき、ピアノが自動で音楽を奏でていく様子が見られます。
(レキシコン・ソナタ)
本日読むのは、エスルの初期の器楽アンサンブル曲の代表作『デヴィアシオン』(»Déviation« für Flöte/Altflöte/Piccolo, Bassklarinette, Violine, Violoncello, Klavier und Schlagzeug, 1993)です。「デヴィアシオン」とは、フランス語で「迂回」とか「逸脱」とかそのような意味です。フルート(アルトフルートとピッコロ持ち替え)、バスクラリネット、ヴァイオリン、チェロ、ピアノ、打楽器のための、演奏時間14分ほどの作品です。六重奏は、2つの三重奏のグループに分かれています。客席から見て舞台の左側にはバスクラリネット、ヴァイオリン、ピアノが座し、右側にはフルート、チェロ、打楽器がいます。打楽器は全て調律された楽器のみを用います。マリンバ、ヴィブラフォン、チューブラーベル、アンティーク・シンバルです。
曲の開始部分、フルートとバスクラリネットが同じ音域、基準ピッチであるラの周りを彷徨く蛇行ラインを描きます。冒頭からのセクションはミクロポリフォニー様式によるポリリズムで打点の不明瞭なうねりが続きます。特に最初にデュオを始めるフルートとバスクラリネットのリズム書法は、およそ減速をしてから加速に向かうフルートと、加速から開始して減速に向かうバスクラリネットで計画的に左舷グループと右舷グループの密度の交替が仕組まれています。具体的には、フルートが七連符、六、五、六、五、四(減速)、五、六、五、六、七(加速)と遷移していくのに対し、バスクラリネットは四、五、六、五、六、七(加速)、六、五、四となっています。音程は、ほとんどどの瞬間も微分音程もしくは短2度でぶつかっており、不協和に揺れ動く太い一本の線のような印象です。このリズム書法の生み出す密度の交替はライブ演奏において、より強く独特のステレオ効果を生むでしょう。単純な加速、減速ではなく、分割の揺り戻しを含むことが味わいを一層豊かにしています。ただ、減速に向かうバスクラリネットは分割の揺り戻し(一旦加速しなおすこと)はなく、持続時間がずれています。これは他の楽器群の書法からも明らかなのですが、設計される各ミクロポリフォニーのラインは大きなポリフォニーの視点を持っており、左舷と右舷で完全に鏡のように対応している関係ではないということです。導入を二つの楽器が示した後は、各楽器がそれぞれのタイミングで参入してくることになります。2小節目冒頭でチェロ、2小節目半ばでヴァイオリン、3小節目冒頭でピアノ(フラジオレット)、後半で打楽器が入ってきます。音高に関しては全て中心音Aもしくはその周縁から開始します。
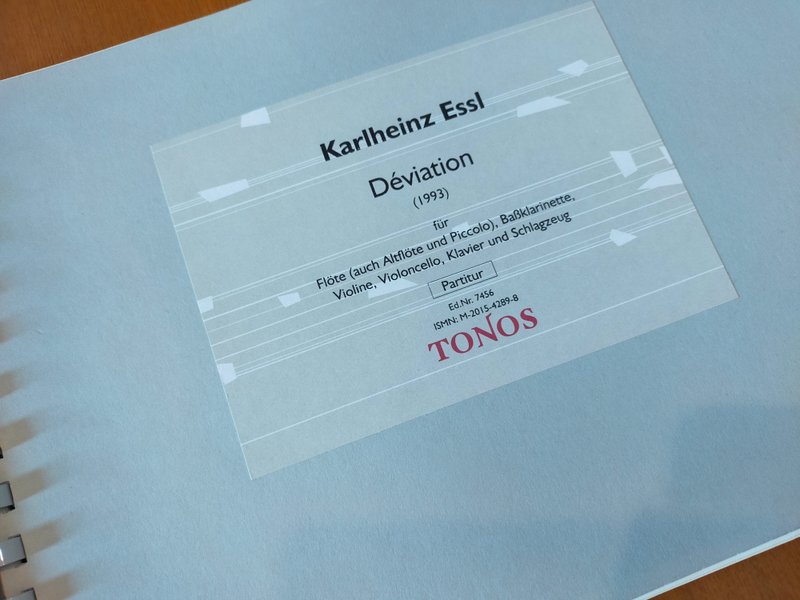
楽器の書法にも特筆すべき点があります。ヴァイオリンは開放弦のA線とD線をコンビネーションで弾き、G線をビスビリャンド奏法でBb(D線)とG#(G線)の音を交替で弾くのですが、D線を弾く際にA線も噛ませるおかげで中心音の存在を際立たせながら、その周りの音と作り出す強い不協和を味わうことができます。BbとG#はそれぞれ開始直後からグリッサンドしてA音を目指します。ヴァイオリンは続くフレーズではAbからGとBbへのビスビリャンド・グリッサンドを弾きます。中心音Aに近づいて行ったり、離れて行ったりする様子は、「迂回」とか「逸脱」というタイトルにふさわしいように聞こえます。最初に大きく逸脱を始めるのはバスクラリネットです。ミクロポリフォニーの細かい分割リズムを演奏するのは変わりませんが、少しずつ動く音程を大きくしていき、クラリネットのいるグループがまず逸脱に向かいます。ピアノも動きの幅を大きくし、追うようにして反対のグループのフルートが慎重に音域を拡大していきます。
ある程度各楽器の動きが大きくなると最初の休止が訪れます。微分音の使用はやや控えめになり、大きな跳躍音程が聞かれるようになります。うねりの中から時折アクセントによって聞かれていたメロディーラインは、独立して点描的なリズムを描くようになります。線のうねりの上下動が確定してからしばらくすると、その動きはアルペジオに近くなっていきます。アルペジオ様の動きが旋律として割と長い音価において使われる際には気にならないのですが、素早い動きのアルペジオになると、少し音の選別が気になりました。結構な割合で完全4度もしくは完全5度と減5度(増4度)を組み合わせる形が聞かれるのですが、これは現代音楽のクリシェのような響きがしますし、入念に微分音をぶつけ合って響きを設計していた冒頭に比べて一時代前の現代音楽の響きがします。演奏の難易度への配慮なのか、大きく音が動く時には微分音程よりもジェスチャー自体に耳が行くと考えたのか定かではありませんが、結局響きというものは、鳴っている音全体の関わりの中で決定されますから、あまりシンプルな響きに擦り替えるのは曲の意図と比べてどうなのかなと思いました。
ただ、そのような時間が長く続くわけではありません。次第に速い音型よりも遅い音型の方が支配的になっていく中で、同音を連打したり、微分音的に少しずつ音程を変えて変容する同音連打のようなパルス音型が現れ、それが中間部での曲の主体になります。音域は上下に大きく開いており、それぞれの音域で個別の微分音のズレが生じており、非常に居心地の悪い擬似コラールが聞かれます。パルス自体もほとんどシンクロしないのに、セクションがほとんど終わる第90小節に至って一瞬だけ単純な4分音符連打が現れてまたズレていくので、なかなか粋な聞き応えがありました。
曲の後半が始まると、ほとんどパルスも消失して、ロングトーン中心の短いセクションがあります。時折、以前聞いたようなアルペジオや素早いウロウロ・ラインが出てくるのですが、なかなか像を結びません。また、パルスの同音連打が気まぐれに挿入されたりして、少しずつ音楽が形を見せます。各楽器の響きも様々に工夫されていて、不思議な空間を演出するのに適しています。一つ具体例を挙げると、素早いパッセージをヴィブラフォンが演奏した後、そのそれぞれの音をパッセージの最後の音から逆順でゆっくりと手でミュートをかけて消していったりします。なかなかに神経質な、そして行き届いたオーケストレーションです。
後半で示されるマテリアルはほとんど全て前半で出尽くしていると言っても過言ではありませんが、極めて断片的に示される状況から少しずつ分量が増えていきます。また、前半で聞かれた主要な素材、うろつく線(細かい分割もしくはロングトーン)、アルペジオ、様々な音価のパルス、が立体的に対位法的に配置されるようになっていきます。この時点で音楽は高度に層状で、前半の音楽とは相当様子が違うのですが、そこで用いられているマテリアルは、前半で聞いた感じではそれぞれが「変容」によって導き出されたものでした。つまり冒頭の音楽に楽曲全体の萌芽があったはずなのですが、耳をコンセプチュアルに導いていった結果、後半で示される響きの対位法的世界はとても新鮮に聞こえます。層が十分に充実したら、また時間をかけて減衰へと向かっていき、曲は終わります。
この曲を書いたのは33歳という若さの作曲家で、設計の緻密さに驚きました。読みにくい記譜も演奏家への熾烈な要求もなく、技術に溺れているという感じもありません。西洋音楽の作曲家には自らが準備した作曲素材をものすごく大事に使う作曲家が多いイメージがあります。ただ、それがあまりにも直接的だと、ちょっと物足りなく感じることもあるのですが、入念に作曲し尽くされていると、そもそも楽譜を読むまで根を同じくしている素材だと気付けないことも多いのです。これは現代音楽の作曲家に限ったことではありません。一つの音楽素材が多面的な表情を持つことを確信している人ができることなのでしょう。このような技術の高みは、憧れる面もありますが、その考え方はあまりにも西洋的とも感じるので、目指そうとは思わないようになりました。しかし、エスルの『デヴィアシオン』に見られるような作曲技術をたまに読むことはとても良い刺激になります。作曲意欲もそそられる読譜となりました。
*「楽譜のお勉強」シリーズ記事では、著作権保護期間中の作品の楽譜の画像を載せていません。ご了承ください。
作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
