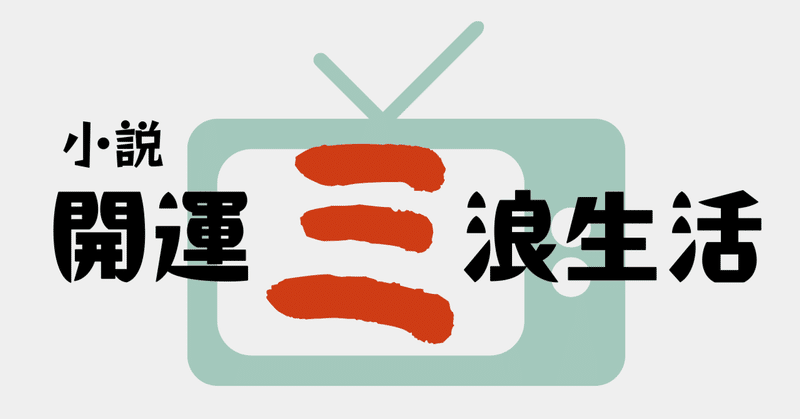
小説 開運三浪生活 21/88「燃え尽き小休止」
期待を裏切らずH高理数科に進学した文生に対し、村の人間たちは相変わらず好奇の目を向けていた。
「フミオちゃん、理数科でも一番なのけ?」
言外に挫折を願う響きを持たせ、周囲の人間は母親を勘ぐった。その重圧に耐えきれなくなると、母親の感情の矛先は文生へと向いた。
「フミオ、もう、伸びないんでしょ……」
一学期の成績を見てあからさまにがっかりした母親は、我が子が努力しているのにかかわらず伸び悩んでいるものと思い込んだ。才能ある人は努力しなくても伸びる、才能がない人はいくら努力しても伸びない――そういう価値観の人だけに、才能があるはずの我が子に裏切られた思いだった。
当の文生は、高校に入りほとんど勉強をしなくなっていた。気だけは急いて、放課後に教室に居残り参考書を開いてはみるものの、あまりにちんぷんかんぶんなのでまったく進まなかった。そのうち居残り勉強もやめ、放課後は早々に帰宅して読書と音楽鑑賞で時間をつぶした。さすがに試験前はそれなりに机に向かってみたものの、赤点回避が目標という、およそ理数科生としては志の低すぎる努力だった。そのくせ、元・優等生としてのプライドは完全には死んでいなかった。たびたび亡霊のようによみがえっては、勇ましい寝言を心の中でぬかすのだった。
――俺の実力はこんなもんじゃねえ!
勇んで買い込んだ青チャートが、机の隅に虚しく置かれていた。
秋が深まる一年生の二学期後半、下校後の文生がバスに乗っていると、少し錆がありながら嬉々とした聞き覚えのある声にいきなり話しかけられた。
「おめえ、理数科行って落ちぶれたらしいな」
ブレザーを不良風に着崩した、タツヒコだった。小中と何かにつけて文生を非難してきたガキ大将である。彼が通う工業高校は文生の高校と同じバス路線にあった。あからさまにニヤニヤしながら文生の反応を伺っている。近くの席に座る高校生たちがこちらを見るので、文生は思わず赤面した。
「……おい、無視すんじゃねえよ」
「まあ、ね」
文生は肯定で余裕を見せた。
「こいつ、認めたわ! もうおめえ、顔だけ優等生だな」
高校に入ってさらに視力が落ち、文生の瓶底眼鏡はより厚くなっていた。なにしろ的確な指摘だけに、文生は瞬間的にムッとした。文生としても、ここは一言応戦しておかなくてはいけない。周囲の目がある。
「まあ、最終的に行きたい大学に行けてれば、それでいいんじゃね」
「――ふうん。長い目で見てろってことけ。期待してるわ」
声の主は鼻で嗤った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
