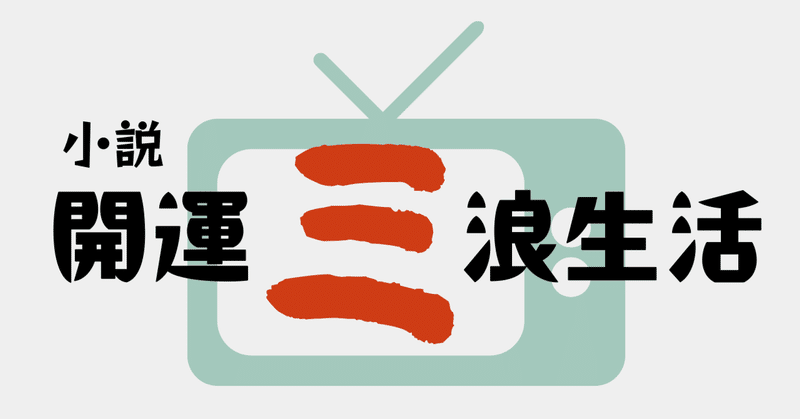
小説 開運三浪生活 20/88「高校デビュー」
結果として、文生は念願のH高理数科に受かった。合格発表で自分の受験番号を見つけた文生に、合格を勝ち取ったという感覚はなかった。安堵だけだった。下降気味だった学力が、合格ラインまで持ちこたえてくれてよかった。親の期待に応えることができた。村の世間からの期待にも応えることができた。文生は心底ほっとしていた。
――これでやっと、解放される……。
静かな城下町の家並みの端に、その男子校はあった。文生は毎朝バスで三十分かけて通学した。それぞれの中学でトップ争いをしてきたクラスメイトたちは、どの顔も賢く見えた。理数科は他のクラスよりも英語と数学の授業が多く、教科書の進度が速い。これから始まるであろう氷のように厳しい勉学の日々に、文生はさすがに身の引き締まる思いがした。
その一方で、合格発表した日から続く安堵も相当なものだった。中学の定期テストでは、順位を落とせばここぞとばかりにバッシングをしてくるに違いない周囲からの視線を跳ね返そうと、ほとんど根性だけで乗り切ってこれた。でも今は、優等生が集うクラスに自分はいる。
――もう、俺が頑張って目立たなくてもいいや。
幸か不幸か、この年文生の中学から理数科に入ったのは一人だけだった。中学時代までの自分を知る者はクラスにいない。完全に肩の荷が下りた。そういう気持ちだった。
テレビは相変わらず観ていなかった。観るのをやめてからすでに九年目に入っていた。もはや観ないことが習慣になっていたので、中学の三年間でもわざわざ観たいと思わなかった。ただ、高校ではクラスメイトに知られたくなかった。もう好奇の視線を浴びるのはごめんだった。
理数科の授業は前評判どおりの厳しさだった。相当な量の予習が求められ、宿題も多かった。これからが本当の頑張りどころだというのに、優等生としての文生のプライドは高校受験でまったく使い果たされていた。ショックだったのは、得意だった数学が急に解らなくなったことだった。数学Ⅰの最初の二次関数でいきなりつまずいた。数式を曲線で表すという文化を、数学が得意だったはずの文生の頭はなかなか受けつけなかった。教科書と参考書を何度にらんでも一向に理解できず、何が解らないのかすら判らなかった。あまりに漠としていて教師に質問に行く気も起こらず、のっけから授業についていけなくなった。
五月の末に行われた最初の中間テストで、十九点という見たことのない点数を文生は叩き出した。解けていないという自覚はあったものの、実際の点数を目にして、頭を鈍器で殴られた思いがした。この瞬間、文生は数学アレルギーになった。中一で最大値を迎えゆるやかに下降していった文生の学力は、高三の五月を変曲点にして最小値へと向かっていったのである。
ちなみに、期末テストは十一点だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
