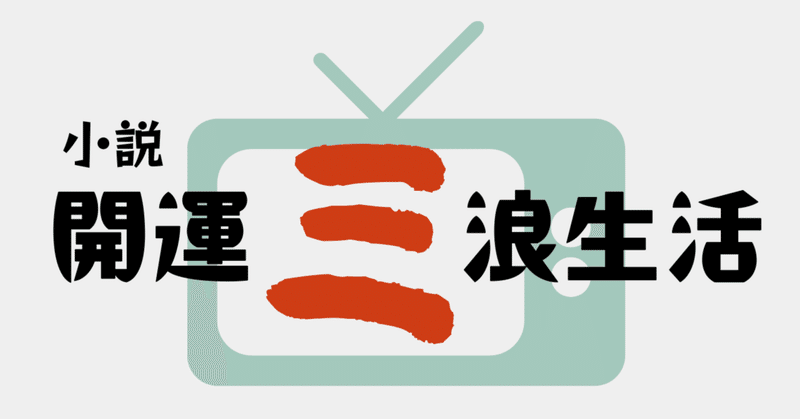
小説 開運三浪生活 15/88「喜ぶ人、悲しむ人」
苦手な体育の授業になった途端、文生はいつも劣等生になった。タツヒコの子分たちも非難に加勢した。なかでもサッカーの時間が拷問だった。
「どこ蹴ってんだ下手くそ!」
「フミオのせいで負けた!」
「勉強ばっかしてっからそんなよわっちいキックしかでぎねえんだ!」
喧嘩したところで勝てもしなかった。文生はその都度黙り、無表情をつくってやり過ごした。
――こんなの、どうせ過去になるんだ。今だけだ。
努めて取り繕った鉄面皮が、かえって周囲からの反感を煽っていた。
依然として特等席に居座り続ける文生に対して、タツヒコだけでなくほかのクラスメイトからも非難が飛ぶようになった。ある日の帰りの会で、文生はついに屈した。後方の席に移動したのである。
翌日はさんざんだった。担任が話している間はまだ授業についていけたが、いかんせん板書が読めない。算数の授業で五問だけの豆テストがあった。黒板に書かれた質問を解き、隣同士で採点しあう。文生の右隣に座った男子から、驚きとも喜びともつかない声が上がった。
「うわ! フミオ0点だ!」
教室は騒然とした。喜んだのはタツヒコである。
「ざまみろ。これで化けの皮はがれたわ!」
「……」
「あいつから勉強取ったら何もねえんじゃね?」
子分たちがどよめいた。文生は無言と無表情を決め込んだ。恥ずかしさと悔しさで、どこを正視していいかわからなかった。
「眼鏡、かけたい」
その日、潮時を悟った文生がついに母親に告げると、あからさまに表情を曇らせた。
「ああ……そうけ……」
想像したとおりの反応に、文生は半ばげんなりした。
「言われるわ、ヒトから。”フミオ君、勉強させすぎで目ぇ悪くしたんだっぱい?“って」
悲劇のヒロインよろしく、母親は悲しげに眉をひそめ深いため息までついている。
「もう、黒板の字ぃ、見えない」
文生は懸命に粘った。ここで抵抗しなければ困るのは自分である。
「だったら、前に座らしてもらえばいいばい。先生に電話して頼んでみっから」
「いや、一番前の席でも全然見えない」
とっさに嘘が出た。親から担任への直談判だけは避けねばならぬ。これ以上、クラスでの孤立に耐えられる強心臓を文生は持ち合わせていなかった。
「…………しょうがない。眼科さ行ってきな」
翌週、文生は牛乳瓶の底のように分厚い眼鏡をかけて登校した。急にひらけた視界は思っていたよりも暗くて狭く、しかしレンズ越しに見える一つひとつの景色には確かな感触があった。ぼんやりとしか見えていなかった教室の喧騒が、くっきりとした雑然を文生の網膜に映し出していた。長らく遠ざかっていた感触に、自席に腰掛けた文生は静かに感動していた。
「うわ! ガリ勉だ!」
教室に入ってきたタツヒコの声で、文生は感動から覚めてしまった。タツヒコの子分たちが文生を指差し、ゲタゲタと嗤っていた。文生は赤面しながらも努めて無表情を装い、罵声を受け流した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
