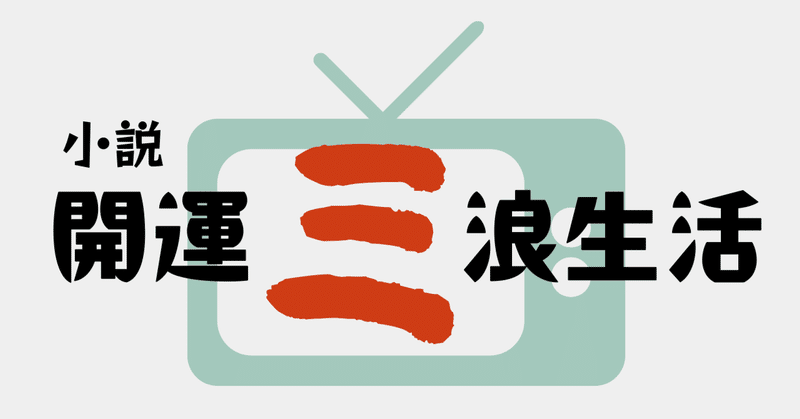
小説 開運三浪生活 11/88「指定席」
勢いとは言え、息子自ら素晴らしい宣言をしてしまったものだから、母親の喜びと期待は大変なものだった。
例えば、文生はテレビゲームをしなかったし、欲しがろうともしなかった。
――うちの文生がゲームなんか、やりたがるわけがない。
そんな暗黙の期待を、母親の言動の端々から文生は感じ取っていた。この前年、文生は突如読書にハマり、なぜか学校の勉強にも積極的に取り組むようになっていた。そこに本人の口から飛び出したテレビ断絶宣言である。母親の期待は確信へと変わり、まだ十歳にも満たない我が子を「この子は将来きっと大物になる」と決めつけた。文生とて、周りの同年代の男子全員がやっているゲームに興味はあった。が、それを口にしようものなら母親があからさまにがっかりする姿が想像できて、おくびにも出せずにいた。
それは弟の武登にも飛び火した。こちらはゲーム欲を隠すことなく、ファミコンの購入を何度も母親に訴えたが、その都度「あんたはただでさえ勉強しないから駄目」と突っぱねられた。スポーツなら何をやっても人並み以上にはできてしまうものの、勉学への興味をなかなか示さない武登には、何のプレッシャーもかからなかった。だから、兄の文生に比べればだいぶ伸び伸びと育っていった。
文生の母親はテレビゲームに否定的だっただけでなく、電子機器という存在自体が性に合わないようだった。だから田崎家には電子レンジもエアコンもなかったし、世の中では生きた化石扱いされていた黒電が、当たり前に現役を続行していた。
テレビと絶縁せざるをえなくなった文生だったが、最初の二週間はさすがにきつかった。テレビに背を向けて座る文生をしり目に、両親と武登はそれぞれが好きなテレビを観ていた。いやでも音声が耳に入ってくると、文生はいてもたってもいられなくなった。そのたびに母親のなじる声が脳裏によみがえり、振り返るのをぐっとこらえた。
三週間、四週間と過ごしていくうちに、家族で自分だけテレビを観ていないという異常な状況が、文生のなかで爽やかな快感に変わりつつあった。最初は修行の感覚だったが、気がつくともはや習慣と化していた。
二ヶ月も経つと、テレビがついていようがいまいが文生はいっさい気にかけなくなった。不思議なもので、テレビゲームへの興味も消えていた。学校でクラスメイトがゲームやアニメの話に興じていても、もうどうでもよくなっていた。休み時間になるとひとりで本を読むくらいしかすることがなくなったが、その状況がかえって文生の意志を強くさせていた。
――俺には関係ねえ。俺は俺だ。
武登も、そんな風変わりな兄がだんだんと気にならなくなっていた。まるでそこに文生がいないかのようにテレビを愉しんだ。
「にいちゃん、テレビ見えない」
「……ああ」
たまに兄の顔がテレビの画面をふさぐ時だけ、苦情を言う。兄弟の会話は徐々に減っていった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
