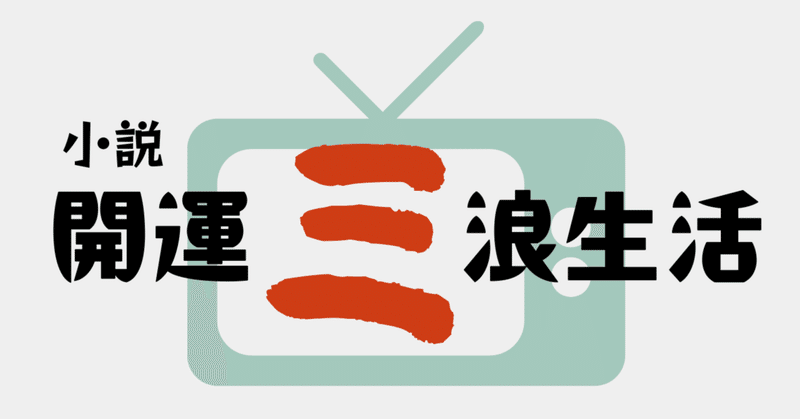
小説 開運三浪生活 12/88「こんにゃく男児」
東北の南端、関東の北隣にあたる農村に、田崎文生は生まれた。村の中央には平地が広がり、南に向かうに連れて緩やかに高度が上がっていく。五、六百メートル級の山々が幾重にも重なり、地図上ではそのずっと先に関東平野が広がっているとのことだった。
扇状地の端部に田崎家はあった。今でこそただの住宅地になってしまったが、文生が幼少の頃は八百屋、肉屋、魚屋、寿司屋、靴屋、おもちゃ屋、そしてスーパーが軒を連ね、村の中心部としての活況を呈していた。北に五分ばかり歩けば家並みは終わり、一面に田んぼが広がっていた。若葉の季節になるとカエルの合唱を聞きながら眠りにつき、夏が近づくと盆踊りの太鼓の練習の音に胸を弾ませた。
旧商店街の小さな家に育った文生は、とにかく運動が苦手だった。なわとびにしても鉄棒にしても、他の子どもたちが難なくこなせることがなかなかできなかった。見た目も色白で線が細く、体幹がしっかりしていなかったのか、いつも身体がふらふらしていたので、幼稚園の担任からは「こんにゃく!」と同級生の面前でといじられ、小学校の体育の授業ではことあるごとに「フミオって、運動シンケイねえよな」とクラスメイトたちから馬鹿にされた。初めは体育以外の科目も芳しくなく、ほどよい明るさも持ち合わせず、学校に行っても楽しみがなかった。
転機は、まだテレビにかじりついていた小学校二年生の夏休みに突然訪れた。
都会から毎年泊まりに来る五つ上のいとこが、野口英世の伝記を文生に貸してくれた。同じ福島県の貧しい家に生まれた主人公が身体のハンデを克服し、やがて世界に飛び出していくというサクセスストーリーに、文生少年はいたく感動した。あたかも自分が物語の主人公になったかのように錯覚し、気が大きくなった。本に没頭している間は誰からも馬鹿にされずに済んだし、なにしろ独りで楽しむことができた。
野口英世をきっかけに、文生の読書欲は泉のように湧き出した。親にせがんで湯川秀樹、織田信長、西郷隆盛、マルコ・ポーロ、リンカーンと次々に伝記を買ってもらい、その都度すぐに読み終え、結局はその伝記シリーズ全五十冊を夏休み中に読破した。大昔の景色や外国の街並みを思い浮かべながら、高級なビスケットを喰むように一ページ一ページじっくり読み進めるのは何より楽しい時間だった。武登が近所の子どもたちと一緒に真っ黒になってミヤマクワガタやアメリカザリガニや白球を追っている時間に、文生はほとんど家から出ず活字を追い続けた。たまには外で遊んで来い、と言う大人はいなかった。父親は仕事と趣味に夢中で教育には無関心だったし、母親などはむしろ誇らしげに我が子を眺めていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
