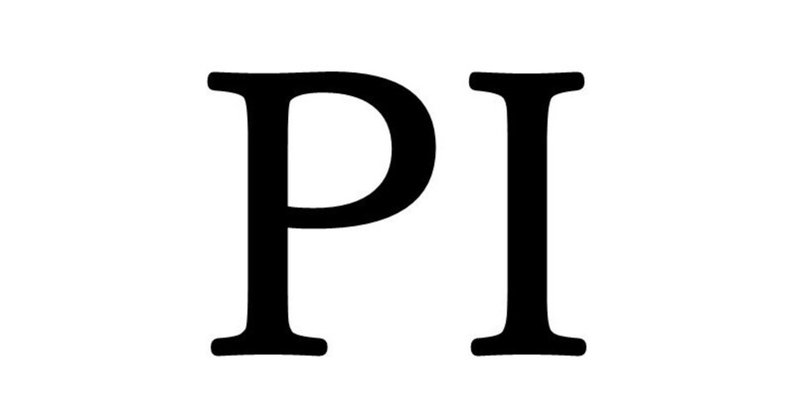
大学パーマネント職の選考の特徴と対策
「大学の先生にどうすればなれますか?」と質問されることがよくある.これは簡単に答えるのは難しいが,「大学教員公募に応募して採用されれば大学の先生になれる.」というのが私の答えかもしれない.この大学の教員公募というのが,企業への新卒採用が一般的な日本の学生にとってはイメージが沸かないために先の質問につながるのかもしれない.私も学生時も企業エンジニアだった際もよく理解していなかった.そこで,ここでは大学教員公募の特殊な状況と,それゆえの対策の方向性について私なりの考察を紹介します.自分なりの対策を考える際の参考となれば幸いです.また,具体的に私がとった対策は「大学パーマネント職を得るためにした12のこと」に12対策にわけて説明してるので,よかったら見てください.
そもそも大学教はどんな働き方?
大学教員(公募)には,大学(私立,国立)の2組織の特性と,2種類(あるいは3種類)の雇用形態で,4種類により差があると分析しています.
これを説明する上でまずは雇用形態から説明したほうが分かりやすいので,雇用形態と大学組織について説明します.
大学教員の雇用形態
・パーマネント
いわゆる終身雇用.任期なしの専任講師,准教授,教授のこと.この教員雇用形式は,大学学部か大学院に雇用されており,学部大学院の授業や運営も担当しながら研究開発も行う.
・任期付き雇用
字のごとく任期が決まっている雇用.任期はその公募により異なり,短いものだと1年,長いもので10年などもあります.いずれにせよ,終身雇用ではなく,次の仕事を見つける必要があります.
・テニュアトラック雇用
任期中に所定の業績を満たせばパーマネント雇用へつなげるという約束付きの任期付き雇用.なぜ,教員雇用形式を3種類と言い切らなかったかというと,このテニュアトラック制度は,(日本の)大学によりその度合いがまちまちで,テニュアトラックといいながら実質任期付きと同様で,その先のポストがない場合や,テニュアトラックといいながらパーマネントへの基準がとても低くほぼパーマネントといえる良心的な場合まで千差万別です.そのため,このテニュアトラックについては,その公募(その大学)ごとによくルールや契約を見て判断するしかないです.
国立と私立の大学教員の違い
・国立大学(講座制)
国立大学の場合は,多くが講座制をとっており,教授が主催する講座に,准教授と助教の枠が紐づいています.講座制の場合は,講座の教授の元で助教や准教授として研究をサポートしながら自分の研究をします.この講座に紐づく准教授と助教は,表面上な任期がないパーマネント職である場合もありますが,教授がいなくなった場合(退職,転職,死去)に,准教授が教授に,助教が准教授にエスカレータで昇給できるとは限らない.そのため,国立大学の准教授や助教の場合,パーマネントといいつつ,大学によっては任期付きともとれる雇用形態となっています.また,教授が教授でいる限りは,その講座の准教授が,その講座の中で教授にはなない場合が多い.別の研究室を准教授として構えてから昇進する必要があります.このあたりの細かなルールは,大学ごとのルールなので,公募の都度調べる必要があると思います.
・私立大学
私立大学の場合は,教授,准教授,専任講師はそれぞれが自分の研究室を構える場合が多い.つまり講座制ではない大学が多い.この場合,学科や学部内の教授の人数に制限はない場合が多く,准教授は要件(年齢や業績)を満たして,教授らの承認を得られれば,基本的に教授に昇進できます.そのため,専任講師や准教授で採用されても,基本的にはパーマネント職として終身雇用されます.
組織,雇用形態ごとの大学教員公募の特性と対策
国立大学(講座制)の助教や准教授の公募
国立かつ講座制の場合,少なくとも上司である教授(と准教授)と交流があるか共通の知り合いの推薦がないと公募時に大きく不利になると予想されます(しました).あるいは,事前にその上司に自分の存在を認知してもらい,交流を深めておく必要があるといえます.
私立大学の准教授,専任講師の公募
1学科8~12名程度のパーマネントの先生がすでに居て,その先生らが審査員です.年齢にもよりますが,年齢が近い先生は,その先30年以上の同僚を選ぶことになります.10名程度という狭い組織の30年間の同僚を選ぶ公募にて,考えることは リスク であると分析します(しました).特に考えるのは,学生や自分達に不利益が発生しないかどうかです.具体的には,同僚として交流が難しくないか,学校の雑務を円滑にこなせそうか,学生とうまく交流できそうか,学生を教育できるような人格か,などです.もちろん研究の将来性も見ているが,それと同等くらいに,私立大学の公募では,このリスクがどれだけ低いかという部分が重要であると分析しています.
国立大学や私立大学の任期付き公募
任期付きの公募は,リスクはそこまで意識していないと考えます.もちろん大学の名前に泥を塗るだろうと明らかに予想できるような人は雇用しないだろう.しかし雇用側も何か問題あればその任期後に雇用を解消できるという安心があるため,「おもしろそうなやつ」「今流行の研究だ!!」「いい研究成果を出している!!」などの部分で選考されると考えられます.
まとめ
以上のように,大学組織や雇用形態で,その対策のベクトルが大きく変わるだろうことは共有できたのではないだろうか? このような簡単な分析の後に私は早くパーマネントとなりたいと考えて,私立大学の准教授になることを目標に具体的な対策を検討しました.実施した対策は「大学パーマネント職を得るためにした12のこと」で12個ほど紹介しています.様々な分野や大学ごとに状況は異なると思います.私の限られた知見の中での意見です.何か参考となれば幸いです.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
