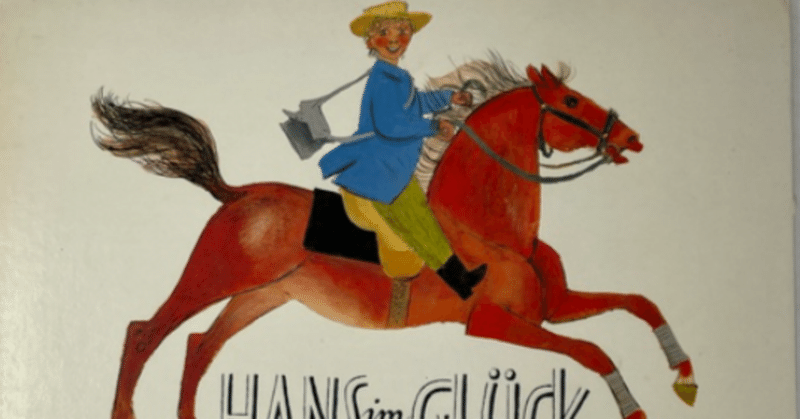
生きるとは、いかに損をしていくか
突然だが、グリム童話の「幸せハンス」という絵本をご存じだろうか。先日、子どもに読んだ本で思いがけず良かったので、少しあらすじを紹介する。
主人公のハンスは7年間仕えた主人から大きな金塊をもらい、暇をもらうと母親の待つ故郷へ向けて出発した。途中、ハンスは馬に乗った人を見かけた。金塊が重く、馬に乗る方が楽しそうなので、金と馬を交換した。次にハンスは牛を引く村人に会い、牛乳やバターがとれる牛のほうが馬よりいいと馬と牛を交換した。
ハンスは暑くてのどが乾き、牛から乳を搾ろうとしたが、乳は一滴も出なかった。そこへ子豚を連れた肉屋がやってきた。ハンスは「牛より豚肉のほうがソーセージにもなる」と言って、牛と子豚を交換した。
次にハンスは、がちょうを抱えた若者と会った。若者は「その豚は村長さんのところから盗まれたものかもしれない。村人たちが見たら、あなたは捕まるよ」と言ったのでハンスは若者に助けを求め、子豚とがちょうを交換した。
ハンスは最後の村までやってきた。そこにはさみの研ぎ屋がいて「砥石をもって研ぎ屋になれば、お金に困ることはないよ」と言ったので、ハンスはがちょうと引きかえに研石を手に入れた。しばらく歩いて、ハンスが井戸で水を飲もうとしたとき、砥石を井戸の中に落としてしまう。ハンスは石が井戸の底に沈んでいくのを見て、嬉しくなった。重い石をうまく放り出すことができた。「おれほど幸せな人間はほかにいないぞ!」と叫びながら、身も心も軽くなって、うきうきと母親のもとへ帰って行った。
と、こんなお話だが、皆さんはどう思うだろうか。愚かなハンスがただ損をし続けた物語と思うだろうか。私のこの物語への解釈は後ほど述べることにする。
さて、少なからず、だれもが「どう生きるべきか?」と考えるときがあるだろう。だが、大抵は「何をするか?」「より良い生活を、地位を、給料を、評価を、パートナーを、名声を手に入れるにはどうすればよいか?」という次元の話ではなかろうか?
私にしたって、そうだ。中学生から今まで、何度も「どう生きるべきか」考えてきた。だがそれは、学校の成績を上げる方法、いい大学に入る方法、いい会社に入る方法、いい人と結婚する方法、お金を貯める方法、出世する方法、昔は歴史に残る人物になる方法なんてことだった。
これらの考えは一見異なるように見えて、みんな「いかに得するか?」という視点で考えているという意味で全て同じ種類のものだ。何もそのことが悪いと言っているわけではない。得られるものは得たほうがいいとは思う。ただし、「いかに得するか?」ということだけを考え続けて、みんな本当に幸せになっているだろうか?
「いかに得するか?」という視点で考え続ける人は、本当は幸せではないのではないだろうか。少なくとも私はそうだった。なぜなら、この考えに凝り固まれば凝り固まるほど、「得し続けなければならない」という強迫観念にとりつかれるからだ。
いい成績をとっても、次回は下がるかもしれない。いい大学に入っても、いい会社には入れないかもしれない。お金を貯めても失うかもしれない。出世してもいつか左遷されるかもしれない。というように何かを得たとしても失う恐怖に怯えることになるし、得られなかった時の絶望感は果てしないものがある。
考えても見て欲しい。私たちは生まれて、死ぬまでずっと失い続けている。若さだって、可能性だって、人生の途中で手に入れたものだって全てだ。みんな、死に向かっているのだから。どんなにいい家も、稼いだ大金も、どんなにいいパートナーも、どんなにすごい肩書も、あの世に持っていくことはできない。
このことに目をつむって、「どう生きるべきか?」を「どう得するか」という損得の次元だけで考え続けると、死ぬときに大いに後悔することになるだろう。なにしろ、何も残らないのだから。それに生きているうちに、上手いこと得し続けていたとしても、失う恐怖・不安が人生を埋め尽くし、幸せになることができない。
では、どうすれば、私たちはこの不安の連鎖から抜け出し、幸せになれるのだろうか?ここで冒頭に紹介したハンスの話に戻る。私はハンスを愚か者だとは思わない。損したことも分からない「(愚かな)幸せ者」とも思わない。きっと損したことも分かって、一時は血が噴き出るほどの悔しさも抱えたに違いない。しかし、それでも彼は最終的には幸せだったと思う。なぜなら損得を超える人生の視点を持ったからだ。
幸せになるには、「いかに得するか」という思考を止めて、「いかに損するか」という思考を働かせればよい。例えば、会社で上司に忖度すべきか否かという選択肢があったとして、自分の信じることならば忖度せず、貫いてみればいい。他にも失敗するかもしれない課題があったとして、自分がやりたいと思ったら失敗を恐れずやればいい。失敗してみればいい。その結果、損するかもしれないが、損してみれば清々しい気持ちになれる。
もちろん、いきなり全てをわざわざ失うような選択肢を取る必要はない。自分が損できそうなところから損すればいい。いきなり全てを失う選択肢を取れば、生きていけなくなる可能性もある。だが、自分の人生の一部分でも「得すること」ではなく「損すること」を選ぶ習慣をつけると、少しずつ損得の物差しで物事を見る癖が外れていく。
損得を超えた視点は、おのずと自分の魂から出てくる欲求に従う行動に繋がるだろうし、この行動の積み重ねが幸せな人生へと導き、死を前にしても後悔しない自分を作るのだろうと信じている。
繰り返すが、「得したい」という考えが悪いことではない。こういった考えは人間にとって自然な感情だし、この視点がないと生きていけないとも思う。しかし、同時に損得を超えた視点がないと、私たちは、得することばかり、勝つことばかり、効率よく、世渡り上手に生きていくことばかりに追われることになる。
もうすでに今の世の中では、そういうことばかりが良いことと押し付けられて、追い求めさせられて、本当はみんな疲れてるんじゃない?損する、非効率、世渡り下手な選択肢を選んだっていいんだよ?という提案でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
