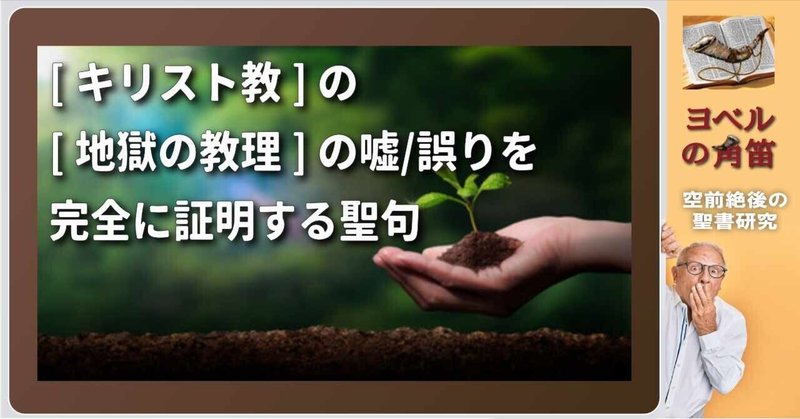
[ キリスト教 ] の [ 地獄の教理 ] の嘘/誤りを完璧に証明する聖句
ある質疑応答の形を採るサイトに、このような解説がありました。
«「誰が地獄へ行くの?」
【人間はみな罪人なので、すべての人は地獄に行く定めにあります。(ローマ書5:12)神に対する反逆のための正しい罰として、私たちは地獄に行くのが当然なのです。(ローマ6:23)】»
では最初に、ここに参照されているローマ5:12を引用しておくことにしましょう。
《このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。》ローマ5:12
つまり、すべての人間が地獄にゆくのは、アダムに起因する「原罪」に基づくというのが、その根拠とされています。
では動物はどうなりますか。哺乳類、爬虫類、魚類、鳥類など。
人間以外のすべての動物は、神の設計されたそれぞれの本能で生きるようになっており、人間だけが例外的に、神に対して反逆することが可能な能力というか、自由意志を与えられています。
すなわち動物は、敢えて意図的に神に反逆する、つまり罪を犯すことはできません。ですから当然、動物には原罪などありません。
すべて罪人である人間と、完全無罪の動物は、死ぬとそれぞれどうなりますか。
《人間に臨むことは動物にも臨み、これも死に、あれも死ぬ。同じ霊(ヘ語:ルーアフ)をもっているにすぎず、人間は動物に何らまさるところはない。すべては空しく、 すべてはひとつのところに行く。すべては塵から成った。すべては塵に返る。》伝道3:19,20
まず19節の聖句から明らかなのは、「人間と動物は同じ霊を持つ」ということです。この【同じ】は(ヘ語:エハード)で、字義的には「数字の1」を表す単語です。
以下の他の聖句からも分かるように、完全に同一のものを指す時に使用されます。
《彼らがみな、【一つ】(エハード)の民、【一つ】(エハード)のことばで、このようなことをし始めたのなら・・》創世記11:6
《ふたりとも【同じ】(エハード)夜にそれぞれ夢を見た》創世記40:5
《このおしえは、この国に生まれた者にも、あなたがたがの中にいる在留異国人にも【同じ】(エハード)である》出エジプト12:49
《幕の幅は、おのおの四キュビト、幕はみな【同じ】(エハード)寸法とする。》出エジプト26:2
そして3:20では、「人間と動物は一つの場所に帰る」
この【一つ】も(ヘ語:エハード)です。
言い換えれば人間は死ぬと、死んだ動物と同じ場所に帰る。つまり両者の死は完全に同じ状態にあるということです。
「人間は動物に何らまさるところはない。」ということは、人間は動物に劣るところも何もないということです。
言い換えれば人間は死ぬと、死んだ動物と同じ場所に帰ります。
「すべて罪人である人間と、完全無罪の動物の死後は、まったく同じ状態にあると聖書は明言しているのです。
何らの罪のない動物が地獄で苦しめられる根拠は微塵もありません。
動物だけが「土」と化し、人間だけが「地獄」にゆくなどという概念は聖書には存在しないということです。
ここではっきり断言しますが、これが聖書の示す「死」に関するストレートな表現です。
伝道3:19,20の意味するところは、すなわち人間も動物も、死に際して同じ道を辿る(無存在から存在物となった創造の逆の手順を踏む)ので両者とも「無存在」に戻るということです。
動物にはこの地の領域以外、生死の如何を問わず、他に生息領域は存在しません。人間も同一だということです。
ここで「死」は完全に「無存在」だと言い切る理由は他にもあります。
19節末尾にある「すべて空しく」というフレーズです。この「むなしい」と言う語は「へベル」という語ですが、この語の使用例で一番有名なのは次の聖句でしょう。
《空の空。伝道者は言う。空の空。すべては空。》伝道の書1:2
(この1節だけに「へベル」が5回使用されている)
「空」と訳されるように、この語の英語聖書での訳語を幾つか挙げてみます
vain (空疎) delusion(妄想) emptiness(空虚、空っぽ) nothing(皆無)などです。その意味するところを解りやすい言葉で表すなら「なんにも無い」ということです。死んで土に戻った後は一切「空」で「無」であるということです。
更に他にも使用例を幾つか挙げて見ましょう。
《人間は息(ヘベル)にも似たもの。彼の日々は消え去る影。》詩篇144:4人間一生はため息のように、影のように消え去るということです。
《その子(流産の子)は空しく(ヘベル)生まれ、闇の中に去り》6:4「空しく生まれ」と表現されていますが、「流産」なので、実際には人として誕生していないと同様、「闇の中に去り」とはつまり、廃棄処分を余儀なくされる。すなわち無存在を表すのは誰が考えてもそう認めるところでしょう。
偶像に関連してもこの語が多く使われています。
《もろもろの民が恐れるものは空しい(ヘベル)もの。森から切り出された木片》エレミヤ10:3
これが聖書に記されている「死」に関する正しい認識です。
「死後の世界」や「火の燃える地獄」などという妄想はこの簡潔な聖句で完全に破棄されます。
2000年ほど昔の無知の時代に導入された「地獄」という誤った神学を未だに教えているのです、その愚かさたるや半端ではありません。
「キリスト教」の最大の間違いの一つは、ハデスやゲヘナ、火の池、などの比喩的な表現を皆「文字通り」のことだと受け止めてしまっていることです。
新ブリタニカ百科事典には、「西暦2世紀の半ば以降、多少ともギリシャ哲学を学んだクリスチャンたちに最もよく合った哲学はプラトン主義だった」と書かれています。
アウグスティヌスやトマス・アクィナスなどによりキリスト教とギリシア哲学を合体させたことにより、霊魂不滅、地獄、三位一体などみな同じ頃に成立してきました。
さて、こうしたテーマで記事を書くと、必ず似たような反論があり、「聖書には「体」と「霊魂」は分離することがはっきりと示されている」と主張する人々がいます。
その根拠としてよく取り上げられるのが次の聖句です。
《塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。》伝道の書12:7 新共同訳
《・・霊魂はこれを賦けし神にかへるべし》文語訳
確かにこの聖句には、大地に帰るものと、神に帰る2つの別々のものがあるように書かれています。しかしこれを根拠に、人間は「肉体と霊魂の合体である」という主張は霊(ルーアフ)と魂(ネフェシュ)を完全に混同しているだけで、それがすべての間違いの元です。
文語訳で「霊魂」と訳されているのは「ルーアフ」です。
しかしこの「霊魂」という語はそもそも「仏教用語」です。様々な教理に仏教思想が浸透しているのが「キリスト教」です。
聖書中に「霊魂」というような概念を指す語は存在しません。
新改訳や新共同訳では「霊」、聖書協会共同訳では「息」、フランシスコ訳では「息吹」と訳されています。
多くの翻訳者たちが,「霊」に替わりうる訳語として「息」という語を使い,その部分の原語が,人格を持たないながら生命の存続に必須なものを指すことを示している点は注目に値します。
「体」は土に戻ります。「霊」或いは「息」は、「別の、死後の世界」に移るわけではありません。そうではなく「神のもとに帰ります。それはどういうことでしょう。
■ 「神に帰る霊とは」とは?
改めて「霊」についてもう少し掘り下げてみようと思います。
話が前後するようですが、冒頭でとりあげた、伝道の書 3章の中で、「人間と動物は同一の霊を持つ」ということでした。
しかし姿かたち、機能や特性は異なるのに、「異なる霊」ではなく、なぜ人間と動物が「同一の霊」なのでしょうか。
それは、同じ神から造られた同じ生命体だからですが、もっと明確な理由を示すと、「霊」は創造されたものではないからということになります。
ヨハネ4:24には神は霊である※(ギ語:プニューマ ホ セオス)[ the God is spirit ] と記されています。肉体を持たない生命体であるということです。
※ このギリシャ語 「プニューマ」は、「風」という意味の「プノエー」という語から派生したものです。 ヘブライ語の「ルーアフ」は普通名詞の「風」という語と全く同一の単語です。つまりどちらも、言葉の成り立ち、概念は共通しています。
恐らく、眼には見えないけど、物を動かすようなエネルギーというようなイメージから派生しているのでしょう。
ですから、ヘブライ語「ルーアフ」には「エナジーやフォース」という意味合いもあります。
「霊」についてまず、知っておくべきことは、全生物の「生命と霊は」は神の所有物だということです。
《見よ。すべてのいのちはわたしのもの。父のいのちも、子のいのちもわたしのもの。》エゼキエル18:4
《すべての生き物のいのちと、すべての人間の【息】(ルーアフ 霊)とは、その御手のうちにある。》ヨブ12:10
洪水で人間と動物の生命が断たれたことについて,聖書はこう記しています。
《その鼻に命の息と霊のあるものはことごとく死んだ。》創世記7:22
「命の 息 と 霊 」という部分は「カーイ ネシャマー ルーアフ というヘブライ語の単語で構成されています。
ここでは息と霊はそれぞれ別の単語で表されていますが、多くの翻訳で、ルーアフは「ストレートに「霊」、時折「息」、文脈によっては「風」と訳されていますが、ネシャマーとルーアフとは同義語に近いと言えます。
《 私の息が私のうちにあり、神の霊が私の鼻にあるかぎり、》ヨブ27:3 新改訳
どちらの聖句も、神の霊は「鼻」の中にあるとされています。
明らかに「霊 ルーアフ」のもっとも基本的な意味は「生命力」を意味すると言えます。
「霊」は神のものだから、死んだ時、その「霊」は神に帰るのです。
もっと分かりやすく表現すれば、人間や動物の「霊」は、創造されたものでは無く「霊であられる神」のもとから、移されたというか注入されたというか、おおよそそういうものです。
先程伝道の書12:7 を取り上げました。今一度その後半部分を引用してみます。
《霊は与え主である神に帰る。》伝道の書12:7
この「与えた」と訳されている語は 「ヘ語:ナーサン」で 基本的な意味は「 put, set」です。(ナーサンが使われている他の参照聖句)
《神はそれらを天の大空に【置いて】(ナーサン)、地を照らさせ》創世記1:17
《わたしは雲の中にわたしの虹を【置く】(ナーサン)ナーサン》創世記9:13
日本語で「与える」というと「所有権が移る」という概念が働くと思います。
これは「もらったもの」と受け取ります。しかし、「手の上に置いた」というと微妙です。もう少し具体的言うと、「生き物」は神の霊の一部(生命)を「セットされている」ということです。
「神の元に帰る」ということは「命」は神から「与えられた」ものではなく、また取得したものでも、親から「もらった」ものでもなく、単にシステム的に受け継がれて来たものでもなく、言わば「レンタル」されているようなものと言ったら解りやすいでしょうか。
だからこそ、人間にしろ動物にしろ、死ぬとその霊はもれなく「神の元に帰る」のです。
これは、「エネルギー保存の法則」※ に通ずるように思えます。
※ (エネルギーが、ある形態から他の形態へ変換する前後で、エネルギーの総量は常に一定不変であるという法則。高所にある物体は落下によって位置エネルギーが減少するが、運動エネルギーを得て、その和は常に一定であり、これを力学的エネルギー保存の法則とよぶ。)
《主なる神は、土(アダマ)の塵で人(アダム)を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きる者となった。》創世記2:7
アダムは「霊を持つもの」として創造されたのではなく、土から形造られた後、命の息を「吹き入れられた」のです。
《その霊[ルーアフ]が出て行くと,その者は自分の土に戻る。その日に彼の考えは滅び去る》146:4
記事の初めに「誰が地獄へ行くの?」というサイトの一節を紹介しましたが、その解説に«神に対する反逆のための正しい罰として、私たちは地獄に行くのが当然なのです。(ローマ6:23)»と記されていました。
勘違いも甚だしいと言わねばならないでしょう。
聖書のどこに「罪の代償は「地獄」」だなどと記されているのでしょうか。
《罪が支払う報酬は死です》ローマ6:23
「死」そのものが裁きであり、言わば「刑罰である」というのが聖書が明確に述べていることです。
「原罪」に対する処罰は永遠に生きる権利を剥奪する「死刑」なのです。
寿命が限られていることそのものが、神からの死刑執行なのです。
罪のない人は死ぬことはありません。「死ぬ」というのは「罪」のためです。「死」によってその人のすべての罪の代価がその命によって支払われます。
【死後」つまり死んだ後は自分の罪から放免されているのです。
「死後」なおも罪を問おうとするのは、あたかも、刑期を満了して無罪放免となった受刑者が刑務所を出た途端につかまえて「無期懲役」に放り込むようなものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
