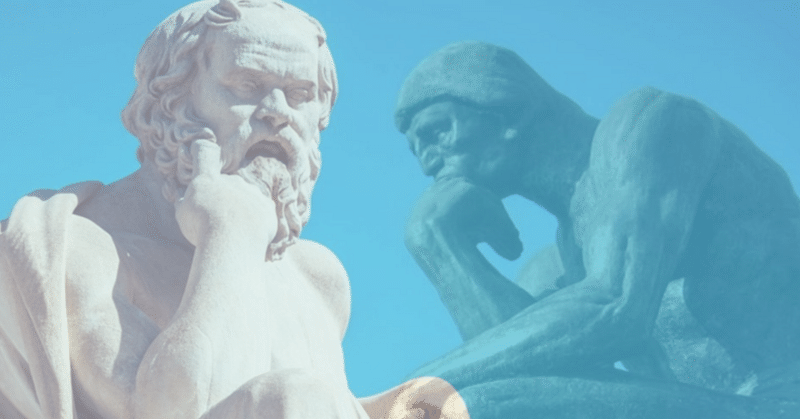
問い続けることを「オッペンハイマー」に学ぶ〜センスメイキング道場第1回 振り返り
はじめに・・科学と哲学と人間性
今年のアカデミー賞作品「オッペンハイマー」は、現在から過去、過去のそのまた過去、未来と目まぐるしく時間軸が動いていきます。
時系列に経緯を追うのではなく、現在と過去がデュアルモードで展開する描き方は、クリストファー・ノーラン監督の得意とするところでしょうが、単なる演出ではなく、実際我々はそんなふうに思考を巡らしていることを思わされます。
(科学の追求が人間のためになるのか)
原爆開発者である主人公が、自分の功績を求めて原爆開発に突き進む姿は科学者らしい姿だとも思います。
しかし、ナチスよりも先に開発することを目指した計画は、そのナチスが降伏しても尚、成果を確認するために進められます。
核爆発の引き起こす連鎖反応で地球が破壊される可能性があるという結果が想定されても、競った成果を確認しないと止まらない。
日本でも頻発している大企業の不正行為にも似て、目的と手段が入れ替わっていくようであり、科学を科学だけで考える危険性も感じます。
今もAIの開発で同じようなことはないのだろうかと考えてしまいました。
(不確実性を受け入れることができるか)
原爆が起こす連鎖反応で世界が壊滅するのではないかという不安を抱いたオッペンハイマーは、アインシュタインに相談に行きます。
しかし、アインシュタインは「君は量子力学が示す不確実性の世界に直面したから会いにきたのだろうが、私は数学を見下しているから君が求めている確実性に対する答えは出せない」と断ります。
正解を求めようとするオッペンハイマーと不確実性の世界を探求しようとするアインシュタインの姿が対比されます。
(人間を軸にして多様な視点から物語を紡ぐ)
この作品は、時間軸をバラバラにし、たくさんの人間の思考を描き、視点を切り替えながら映し出すことで、前半わかりにくいと感じたことが、後半の聴聞会での陳述や展開でつながってきます。
科学技術の進展と人間の尊厳、人間の持つ正と悪、人間に共通する根源的な思考を表現するストーリーメイキング、ストーリーテリングは素晴らしいと感じます。
(人間として鍛錬すべきは思考行動様式か)
4月から始まったセンスメイキング道場は、不確実な社会の中で自身の目的を見つめ直し、自身が感知したことを大切にして、商品やサービスのコンセプト開発に役立てるような思考行動様式を鍛錬することを目的としています。
1. 多様な視点からストーリーを作り出す~VTSで体感する対話型鑑賞法
①多様な視点を受け入れる
センスメイキングでは、この時間軸の捉え方、視点の置き方が大事なことです。
センスメイキング道場の第一回では、VTS(Visual Thinking Strategies)やビジョンスケッチを通じて、観察眼を養い、表現することで生まれる思考の一端を体感しました。
まずはVTS。
作者や作品名などこの絵についての情報は一切なく、この絵のテーマを考えようというのがVTSです。

VTS 1周目
この絵をじっと見て感じたことを各自自由に語ります
「この絵は昼なのか夜なのかわからないと思った」
「真ん中のライオン?の目がこちらに何かを語っている」
「後ろの方にいるのは象だ」
「裸婦がヘビを指さして危険を伝えようとしている」
「なんで裸婦はソファーに寝ているのだろうか」
「真ん中にラッパがある」
「女性は何かを投げた」
「投げたのは青い花」
最初パッと見て目についたことを表現し、他の人の目の付け所を聞いていくと、自分が見ていないことや想像していない捉え方に気づきます。
すると、違う視点で見え始めます。
順番に話していくと、自分一人では見えていなかったことが見えてきて、色んなところを見たくなります。
前の人が目をつけたのとは違うところを探したくなりますし、同じところを見ても独自の解釈をしたくなってきます。
②見つけたことのつながりを考える
VTS2周目
一通り参加者全員が気になったところ、感じたことを聞きながら改めて見ながら2回目の表現をします。
最初に自分が見た時とは違う印象で語ります。
「草の陰で人がラッパを吹いているのが見えてきた!」

これを聞いて、みな目を凝らしてジッと見ていると、真ん中の派手な装飾品がスカートのような衣装で、その後ろに背景と同化したような人がラッパを手に抱えるようにして吹いている姿が浮かび上がりました。
「おおーーー」
皆驚嘆。
植物と動物に囲まれた森の中で一人寝そべる裸婦の絵に、別の人物が現れ、ラッパを吹いていることが確認できると絵の見方が更に変わります。
「ラッパ吹きがヘビや動物をコントロールしている!」
今まで見えなかったものが見えてきて一層面白くなってきました。
全体を見て、それからディテールに注目していく、観察法の基本としては、このように遠近で見ることが大切です。
そして、他人の視点も取り入れながら、見方を変えていくことで違った発見があります。
対話によって視点が広がり、変化していく対話型鑑賞法を体感的に理解しました。
③ 気づき、発見からストーリーを紡ぐ
絵を見ながら気づいたこと、発見したこと1つ1つは、まだ点としてバラバラに存在しています。
これらを繋いで物語を紡ぐ、ストーリーを想像(創造)することができるともっと面白くなります。
「ラッパの音に危険を感じた裸婦が青い花を投げてライオンがギョッとした」
それぞれが点で見ていたものが繋がってストーリーのかけらができてきました。
「これは夜なのか昼なのか」
最初に全体を見て感じたこの感覚に戻って考えると、昼だとしたらどんなストーリーが描けるのか、夜だとしたらどんなストーリーになるのか、そんなふうに思考を巡らしていけるとVTSが更に進化します。
見て、感じて、重ねて、発見したことをつなぎ合わせてストーリー化するという体験は、感知したことを表現するセンスメイキングのはじめの一歩になります。
残念ながら今回は、「この作者は我々に何を問うたのか」を解読するまでには至りませんでした。
たくさんの視点は出てきて、自身の見方を変化させるという体験はできたので、次は、それをつないでストーリーを作り、そこにテーマを感じ取り、論議するところまで行きたいと思います。
2.表現することから始まる〜ビジョンスケッチによる思考表現
①これからのことを言葉にしてみる
今回事前課題として「やりたいこと、なりたい自分」を描くビジョンスケッチにトライし、それを発表することで自己紹介としました。
この課題を聞いて私は、東京で働き始めたばかりの頃に上司に言われたことを思い出しました。
「名古屋では、今まで何してきたか、と聞かれる。大阪では、今何しているか、と聞かれる。東京では、これから何するか、と問われるから常に考えておけ」と。
後年、新しく事業を始めようとたくさんの人に会っていた時期にこの言葉の意味を痛感しました。
その頃年間で400人くらいの人に会って、様々な場面で自己紹介をしました。
その時に、自分は何をやってきたか、今どういう立場かというような自己紹介をするよりも、これから何をやりたいと思っているかを自己紹介した方が、近づいてきてくれる人が多く現れ、関係が深まるということを経験しました。
そして何度もこれからのことを自己紹介していくと、だんだんと自分が発する言葉が変化し、研ぎ澄まされていくような感覚がありました。
これから何をしたいか、どうなりたいか、未来を描いて自分を紹介した方が共感を得たり、興味を持ってもらえるのだと思います。
実際、そういうことを語る人の方が魅力的に見えますしね。
日頃目の前の課題に追われて自分のビジョンを考えることはなかなかないでしょうから、「やりたいこと、なりたい自分」を問われると改めて考えることになります。
「お前はこれからどうしたいのか?」
自分に問いかけることは、未来を想像することのようで、過去と現在を振り返ることにもなります。
②スケッチで右脳を活性化させる
絵にするという行為は右脳を使います。
ロジカルシンキングの左脳、クリエイティブシンキングの右脳、この両方を行き来しながら表現することで自分の本質を見つめることになります。
現代はロジカルシンキング過多の傾向があるので、左脳を使う機会の方が多いでしょう。
言語で左脳を働かせながらスケッチで右脳を稼働させる。両方を行き来しながら、ビジョンが膨らんでいきます。
③ 記憶を紡いで未来を考える
ビジョンスケッチに取り組むことで自分に問うた問いの答えが自己紹介として語られます。
「家族や周囲の感謝に囲まれる姿」
「天使が助けてくれる世界」
「夫婦で理想の場所に暮らす姿」
「故郷を活性化させることに貢献している自分」
「のんびりしたワークコミュニティを作りたい」
考えていることを絵として表現してみる。
上手い下手は関係なく、思い浮かんだことをまず手を動かして描いてみる。人の姿でも、風景でもいいので描いて、眺めていると段々思考が整理されてきます。
思い浮かんだことが繋がって、広がって、自分はそんなこと考えていたんだなと気づき、それが過去の記憶や子供の頃の夢とも繋がって、未来が想像されます。
自分が今やっていること、これからやりたいことは、これまでの人生の記憶にもつながっているのです。
一見バラバラで関係ないように見えることも自分がやりたかったこと、楽しいと感じたことなど自分自身の記憶に残るワクワクした気持ちとやりたいこと、ありたい姿を重ねていくと自分自身のストーリーになっていきます。
④ビジョンは変化しても本質は変わらない
自分自身で自分のビジョンを語りながらどう感じたでしょうか。
もしかしたら他の人に説明しようとしたために歪んだところはなかったでしょうか。
語りながら実は少し違ったと思うことはなかったでしょうか。
これもまたVTSと同様に右脳と左脳を行き来することで描かれました。
そして自分で描いたものを見て、語り、他人のビジョンを聴きながら、また未来を思考する。
ビジョンは揺るぎないもののように思われますが、必ずしも不変ではないということを考えさせられます。
⑤ 相互主観を重ねることで飛躍する
各人のビジョンはそれぞれその人のものです。組織の目標のような共有すべきタスクではありません。
また、正解や不正解もなく、他人事でもあります。
相互主観とは、お互いの主観を重ねて新たな見方・考え方を生み出していくことです。
他人の主観を受け止めると「なるほど」と思い、そこから「だとしたら」と考えが膨らみます。
そのようなアウスヘーベン(止揚)を繰り返すことで思考がスパイラルに上昇していくような体験を繰り返し鍛錬していきます。
3.問い続けることでテーマは生まれる
コンセプトを作るときに、生活者の課題や問題点、困りごとに目を向けることが多いと思います。
しかし、今や課題や問題点は見つけようと思っても見つかるものではありませんし、無理に見つけてもそこから新しいことは生まれにくいです。
センスメイキングではもっと漠然と、ふと気になったこと、違和感を感じたこと、心に残ったこと、これらを大切な種として、そこに様々な事象や他人の意見や更なる自分への問いが加わって、メタ心理学的に考えることでテーマが生成されていきます。
問い続けることによって、「あーそういうことか!」と視界が急に開けたり、「だったらこういうのありだな」とひらめいたりするアブダクション思考で、関係ないと思われたものが繋がったり、飛躍した考えが浮かんだりします。
ノーラン監督は作品を作るにあたって、常に自分に問い続けるのだと言います。
「答えの見つからない問いが、ひとつの方向へ私を導いてくれる」と以前言ったことがありますが、それは、無意識のうちにそうなっていて、後になってわかるものなのです。ある物語に惹き込まれる時には、あまり意識せずに自分の直感に従うようにしています。
最後に・・センスメイキングは人間性を鍛錬する
ビジョンスケッチを描いているとき、過去の記憶とのつながりを感じてワクワクします。
VTSで他人の意見を聴きながら絵を見ていると、いろんなものが見えてきてワクワクします。
主観的に自分の直観に従って考えることはワクワクしますが、そのワクワクを瞬間の感情に留めずに、これでいいのかと常に自分に問い続けることが大切だとノーラン監督にも学びました。
VTSでは今回この絵のテーマを解釈するところまでは至りませんでした。
ビジョンスケッチでは自分の存在意義を突き詰めて自分のビジョンをしっかり掴めたでしょうか。
冒頭この道場の目的を、思考行動様式を鍛錬することと記しましたが、どうやらここで鍛錬されることは、手法の使い方や思考の方法ではなさそうです。
この道場を通して、自分は何者かを問い続け、他人と対話して、表現し、根源的な思考を読み解いていくことで、自身の人間性や人間味が鍛えられるのではないかと感じています。
センスメイキング・アソシエイツ事務局
株式会社トークアイ 池谷 雄二郎
付属資料:センスメイキング道場第1回議事録




#センスメイキング #VTS #ビジョンスケッチ #オッペンハイマー #クリストファー・ノーラン #相互主観 #アウスヘーベン #鍛錬 #問い
