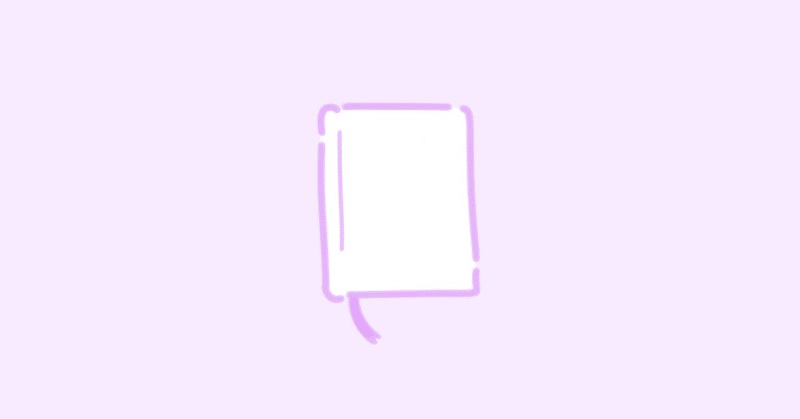
一冊の葵色の本
一冊の本を埋める。大切にビニールに入れて空気を抜き、そっと桐の箱に入れ、新聞紙でくるみ、布でくるんで、お菓子の空き缶に入れ、養生テープでしっかり封をする。藤の木を目印に、その少し手前の土の中に埋めた。
その日は、葵の二分の一成人式の日だった。葵が帰ってくるなり、私に言った。
「お母さん、ただいま。この本を埋めたいんだけど、いーい?」
「本を埋めるの? もう読まないの?」
「ううん、また読むよ。でも、それは九年後の僕の誕生日。というより、九年後、お母さんにも一緒に読んでもらいたいんだ」
「え、お母さんが読んでいいの?」
「うん」
「今はだめなの?」
「だめだよ。九年後読むための本なんだから」
「そう。わかったわ。どこに埋めたいの? おうちのどこかじゃないと、公園や人様のところに勝手に埋めちゃだめだよ」
「わかってる。藤の木のところはどうかな」
「いいよ」
「じゃあ埋めてくるね!」
「ちょっと待って。そのまま埋めたんじゃ、九年後ぼろぼろになって読めなくなっちゃうでしょう。お母さんも一緒に埋めるから、少し待っていなさい」
「えー。もう早くしてよー」
「はいはい」
葵は最近、少し意見を主張するようになった。小さかった葵ももう九歳。スミレちゃんともすっかり仲良くなって、トラブルがないことはないけれど、それなりに日々を元気に楽しく過ごしている。成長がうれしいような、寂しいような。ううん、喜ばないとね。いったいどんな本なのかしら。気になるなぁ。
「お母さん、まだー?」
「はいはい、もう少し待ってなさい」
「はーい」
さてさて、葵を待たせないように、準備しなくっちゃ。
そうして、材料を揃えて、本を埋めた。
僕がまだうんと小さい頃、誕生日にお父さんが一冊の本をくれた。
「茜さん、あれ、渡そうか」
「そうね、はい、藍さんからお願い」
「ありがとう。葵、お誕生日おめでとう!」
「おとうしゃ、おかあしゃ、あいがとう」
「葵~、よく言えたな~! 葵は天才だな~!」
「てしゃい?」
「天才だよ~よしよしよし」
「もう、あなた、葵がちょっと困ってますよ」
「ごめんごめん。葵、これはね、葵が主人公の本なんだよ」
「ほう?」
「そう、本だ。葵が生まれて今までのことが書いてあるんだよ。その後は白くなっていてね、続きが書けるんだ。まだ小さいから読むのも難しいと思うんだけど、もう少し大きくなったら読み聞かせてあげるからな。そしてさらに大きくなったら、少しずつ、続きを書いていってほしいんだ。ちょっと難しいかな?」
「わかた!」
「本当かい? わ~、やっぱり葵は天才だ~!」
「てしゃい! てしゃい!」
「はいはい。さあ、ごはんを食べましょうね。食べたらケーキもあるわよ~」
「ケーキ! やったな葵!」
「けーき!」
「いちごがいっぱい乗ってるよ~」
それから少しずつ大きくなって、僕はまず、この本の最初を読んだ。ひらがなで、僕が生まれる前のこと、生まれる日のこと、お父さんとお母さんがどんなに僕が生まれるのを心待ちにし、喜んだかということが書かれていた。僕の名前の由来も書いていた。今改めて読み返すと、なんだか照れくさいや。
そして、字が書けるようになってから、埋めていった。お母さんと書くお父さんへの日記とは別に、お母さんに内緒で。卒園式、入学式のこと、あの光る種のこと、きらりちゃんと遊んだことも書いた。いわゆる、自分史というものなんだと思う。そして今日も書いた。二分の一成人式のこと、それから今の思い。まだ空白のページがある。それは、九年後に埋めて完成させてから、お母さんにも読んでもらいたい。
表紙は「葵色」。僕の名前の色だ。お父さんとお母さんの色が混ざった色。お父さんの優しさ、お母さんのひたむきさを受けて、すくすく育ってほしいとの願いが込められた名前の色。
葵と本を埋めて、二分の一成人式パーティーをした。手によりをかけて作った葵の好きなおかず、混ぜご飯と、いちごの乗ったショートケーキを食べながら、今日のパーティーの話を聞く。私も招待してもらっていたのに、残念ながら仕事をどうしても休めなかった。でも、葵が私に向けて書いてくれた作文を音読してもらい、目頭を押さえながら、多幸感に包まれた。藍さん、私ばっかりごめんなさいね。写真の藍さんと聞き入って、お風呂に入り、明日の支度を整えた。
その日が来た。私は毎年、新しい手帳を買うたび、葵の誕生日に「●年後、藤の木の下で、本の箱を掘り起こす」と書いて、決して忘れないようにしてきた。
一週間前、葵から声をかけられた。
「母さん、あの本のこと、覚えてる?」
「もちろんよ。来週ね」
「うん、空けといて」
「わかった。帰り遅くなると思うけど、ちゃんと真っ直ぐ帰るから」
「俺も部活で遅くなると思うし、気にしないで。急いでこけんなよ」
「わかってるわよ」
「いやいや、母さんも年取ってんだから、無茶すんなよ」
「年寄り扱いしないの、まったくもう」
私を気遣ってくれているのはわかる。年頃なのに、文芸部で副部長をしながら、週に二日アルバイトもして、家計を助けてくれている、親孝行な息子なの。でも恥ずかしいみたいで、口は悪いし、前みたいにその日あったことを話してくれなくなった。健全に大きく育ってるのよね。もうすぐ成人だもの。ちなみに文芸部部長は、あのきらりちゃん。
「葵、取り出すわよ」
「ああ」
傷つけないように、スコップで少しずつ二人で掘っていく。しばらくすると、カン、と音がした。手で周りの土をよけると、ああ、あのときの缶だ。
「中身大丈夫かな」
「どうかしら」
恐る恐る蓋を開ける。幾重にも重なった布を外し、新聞紙をどけ、桐の箱をそっと開ける。布や新聞紙は傷んでいたが、ビニールの中の本はどうやら無事なよう。
「大丈夫そうね、表紙も少し色が落ちてるけど、無事みたい」
「ちょっと待って。これ、まだ読まないで」
「え?」
「少し書き加えるから、手洗って待っててよ。この穴埋めたり後のことは俺がやっとくから」
「そう。わかったわ」
そうしてしばらく待つと、葵が自分の部屋から出てきた。
「はい、いいよ、読んで」
「うん」
あのときの本だ。藍さんと一緒に作った、あの本。文章は私が書いて、絵は藍さんが描いたの。
「この絵、藍さんが描いたのよ。文章は私が書いたの」
「そうだったんだ」
「じゃあ、続き、読むわね」
あの白紙のページは、小さい葵の大きな文字で始まり、だんだんと大人びた小さな字に変わっていった。それでも、今よりはまだあどけなさの残る字。日記や漢字練習帳の宿題をみていたのを思い出す。懐かしい出来事でいっぱいに埋め尽くされていて、心が満たされていくのを感じる。
そして、最後から一つ前のページに差し掛かる。
今日は二分の一成人式。
お母さん、大人になった僕と、今これを読んでいますか?
お母さん、九年間、育ててくれてありがとう。
お母さんはいつも、お父さんがいないことで僕に悲しい思いをさせてるんじゃないかと心配しているみたいだけど、僕はそんなこと思ってないから安心して。
お母さんとの毎日は楽しいし、お父さんも藤の木と一緒に見守ってくれてる。写真の前で話しかけながら日記書いてるし、全然寂しくないよ。
大きくなったら、いっぱい恩返しするから、もう少し待ってて。
大人の葵、これを読んだらちゃんと恩返しをすること!
二分の一成人 九歳の葵より
本が滲まないように、涙をぐっと堪える。そして、いよいよ最後のページ。
今日は十八歳の誕生日。
九歳の俺、心配すんな。ちゃんと恩返しするよ!そのために、アルバイトで、こっそり貯めてきたんだ。
母さん、今までありがとう。
受験が終わったら、多分ここを離れることになる。
母さん一人をこの家に残すのは心配だけど、父さんも見てくれてるはずだし、藤の木もあるし、母さんなら大丈夫だ。
これからは、自分のために人生を楽しんでほしい。
とりあえず、受験がんばる。
そして、これから少しずつ恩返ししてくから、長生きしてよ。だから、あんまり仕事、無理すんなよな。
成人した十八歳の葵
本を閉じて、奥に追いやる。とうとう溢れだす涙を止められなかった。
「泣きすぎ」
「あんたが泣かせたんでしょ」
「老けて涙もろくなったんだろ」
「ちょっと、なんでそういうこと言うかなぁ」
「うるさいな、ほら、これ」
「なあに?」
「手袋。今使ってるの、ぼろぼろだろ。手もあかぎれだらけだし。使ってよ」
「ありがとう。大切にする。こんなの使えないじゃない」
「いや、使えよ?」
「わかった」
「じゃあ、ごはん食べよう。今日は俺が作った」
「まあ! ありがとう!」
「俺と母さんの好きなやつ。あっためなおすから待ってて」
「うん。本当に、いろいろとありがとう。今日は葵の誕生日なのに」
「プレゼントなら朝もらったから。ありがとう。マフラー、大切に使うよ」
「受験前に風邪ひかないようにね」
「わかってる」
本当は十分、恩返ししてもらってる。今日の日を、きっと私は忘れずに、何度も思い出す。本を胸に埋めて、大切に桐の箱に戻し、藍さん、葵との思い出が詰まった引き出しにしまった。
📘
小牧幸助さん、毎週の癒しをありがとうございます!
このシリーズの続編です。
ここにきて数字の表記ゆれが発生してしまったので、前作のほうを直そうかと思います。
今回、視点が変わったり回想を挟んだりでやや読みづらいかもしれません。すみません。
同じ文から始まるさまざまな作品を味わえる、お一人お一人のつくられる世界観、その人らしい小説、詩を楽しめるこの企画に、たくさん元気をいただいています。
この企画を通しての出会いもあります。
またゆっくりみなさんの作品を味わっていきたいです。
サポートしてくださる方、ありがとうございます! いただいたサポートは大切に使わせていただき、私の糧といたします。
